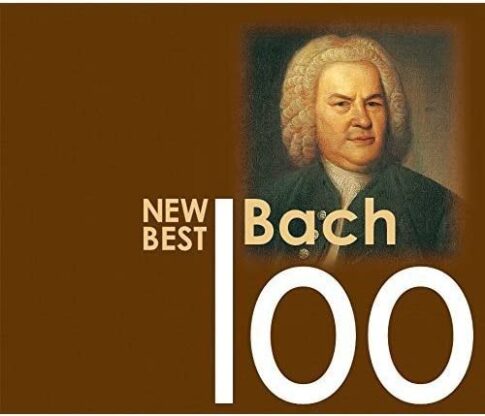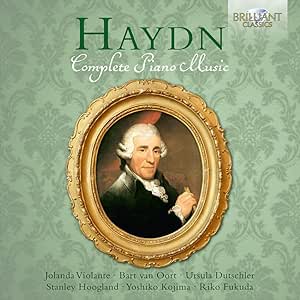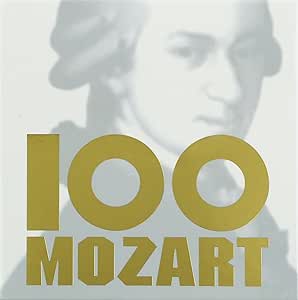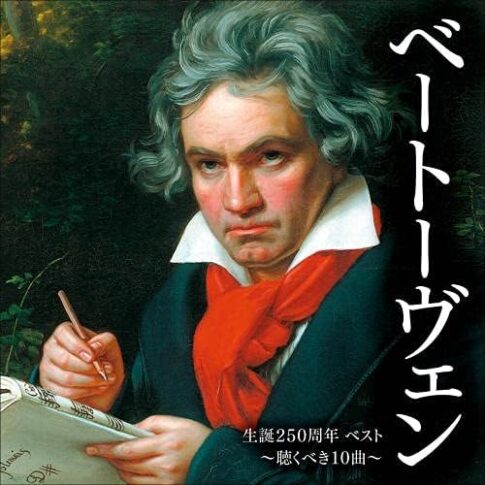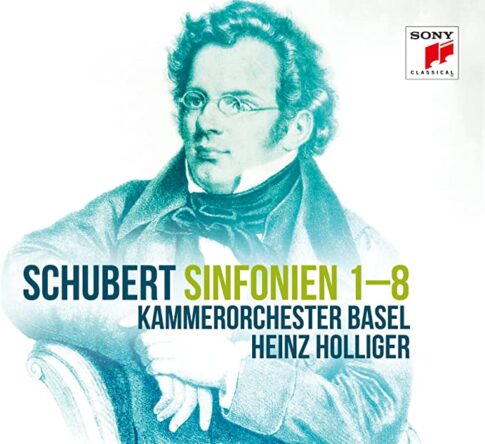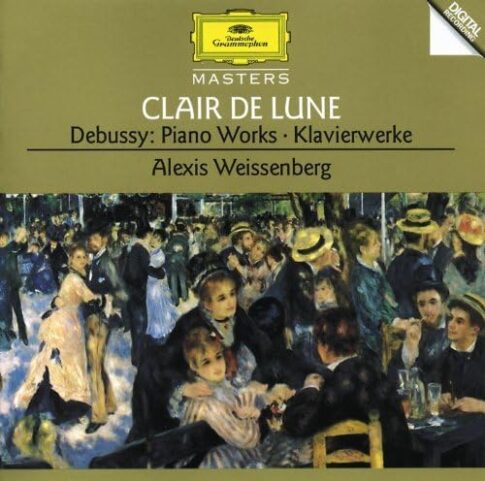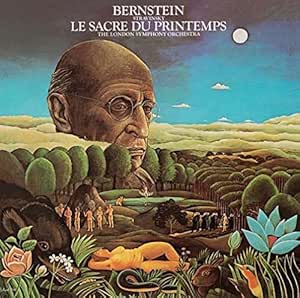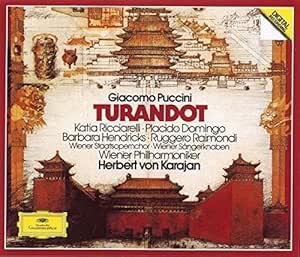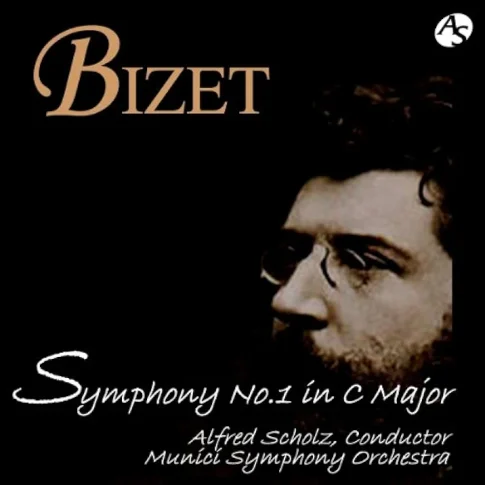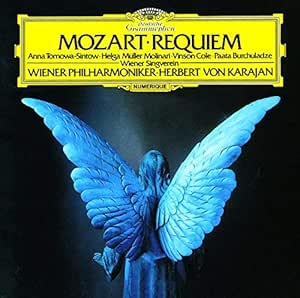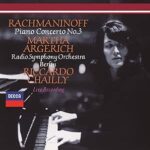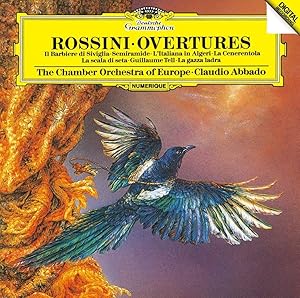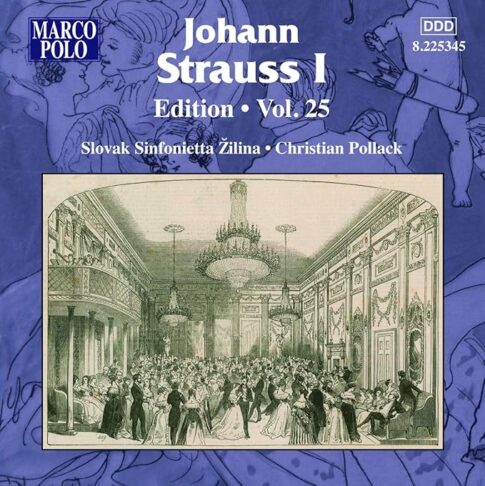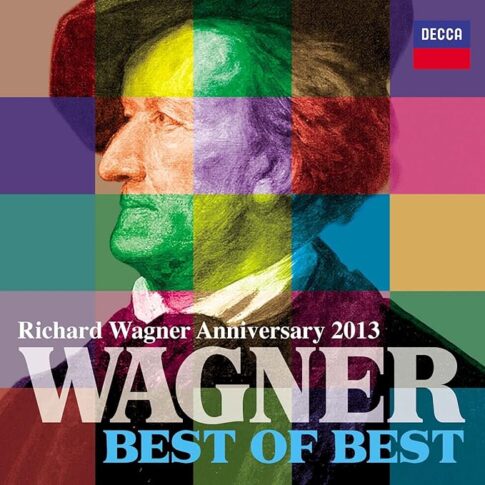この記事では「クラシック音楽とは何か?」をテーマに、初心者の方にもわかりやすく、ザックリと解説しています。
「興味はあるけれど、どこから始めればいいのかわからない…」
そんな方のための入門的内容になっていますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください!
この記事を読むとわかること
こんなことが理解できます。
この記事を読む前と読んだ後では、知識量が格段に上がること間違いなしです!
クラシック音楽とは?基本を知ろう!

まずは、「クラシック音楽ってどんな音楽?」から見ていきましょう。
難しいことは書いていないので、大丈夫ですよ!
クラシック音楽の定義とは?
クラシック音楽とは、西洋で発展した芸術音楽の総称。
単に「クラシック」と呼ばれることも多いです。
一般的には、17世紀から20世紀初頭にかけて作曲された音楽作品を指します。
作曲者による厳密な楽譜に基づいて演奏され、複雑な構造と豊かな表現力が特徴です。
19世紀後半から20世紀以降は、作曲スタイルが大きく変化します。
「クラシック=古い音楽」ではない?
「クラシック」というと、単に「古い音楽」と思われがちですが、それはちょっと偏見かもしれません。
というのも、現在も新たなクラシック音楽が作曲され続けているので。
また、「クラシック」には「古典的」「最高水準の」「由緒のある」という意味もあり、時代を超えて評価される質の高さを表しています。
なぜ今でも世界中で聴かれているのか
クラシック音楽が何世紀にもわたって愛され続ける理由はたくさんありますが、その最たる理由は美しさと深い感情表現にあります。
言葉の壁を超えて人々の心に響く力があり、技術的な完成度の高さも魅力のひとつ。
また、現代の音楽のルーツとなっている要素も多く含まれており、音楽史において重要な位置を占めています。
クラシック音楽の特徴とは?
ここでは、クラシック音楽の特徴を解説します。
ザックリと以下のことを覚えておけばOKです。
1つずつ解説します。
楽譜に忠実に演奏する
クラシック音楽の大きな特徴は、作曲家が残した楽譜に忠実に演奏すること。
ポピュラー音楽やジャズのように即興で大きくアレンジすることは少なく、作曲家の指示(テンポや強弱など)を尊重しながら演奏するのが特徴です。
古い時代のクラシック音楽では、即興で演奏する「カデンツァ」も多くありました。
交響曲・オペラ・協奏曲などの形式がある
クラシック音楽には、ジャンルが豊富。
交響曲、ソナタ、協奏曲、オペラ、バレエなど様々な形式があります。
それぞれに独自の構造やルールがあり、作曲家はその枠組みの中で創造性を発揮してきました。
国や時代背景によって異なり、本当に多種多様です。
様々な楽器が組み合わさる
オーケストラによる演奏、1度は見たことがあると思います。
クラシック音楽では弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器など多様な楽器が組み合わされ、豊かな音色を生み出すのも魅力です。
また、ピアノやバイオリンなど、ソロ楽器のための作品も数多く存在します。
作曲家の意図を大切にする
演奏者は作曲家の意図を尊重しつつ、自分なりの解釈で作品に命を吹き込みます。
同じ曲でも演奏者によって微妙に異なる表現があるのも、クラシック音楽の魅力のひとつです。
とはいえ実際には、作曲家と演奏家の解釈がぶつかることも結構あります。
作曲家の意図vs演奏家の表現の追求みたいな感じです。
100年以上前の作品が今も演奏される
ポピュラー音楽では数年前の曲が「懐メロ」と呼ばれることもありますが、クラシック音楽では200年以上前の作品が今も現役で演奏され続けています。時代を超えた芸術性を持つ作品が多いことを示しています。
クラシック音楽とは?:その歴史をざっくり解説!

歴史を知る上で「これだけは覚えておこう!」という項目をまとめました。
実際には、もっと前から伝統が続いていますが、ひとまずこれだけ覚えておけば大丈夫です。
覚えておくべき項目は以下の4つ。
なお、年代については厳密には言えません。
なので、「このくらいの時期」という理解です。
バロック時代(1600年~1750年頃)
バロック時代は「過度な装飾」を意味するバロック様式の美術と同様に、華やかで装飾的な音楽が特徴。バッハの「ブランデンブルク協奏曲」やヴィヴァルディの「四季」など、今も愛される名曲が多く生まれました。
古典派(1750年~1820年頃)
古典派の特徴は「秩序と均衡」を重視し、形式美を持つ点です。
モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」やベートーヴェンの初期交響曲など、親しみやすい数多くのメロディが生み出されました。
ロマン派(1820年~1900年頃)
- 感情表現を重視した音楽
- 国民楽派の誕生と民族的要素の取り入れ
- ベートーヴェン(後期)、シューベルト、ショパン、チャイコフスキーなどが活躍
- プログラム音楽(標題音楽)の発展
- オーケストラがさらに大編成化
ロマン派は感情や自然、幻想といったテーマを重視し、個人の内面を表現する音楽が多く作られました。ショパンのピアノ曲やチャイコフスキーのバレエ音楽など、感情豊かな作品が特徴です。
近現代(1900年~)
20世紀以降になると、調性(音階)から離れた実験的な音楽や、民族的要素を取り入れた作品など、多様な音楽が生まれます。ドビュッシーの印象主義音楽や、ストラヴィンスキーの「春の祭典」など、革新的な作品が登場したのが特徴です。
クラシック音楽とは?たくさんのジャンルに分かれる
いろいろなジャンルがあるのも、クラシック音楽の醍醐味の1つ。
ここでは、主要ジャンル5つを紹介します。
交響曲(オーケストラによる壮大な音楽)
交響曲とは、オーケストラのために書かれた大規模な音楽作品のこと。
通常4楽章から成り、様々な感情や物語を表現します。
ベートーヴェンの「第5番(運命)」や「第9番(合唱付き)」、ドヴォルザークの「新世界より」など、クラシック音楽の中でも特に壮大で感動的な作品が多く含まれています。
オーケストラの迫力と多様な音色を最大限に活かした音楽形式です。
3大交響曲
・ベートーヴェンの「交響曲第5番」
・ドヴォルザークの「交響曲第9番(新世界より)
・シューベルトの「未完成交響曲」
協奏曲(ソロ楽器+オーケストラ)
協奏曲は、ソロ楽器とオーケストラが「対話」するような形式の音楽です。
ピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲など、様々な楽器のために書かれています。
モーツァルトのピアノ協奏曲やチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲など名曲が多く、ソリストの技巧的な演奏とオーケストラの響きが融合する醍醐味があります。
ソロパートの華やかさと、オーケストラとのコントラストを楽しめる形式です。
オペラ(歌と演技が融合した舞台芸術)
オペラは、歌、演技、オーケストラ、舞台美術などが融合した総合芸術。
物語性があり、登場人物が歌で感情や状況を表現します。
モーツァルトの「魔笛」、プッチーニの「蝶々夫人」、ビゼーの「カルメン」など、ドラマティックな作品が多く、視覚と聴覚の両方で楽しめます。アリア(独唱曲)やデュエット(二重唱)など聴きどころも満載です。
オペラの中にもたくさんのジャンルがあり、国により特徴も異なります。
室内楽(少人数のアンサンブル)
室内楽は、少人数の演奏者によるアンサンブル音楽。
弦楽四重奏(バイオリン2、ビオラ1、チェロ1)が代表的ですが、他にもピアノ三重奏や木管五重奏など様々な編成があります。
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲やシューベルトの「ます」など、親密で繊細な音楽表現が特徴です。各パートが独立しながらも調和する、会話のような音楽が楽しめます。
宗教音楽(ミサ曲、オラトリオなど)
宗教音楽は、キリスト教の礼拝や儀式のために作られた音楽です。
ミサ曲(典礼音楽)、オラトリオ(聖書の物語を題材にした声楽作品)、レクイエム(鎮魂曲)などがあります。
バッハの「マタイ受難曲」、ヘンデルの「メサイア」、モーツァルトの「レクイエム」など荘厳で精神性の高い作品が多く、合唱と管弦楽が織りなす壮大な音楽世界を堪能できます。
クラシック音楽とは?:代表的な作曲家と名曲
ここでは、有名な作品を動画で見てみましょう。
どの作品も、きっと一度は耳にしたことのある名作です。
バッハ:「G線上のアリア」
出典:YouTube
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685-1750)は、バロック音楽の最高峰とされる作曲家。「G線上のアリア」は弦楽器の深い響きが心に染みる名曲ですが、他にも「ブランデンブルク協奏曲」「平均律クラヴィーア曲集」「マタイ受難曲」など多くの傑作を残しています。
緻密な対位法(複数の旋律が絡み合う技法)に優れ、「音楽の父」とも呼ばれています。
モーツァルト:「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」など
出典:YouTube
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)は、言わずと知れた古典派を代表する天才作曲家。
「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は親しみやすいメロディで有名ですが、「レクイエム」「ピアノ協奏曲第21番」「フィガロの結婚」など、あらゆるジャンルで名作を残しています。
わずか35年の生涯で600曲以上の作品を作曲し、その音楽は明快さと深い感情表現を兼ね備えています。
ベートーヴェン:「交響曲第5番(運命)」など
出典:YouTube
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)は、古典派からロマン派への架け橋となった作曲家。
「交響曲第5番(運命)」の冒頭は「運命の動機」として有名で、「交響曲第9番(合唱付き)」「月光ソナタ」「エリーゼのために」など、現代でも広く親しまれている作品を多数残しています。晩年は耳が聞こえなくなりながらも作曲を続けた強靭な精神力も有名ですね。
大のコーヒー好きで、きっちり粒を数えて淹れるのが日課だったそうですよ
ショパン:「ノクターン第2番」
出典:YouTube
フレデリック・ショパン(1810-1849)は、「ピアノの詩人」と呼ばれるロマン派の作曲家です。「ノクターン第2番」は夜想曲として美しい旋律が特徴ですが、「別れの曲」「革命のエチュード」「雨だれの前奏曲」など、ピアノ曲を中心に多くの傑作を残しています。
繊詩的な表現と技巧的な難しさを併せ持つ作品が多く、ピアノ音楽に革命をもたらしました。
その他の有名作曲家(リスト、ドビュッシー、チャイコフスキーなど)
ドビュッシー「月の光」:出典:YouTube
リストは超絶技巧のピアノ曲「ラ・カンパネラ」などで知られるヴィルトゥオーゾ(超絶技巧の演奏家)でもあった作曲家です。
ドビュッシーは「月の光」「アラベスク」など印象主義音楽の先駆者として独自の音楽世界を築きました。
チャイコフスキーは「くるみ割り人形」「白鳥の湖」などバレエ音楽や「1812年序曲」で知られる、感情豊かなメロディの名手です。その他にもシューベルト、ブラームス、ワーグナーなど、個性豊かな作曲家が多数います。
クラシック音楽とは?:使用される代表的な楽器を紹介
弦楽器
弦楽器はオーケストラの中核を担い、豊かな表現力を持っています。
・バイオリン
・ビオラ
・チェロ
・コントラバス
の4種類が弦楽四部を構成し、弓で弦をこすって音を出します。
バイオリンは最も高音で、メロディを担当することが多く、チェロは人間の声に近い温かみのある音色が特徴です。
ビオラは中音域、コントラバスは最低音を担当し、これらが揃うことでオーケストラは豊かな響きを生み出します。
木管楽器
木管楽器とは木材で作られた管に息を吹き込んで音を出す楽器のことです。
明るく透明感のある音色が特徴。
・オーボエ
・クラリネット
・ファゴット
・フルート
などがあり、それぞれ独特の音色を持っています。
フルートは澄んだ高音、オーボエは哀愁を帯びた音色、クラリネットは柔らかく滑らかな音色、ファゴットは低く温かみのある音色で、オーケストラの色彩感を豊かにしています。
フルートは金属でできていますが、昔は木で作られていたことと、木管楽器特有のリード使うことから木管楽器に分類されています。
金管楽器
金管楽器は金属製の管に息を吹き込み、唇の振動で音を出す楽器です。
・トランペット
・ホルン
・トロンボーン
・チューバ
などがあり、華やかで力強い音色が特徴です。
トランペットは明るく華やかな高音、ホルンは森の響きを思わせる柔らかな音色、トロンボーンは荘厳で力強い響き、チューバは重厚な低音を担当します。金管楽器は祝典的な場面や壮大なクライマックスで活躍します。
打楽器
打楽器は叩いたり振ったりして音を出す楽器で、リズムや音の効果を担当します。
ティンパニ(ケトルドラム)は調律できる太鼓で、ドラマティックな効果を生み出すのが特徴です。
その他、
・大太鼓
・シンバル
・トライアングル
・グロッケンシュピール(鉄琴)、
・シロフォン(木琴)
などがあり、曲の表情や緊張感を高める役割を果たします。
クラシック音楽では、色彩感やアクセントとして重要な役割を担っています。
クラシック音楽とは?:その魅力について
なんとな〜く堅苦しいイメージがあるクラシック音楽。
でも実際は、ぜんぜんそんなことありません!
いつ、どこで聴いてもOKですし、どんなシチュエーションにも合う音楽です。
そんなクラシック音楽の魅力をいくつか紹介します。
どんな場面でも楽しめる
クラシック音楽は、集中して聴くコンサートだけでなく、読書や仕事中のBGM、リラックスしたい時、気分を高めたい時など、様々なシーンで活躍します。
また、テンポや曲調も豊富なので、気分や目的に合わせて選べるのも魅力。
季節や時間帯に合わせた曲選びも楽しめます。
演奏者によって解釈が変わるのが面白い
同じ曲でも演奏者によって全く違った表情を見せるのが、クラシック音楽の大きな魅力。
テンポ、強弱、フレージング(音楽的なまとまり)など、演奏者の解釈によって曲の印象が変わります。
例えば、ベートーヴェンのピアノソナタを複数の演奏者で聴き比べると、同じ楽譜から生まれる音楽の多様性に驚かされます。この「演奏による違い」を楽しむのもクラシック音楽の醍醐味です。
下の演奏を聴き比べてみてください。演奏家による違いが楽しめますよ!
ベートーヴェンのピアノソナタ「悲愴」第2楽章です。
出典:YouTube
映画やCMなど、意外と身近にある
クラシック音楽は、実は私たちの生活のあちこちに潜んでいます。
映画「2001年宇宙の旅」で使われたR.シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」、CM音楽になったビゼーの「カルメン」、スマホの着信音になっているベートーヴェンの「エリーゼのために」など、意外なところで耳にしているものです。
身近な曲から入ると、クラシック音楽がぐっと親しみやすくなりますよ!
ツァラトゥストラはかく語りき:出典:YouTube
初心者におすすめの聴き方
まずは有名な曲から聴いてみよう
クラシック音楽を楽しむ第一歩は、誰もが知っている有名な曲から始めるのがおすすめ。
など、名曲と呼ばれる作品はそれだけの理由があります。
こうした曲は親しみやすいメロディや構成なので、初心者でもすんなり楽しめますよ。
オーケストラ・ピアノ・室内楽、どれから聴く?
正直に言って、どこからでも問題なしです。
でも、初めは自分の好みや興味に合わせて、入りやすいジャンルから始めると良いと思います。
迫力を求めるなら交響曲などオーケストラ作品、繊細な表現を楽しみたいならピアノ曲、親密な対話のような音楽を楽しみたいなら室内楽などなど。
また、映画音楽が好きな方は交響詩や管弦楽組曲から、歌が好きな方はオペラやアリアから入るのもおすすめです。まずは自分が心地よいと感じる音楽との出会いを大切にしましょう。
YouTubeやストリーミングで気軽に楽しもう
現代では、クラシック音楽を楽しむハードルが大幅に下がっています。
YouTubeでは無料で名演奏を視聴でき、SpotifyやApple Musicなどの音楽ストリーミングサービスでも膨大なクラシック音楽のカタログが提供されています。
「クラシック初心者におすすめ」「作業用クラシック」といったプレイリストも充実しているので、お好きなものから。
また、演奏会の映像を見ることで、視覚的にも楽しむことができますよ!
月額980円で1億曲以上が聴き放題!
クラシック音楽とは何か:まとめ
ということで、大分長くなりましたが、今回のまとめです。
- クラシック音楽は17世紀から現代まで続く西洋の芸術音楽で、時代を超えて愛される普遍的な魅力がある
- バロック、古典派、ロマン派、近現代など時代ごとに異なる特徴や様式
- 交響曲、協奏曲、オペラ、室内楽など多様なジャンルがあり、様々な楽しみ方ができる
- バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ショパンなど、多くの天才作曲家が素晴らしい作品を残している
- 弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器など多彩な楽器が織りなす音色の豊かさも魅力
- 演奏者による解釈の違いを楽しんだり、日常生活の中で耳にする機会を見つけたりして、身近に感じる
- 初心者は有名な曲から始め、YouTubeやストリーミングサービスを活用すると気軽に楽しめる
- クラシック音楽は敷居が高いと思われがちですが、実は誰でも楽しめる豊かな音楽世界
クラシック音楽は何百年もの歴史を持ちながら、今なお多くの人々に感動を与え続けています。この記事をきっかけに、ぜひクラシック音楽の世界に一歩踏み出してみてください。
きっと新たな発見と感動が待っているはずです!
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。