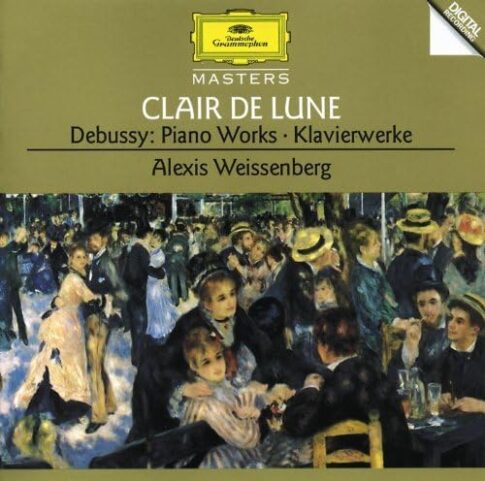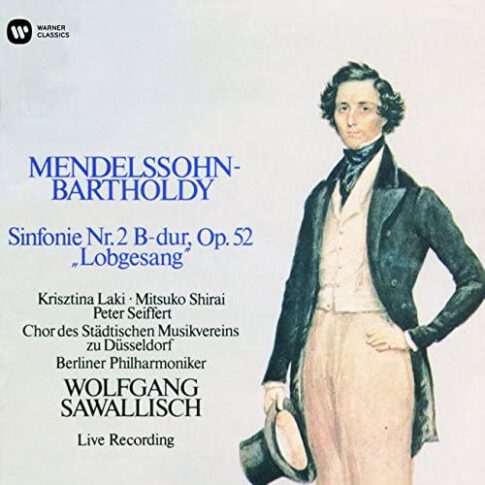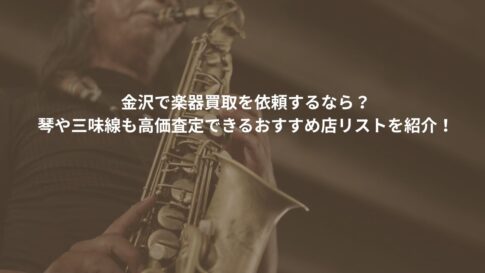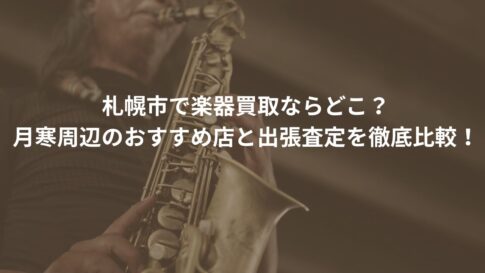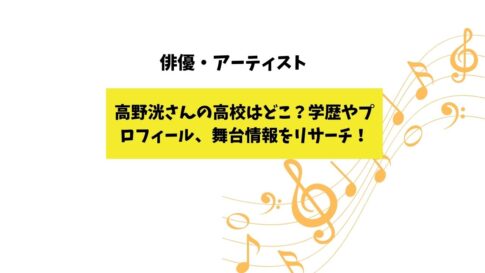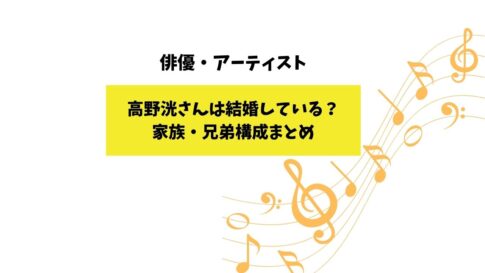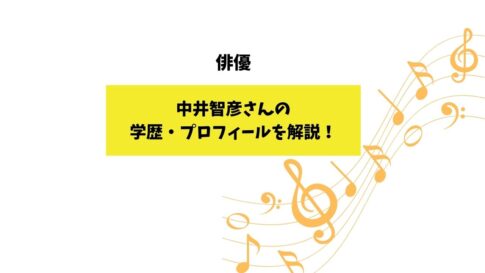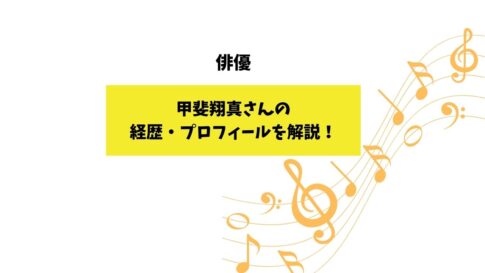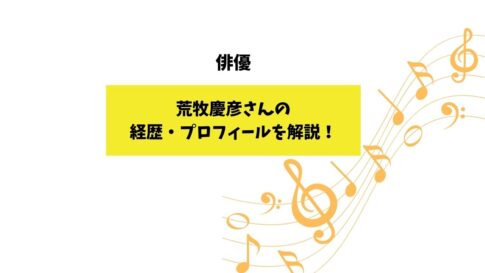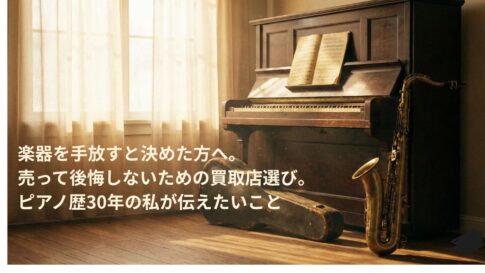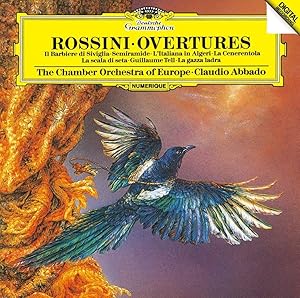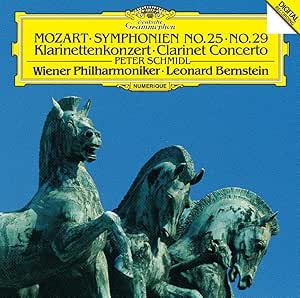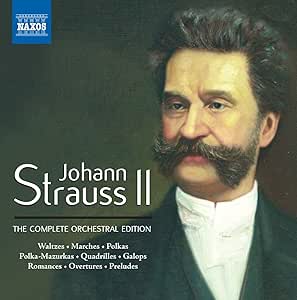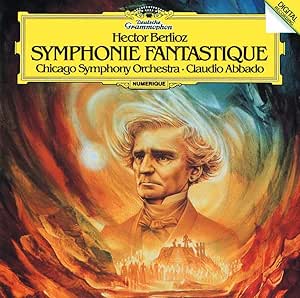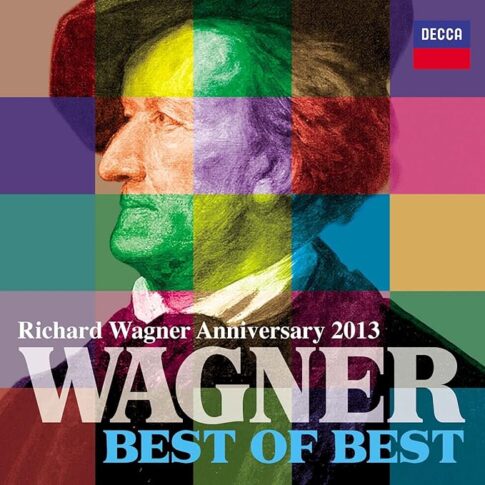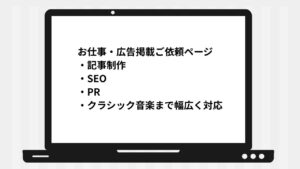今回紹介するのは、メンデルスゾーンの傑作「ロンド・カプリチオーソ 」。
本作は、華やかさと繊細な美しさにより、多くのピアノ愛好家を魅了するロマン派の傑作です。
発表会やコンクールでも人気である一方、高度な技術と深い音楽性が要求される難曲でもあります。
そのため「難易度は?」「自分に弾ける?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事でわかること
ちなみに、管理人は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノを弾いています(音大には行ってません)。
画像出典:アマゾン:パノラマ メンデルスゾーン作品集(2CD)
ロンド・カプリチオーソはどんな曲?
出典:YouTube
まずは、「ロンド・カプリチオーソ」について超ザックリと解説しますね。
本曲はドイツ・ロマン派の代表、メンデルスゾーン(1809-1847)の作品。
古典的な形式美とロマンティックな感情表現、洗練された旋律美が特徴です。
構成は明確な二部形式となっています。
・序奏(Andante, ホ長調): 穏やかで歌うような旋律が美しい。豊かな和声と深い表現力が求められ、内省的な雰囲気も持っています。
・ロンド(Presto leggiero, ホ短調): 序奏から一転、非常に速く軽快な主題がエピソードを挟んで繰り返されるロンド形式。技巧性は次第に高まり、華々しいクライマックスへ向かいます。
“妖精の音楽”とも形容される幻想的な雰囲気が魅力です。
演奏時間は6〜7分程度です。
ロンド・カプリチオーソの難易度レベルを徹底分析
これからチャレンジする方にとって、やはり気になるのは難易度ですよね。
管理人の実体験と音楽メディアの難易度を総合して解説します。
その他、このセクションでわかることは次の2点。
総合的な難易度:どのくらいのレベル?
結論!
ロンド・カプリチオーソは一般的に「中級の上」から「上級」の入り口レベルと考えてよいと思います。ピアノ学習者にとっては、まあまあの難易度ですね。
以下の基準が参考になると思います。
・全音ピアノピース: E(上級)とされています。
・PTNAコンペ: 課題曲採用歴があるようです。専門的な学習が必要とのこと。
・ヘンレ社: 7段階評価(近年9段階)で「7」程度に分類されることもあり、明確に上級レベルと位置づけられています。
参考としてPTNAでの素晴らしい動画を紹介しますね。
出典:YouTube
見ていただいてわかるように、高度な技術と音楽性を追求する「上級への挑戦」段階で取り組むべき本格的な難曲です。レベルアップへの大きな一歩という感じかなと思います。
技術的な難所ポイント解説
具体的に難しい技術ポイントを解説します。
- 序奏(Andante):歌わせる表現力、和音の響かせ方
美しいレガート、深いタッチ、和音のバランス感覚、繊細なペダリングによる響きのコントロールが求められます。フレーズの呼吸や歌心を感じさせる表現力が問われます。 - ロンド(Presto leggiero):速いパッセージの軽やかさと正確性
最大の難関。高速テンポでスケール等を”leggiero”(軽く)指示通り、粒立ち良く弾く必要があり、指の高い独立性、回転運動、そして高度な「脱力」が不可欠。 - スタッカート奏法:”妖精の粉”のような軽快さを出す難しさ
メンデルスゾーン特有の軽やかで輝きのあるスタッカート。速い動きの中で質感を保つには、力まず手首や指先の瞬発力と柔軟性を使う技術が必要です。 - 跳躍:正確な打鍵とミスタッチの回避
特に左手伴奏や両手での素早い移動。高速テンポでの正確な音の捕捉と、流れを止めないスムーズな移動技術、鍵盤感覚が重要です。 - 左右の手の受け渡しとポリフォニックな要素:
旋律の滑らかな受け渡しや、複数声部が複雑に絡み合う箇所での、各声部の流れを明確にしバランス良く弾き分ける能力。 - ダイナミクスの幅広さとコントロール:
ppからffまでの幅広い音量と、それに伴う音色変化を的確にコントロールし、表現に深みを与える能力。 - 持久力:最後まで弾き切る体力と集中力
約6〜7分間、高度な技術と表現を維持するための精神的・身体的スタミナ。特にPresto部分でのエネルギー配分と効率的な身体の使い方が重要です。
音楽的な表現の難しさ
技術課題に加え、音楽表現も深い理解と工夫が求められます。
- AndanteとPrestoの対比: 静謐な序奏から軽快なロンドへの雰囲気の変化を、自然かつ説得力を持って表現。性格、テンポ感、音色を明確に描き分けることがドラマ性を際立たせます。
- “Capriccioso”(気まぐれに)の表現: タイトルのニュアンス(気まぐれ、自由、遊び心)を、微妙なテンポの揺らぎやアクセント、アーティキュレーションの変化等で表情豊かに演出してみてください!
- ペダリング: 響きを豊かにする一方、速いパッセージで音が濁らないよう、極めて繊細で的確な操作(ハーフペダル等も含む)が不可欠です。
ロンド・カプリチオーソと他の作品との難易度比較
シューマン作曲「飛翔」:出典:YouTube
「ロンド・カプリチオーソ」とシューマンの「飛翔」どちらが難易度高い?
よく言われるのが「シューマン『幻想小曲集 Op.12』の『飛翔』とどちらが難しいか?」という問題。
これについては、「一概には言えない」というのが結論です。
要求される技術や音楽性も違いますし・・・。
全音の難易度では、「D」(中級上)に設定されていて、ロンド・カプリチオーソよりも低い難易度となっています。
2曲の違いを比較するとこんな感じです。
・飛翔: 情熱的な和音連打、厚い響き、内声処理、シンコペーションが特徴。和音を掴む力、腕を使った打鍵、複雑な声部処理、内面的な情熱の表現が求められます。
・ロンド・カプリチオーソ: 高速な指の動きの軽快さ・正確性、繊細なタッチ、跳躍の精度、構成力、持久力が特徴。指先の敏捷性、脱力、輝かしい音色、知的な構築力が必要。
指先の速さ・軽快さはロンド・カプリチオーソ、和音のパワー・情熱表現では飛翔という感じでしょうか。一般的に同等レベルの難曲とされていますが、得意不得意があるので、やはり一概には言えないと思います。
ショパン、リストなど同時代の作曲家の有名曲との比較
- ショパン「幻想即興曲」: 同等レベルか、やや取り組みやすいと感じる人も。ポリリズムが特有の難しさ。
- リスト「ラ・カンパネラ」: 明らかにこちらの方が難易度が高く、超絶技巧。
- ドビュッシー「アラベスク 第1番」: 技術的には易しいが、独特の音楽表現が難しい。
こうして見ると、中級から上級へのステップアップにおいて、技術と音楽性の両面を高いレベルで統合することが求められる重要なレパートリーだと思います。
こちらの記事も参考になりますよ!
ロンド・カプリチオーソに挑戦するには?
クラウディオ・アラウ演奏:出典:YouTube
どのくらいのレベルになったら挑戦できる?
目安として以下が挙げられます。
- 学習歴: 継続的・集中的学習5年以上(個人差大)。
- 既習曲: ソナチネアルバム修了レベル以上、バッハのインヴェンション・シンフォニア、チェルニー30番マスター・40番レベル、ショパンの比較的易しい作品(ワルツ、ノクターン等)を表現豊かに弾ける。
ピアノを始めて5年くらいで弾けたら、相当早いと思います。
事前に習得しておきたいテクニック
必要な基礎技術は以下です。といっても、あらゆる作品に対して共通しますが・・・。
ハノンなどの基礎練習は欠かせません!
効果的な練習方法と弾き方のコツ
もちろん、質の高い計画的な練習も不可欠ですよ。
ここまで弾けるようになる方には当たり前のことだと思いますが・・・。
- ゆっくり正確に: 最重要。非常に遅いテンポで一音ずつ指使い、リズム、タッチ等を耳で確認。完全に記憶してから徐々にテンポアップ。
- 分割練習: 難しい箇所を短い単位で徹底反復。弾けるようになったら前後と繋げる。
- 指の独立性トレーニング: ハノン等を活用し、指の強化と独立性を高める。
- 軽快なタッチ(leggiero)習得: 鍵盤表面近くを指先で素早く浅く弾くイメージ。脱力が必須。
- メトロノーム活用: 正確なテンポ感とリズム安定に有効。ゆっくり練習から段階的に使用。音楽性も忘れずに。
- 音楽表現を豊かに: 歌う、物語をイメージする、構成を分析し意識して弾き分ける。
- 参考演奏の活用: 多様な解釈を聴き比べ、分析的に聴いて自分の演奏のヒントを探す。最終的には自身の解釈で。
ロンド・カプリチオーソの理解を深めるための豆知識

ここからはロンド・カプリチオーソに関するちょっとした豆知識を紹介します。
頭の片隅にでも入れておくと、何かの時に役立つ「かも」しれませんよ。
ロンド・カプリチオーソは何歳の時の作品?
調べてみたところ、メンデルスゾーン19歳の頃の作品とのこと※。
10代にしてこの完成度は本当にスゴすぎますね。
文豪ゲーテが「モーツァルト以上の才能」と評価したのも頷けます。
※参考|ピティナ・ピアノ曲事典より
ロンド・カプリチオーソは何語?意味は?
イタリア語です。
Rondo(ロンド): 主要主題(A)がエピソード(B, C…)を挟んで繰り返される形式(A-B-A-C-A…)。
Capriccioso(カプリチオーソ): 「気まぐれな」「奇想的な」「奔放な」「自由な」といった意味。曲の性格を表し、形式感の中に自由な表現が含まれることを示唆します。
なのでタイトル全体としては「気まぐれで自由な雰囲気を持つ、ロンド形式の楽曲」という意味を表しています。
作曲の経緯や献呈相手について
ミュンヘンの才能ある女性ピアニスト、デルフィーネ・フォン・シャウロート嬢に献呈されました。彼女の優れた技巧を念頭に作曲したのかもしれませんね。
ロンド・カプリチオーソの楽譜(版)について
楽譜選びも重要。「原典版」と「実用版(校訂版)」があります。
原典版(ヘンレ、ウィーン原典など)
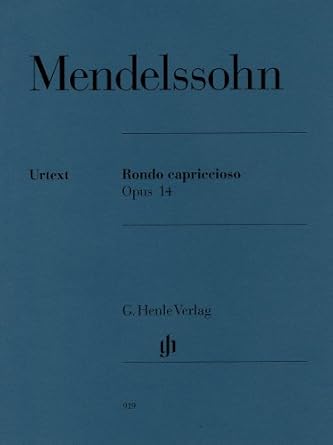
作曲家の意図に近い。校訂者の解釈は最小限。上級者向き。
実用版(全音、春秋社など)
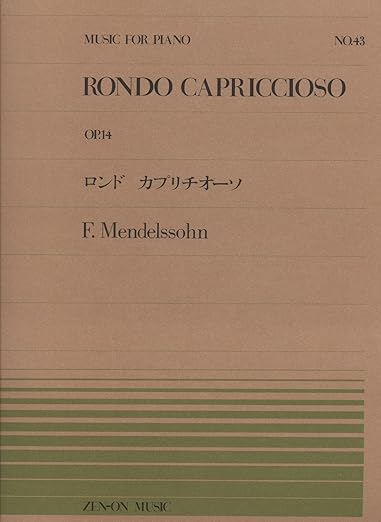
学習者向けに指使い等が補われ、解説付きも。中級者や指導者の参考に便利。校訂者の解釈が反映。
レベルや目的に合わせ、可能であれば複数の版を比較検討し、運指は自分の手に合うか吟味できればベストです。
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。
そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。
もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!
ロンド・カプリチオーソの難易度解説:まとめ
メンデルスゾーンの「ロンド・カプリチオーソ」は、輝かしい旋律と洗練された技巧で魅了する一方、演奏者には中級上~上級レベルの高い技術力、深い音楽的洞察力、豊かな表現力を要求する、挑戦しがいのある難曲です。
軽快かつ正確な指の動き、跳躍、タッチコントロール、ダイナミクス、構成力、持久力など、乗り越えるべき課題は多いですが、達成感は格別です。この曲のマスターは、ピアニストとしての総合的な成長に繋がります。
これからチャレンジする人にとって、少しでも参考になれば幸いです。
なお、「メンデルスゾーンについてもう少し知りたい!」という方はこちらの記事も参考になりますよ!