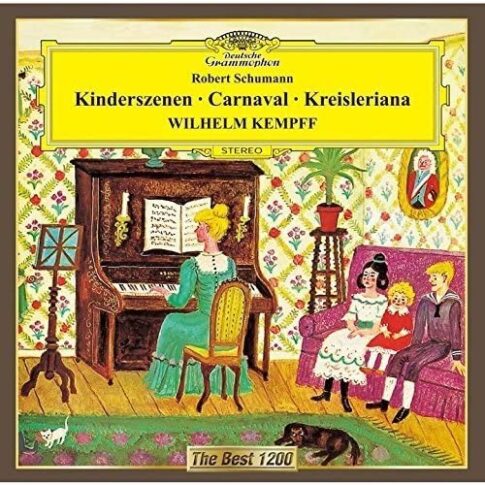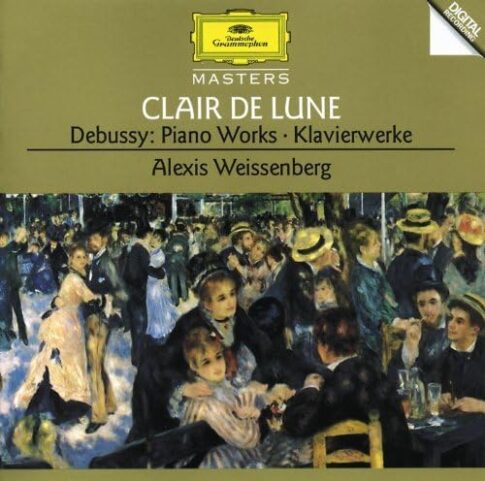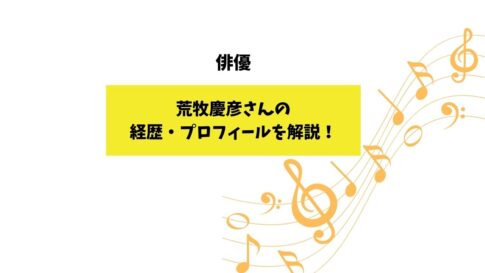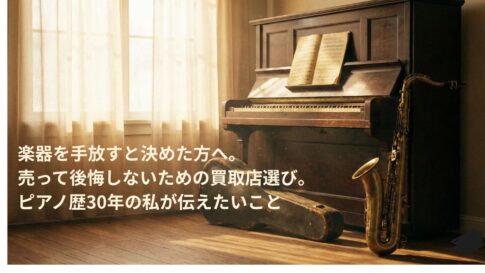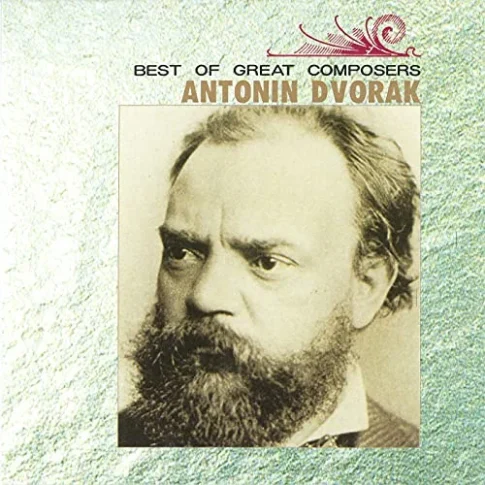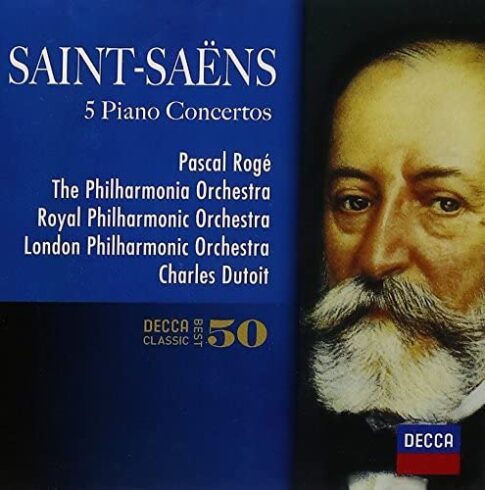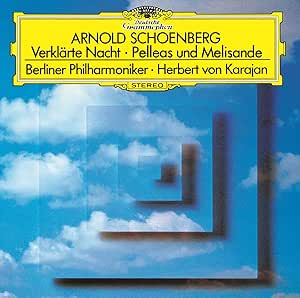この記事では、ロベルト・シューマン作曲「アラベスク」の難易度や演奏のコツを解説します。
ロマン派を代表する作曲家、ロベルト・シューマン。
彼のピアノ作品の中でも、特に優雅で美しい旋律を持つ「アラベスク」は、多くのピアノ学習者にとって憧れの一曲です。
この記事では、そんなシューマン アラベスクの魅力に触れながら、気になる難易度、そして美しい演奏に繋がる弾き方のコツや練習方法を、ピアノ中級者の方にも分かりやすく解説します。
「シューマンのアラベスク、弾いてみたいけど自分には難しいかな?」「どうすればもっと素敵に弾けるんだろう?」そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、30年以上ピアノに触れています(音大には行ってません)
単発でのレッスンにも対応
シューマン作曲「アラベスク」 とは?
出典:YouTube
シューマンによる「アラベスク」は、1838〜1839年に作曲されたピアノ独奏曲です。
タイトルの「アラベスク」は、本来アラビア風の唐草模様を意味しますが、音楽においては装飾的で優美な旋律を持つ楽曲を指すことがあります。
この曲は、シューマンが後の妻となるクララ・ヴィーク(のちのクララ・シューマン)への想いを馳せながら書かれたとも言われ、全体を通して軽やかで夢見るような、ロマンティックな雰囲気に満ちています。
しかし、ただ甘美なだけでなく、時折見せる情熱的な表情や、内省的な深みも併せ持っているのが、この曲の大きな魅力と言えるでしょう。
構成はロンド形式(A-B-A-C-A-コーダ)で書かれており、親しみやすい主要主題(A)が、性格の異なる中間部(B、C)を挟みながら繰り返されるため、比較的構成は掴みやすいかもしれません。
アラベスクを最初に音楽のモチーフにしたのは、シューマンだと言われています。
アラベスクの難易度は?レベルと技術的ポイント
出典:YouTube
では、具体的にシューマン アラベスクの難易度はどのくらいなのでしょうか?
一般的には、ピアノ中級~中級上レベルとされています。
実体験としてもそれくらいが妥当かなと。
ピアノ学習の過程で言うと、ソナチネアルバムを終え、ソナタアルバムに入るくらいのレベル感が一つの目安となるでしょう。有名なヘンレ社の難易度評価では、9段階中の「5~6(中級)」、全音ピアノピースでは難易度「D」となっています。
決して超絶技巧が求められるわけではありませんが、シューマン特有の書法による技術的、そして音楽的な課題が含まれています。
得意・不得意があるので、もっと難しく感じる人も結構いると思います。
アラベスクの技術的な難易度
実際に弾いてみて感じた技術的な難易度としては、以下のことが挙げられます。
ロマン派の情緒豊かなメロディーを、いかに表現できるかが重要かなと思います。
アラベスクの音楽的な難易度:シューマンらしい表現のポイント
シューマンとドビュッシーのアラベスク、どっちが難しい?
「アラベスク」と名の付くピアノ曲で、シューマンと並んで有名なのがドビュッシーの「2つのアラベスク」です。
では、シューマンとドビュッシーのアラベスクは、どっちが難しいのでしょうか?
これは一概には言えませんが、それぞれ異なる種類の難しさを持っていると言えます。
それぞれのポイントはこんな感じです。
結論!技術的にはシューマンの方が難しい!
シューマンは指のコントロールや内声の処理、歌わせ方に重点が置かれる一方、ドビュッシーは響きのコントロールや軽やかさ、ペダリングの技術がより求められる傾向に。
どちらが「難しい」と感じるかは、学習者の得意な技術や音楽的な好みによっても左右されるかなと思います。両方弾いてみることで、それぞれの作曲家の個性の違いを深く理解できるはずです。
あくまで個人的感想ですが、シューマンのアラベスクの方が技術的に難しいと思います。
ドビュッシーのアラベスクについては、こちらの記事を参考にしてください。
アラベスク演奏のコツ:美しい音色で弾きこなすために
出典:YouTube
ここでは、筆者がレッスンで受けたアドバイスをもとに、弾き方のコツを紹介します。
もちろん、これだけではありませんので、参考までにということで。
ポイントは3つ。
それぞれについて解説します。
指使いとタッチ:軽やかさと深みを両立させる
- 適切な指使い: 楽譜に書かれた指使いは基本ですが、自分の手の大きさや癖に合わせて、よりスムーズに弾ける指使いを研究しましょう。特にレガートで繋ぎたい部分や、跳躍箇所は入念な準備が必要です。
- メロディを際立たせるタッチ: 主旋律を担当する指には少し重みを乗せ、芯のある美しい音で歌わせることを意識します。他の声部はそれに対して軽く、邪魔にならないようにコントロールします。
- 伴奏系のタッチ: アルペジオや伴奏の音型は、軽やかで粒立ちの良いタッチを心がけましょう。ただし、軽すぎると音がかすれてしまうので、指先が鍵盤の底までしっかり届く感覚も大切です。
ペダリング:響きをコントロールする技術
- 濁らないペダル: シューマンの音楽では響きが重要ですが、ペダルを踏みすぎると和音が濁り、せっかくの美しい旋律線がぼやけてしまいます。基本は、和音が変わるタイミングで丁寧に踏み変えることを徹底しましょう。
- レガートペダル: 指だけではレガートで繋ぐのが難しい箇所で、ペダルが音を繋ぐ手助けをしてくれます。ただし、これも響きをよく聴きながら、必要最小限に留めるのがポイントです。
- 響きを作るペダル: 曲の雰囲気に合わせて、響きを豊かにしたり、逆にクリアにしたりと、ペダルで音色をコントロールすることも意識してみましょう。セクションごとにペダルの深さやタイミングを変える工夫も有効です。
構成と解釈:シューマンの世界観を表現する
- ロンド形式を意識する: 主要主題(A)は優しく語りかけるように、中間部(B)は少し情熱的に、あるいは翳りを帯びて、中間部(C)はより内省的に、といったように、各セクションの性格の違いを弾き分けましょう。主題が戻ってくるたびに、少しずつ表情を変えるのも面白いでしょう。
- テンポ・ルバート(揺らぎ): シューマンの音楽には、テンポを微妙に揺らす「ルバート」が効果的な場合があります。ただし、やりすぎると不自然になるので、あくまで音楽の流れの中で、自然な呼吸を感じさせるように用いるのがコツです。
- 自分なりのストーリーを: この曲からどんな情景や感情をイメージしますか?自分なりの解釈を持つことで、演奏に深みが生まれます。例えば、「優しい思い出」「心のときめき」「ふとした物思い」など、自由にイメージを膨らませてみましょう。
アラベスク効果的な練習方法
出典:YouTube
シューマン アラベスクをマスターするためには、計画的で質の高い練習が不可欠。
とくに、これからチャレンジする方は、以下のポイントに注意しながら練習してみてください!
- ゆっくり、片手ずつ
まずは非常にゆっくりなテンポで、片手ずつ確実に音符とリズム、指使いを確認しましょう。難しい箇所は、さらにテンポを落として反復練習します。 - 部分練習
通し練習だけでなく、苦手な箇所や特定の技術(アルペジオ、跳躍、多声部など)に焦点を当てた部分練習を重点的に行いましょう。数小節単位で区切り、できるようになったら少しずつ範囲を広げていきます。 - リズム練習
正確なリズム感を養うために、付点リズムや逆付点リズムなど、リズムを変えて練習するのも効果的です。 - メロディを歌う
旋律線を美しく歌わせるために、実際に声に出して歌ってみる、あるいは頭の中で歌いながら弾く練習は非常に有効です。 - 録音して客観的に聴く
自分の演奏を録音して聴き返すことで、弾いている時には気づかなかった課題(テンポの揺れ、ミスタッチ、音のバランスなど)を発見できます。 - 信頼できる楽譜を選ぶ
版によって指使いや強弱記号の指示が異なる場合があります。一般的には、原典版(Urtext)とされるヘンレ版やウィーン原典版などが、作曲家の意図に近いとされています。
ココナラでピアノレッスンを受けてみる!
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。
そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。
もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!
アラベスク(シューマン)の難易度・演奏のコツ:まとめ
シューマン アラベスクは、中級レベルのピアノ学習者にとって、技術的にも音楽的にも多くの学びを与えてくれる素晴らしい楽曲だと思います。
軽やかで美しい旋律の裏には、指の独立性や多声的な処理、そしてロマンティックな表現力といった、ピアノ演奏の基礎となる重要な要素が詰まっています。
今回ご紹介した難易度のポイントや弾き方のコツ、練習方法を参考に、ぜひこの魅力的な作品に挑戦してみてください。
最初は難しく感じる部分もあるかもしれませんが、一つ一つの課題を丁寧にクリアしていくことで、必ずあなたのピアノ演奏は向上し、シューマンの音楽の奥深さに触れる喜びを味わえるはずです。