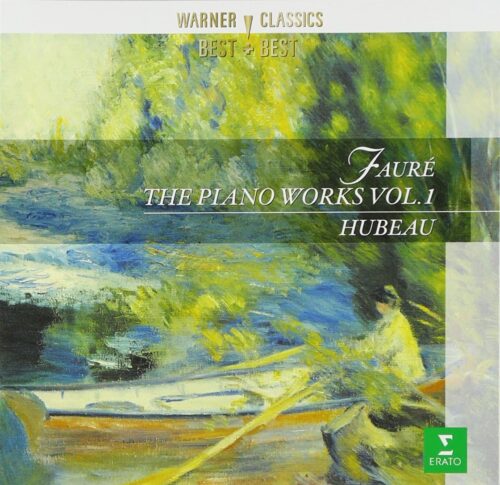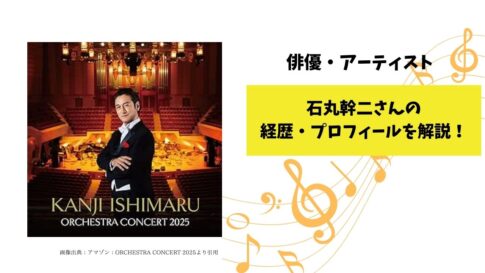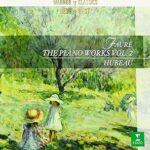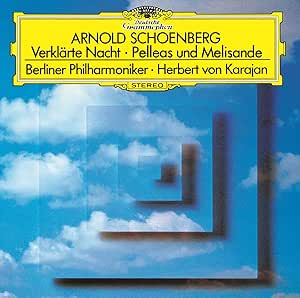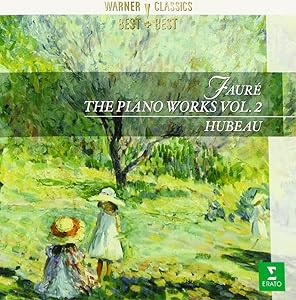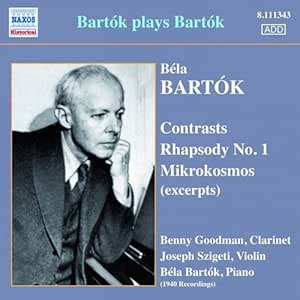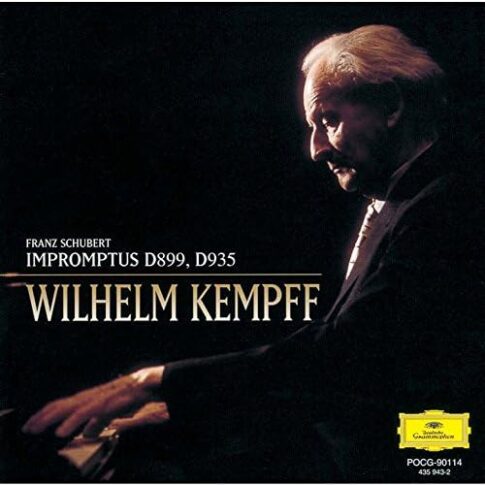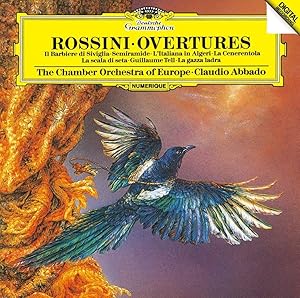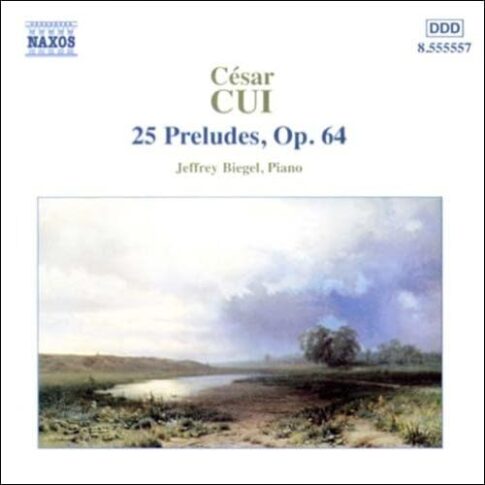今回は、フランス近代音楽の巨匠、ガブリエル・フォーレの「ノクターン」の難易度を1曲ずつ徹底解説します。
「フォーレのノクターンに挑戦したいけど、どの曲から弾けばいいの?」
「それぞれの曲の難易度や特徴が知りたい」
そんな疑問に答えられる記事です。
フォーレのノクターンは、ショパンとはまた異なる、繊細で奥深い詩情を湛えた美しい作品ばかり。
この記事を読めば、あなたにぴったりの1曲が見つかるはずです。
記事の前半では「フォーレについて」「ノクターンの難易度」を解説し、記事の後半では「おすすめランキング」やノクターンの楽譜を紹介します。
それぞれの解説には、素晴らしい演奏動画も紹介しているので、ぜひ聴いてみてください!
筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています(音大には行かず、哲学で修士号を取得)。
ガブリエル・フォーレについて

ガブリエル・ユルバン・フォーレ(1845年5月12日 – 1924年11月4日)は、フランスの作曲家、オルガニスト、ピアニストであり、教育者としても活躍しました。
サン=サーンスに師事し、その音楽はロマン派後期から近代フランス音楽への橋渡しと評価されています。
フォーレの作風は、優雅で洗練された旋律、精妙な和声、そして古典的な形式美を特徴とします。
特に声楽曲や室内楽曲、ピアノ曲に傑作が多く、「レクイエム」Op.48、「夢のあとに」Op.7-1、ヴァイオリンソナタ第1番 Op.13などが広く親しまれています。
また、パリ音楽院の院長を務め、モーリス・ラヴェルなど多くの後進を育てたことでも知られています。彼の音楽は、後の世代の作曲家たちに大きな影響を与えました。
フォーレ「ノクターン」の解説について
今回紹介するフォーレの「ノクターン」は、彼の生涯にわたって作曲された、全13曲からなるピアノ独奏曲集です。
1875年頃(20代後半)から1921年(70代後半)という長い期間に渡って書かれ、その作風も初期のロマンティックなものから、晩年のより内省的で深遠なものへと変化していきます。
まさに、フォーレのライフワーク的作品集と言えますね。
ショパンのノクターンが甘美で抒情的な旋律を特徴とするのに対し、フォーレのノクターンは、より複雑な和声、移ろうような転調、そして内面の感情の機微を丁寧に描き出す点に特徴があります。
聴き込むほどに、そして弾き込むほどにその魅力に引き込まれる、奥深い作品群と言えるでしょう。
ショパンの作品におとらず、本当に美しい作品ばかりです!!!
フォーレ「ノクターン」の難易度:第1期
ということで。少し寄り道しましたが、難易度解説です。
難易度判定については、一般的な意見➕筆者の体感なので、ほどほどに参考にしてくださればと思います。
結論として、「全体的な難易度は中級上レベル〜」かなと思います(技術的・表現力の面においてもです)。ツェルニー30番後半〜40番前半であれば十分挑戦できると考えて良いでしょう。
ソナチネ終盤〜モーツァルトのソナタなどに取り組んでいる方がチャレンジできるかなと。
フォーレの「ノクターン」は、作曲時期によって大きく3つの期に分けられます。
なので、初期の作品から順に紹介していきます。
この時期の作品は、比較的ロマンティックな雰囲気を持ち、ショパンやリストの影響も感じられます。
ノクターン第1番 変ホ短調 Op.33-1
- 作曲年: 1875年頃
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (6/10)
- 解説: フォーレのノクターン全集の幕開けを飾る作品。美しいメロディに乗せて、哀愁を帯びた旋律が歌われます。中間部では情熱的な盛り上がりを見せ、若きフォーレの瑞々しい感性が光ります。技術的には、左手のアルペジオの滑らかさ、右手声部の歌わせ方がポイントです。
出典:YouTube:Ichiro Kaneko様より
第2番 ロ長調 Op.33-2
- 作曲年: 1880〜81年頃
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
- 解説: 明るく華やかな雰囲気を持つノクターン。軽快なリズムと輝かしいパッセージが特徴的です。中間部は結構技術的な挑戦となります。音の粒立ちを揃え、華やかさの中にも品格を保つ表現が求められます。
出典:YouTube
第3番 変イ長調 Op.33-3
- 作曲年: 1883年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (6/10)
- 解説: 甘美でロマンティックな旋律が印象的な作品。フォーレらしい繊細な和声感が随所に現れます。比較的演奏しやすく、フォーレのノクターン入門としても人気があります。
豊かな表情で歌い上げてみましょう。
出典:YouTube
第4番 変ホ長調 Op.36
- 作曲年: 1884年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
- 解説: やや規模の大きなノクターンで、劇的な要素も含まれています。幅広い音域を使い、情熱的な高まりから静寂へと巧みに移行します。和声の色彩感が豊かで、まさに表現する力が問われ作品です。
出典:YouTube:福間洸太朗様より
第5番 変ロ長調 Op.37
- 作曲年: 1884年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (6/10)
- 解説: 穏やかで美しい旋律が魅力のノクターン。舟歌のようなゆったりとしたリズムに乗って、優美な音楽が展開されます。左手の伴奏形がやや複雑で、ペダリングにも工夫が必要です。全体的に落ち着いた雰囲気でまとめたい作品です。
出典:YouTube
フォーレの「ノクターン」の難易度:第2期
第2期に入ると、フォーレの作風はより個性的になり、内省的な深みを増してきます。和声はさらに洗練され、独自の語法が確立されていく時期です。
ノクターン第6番 変ニ長調 Op.63
- 作曲年: 1894年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)
- 解説: フォーレのノクターンの中でも特に有名な傑作の一つ。夢見るような美しい旋律で始まり、中間部では情熱的なクライマックスを築きます。後半の静寂の中に戻っていく部分の美しさは格別です。構成力があり、表現の幅も求められる難曲です。
出典:YouTube
第7番 嬰ハ短調 Op.74
- 作曲年: 1898年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (9/10)
- 解説: 非常に内省的で、深い悲しみを湛えた作品。複雑な対位法的な書法や、大胆な転調が特徴です。技術的にも難易度が高く、精神的な深みも要求される大曲です。フォーレのノクターンの頂点の一つとも言えるでしょう。
出典:YouTube
第8番 変ニ長調 Op.84-8
- 作曲年: 1902年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (6/10)
- 解説: このノクターンは、「8つの小品」Op.84の終曲として作曲されました。比較的簡潔な形式で書かれており、親しみやすい旋律を持っています。技術的にはそれほど難しくありませんが、フォーレらしい透明感のある響きを出すのがポイントです。
出典:YouTube
フォーレの「ノクターン」の難易度:第3期
晩年の第3期には、フォーレの音楽はさらに凝縮され、無駄のない、研ぎ澄まされた表現へと到達します。静けさの中に深い感情が込められた作品が多く見られます。
ノクターン第9番 ロ短調 Op.97
- 作曲年: 1908年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
- 解説: 晩年のフォーレ特有の、穏やかでありながらもどこか寂寥感を伴う美しいノクターン。静かな語り口の中に、深い感情が込められています。音色のコントロールと、内面的な表現が重要になります。フォーレ作品の中でも、近代的な響きが特徴的です。
出典:YouTube
第10番 ホ短調 Op.99
- 作曲年: 1908年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)
- 解説: 第9番と同時期に書かれ、同様に内省的な雰囲気を持つ作品です。比較的短い中に、フォーレらしい旋律と和声の美しさが凝縮されています。技巧的な難しさはそれほどありませんが、音楽的な深みを表現するには熟考が必要です。
出典:YouTube
第11番 嬰ヘ短調 Op.104-1
- 作曲年: 1913年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)
- 解説: 舟歌のようなリズムと、悲しみを帯びた美しい旋律が特徴です。晩年のフォーレらしい澄み切った響きと、簡潔ながらも深い情感が込められています。演奏には繊細なタッチと表現力が求められます。
出典:YouTube
第12番 ホ短調 Op.107
- 作曲年: 1915年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)
- 解説: 第一次世界大戦中に書かれた作品で、どこか不安げな影と、諦観(ていかん)のような静けさが同居しています。フォーレの晩年の書法の特徴である、簡潔さと凝縮された表現が見られます。深い精神性が要求される作品です。
出典:YouTube
第13番 ロ短調 Op.119
- 作曲年: 1921年
- 難易度: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (9/10)
- 解説: フォーレ最後のピアノ作品であり、彼の白鳥の歌とも言えるノクターン。これまでのノクターンの集大成とも言える内容で、非常に純粋で透明感のある響きを持っています。
技術的にも表現的にも極めて難易度が高く、深い理解と共感を持って臨むべき作品です。
出典:YouTube
フォーレ「ノクターン」おすすめランキング
全13曲の中から、目的別におすすめのノクターンを選んでみました。
こちらは、完全に筆者の独断によるものです・・・。
なので、ご自身のセンスにあった作品にチャレンジしてみてください!
初心者におすすめ
- ノクターン第3番 変イ長調 Op.33-3
- 理由: 甘美な旋律と比較的平易な技巧で、フォーレのノクターンの入門として最適です。ロマンティックな雰囲気を楽しめます。
- ノクターン第8番 変ニ長調 Op.84-8
- 理由: 「8つの小品」の一つで、簡潔ながらもフォーレらしい美しさを味わえます。他のノクターンに比べて取り組みやすいでしょう。
フォーレらしさを感じたいなら
- ノクターン第1番 変ホ短調 Op.33-1
- 理由: 初期作品ながら、後のフォーレを予感させる繊細な和声と美しいアルペジオが特徴的です。フォーレのノクターンの原点とも言えるでしょう。
- ノクターン第6番 変ニ長調 Op.63
- 理由: 中期の傑作で、フォーレの個性が際立っています。夢幻的な美しさと情熱的な展開は、まさにフォーレならではの世界観です。
音楽的に深い名作(2曲)
- ノクターン第7番 嬰ハ短調 Op.74
- 理由: 内省的で深遠な内容を持つ、フォーレのノクターンの中でも特に精神性の高い作品。聴き手にも演奏者にも深い感動を与えます。
- ノクターン第13番 ロ短調 Op.119
- 理由: フォーレ最後のピアノ曲であり、彼の音楽人生の到達点を示す傑作。技術的にも音楽的にも最高峰の作品の一つで、深い余韻を残します。
フォーレ「ノクターン」楽譜紹介3選
ここまで、フォーレの「ノクターン」の難易度について解説してきました。
どの作品も、フォーレらしい深淵さと、祈りのようなメロディーが、聴く人・演奏する人に感銘を与えてくれます。
そんな素晴らしい作品にチャレンジしてみたい人のために、楽譜紹介を紹介して、この記事を終わりにしたいと思います。
まずは手に入りやすいものから、購入してみてください!
全音版
安定の全音版。日本語解説付きなので、作品の特徴や背景など、理解しやすいと思います。
世界音楽全集版
フォーレ全集の第1巻に収録されています。楽譜が見やすく、演奏しやすい気がします。
ペータース社
海外版で取り組みたい方におすすめです。でも、お値段ちょっと高めです・・・。
フォーレ「ノクターン」難易度解説:まとめ
今回はフォーレ「ノクターン」の難易度を解説しました。
最後に、フォーレのノクターンを学ぶ上でのポイントをまとめますね。
- 全13曲、生涯にわたる作風の変化: 初期から晩年まで、フォーレの音楽的進化を辿ることができます。
- ショパンとは異なる魅力: 甘美さだけでなく、複雑な和声や内省的な深みが特徴です。
- 難易度は中級から上級: 初心者向けの簡単な曲は少なく、ある程度の技術と読譜力が必要です。
- 初期(1~5番)は比較的ロマンティック: ショパンの影響も感じられ、取り組みやすい曲も含まれます。
- 中期(6~8番)で個性が開花: 第6番、第7番は特に有名で、フォーレらしさが際立ちます。
- 後期(9~13番)は深遠な世界: 晩年の凝縮された表現と澄み切った響きが特徴です。
- ペダリングが重要: 繊細な響きを作るために、ペダルの使い方に細心の注意が必要です。
- 和声の理解を深める: フォーレ特有の移ろうような和声感を掴むことが、表現の鍵となります。
- 一曲一曲、じっくりと向き合う: 表面的な技巧だけでなく、作品の背景や内面的な感情を理解しようと努めましょう。
- まずは聴くことから: 様々なピアニストの演奏を聴き比べ、自分なりのイメージを膨らませるのがおすすめです。
フォーレのノクターンは、弾き込むほどにその奥深さに魅了される作品群です。
この記事が、読者の方にとって、挑戦の一助となれば幸いです。