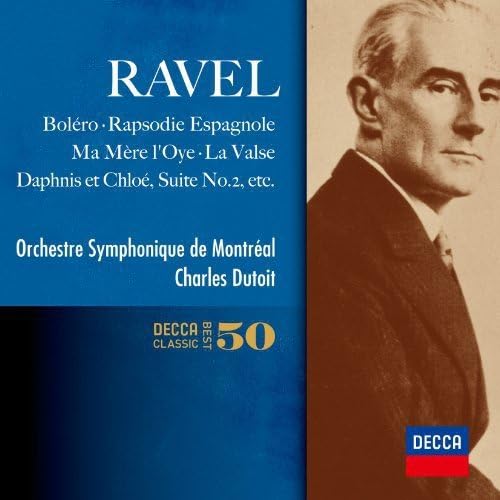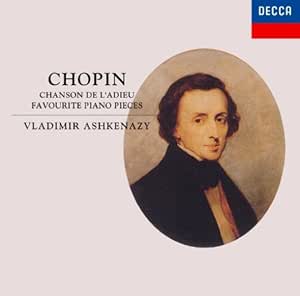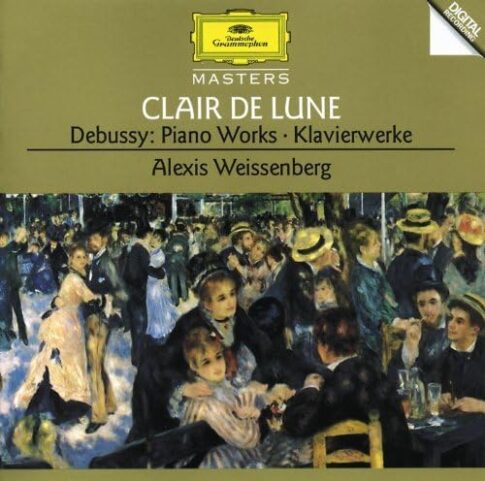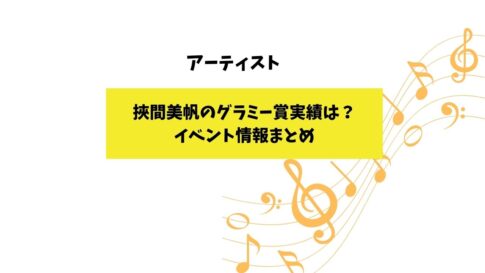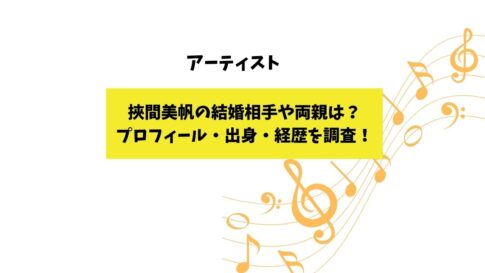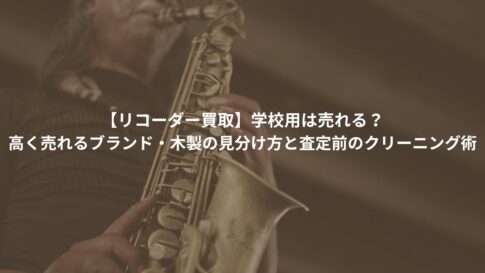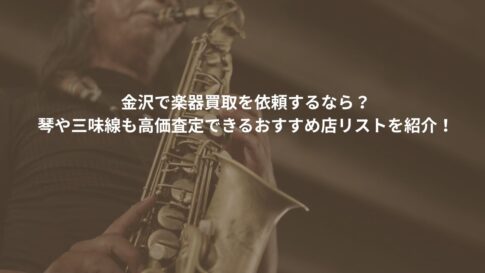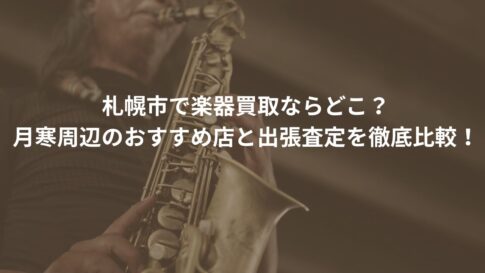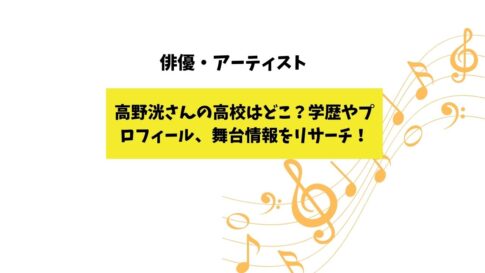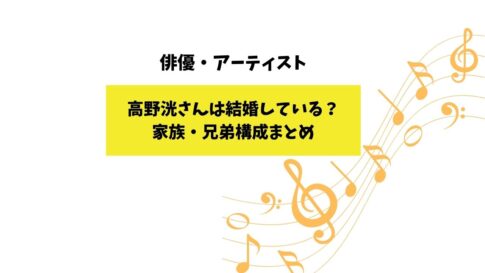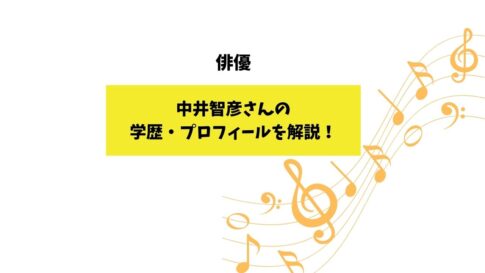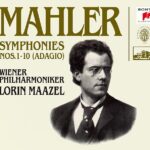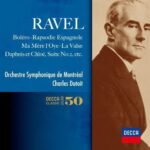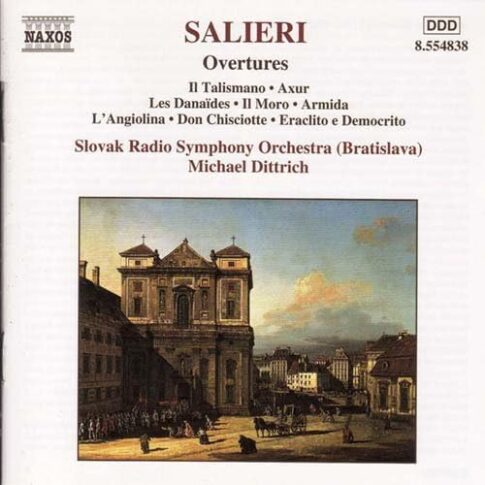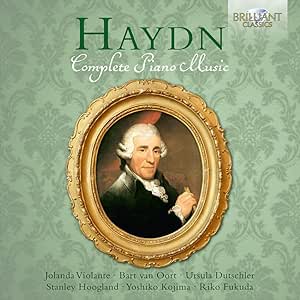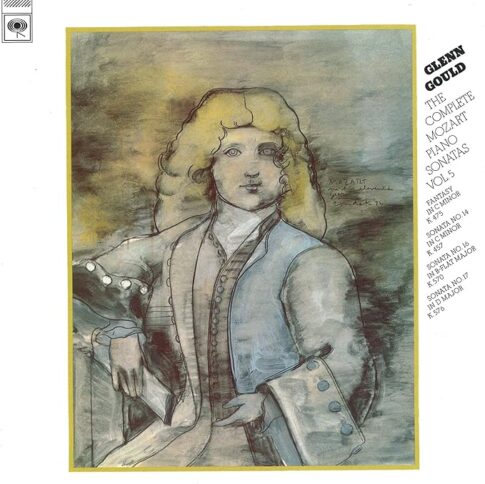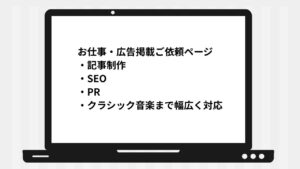クラシック音楽に燦然と輝く名曲『ボレロ』。
コンサートだけでなく、さまざまなメディアで使用されているので、1度は聴いたことのある方も多いのではないでしょうか。
しかし、『ボレロ』がどんな意味で、どのような経緯で作曲されたことはあまり知られていません。
そこで本記事では、ラヴェル作曲のバレエ音楽『ボレロ』について、おすすめ名盤を紹介しながらざっくり解説します。
これを読むだけで、結構詳しくなれると思いますので、ぜひ最後までお読みいただき、教養の一部として参考にしてくださいね。
本文の前に、ラヴェルについてちょっと詳しくなりたい方はまずコチラ。
その他の作品については、コチラも参考にしてください。
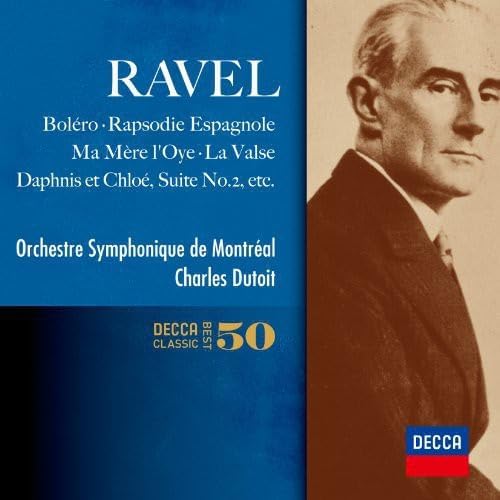
そもそも『ボレロ』って何?

クラシック音楽の中でも、特に人気の高い作品として知られていますが、「そもそもボレロって何?」という方も多いのではないでしょうか。
そこでまずは簡単に、「ボレロ」について解説します。
スペインのダンス音楽が起源
ラヴェルの作品といえば「ボレロ」を思い浮かべる人が多いですが、もとを辿ると、スペインのダンス音楽が起源と言われています。
また、そのダンスが軽やかだったことから、「飛ぶ」を意味するvolar(ヴォラール)から「ボレロ」と名付けられたと考えられているようです。
その始まりは18世紀後半とされ、1780年頃にセバスティアーノ・カレッソという自分が生み出しました。
そのため、ラヴェル以外の作曲家も「ボレロ」のタイトルで作品を残しています。
たとえば、ショパンのボレロはこんな曲。
基本的なボレロの形式は3拍子とされ、歌に合わせてカスタネットやギターでリズムを刻みダンスを踊ります。
当初はスペインでのみ用いられていたダンス音楽ですが、19世紀頃にヨーロッパ全土に広がりました。
また、キューバ発祥のルンバの起源とも言われています。
衣装じゃないの?
一般にボレロと聴くと、「衣装のことじゃないの?」と思われる方もいるのではないでしょうか。
その通り。ボレロは闘牛士が着ている上着のことを指します。
やがてそれが時代とともに変化し、現在のファッションに応用されました。
さらに遡ると、闘牛士の衣装は「ボレロを踊る際の踊り子たちの衣装」に由来するそうです。
こうしてみると、「ボレロ」はファンションからダンス、音楽までさまざまなシーンで使用されているのことがわかります。
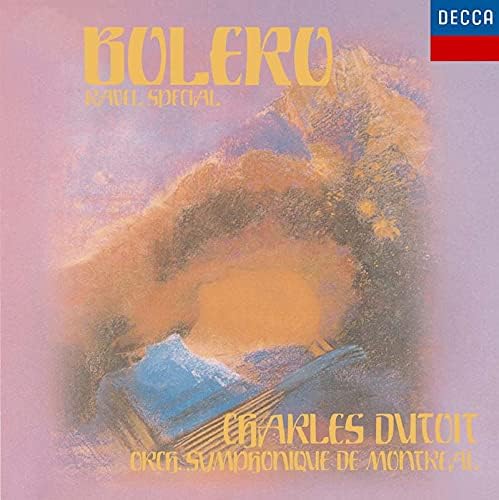
ラヴェルの『ボレロ』の解説

ではラヴェルの作品について見てみましょう。
ラヴェルは伝統あるボレロの形式をバレエという手段で表現しました。
バレエ音楽として生み出された
同じリズムが刻まれ、わずか2つのメロディーで構成された「ボレロ」。
本作は、1928年に作曲されたバレエ音楽です。
この時ラヴェルは53歳だったことを考えると、後期の傑作に分類されます。
「えっ?バレエ音楽なの?」と初めて聴いた方もいることでしょう。
この作品は、ロシア出身のバレリーナ兼役者だった、イダ・ルビンシュタインという女性の依頼で作曲されました。
イダ・ルビンシュタインは当時のバレエ界では異彩を放つ人物で、ドビュッシーやストラヴィンスキー、オネゲルといった作曲家も彼女のために作品を残しています。
初演は1928年11月22日に行われ、その演出は観衆に衝撃を与えたそうです。
作品のインスピレーションは工場見学から
2つのメロディがバリエーション豊かに展開する「ボレロ」。
ラヴェルは、一体でこのアイディアを思いついたのでしょうか。
これについてラヴェルは後年、「スペインで見た工場の風景にヒントを得た」と語ったそうです。
次から次へと同じものが規則正しく流れ、そして別のものに変化していく。そうした風景に、「ボレロ」の原型があるのかもしれません。
発表当時は『ファンタンゴ』のタイトルが予定されていましたが、のちに『ボレロ』に変更されました。
ちなみに、「ファンタンゴ」もスペインを起源とするダンス様式です。
いずれにしても、スペインにゆかりのあるラヴェルらしいネーミングと言えるでしょう。
バレエ「ボレロ」のあらすじ
本記事の冒頭で、「ボレロ」はバレエ音楽であると書きました。
わずか15分程度の短い作品ですが、そこには情熱的な物語が展開されています。
そんなバレエのあらすじを簡単に説明すると、
場所はセビリアにある町の酒場。酒場には踊り子用の舞台が設置されている。
その舞台に踊り子が1人。ダンスのために足慣らしを始める。
足慣らしのつもりが、徐々に盛り上がりを見せる客と踊り子。
ついには客と踊り子が一体となって踊り始める。
これが物語のストーリーです。
少しずつ楽器パートが重なり、最後に爆発的な盛り上がりをみせるのは、まさにこの作品の醍醐味でもあります。
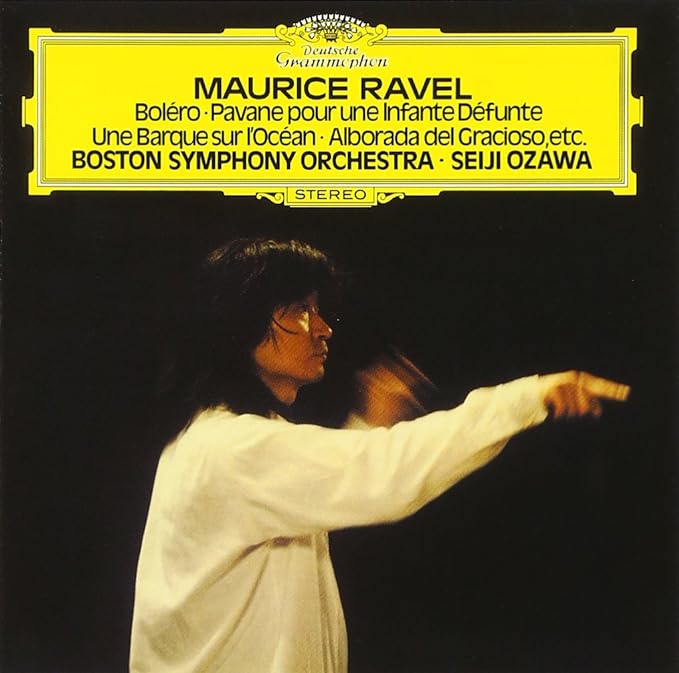
『ボレロ』の特徴や魅力について
では、この作品の特徴や魅力についてもざっくりと見てみましょう。
明日使えるかもしれない豆知識も紹介しています。
特徴と魅力その1、「たった一つのクレッシェンド」
冒頭からラストまで同じリズムが続き、2つのメロディのみで構成されている『ボレロ』。
これだけでもユニークな作品ですが、もっと興味深いことが『ボレロ』には隠されています。
みなさんは、音楽記号で「クレッシェンド」をご存じですか?
クレッシェンドとは「徐々に音を大きく」を支持する際に用いる音楽記号です。
「<」☜こういうやつ。音楽の授業できっと見たことがあると思います。
本来であれば、作品のさまざまな箇所で使われる記号ですが、『ボレロ』では最初から最後まで、「なが〜〜〜〜いクレッシェンド1つ」のみなんです。
そのため、少しずつ音楽が大きくなっていくことから、「世界一長いクレッシェンド」とも言われています。
特徴と魅力その2、「楽器のオンパレード」
『ボレロ』には、多種多様な楽器が用いられています。
なかでも管楽器が豊富に使われおり、楽器の名前を覚えるにはうってつけの作品と言われています。簡単に登場順番を書いてみると、こんな感じです。
1、スネアドラム
2、フルート
3、クラリネット
4、ファゴット
5、Esクラリネット
6、オーボエモダーレ
7、フルートとトランペット
↓
ラスト
このように、楽器が徐々に追加されていき、爆発的なラストを迎えます。
特徴や魅力その3、繰り返しがクセになる
『ボレロ』は非常に単純な旋律とリズムがほとんど無限に繰り返されることで知られています。
全曲を通じて同じ旋律が反復されることで聴衆は緊張と興奮を感じ、次第に気持ちの高鳴りはMAXへ。
またリズムにも非常に中毒性があり、耳に残りやすく。
これは踊りや振り付けを盛り上げます。
今でこそ、魅力満載の『ボレロ』ですが、初演を聴いた観衆から「この曲は異常だ」との手厳しいコメントがあったとか。これに対して当のラヴェルは、「この曲をよく理解しているね」と応じたと言われています。
『ボレロ』のおすすめ聴き比べ3選
最後に『ボレロ』の聴き比べをお楽しみください。
指揮者やオーケストラが違うだけで、作品の魅力は大きく変わることが実感できるはずです。
歴史的名盤の演奏もあるのですが、今回はなるべく録音が新しく、聴きやすい演奏を取り上げてみました。
聴き比べその1、ヴァレリー・ゲルギエフ指揮
1つ目は世界的指揮者ヴァレリ・ゲルギエフ指揮。
表現力豊かなゲルギエフの『ボレロ』は、最後まで繊細さと押さえ込まれたエネルギーの爆発力が魅力です。指揮棒にも注目!!!(爪楊枝???)
聴き比べその2、グスターボ・ドゥダメル指揮
2つ目は、ベネズエラ出身の若き天才指揮者・グスターボ・ドゥダメルの演奏。
ウィーンフィルとの共演ですが、堂々とした指揮ぶりが良いですね。
冒頭のフルートの音色がはっきりしていて、物語の始まりを告げるようです。
聴き比べその3、アロンドラ・デ・ラ・パーラ指揮
ラストはメキシコ出身の指揮者アロンドラ・デ・ラ・パーラ指揮。
『ボレロ』が持つ優雅さが存分に発揮された演奏です。
しかし、カッコ良い指揮者ですね。
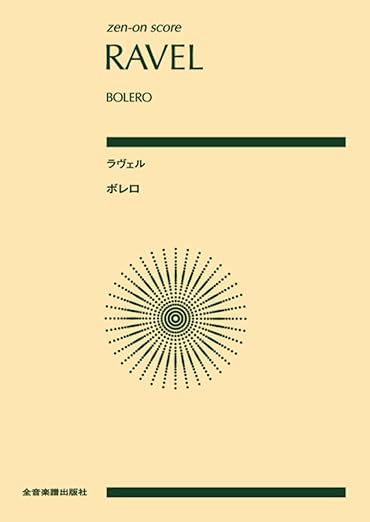
気になった曲を、プロの演奏で楽しもう
この記事で気になった作品、耳でも味わってみませんか?
Amazon Music Unlimitedなら、クラシックの名曲がいつでも聴き放題。
名演奏を聴き比べたり、新たなお気に入りを見つけたりと、楽しみ方は自由自在!
今なら30日間無料体験も実施中。ぜひ気軽にクラシックの世界をのぞいてみてください。
>>Amazon Music Unlimitedでクラシックを聴いてみる
『ボレロ』の解説まとめ
ということで、今回は『ボレロ』の特徴や魅力についてざっくりと解説しました。
クラシック音楽の中でも、とくに有名な作品ですので、きっと飽きずに最後まで聴けるはずです。
指揮者ごとの違いを探してみるのも、クラシック音楽の楽しさの1つ。
ぜひご自身でお気に入りの演奏を見つけてみてください!
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。
クラシック音楽を聴き始めた方のために
ここまでお読みいただきありがとうございました。
この記事をご覧になった方の中には、
最近クラシック音楽に興味を持たれた方もいらっしゃると思います。
そんな方に向けた「クラシック音楽聴き方ガイド」記事を作成しました。
よろしければそちらもご一読いただければ幸いです。