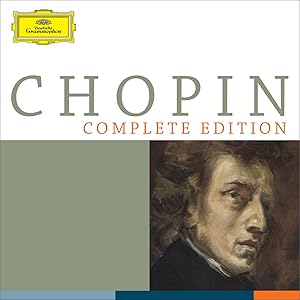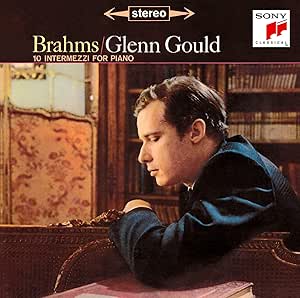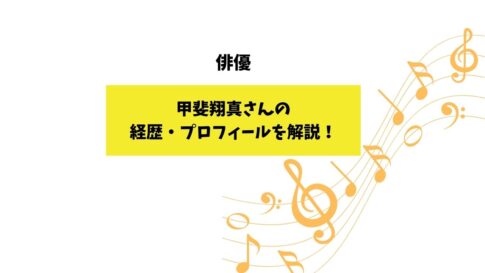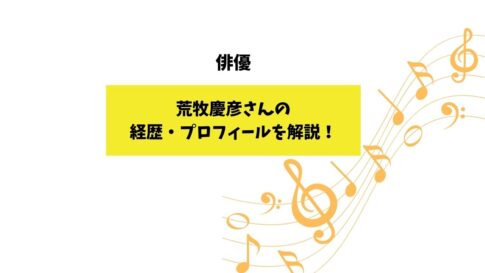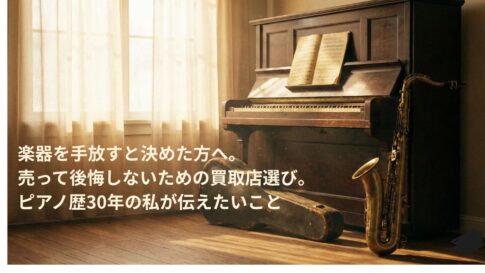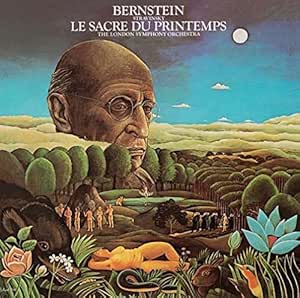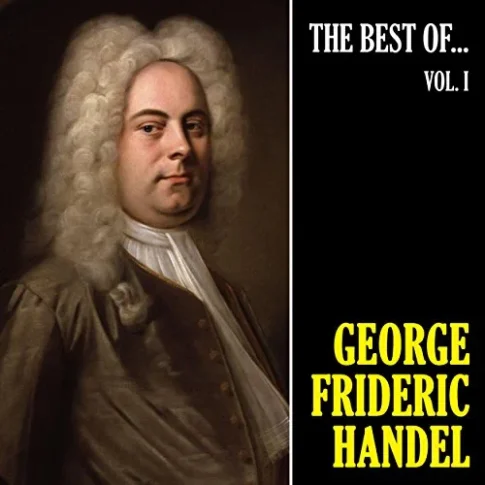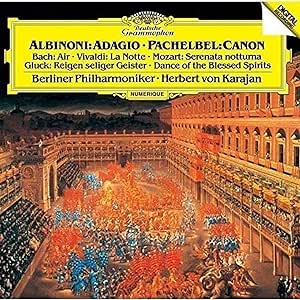この記事では、ブラームスの間奏曲(118-2)の難易度を解説します。
甘美で切ないメロディが心に響く、ブラームスの最高傑作の一つ、ピアノ小品 Op.118。
その中でも特に人気の高い第2番「間奏曲 イ長調」は、多くのピアノ学習者が憧れる名曲です。しかし、「自分にも弾けるだろうか?」「中級レベルではまだ早いのでは?」と、挑戦をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、ブラームスの間奏曲 Op.118-2の難易度を、ピアノ中級レベルの方にも分かりやすく、具体的なポイントを挙げながら徹底解説します。
この記事でわかること
読み終わる頃には、きっと「弾いてみたい!」という気持ちが高まっているはずなので、ぜひ最後までご一読ください!
筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、30年ほどピアノを弾いています(音大には行ってません)。
心を掴む名曲、ブラームスの間奏曲 Op.118-2とは?
出典:YouTube
ブラームス晩年の境地「6つのピアノ小品 Op.118」
ヨハネス・ブラームス(1833-1897)は、バッハ、ベートーヴェンと並び称されるドイツ音楽の巨匠であり、ロマン派音楽を代表する作曲家の一人です。
「6つのピアノ小品 Op.118」は、ブラームスの最終期にあたる1893年に作曲されました。
この時期のブラームスは、交響曲などの大規模な作品から離れ、ピアノ曲や室内楽といった、より内省的で私的な表現に向かった時期でもあります。
全6曲からなるこの曲集は、晩年のブラームスが到達した円熟の境地、深い叙情性、そして緻密で完成度の高い書法で描かれています。
第1番の間奏曲から始まり、バラード、ロマンス、そして終曲の間奏曲まで、各曲が独自の情念を秘めながら、全体として一つの統一された世界観を形作っています。
その中でも第2番の間奏曲 イ長調は、特に親しみやすい旋律と感動的な構成で、単独でも頻繁に演奏される人気の高い作品です。
本作は、敬愛するクララ・シューマン(シューマンの妻)に献呈されました。ブラームスの最後から2番目の作品でもあります。
ブラームスの生涯についてはこちらの記事を参考にしてください!
ブラームスの間奏曲(Op.118-2)の魅力
ブラームスの間奏曲 Op.118-2は、A-B-A’という分かりやすい三部形式で書かれています。
- A部分(イ長調): 冒頭から奏でられる、息の長い甘美な旋律は、一度聴いたら忘れられないほど魅力的。どこか懐かしく、温かい郷愁を感じさせるメロディ。
- B部分(嬰ヘ短調): 中間部は、情熱的でやや翳りのある嬰ヘ短調に転じます。
ここでは、内なる声が切々と歌い上げるような、よりドラマティックな表情を見せます。 - A’部分(イ長調): 再び冒頭の旋律が回帰しますが、単なる繰り返しではなく、より深みを増した響きで静かに曲を閉じます。
穏やかな優しさの中に、ふと寂しさや情熱が顔を覗かせるような、複雑で奥深い魅力が、本作から感じられるはずです。
ブラームスの間奏曲 Op.118-2の難易度は?中級者には難しい?
出典:YouTube
結論:中級の上~上級への入り口
一般的に、ブラームスの間奏曲 Op.118-2は「中級の上」から「上級への入り口」レベルに位置づけられており、筆者の経験からも「そのくらいかな」というのが感想です。
ピアノのレベル分けは様々ですが、例えば、ソナチネアルバムを終え、ショパンのワルツ(例:Op.64-1「小犬のワルツ」)やノクターン(例:Op.9-2)、ドビュッシーの「アラベスク第1番」や「月の光」などに挑戦している、あるいは終えたくらいのレベルの方なら、次に取り組む候補として考えても良いと思います。
ただ、ブラームス特有の重厚な和音、ポリフォニック(多声的)な書法、そして何よりも深い音楽表現が求められるので、中級レベルの中でも難しく感じる人も多いかもしれません。
こちらの記事も参考になると思います。
他の有名曲との難易度比較
より具体的にイメージするために、他の有名なピアノ曲と難易度を比較してみましょう。(※あくまで目安です)
- ショパン「ノクターン Op.9-2 変ホ長調」: 技術的にはノクターンの方が易しいと感じるかもしれませんが、Op.118-2は和声の複雑さ、声部の弾き分け、表現の深さでより高度な要求をします。
- ドビュッシー「月の光」: 有名な「月の光」も表現力が重要ですが、Op.118-2はより緻密な声部処理とダイナミクスのコントロールが求められます。技術的な難所もOp.118-2の方が多いでしょう。
- ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 Op.13『悲愴』第2楽章」: 美しい緩徐楽章ですが、Op.118-2の方が和声感が複雑で、内声の処理やペダリングはより繊細さが要求されます。
こうしてみると、ブラームスの間奏曲 Op.118-2は、技術的な側面と音楽的な側面の両方で、中級レベルから一歩進んだ課題を持っていることが分かりますね。
ここが難しい!ブラームスの間奏曲の課題
では、具体的にどのような点が難しいのでしょうか?主なポイントを4つに絞って解説します。
① 幅広い和音とアルペジオ
② 声部(ポリフォニー)の弾き分け
③ 豊かな表現力とダイナミクスの制御
④ 効果的なペダリング
1つずつ見てみましょう。
ブラームスの間奏曲の課題① 幅広い和音とアルペジオ
ブラームスのピアノ曲の特徴の一つが、厚みのある和音と広い音域にわたるアルペジオです。Op.118-2も例外ではありません。
- 広い和音: 特に左手には、1オクターブを超える10度の和音が頻繁に登場します。手が小さい方にとっては、これらの和音を正確に掴み、かつレガートで繋ぐのが難しい場合があります。無理に掴もうとせず、手首を柔軟に使ったロール奏法(アルペジオのように少しずらして弾く)で対応してみましょう。
- 分散和音・アルペジオ: 右手にも左手にも、広い音域を滑らかに駆け上がる、あるいは下降する分散和音やアルペジオが多く見られます。これらのパッセージを均一な音量で、かつ音楽的な流れを止めずに弾くには、指の独立性と手首の柔軟な動きが不可欠です。
ブラームスの間奏曲の課題② 声部(ポリフォニー)の弾き分け
このブラームスの間奏曲では、複数の独立した旋律(声部)が同時に進行するポリフォニックな書法が多く用いられています。特にA部分では、右手で主旋律を歌わせながら、同時に内声の動きも美しく響かせる必要があります。
- 主旋律の際立たせ: 複数の音が同時に鳴っている中で、聴かせたい主旋律を他の声部よりも少しだけ強く、しかし自然に浮き立たせる技術が必要。指先のコントロールと、各声部の役割を意識することが重要です。
- 内声の処理: 主旋律を支える内声も、単なる伴奏ではなく独自の歌を持っています。内声が埋もれてしまわないよう、バランス良く響かせる必要があります。
- ペダリングとの関係: ペダルを踏むと響きは豊かになりますが、複数の声部が濁って混ざり合ってしまう危険性もあります。各声部をクリアに保ちながら、豊かな響きを作るための繊細なペダリングが求められます。
声部の弾き分けは、バッハの作品などで訓練を積んでいると取り組みやすいかもしれません。
ブラームスの間奏曲の課題③ 豊かな表現力とダイナミクスの制御
技術的な課題をクリアした上で、この曲の核心とも言えるのが音楽表現の深さです。
- 歌心(カンタービレ): ブラームスが求めたのは、器楽でありながらも「歌う」ような表現です。特にA部分の旋律は、息の長いフレーズ感を意識し、心を込めて歌うように演奏する必要があります。
- アゴーギクとルバート: 楽譜には書ききれないテンポの揺れ(アゴーギク)や、表情豊かなテンポの伸縮(ルバート)を、音楽の流れの中で自然に取り入れることが、この曲の魅力を引き出す鍵となります。ただし、やりすぎは禁物。
- ダイナミクス: pp(ピアニッシモ)からff(フォルティッシモ)まで、幅広いダイナミクスが要求されます。特にB部分の情熱的な盛り上がりや、A’部分の静謐な終わり方など、場面に応じた音量と音色の変化を滑らかにコントロールする必要があります。
楽譜の指示を読み解くだけでなく、曲全体の構成や感情の流れを理解し、それを自身の音で表現する力が試されます。
ブラームスの間奏曲の課題④ 効果的なペダリング
ペダリングは、この曲の響きを豊かにし、レガートな旋律線を助ける上で非常に重要ですが、同時に難しさも伴います。
- 和声の濁りを避ける: 前述の通り、ポリフォニックな部分や和音が変化する箇所でペダルを踏みすぎると、響きが濁ってしまいます。和声の変化に合わせてペダルを細かく踏み変える技術が必要です。
- 響きのコントロール: ハーフペダル(ペダルを半分だけ上げる)や、音を弾いた直後に踏むシンコペーテッドペダルなどを駆使して、響きの量や長さを繊細にコントロールすることが求められます。
- 耳で判断する: 楽譜のペダル記号はあくまで目安です。最終的には自分の耳で響きをよく聴き、ピアノの状態や部屋の響きに合わせて最適なペダリングを見つける必要があります。
こちらの作品と比べてみるのも勉強になります。
中級者がブラームスの間奏曲 Op.118-2を攻略するための練習方法
出典:YouTube
この美しくも手強いブラームスの間奏曲を自分のものにするためには、効果的な練習が不可欠です。
ブラームスの間奏曲の練習法①:焦らずじっくり取り組む心構え
大切なのは、焦らないこと(どんな作品にも言えますが)。
このレベルの曲になると、すぐに全体が弾けるようになるわけではありません。
譜読みには時間をかけ、音やリズム、指示記号を一つひとつ丁寧に確認しましょう。完成を急ぐあまり、基礎的な部分をおろそかにしないことが重要です。
部分練習を根気強く続け、少しずつ全体像を組み立てていくイメージで取り組んでみてください!
ブラームスの間奏曲の練習法②効果的な部分練習のポイント
やみくもに全体を繰り返すのではなく、難しい箇所を特定し、集中的に練習することが効率的です。
- 難所特定: 幅広い和音、指がもつれやすいアルペジオ、声部の弾き分けが必要な箇所、跳躍が多い箇所などをピックアップします。
- ゆっくり練習: これらの難所は、まず非常にゆっくりなテンポで、一音一音確かめながら練習します。正確な音、リズム、指使い、そして脱力したタッチを意識しましょう。メトロノームを使うのも効果的。
- 片手練習・声部練習: 右手だけ、左手だけで完璧に弾けるように練習します。ポリフォニックな箇所は、主旋律だけ、内声だけ、バスだけ、といったように声部ごとに取り出して練習するのも有効です。
- キャラクターの意識: A部分の穏やかで歌うような雰囲気、B部分の情熱的でドラマティックな雰囲気など、セクションごとのキャラクターの違いを意識して練習します。
ブラームスの間奏曲の練習法③表現力を高めるために
技術的な練習と並行して、音楽的な表現力を磨くことも重要です。
- 楽譜の読み込み: 強弱記号(p, fなど)、発想記号(dolce, espressivoなど)、アーティキュレーション(スラー、スタッカートなど)の意味を理解し、それらをどのように音にするか工夫する。
- 聴くこと: 様々なピアニストによるブラームスの間奏曲 Op.118-2の演奏を聴き比べてみましょう。表現の仕方やテンポ設定など、多くのヒントが得られます。
- 録音・客観視: 自分の演奏を録音して聴き返すことは、客観的に課題を発見する上で非常に有効です。弾いている時には気づかなかったバランスの悪さやテンポの乱れなどが分かることがあります。
- 背景理解: ブラームスという作曲家や、この曲が作られた背景について少し調べてみるのも、表現の助けになるでしょう。
ブラームスの間奏曲:おすすめの楽譜と参考資料
楽譜は、学習の質を左右する重要な要素です。ブラームスの間奏曲 Op.118-2を練習する際には、以下の点を考慮して楽譜を選びましょう。
ブラームスの間奏曲:原典版
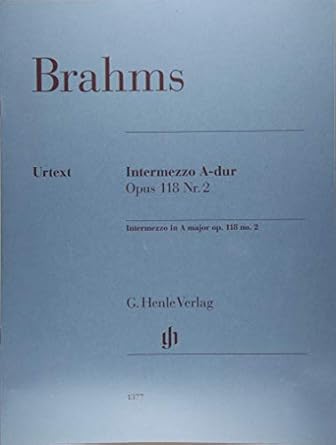
作曲者の意図に最も近いとされる原典版(ヘンレ版、ウィーン原典版など)がおすすめです。余計な解釈や修正が加えられていないため、より深く作品を理解する助けになります。
ブラームスの間奏曲:春秋社版
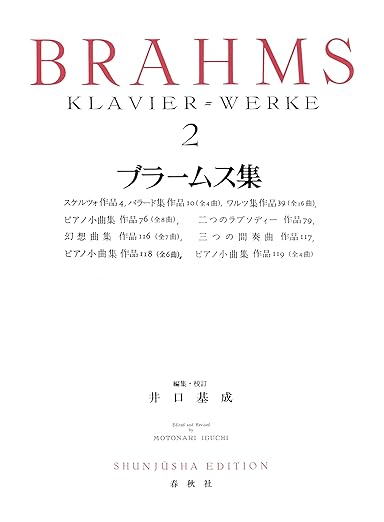
原典版が入手しにくい場合や、解説が欲しい場合は、信頼できる音楽学者やピアニストが校訂した版を選びましょう。運指やペダリングの提案が参考になります。
個人的には春秋社版が見やすいのおすすめです。
参考になる書籍やウェブサイト
より深く学びたい場合は、以下の資料も参考にしてみてください。
- ブラームスの伝記や作品解説書
- ピアノ演奏法に関する書籍
- 信頼できる音楽情報サイト(例:ピティナ・ピアノ曲事典など)
参考|ピティナ・ピアノ曲事典
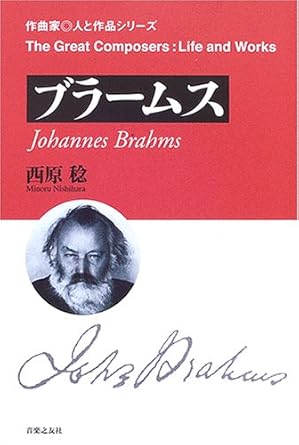
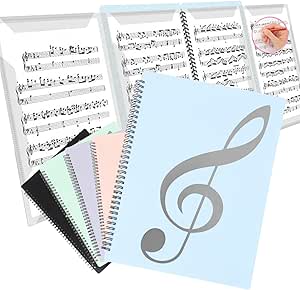
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。
そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。
もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!
ブラームスの間奏曲(118-2)の難易度解説:まとめ
ブラームスの間奏曲 Op.118-2は、その甘美な旋律と深い情感で多くの人々を魅了する、ピアノ音楽の宝物のような作品です。
難易度としては中級の上から上級への入り口に位置し、幅広い和音、ポリフォニックな書法、豊かな表現力、繊細なペダリングなど、技術的にも音楽的にも挑戦しがいのある課題が含まれています。
しかし、適切な練習方法で一つ一つの課題に丁寧に取り組めば、中級レベルの学習者でも必ず弾きこなせるようになるはずです。
焦らず、じっくりと曲に向き合い、部分練習を大切にしてください。