今回はイタリア出身の大ヴァイオリニスト、パガニーニの代表曲を紹介します。
あまりクラシック音楽を聴かない方はご存じないかもしれませんね・・・。
しかし近年では、ピアノ曲『ラ・カンパネラ』が広く知られているほか、
波乱の人生を描いた映画も公開されるなど、徐々にその人気が高まりつつあります。
18世紀末のイタリアに生まれ、
「悪魔に魂を売った」とまで称されたヴィルトォーゾ・パガニーニ。
その類い稀なるヴァイオリンの技術は、フランツ・リストをはじめ、同時代の多くの音楽家に多大な影響を与えました。
ということで、今回はパガニーニの代表曲6選をざっくりと紹介します。
「こんな曲もあるのね」という感じで、いつもながらお読みいただければ幸いです。
また、独断と偏見による最高傑作も挙げていますので、
そちらもぜひ参考にしてください!
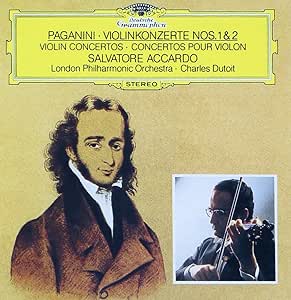
ちなみに、パガニーニの生涯についてはコチラで紹介しています。
1ヶ月無料体験!解約はいつでもOK
amazon music unlimited
パガニーニの代表曲6選

5歳からヴァイオリンを弾きはじめ、13歳で「学ぶべきことがなくなった」ほどの天才パガニーニ。その超絶的なヴァイオリン技術は、聴衆を驚かせたのみならず、ある意味で「恐怖」をもたらすほどだったと言います。
そんなパガニーニの代表曲には『ラ・カンパネラ』や『24の奇想曲』などがありますが、
じつはヴァイオリン作品のみならず、意外にもギター曲も多く手がけています。
そこで以下では、ギター曲を含む、パガニーニの代表曲を6曲お送りします。
どの作品も軽快かつ重厚な作品ですので、ぜひお楽しみください!
パガニーニの代表曲その①、モーゼ幻想曲
1曲目は、1819年頃に作曲された管弦楽曲『モーゼ幻想曲』です。
メロディアスな冒頭のフレーズが聴く人の心を一気に捉える名作。
『モーゼ幻想曲』とは通称で、
正式には「『汝の星をちりばめた王座に』による序奏、主題と変奏曲」です。
ちょっと長いタイトルですが、
本作は盟友ロッシーニの同名タイトルのオペラからインスピレーションを受けて作曲されたと言われています。
しかし、これについては正確なことはわかっていません。
ただ、ロッシーニとは長い友人関係だったことを考えると、
さもありなんという感じかもしれません。
演奏機会は少ないものの、パガニーニの創造性が楽しめる1曲となっています。
演奏時間は6分程度です。
パガニーニの代表曲その②、ヴェニスの謝肉祭
イタリア・ジェノバ生まれのパガニーニ。
そんな彼には、生粋のイタリア人の血が流れていたに違いありません(当時は別々の国ですが)。
本作は、パガニーニが1829年に作曲したヴァイオリン独奏用の変奏曲。
主題にはナポリの民謡がモチーフとして用いられ、
演奏会でも一際華やかな作品として迎え入れられています。
作曲当初、パガニーニは本作のタイトルを『ナポリのカンツォネッタ「いとしのマンマ」によるアダージョ・カンタービレと変奏曲』と題しました。
でもきっと長かったのでしょう。パガニーニの死後は、現在のタイトルとなりました。
動画で演奏しているのは、2013年の映画『パガニーニ 愛と狂気のヴァイオリニスト』でパガニーニ役を演じたデイヴィッド・ギャレットです。

パガニーニの代表曲その③、ヴァイオリンとギターのための6つのソナタ
ヴァイオリンのほかに、パガニーニはギター曲においても優れた作品を残しています。
前回の記事で書いたように、パガニーニの楽器キャリアはマンドリンから始まりました。
まもなくして、ヴァイオリンへと転向したパガニーニですが、
ギターへの愛着は生涯続き、本作が作曲されました。
『ヴァイオリンとギターのための6つのソナタ』は、
1805年から1809年に作曲された初期の作品ではあるものの、
2つの楽器は見事に呼応しており、その完成度の高さが伺えます。
また、パガニーニは『ギター四重奏曲』を作曲するなど、
ギター曲の作曲に熱心に取り組んでいます。
繊細なギターの音色と、ヴァイオリンの力強さが見事に融合した1曲です。
パガニーニの代表曲その④、ヴィアオリン協奏曲第1番
パガニーニが持つ華やかさ、絢爛さが見事に表現された代表作です。
ヴァイオリン協奏曲というジャンルに馴染みのない方でも、
きっと聴きやすい作品だと思います。
テーマも明快で、いかにも「イタリアらしい」爽快さがあります。
本作は1817年から1818年にかけて作曲され、パガニーニのヴァイオリン協奏曲として初めて出版された作品でもあります。
現在でも演奏機会が非常に多く、
とくに若手ヴァイオリニストにとっては、避けて通ることのできない作品と言えるでしょう。
また一説によれば、本作もロッシーニのオペラから大きな影響を受けているそうですよ。
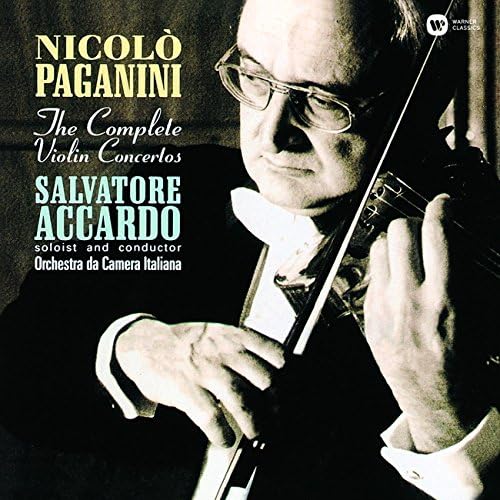
代表曲その⑤、ヴァイオリン協奏曲第4番
パガニーニ最後のヴァイオリン協奏曲です。
詳しい作曲年代はわかっていませんが、友人に宛てた手紙から、1830年ごろに書かれた作品と考えられています。
1番とはだいぶ曲調がことなり、こちらは「勇ましい」作品が特徴です。
パガニーニの死後、楽譜は息子のアキリーノに託されましたが、
いつの間にか処分されてしまいます。
しかし20世紀に入ってからのこと。
イタリア・パルマの回収業者が買い取った紙束の中かからオーケストラの楽譜が発見。
その後、運命のように別の場所かあらヴァイオリンの独奏パートが発見され、
現在へ受け継がれることとなりました。
かつては演奏機会が多くありませんでしたが、
映画で「第2楽章」が演奏されて以降、新たに脚光を浴びる作品となりました。
代表曲その⑥、24の奇想曲
代表曲おすすめの最後は『24の奇想曲』です。
ヴァイオリン独奏用曲で、1800年から1810年の10年をかけて作曲されました。
1800年というと、パガニーニがまだ18歳の頃。
それを考えただけでも、当時の彼がどれほど並外れた才能と技術を持っていたかが想像できますね。
作曲の動機は不明ですが、好評を博し、1820年には楽譜出版がなされました。
とはいえ、弾ける人なんてどれほどいたことか・・・。
24曲では舞曲や行進曲、ジプシー音楽、舟唄などから題材がとられており、
パガニーニの多才さと創造性がこの24曲でまとめて体験できます。
なかでも24番がもっとも有名で、
このテーマを用いたさまざまな変奏曲がのちの作曲家たちにより生み出されました。
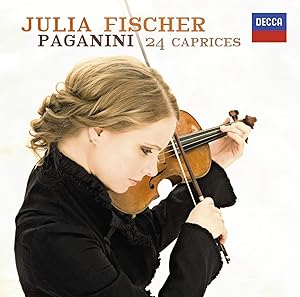
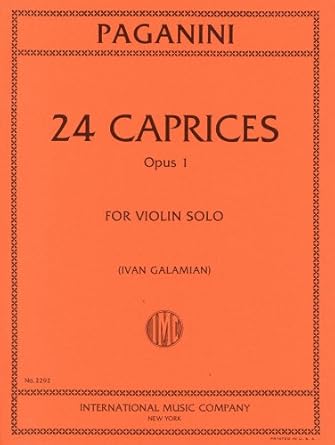
いくつか見てみましょう。
まずは原曲から👇
フランツ・リスト編ピアノ変奏曲👇
ラフマニノフ編👇『パガニーニの主題による狂詩曲』
パガニーニの最高傑作は?

賛否両論を巻き起こす(?)、最高傑作選び。
しかし、ここはあくまでも独断と偏見による選曲なのでご容赦ください。
パガニーニの最高傑作って何かな〜と考えたのですが、
個人的にはこの作品かな、と思います。
パガニーニの最高傑作『ヴァイオリン協奏曲第2番』
作品の規模の面におい、そして構成においても、
この作品が最高傑作なのではないかと思っています。
ただ、パガニーニは生涯で12曲のヴァイオリン協奏曲を作曲したと言われているので、
この後の作品にはもっと優れた作品があるかもしれません。
とはいえ、そのほとんどが紛失しているので、
「再現可能な作品の中で」という但し書きをつけて、この作品にします。
本作の作曲時期については不明で、
1811年から1812年、1819年もしくは1826年との説があります。
ただ、1824年には作曲されていた記録があるらしいので、
大まかな時期はわかっているようです。
他のヴァイオリン協奏曲と同様、全3楽章で構成され、
演奏時間はおよそ30分程度。
パガニーニの情熱と妖艶さ、そして見事なオーケストレーションが混然一体となった傑作です。
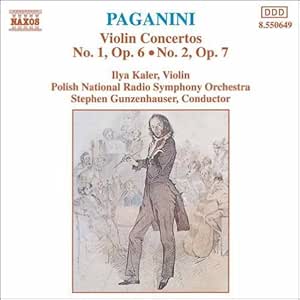
3楽章「ラ・カンパネッラ」が有名
1楽章・2楽章のどちらも、パガニーニの技術の粋(すい)が集められていますが、
とりわけこの作品を有名にしているのが、3楽章の「鐘のロンド」でしょう。
一般に「ラ・カンパネラ」として知られており、
のちのフランツ・リストのピアノ曲でも有名です。
リストのピアノ曲『ラ・カンパネラ』は、崇拝するパガニーニのこの作品をモデルとして作曲されました。協奏曲である分、もちろん音楽の広がりはパニーにの方が広いですが、
そのテーマは『24の奇想曲(24番)』と同じように、後世の作曲家たちに深いインスピレーションを与えました。
原曲と比べてみるのも楽しいと思いますよ!
パガニーニの作品の特徴や魅力

では最後に、パガニーニの作品の特徴や魅力を3つ簡単に紹介します。
今回の記事では、ギター作品も紹介しましたので、
ヴァイオリン作品以外に注目してみるのも、きっと新しい発見があると思いますよ!
パガニーニの作品の特徴や魅力①、超高度な技術的要求
パガニーニの作品といえば、なんといっても超絶技巧。
たとえば、上述の『24の奇想曲』の第24番「テーマと変奏」は、速いテンポ、複雑な運指、ハーモニクス、スピッカート(弓を跳ねさせる技法)など、多岐にわたる技術を要求します。
この曲は、ある意味で、バイオリニストの技術力を試す挑戦状的作品であり、
演奏者には卓越した技術と正確な演奏が求められます。
それに加えて表現力も必要なので、まさに難曲と言えるでしょう。
パガニーニの作品の特徴や魅力②、感情豊かな表現力
パガニーニの作品は、卓越した技術だけでなく感情豊かな表現力も特徴です。
『ヴァイオリン協奏曲第1番』は、その美しい旋律とダイナミックな変化がよくわかる作品じゃないかと思います(最高傑作にしてないけど)。
この作品では、感情豊かなカデンツァ(独奏部分)がとくに印象的で、演奏者が自由に感情を表現できる場となっています。
パガニーニ作品に限ったことではありませんが、
彼の作品は、単なる技術的な挑戦にとどまらない、深い感情表現を伴うものが多いのが魅力です。
パガニーニの作品の特徴や魅力③、旋律の美しさと独自性
パガニーニの旋律は独特で美しく、多くの作曲家に影響を与えました。
今回紹介した『モーゼ幻想曲』を聴いていただくと、わかりやすいかもしれません。
この作品はロッシーニのオペラ「モーゼ」の主題に基づいており、ヴァイオリンのための華やかな変奏曲です。パガニーニは原曲の旋律を巧みに取り入れつつ、自身の独自のスタイルで再解釈しているため、その作品は旋律の美しさと独自性が際立っています。
また、『24の奇想曲』でご紹介したように、
パガニーニは舞曲やジプシー民謡といった、クラシック音楽の外側からも題材を求めた人物でした。さまざまなジャンルから「良いとこどり」をしながら、作品を作り上げたことが、
パガニーニの特徴であり、魅力とも言えるのかもしれません。
1ヶ月無料体験!解約はいつでもOK
amazon music unlimited
パガニーニの代表曲まとめ
今回はパガニーニの作品を紹介しました。
彼が生きた時代は、今からやく240年前。
「そんな時代にこれほどの技術を見せつけられたら、そりゃびっくりするよな」
と思います。
しかも、その作品は現在もなお、ヴァイオリニストにとって必須な作品であるから驚きです。
この記事では紹介しきれない作品もたくさんありますので、
ぜひご自身のお気に入りの1曲を見つけてみてください!
楽器を習いたい方や再開したい方のために、
こちらの記事を書いてみました。【無料体験】(オンライン🉑)もありますので、
ご一読ください👇

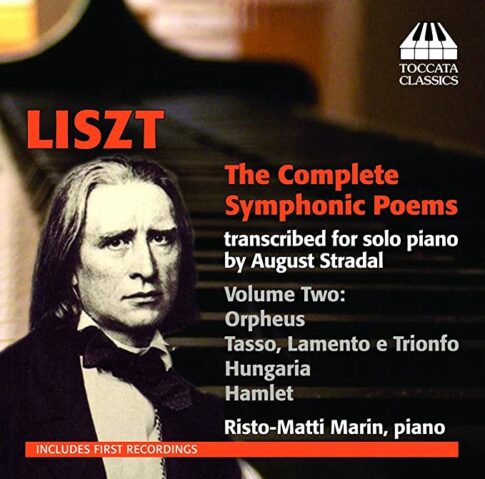
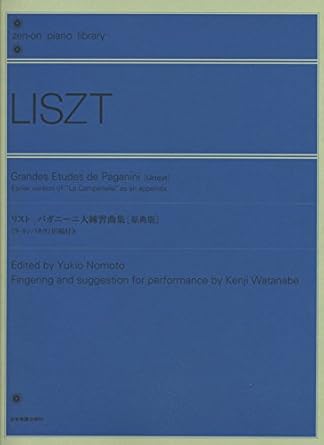

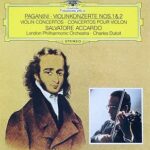
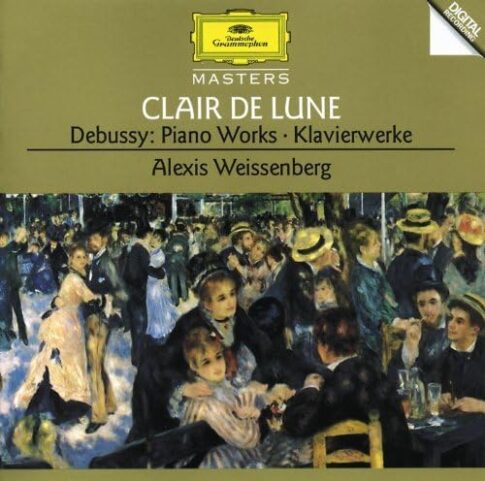
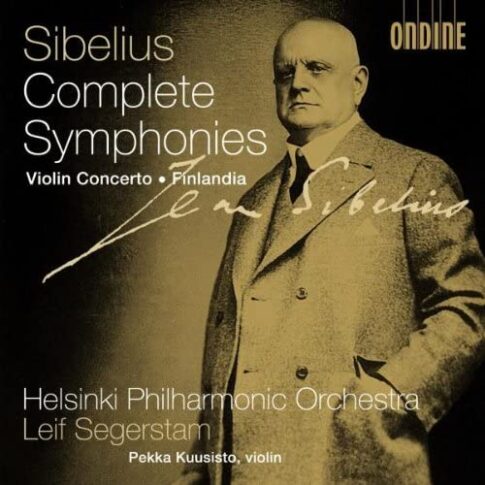
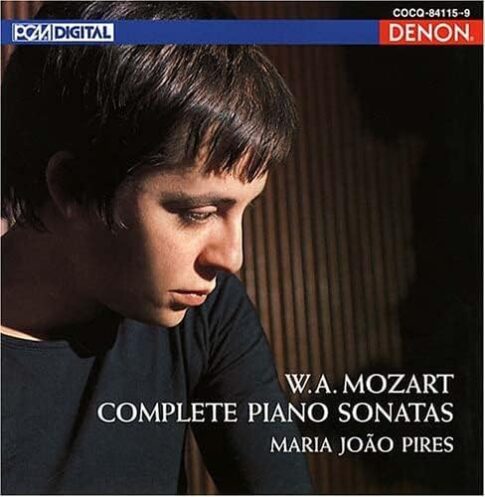
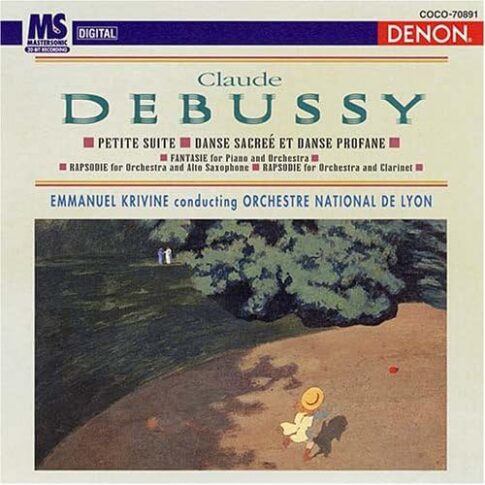

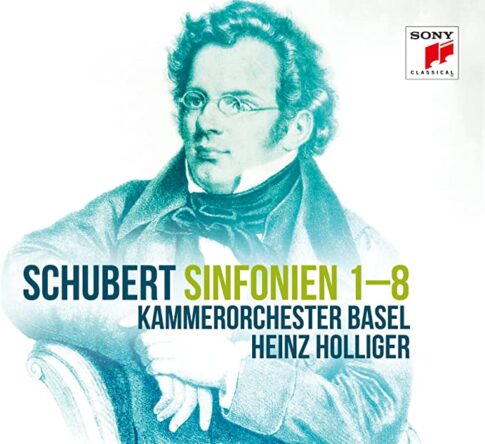
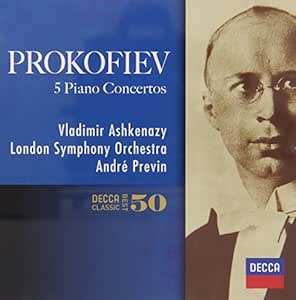
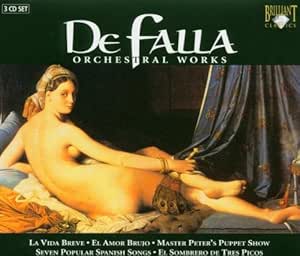



奇想曲・・・カプリース(仏語)やカプリッチョ(伊語)とも呼ばれ、その意味は「気まぐれ」です。そのため、決められた形式などはなく、作曲者が自由な形式で作曲されるのが特徴。