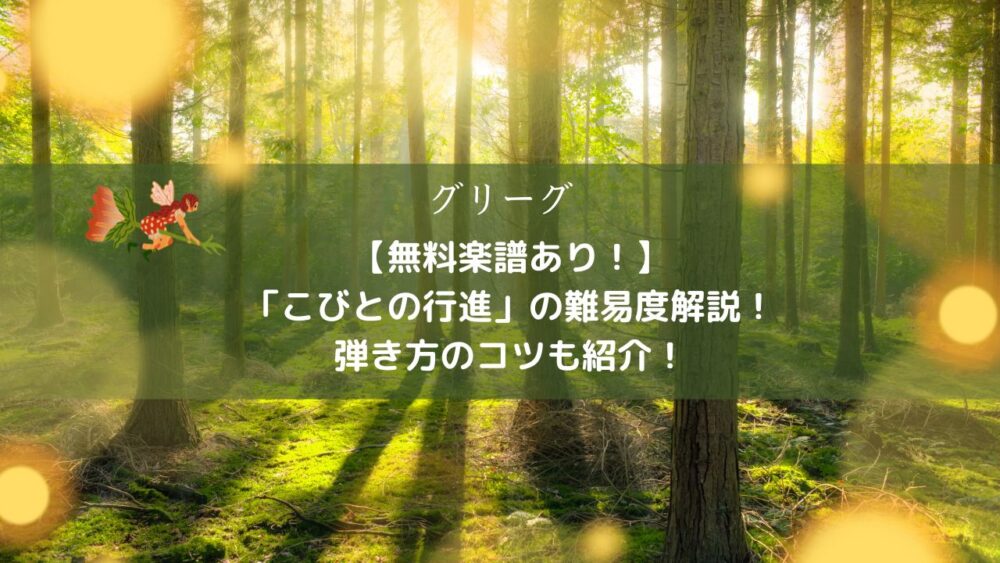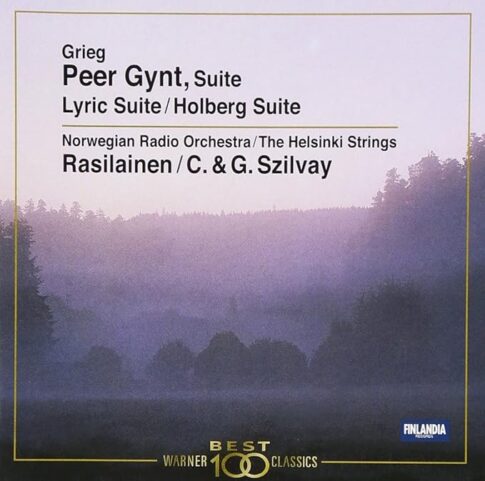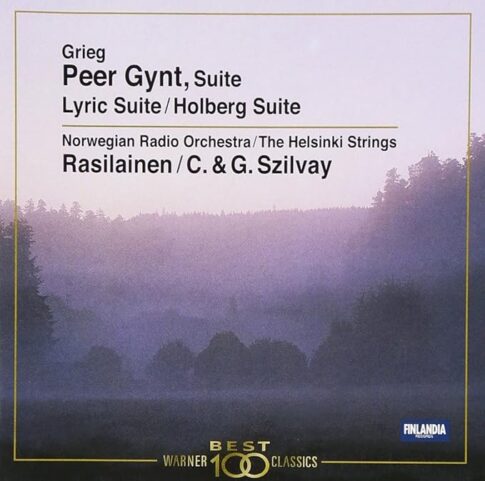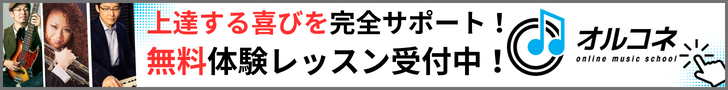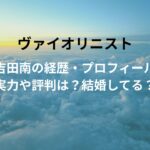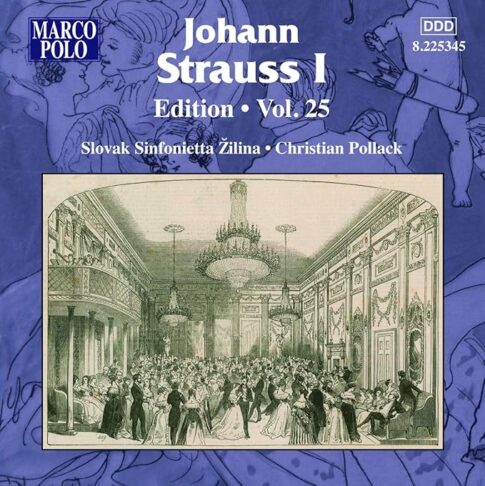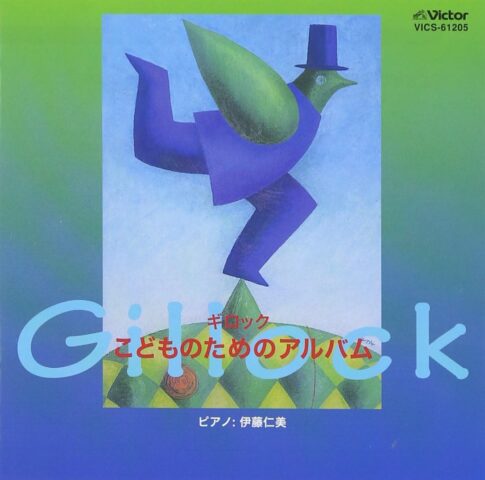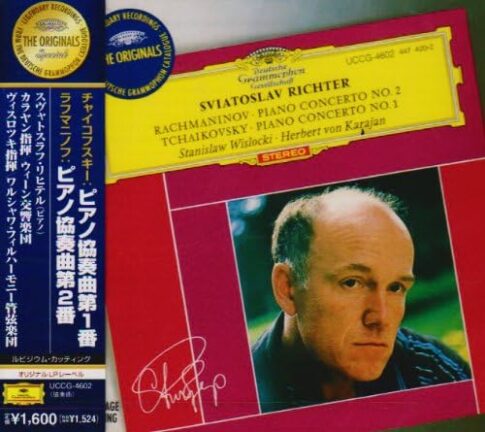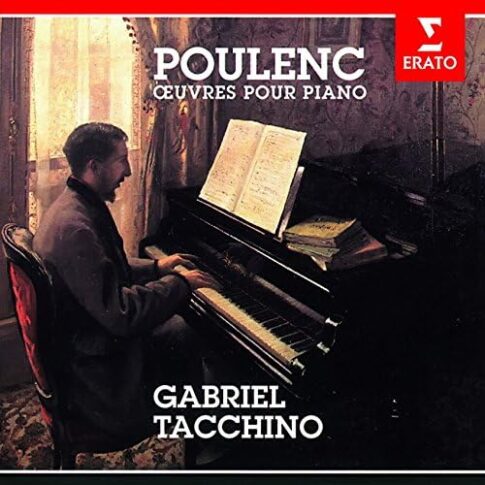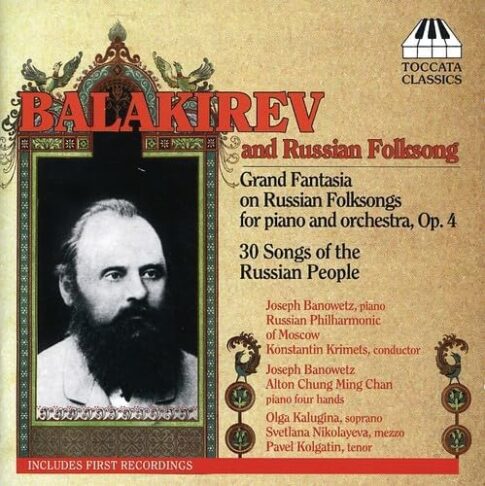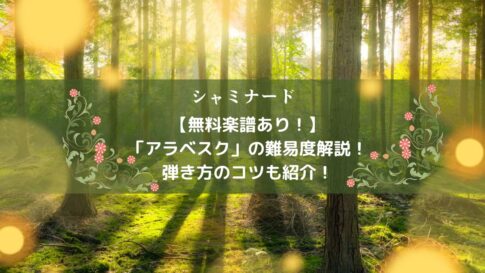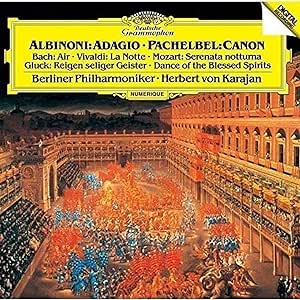グリーグのこびとの行進は、ピアノ学習者にとって魅力的な楽曲の一つ。
北欧の作曲家エドヴァルド・グリーグが作曲したこの小品は、初級から中級への橋渡し的な楽曲として多くの教則本に収録されています。
記事の前半では、筆者の実体験をもとに「こびとの行進」の楽曲や、具体的な難易度分析、効果的な練習方法を紹介し、記事の後半では無料で入手できる楽譜情報まで、ピアノ演奏に必要な情報をお伝えします。
これからこびとの行進に挑戦される方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
筆者は3歳からピアノを開始・紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています。音大には行っておらず、なぜか哲学で修士号というナゾの人生です。
エドヴァルド・グリーグについて
出典:YouTube
いつものように、ちょっとだけ寄り道を・・・。作曲家グリーグについて紹介しますね。
エドヴァルド・ハーゲルップ・グリーグ(1843-1907)は、ノルウェーを代表する世界的な作曲家です。
ベルゲンで生まれ育ったグリーグは、ノルウェーの民族音楽を芸術音楽に昇華させた功績で「北欧音楽の父」と呼ばれています。
グリーグの音楽的特徴は、ノルウェーの民族舞曲や民謡の要素を巧みに取り入れた点にあります。とくに「ペール・ギュント」組曲や「ピアノ協奏曲イ短調」などの大作で知られていますが、ピアノ小品においても数多くの傑作を残しました。
「こびとの行進」は、グリーグの「抒情小曲集」第5集の第3曲として作曲されました。
この抒情小品集は全部で66曲からなる大作で、グリーグのピアノ作品の中でも特に親しまれている楽曲集です。
グリーグ自身が生涯をかけて作曲し続けたこのライフワーク的シリーズは、ピアノ学習者にとって貴重な教材と言えるでしょう。
グリーグについては、こちらの記事で詳しく書いています。
「こびとの行進」の楽曲解説
出典:YouTube
本作は、そのタイトル通り、北欧の伝説に登場する「トロール」(こびとや妖精のような存在)たちの行進を描写した、非常にユニークで魅力的な作品です。
「こびとの行進」の楽曲構成
この曲は、典型的な三部形式(A-B-A’)で書かれており、明確な対比を持つ二つの主要なテーマが展開されます。全体を通して、短調(ホ短調)が基調となっており、神秘的で時に不気味な雰囲気を醸し出しています。
ちょこまかと早足で歩いている雰囲気が、うま〜く表現されていますね。
Aセクション(冒頭~)
曲は、力強く、そしてどこかユーモラスな「こびと」のテーマで始まります。特徴的なのは、右手のスタッカートと左手の重厚な和音の組み合わせです。こびとたちが不揃いながらも力強く行進する様子が描かれています。跳躍が多く、リズムも複雑です。
Bセクション(中間部~)
Aセクションの荒々しさとは対照的に、中間部では長調(ホ長調)に転調し、非常に叙情的で美しいメロディが歌われます。こびとたちが一時の休息を取り、夢見心地で歌を口ずさんでいるかのような雰囲気です。
このセクションは、Aセクションの技巧的な要素から一転して、歌心とレガートな演奏が求められる部分です。
A’セクション(再現部~)
再びAセクションのテーマが戻ってきます。しかし、全体としてより技巧的になり、表現も豊かになります。例えば、オクターブでの演奏や、より速いパッセージが登場し、こびとたちの行進がさらに勢いを増したかのような印象を与えます。
コーダ(終結部)では、行進が徐々に遠ざかっていくように、静かに、そして神秘的に曲を閉じます。
音楽的特徴と表現のポイント
こびとの行進の最大の魅力は、その描写的な音楽表現にあります。
左手の伴奏部分では、一定のリズムパターンが繰り返されることで行進の足音を表現し、右手の旋律部分では軽やかで愛らしいこびとたちの歌声が描かれています。
注目してほしいのは、グリーグ特有の和声進行です。
民族音楽の要素を取り入れた独特の和声は、北欧の神秘的な雰囲気を醸し出しています。また、アクセントの置き方や強弱の付けかたも、グリーグらしくて弾いていて楽しくなる作品です。
「こびとの行進」の難易度解説
出典:YouTube
教則本を例に
こびとの行進は、多くのピアノ教則本で初級から中級への橋渡し的な楽曲として位置づけられています。
実体験としては、ブルグミュラー25の練習曲が終わり、ソナチネの中級レベルが演奏できるレベルかなと思います。ツェルニー30番&ハノンを日頃から取り組んでいれば、それほど難しくないでしょう。
つまり、基本的な読譜力と両手の協調性が身についていれば挑戦できる楽曲かなと。
ただ、音楽的な表現力を求められる楽曲でもあるため、単純に音符を追うだけでは不十分で、楽曲の背景にある物語性を理解した演奏が求められます。
「こびとの行進」と他の曲との比較
こびとの行進の難易度を他の楽曲と比較すると、シューマンの「楽しき農夫」と同程度の技術的要求があります(もうちょい難しいかもですが)。
これらの楽曲と共通するのは、左手の伴奏パターンの安定性と、右手の旋律の歌い方の両方が要求される点。
一方、モーツァルトのソナタK.545第1楽章やクレメンティのソナチネ作品と比較すると、こびとの行進は技術的な難易度はやや低めですかなと。楽曲の持つ物語性や雰囲気を表現することを意識してみましょう!
「こびとの行進」は何年くらいで弾けるかを解説
これも一概にピタッとは言えません(すみません)。
ピアノ学習の進度は個人差が大きいものの、一般的な目安として、週1回のレッスンを受けている場合、ピアノを始めてから3年半から4年程度で取り組むことが可能かなと思います。
この時期は、基本的な指の動きや読譜力が身についており、音楽的な表現に意識を向けることができる段階なので。
大人からピアノを始めた場合でも、集中的に練習すれば2年から3年程度で演奏可能になります(頑張ればですが)。
さらに、大人の場合は理解力があるため、楽曲の背景や音楽理論を学びながら取り組むことで、より深い演奏もできるかもしれません。
ただ、単純に音符を追って演奏できるレベルから、楽曲の魅力を十分に表現できるレベルまでには相当な差があります。音楽的な演奏を目指すのであれば、さらに1年程度の継続的な練習が必要になるかもしれません。
こびとの行進の楽譜紹介:【無料楽譜あり】
出典: YouTube
最後に楽譜紹介をして終わりにしますね。抒情小曲集を買う前に、無料楽譜でチェックしてみるとよいと思いますよ!
「こびとの行進」の無料楽譜の入手方法
こびとの行進の楽譜は、著作権が切れているため、インターネット上で無料で入手することが可能です。最も信頼性の高い無料楽譜サイトとしては、IMSLP(国際楽譜ライブラリープロジェクト)があります。このサイトでは、グリーグの原典版楽譜をPDF形式でダウンロードできます。
「こびとの行進」の無料楽譜ダウンロードはこちら!(7ページ目です)。
こびとの行進:出版楽譜2選
市販の楽譜としては、全音楽譜出版社「グリーグピアノ名曲集 (1) 」があります。
これらの楽譜には、運指や表現記号が詳しく記載されているので安心です。
また、解説も充実しているため、楽曲の背景を理解しながら学習することができますよ。
>>アマゾン:グリーグピアノ名曲集 (1) 全音ピアノライブラリー
より本格的に取り組みたい方は、海外版の楽譜もOKです。ず〜っと練習できますし、全曲収録されているのもありがたいです。ちょっとお値段高めですが、「一生モノ」と考えれば問題ないと思います!
>>アマゾン:グリーグ: 叙情小曲集(抒情小曲集) 全曲集/原典版/Heinemann & Nokleberg編/ヘンレ社/ピアノ・ソロ
こびとの行進:難易度解説:まとめ
グリーグの「こびとの行進」は、技術的には初級上レベルでありながら、音楽的な表現力が重要視される楽曲です。
ピアノ学習者にとって、基礎技術から音楽表現への橋渡しとなる重要な楽曲として位置づけられています。
あらためて、今回の記事のポイントをまとめます。
こびとの行進は、単なる練習曲以上の価値を持つ芸術作品です。技術的な習得だけでなく、音楽的な想像力を育てる楽曲として、多くのピアノ学習者に愛され続けています。ぜひ、この魅力的な楽曲に挑戦してみてください!