前回に引き続きガブリエル・フォーレの作品について解説します。
オルガニスト・教育者・作曲家とさまざまな分野で才能を発揮したフォーレ。その作品には深い精神性と円熟した人間味が込められ、聴く人の心を安らぎへ導きます。
79歳でこの世を去るまで音楽に身を捧げたフォーレは、室内楽をはじめ、歌曲、舞台音楽などで数々の名作を残しました。
そこで今回は、フォーレをもっとも代表する作品3曲を簡単に紹介します。
これさえ知っておけば、ちょっとしたクラシック音楽通かもしれません。
フォーレの作品解説その1、「ペレアスとメリザンド」

最初の1曲目は「ペレアスとメリザンド」を紹介します。劇舞台音楽として発表され、のちに管弦組曲に編曲されました。作中の「シシリエンヌ」はどこかで聴いたことがあるかもしれません。
劇付随音楽から組曲へ
本作は『青い鳥』などの作品で知られる、メーテルリンク作『ペレアスとメリザンド』に音楽を付けた劇付随音楽です。
1898年5月に作曲され、6月にロンドンのプリンス・オブ・ウェールズ劇場にて初演されました。この頃のフォーレは、パリ音楽院教授の仕事やマドレーヌ教会でのオルガニストとして多忙を極めていたらしく、本作は実質1ヶ月で作曲されたと言われています。
そのためオーケストレーションが間に合わず、オーケストレーションは弟子のシャルル・ケクランが担当しました。
初演はフォーレ自身が指揮を担当し、大きな成功を収めています。
その後1898年から1900年にかけて「ペレアスとメリザンド」から3曲を抜粋し、管弦楽用の組曲を作曲しました。
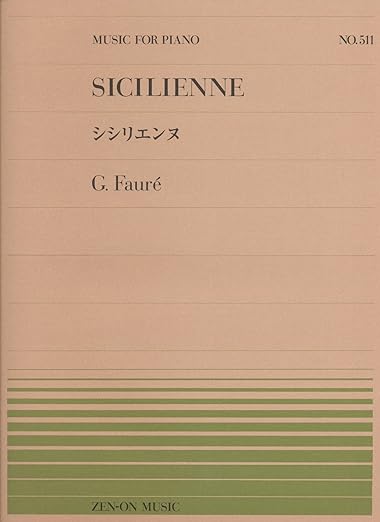
作品の編成について
当初は「前奏曲」「糸を紡ぐ女」「メリザンドの死」の3曲で編成されましたが、のちに「シシリエンヌ」「メリザンドの歌」が加わり、5曲の組曲に編成されました。なお、組曲中の「メリザンドの歌」には声楽が含まれています。
現在では劇付随音楽としての演奏機会はありませんが、組曲は現在も根強い人気の高い、フォーレ中期を代表する傑作です。
組曲全体の構成は以下の通り。
1、前奏曲・・・ト長調、メリザンドを主題を表現する弦楽が印象的な作品
2、糸を紡ぐ女・・・ト長調、19曲ある劇付随音楽中の10作目。オーボエの音色が美しい
3、メリザンドの歌・・・ニ短調、唯一声楽がついている作品
4、シシリエンヌ・・・劇中、ペレアスとメリザンドが泉のほとりで戯れるシーンに使用された作品。フォーレのシシリエンヌとしても有名です。
5、メリザンドの死・・・ニ短調、メリザンドの死を予言する悲哀に満ちたメロディーが魅力
楽器編成について
管弦楽版の編成は以下の通りです。
・フルート
・オーボエ
・クラリネット
・ホルン
・トランペット
・ティンパニ
・ハープ
・弦楽五部
・声楽(ソプラノまたはメゾソプラノ)
組曲以外にもピアノ独奏、ピアノとチェロ版、ヴァイオリンとピアノ版など多くのバリエーションがあります。
フォーレの作品解説その2、「マスクとベルガマスク」
1919年、モナコ大公アルベール1世の委嘱により作曲された、劇付随音楽、管弦楽組曲です。
本作はフランスの詩人、ポール・ヴェルレーヌの詩集『艶なる宴』がモチーフとし、同年4月にモンテカルロにて初演されました。
しかしドビュッシーも同タイトルの作品を発表しており、現在ではもっぱらドビュッシーの作品の演奏機会が多くなっています。
ベルがマスクとはイタリア北部の都市・ベルガモに伝わる舞曲に由来します。
楽曲編成について(劇付随音楽版)
フォーレは本作のために序曲を含めた8曲を作曲しましたが、「(この曲が)それほど演奏されることはないだろう」と考えたようで、楽曲にはフォーレが過去に作曲した管弦楽曲や歌曲が転用されています。()内は原曲の作曲年です。
作品発表時に新曲として発表されたのは2番と5番だけでした。
またこれらのうち、「序曲」「メヌエット」「ガヴォット」「パストラール」の4曲が抜粋され、組曲版として編曲されています。
フォーレの作品解説その3、「レクイエム」
モーツァルト、ヴェルディのレクイエムとともに「3大レクイエム」に数えられる作品です。
フォーレの最高傑作の一つであり、1887年から作曲が開始され、3度の改訂を経て1900年に完成されました。
演奏時間はおよそ40分です。※レクイエムとは「死者のためのミサ曲」を指します。
1900年の第3稿は大成功を収め「1900年版」とも言われています。
「シシリエンヌ」と並び、もっとも演奏機会の多い作品といっても過言ではないでしょう。
レクイエム作曲の動機について、一般に「両親の死」が関係していると考えれていますが、母親が死去した1887年12月以前にはすでに構想されていることから、本作と両親の死とはあまり関係がないようです。
その証拠にフォーレ自身も次のように語っています。
私のレクイエムは、特定の人物や事柄を意識して書いたものではありません。……あえていえば、楽しみのためでしょうか。
マドレーヌ教会での初演の際には、「死の恐ろしさが描かれていない」「異教徒的」といった批判に遭いましたが、ある意味では伝統を乗り越えた斬新な作品だったのかもしれません。
作品編成について
全7曲から構成されており、レクイエムに必須の「怒りの日」が設けられていないのが特徴です。
また、第4曲「ピエ・イェス」を中心とした対称的な配置もフォーレのレクイエムならではと言えるでしょう。
それぞれのタイトルは次の通りです。
1、イントロイトゥスとキリエ・・・ニ短調
2、オッフェルトリウム・・・ロ短調
3、サンクトゥス・・・変ホ長調
4、ピエ・イェズ・・・変ロ長調
5、アニュス・デイ・・・へ長調
6、リベラ・メ・・・ニ短調
7、イン・パラディスム・・・ニ長調
楽器編成について
楽器編成は以下の通りとなっています。
・フルート
・クラリネット
・ファゴット
・ホルン
・トランペット
・トロンボーン
・ティンパニ
・ハープ
・オルガン
・弦楽五部
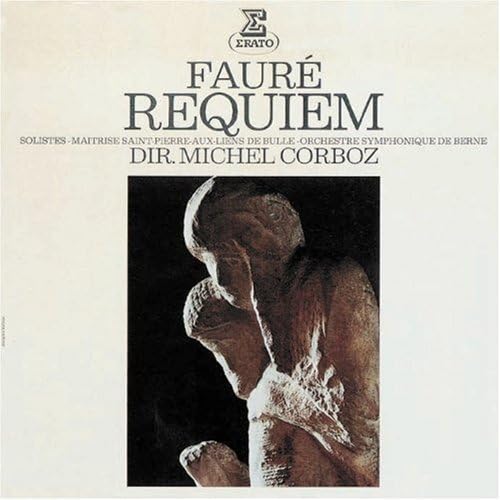
フォーレの作品解説まとめ
今回はフォーレ作曲、「ペレアスとメリザンド」「マスクとベルガマスク」「レクイエム」を紹介しました。
モーツァルトやヴェルディのレクイエムと比べると、豪華さや迫力の面で物足りないと思われる方もいらっしゃるでしょうが、荘厳さや崇高さにおいては他の2曲に引けを取らない作品だと思います。
これまでフォーレの作品に触れたことがなかったか方も、この記事を機会にぜひその荘厳さを感じてみてください。
その他の代表作紹介はこちらから👇
追加料金・広告なしで楽しめる[Amazon music prime]はコチラ!

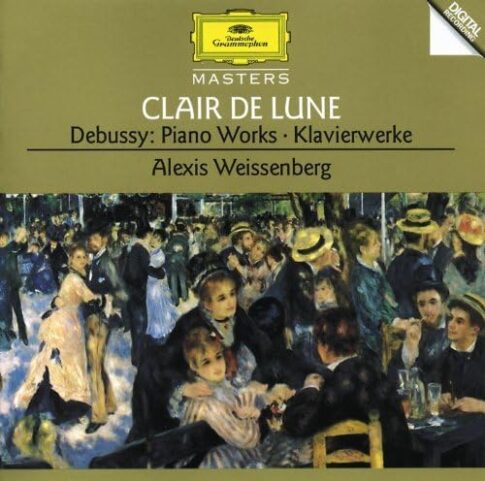
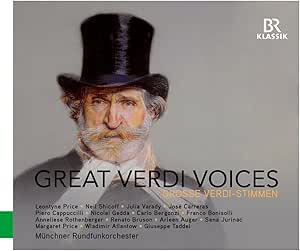
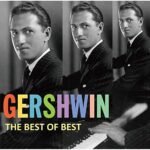

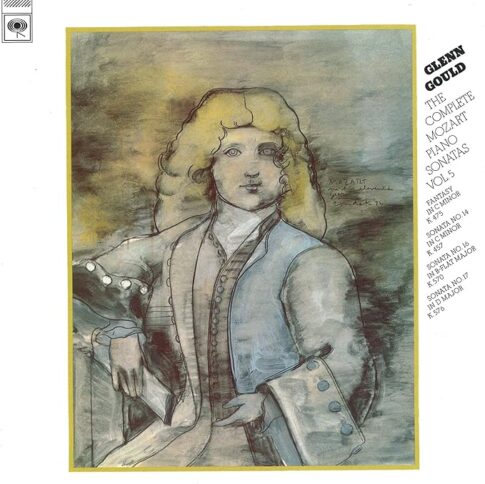


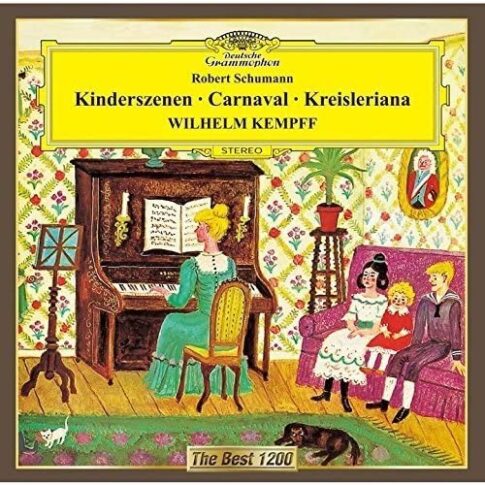
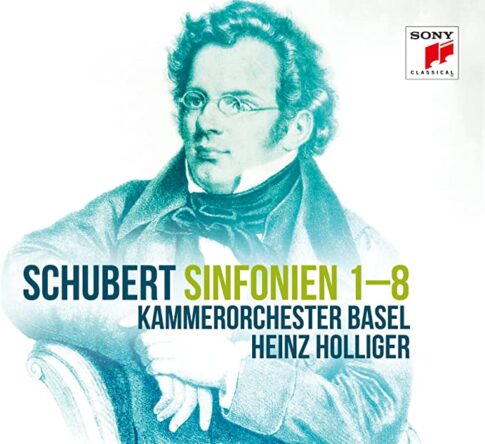
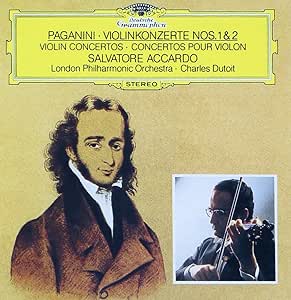
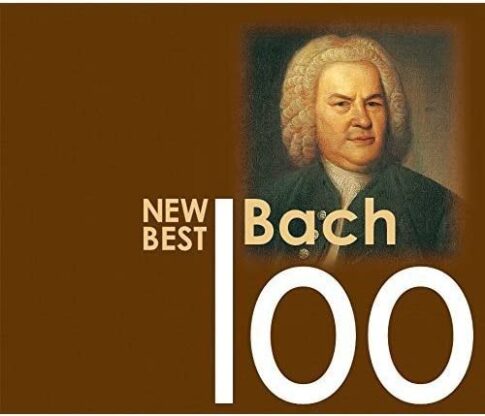
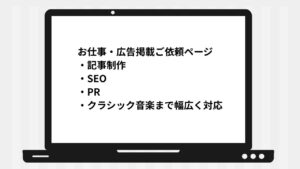


1、序曲(1868年)
2、パストラール(1919年)
3、マドリガル(1883年)
4、いちばん楽しい道(1904年)
5、メヌエット(1919年)
6、月の光(1887年)
7、ガヴォット(1869年)
8、パヴァーヌ(1886年〜1887年)