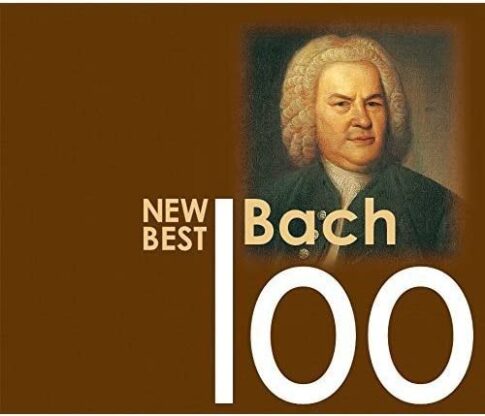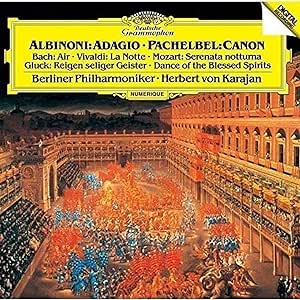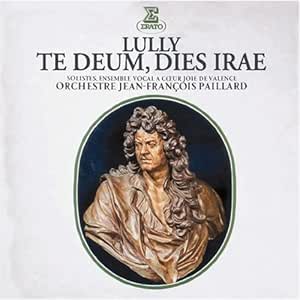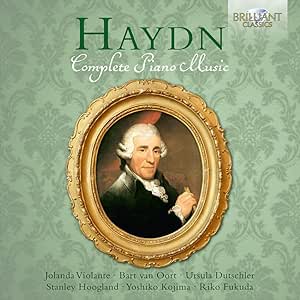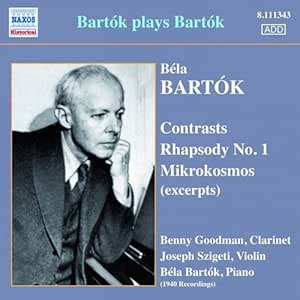今回はバロック音楽の特徴や作曲家、代表曲を解説します。
クラシック音楽の中でも、特に華やかで力強い印象を与える「バロック音楽」。
J.S.バッハやヘンデル、ヴィヴァルディといった巨匠たちが活躍したこの時代の音楽は、現代でも多くの人々に愛され、映画やCMなど、意外な場面でも耳にする機会があります。
しかし、「バロック音楽って具体的にどんな特徴があるの?」「有名な曲は?」と聞かれると、詳しく説明するのは難しいかもしれません。
この記事では、「バロック音楽の特徴」をキーワードに、その魅力的な世界を初心者にも分かりやすく解説します。
この記事でわかること
ぜひ最後まで読んで参考にしてください!
バロック音楽とは?―「歪んだ真珠」と呼ばれた時代の芸術

まずは「バロック」という言葉の由来から。
これはポルトガル語の「Barroco(バロッコ)」=「歪んだ真珠」が語源とされています。
当初は、均整の取れたルネサンス様式に比べて「過剰で不規則」といった、やや否定的なニュアンスで美術様式を指す言葉でした。
しかし、今日では、おおよそ1600年から1750年頃のヨーロッパで栄えた特定の芸術様式、および音楽様式を示す言葉として広く使われています。
この時代は、フランスのルイ14世に象徴される「絶対王政」のもと、王侯貴族が強大な権力を持ち、壮麗な宮殿や文化を築き上げた時代。
同時に、宗教改革後のカトリック教会とプロテスタント教会の対立も続き、教会もまた音楽の重要なパトロンでした。さらには、科学革命により人々の世界観が大きく変化した時代でもあります。
このような、壮麗さとダイナミズム、そして時には宗教的な情熱に満ちた時代背景が、バロック音楽の特徴である、感情豊かで劇的な表現、そして緻密な構成美を生み出す土壌となったわけです。
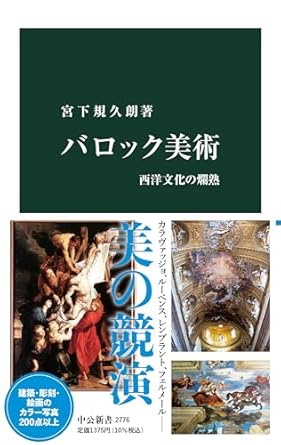
バロック音楽の主な特徴を知ろう!
では、バロック音楽にはどのような音楽的特徴があるのでしょうか?
ここでは、そのポイントをいくつかご紹介します。
一つずつ解説します。
バロック音楽の特徴①:感情の表現を追求した「情念論(アフェクト論)」
バロック音楽の根底にある重要な考え方が「情念論(アフェクト論)」です。
これは、喜び、悲しみ、怒り、驚きといった人間の様々な感情(情念・アフェクト)を、音楽を通して客観的に表現しようとする考え方。
ここから、特定の音型や旋律、リズム、調性(長調・短調)などが、特定の感情と結びつけられ、聴き手の心に直接訴えかけるような、表現力豊かな音楽が追求されました。
この考え方は、特にイタリアで誕生し発展したオペラにおいて、登場人物の心情を劇的に描き出す上で重要な役割を果たしました。
バロック音楽の特徴②:音楽の推進力となる「通奏低音」
バロック音楽のサウンドを特徴づける最も重要な要素の一つが「通奏低音(つうそうていおん)」です。これは、チェロやヴィオラ・ダ・ガンバ、ファゴットなどの低音楽器が旋律線を奏で、チェンバロやオルガン、リュートなどの和音楽器が、その低音に基づいて和音を(多くの場合、即興的に)補って伴奏する演奏形態のことを言います。
楽譜には低音部の旋律と、和音を示すための数字(数字付き低音)が記されていることが多く、これをもとに和音楽器奏者が和音を肉付けしました。この力強い低音の動きと和声感が、音楽全体の進行を支え、バロック音楽の特徴である安定感と推進力を生み出しています。
ヴィオラ・ダ・ガンバ:出典:wikipedia
車田和寿先生が通奏低音についてわかりやすく解説してくれています👇。
出典:YouTube
バロック音楽の特徴③:複数の旋律が織りなす「対位法」の高度な発展
「対位法(たいいほう)」とは、複数の独立した旋律(声部)を、それぞれの旋律的・リズミ的な独自性を保ちつつ、協和的に組み合わせていく技法です(ちょっと難しいですね)。
バロック時代、この対位法は極めて高度に発展し、精緻で複雑な音楽構造を生み出しました。
特に、J.S.バッハによって完成の域に達した「フーガ」は、対位法様式の代表格。
一つの短い主題が、次々と異なる声部に模倣されながら重なり合い、壮麗で知的な音響空間を構築していきます。
この曲、聴いたことありませんか?👇
出典:YouTube
バロック音楽の特徴④:独奏と合奏の対比が魅力の「協奏曲(コンチェルト)」
バロック時代に確立され、人気を博した形式が「協奏曲(コンチェルト)」です。
これは、一人または少人数の独奏楽器(ソロ、またはコンチェルティーノ)と、オーケストラ全体が、交互に現れたり、対比されたりしながら音楽を展開していく形式です。
独奏楽器の華やかな技巧と、合奏の豊かな響きのコントラストが、劇的で聴き応えのある効果を生み出します。ヴィヴァルディの「四季」に代表される独奏協奏曲や、コレッリなどが得意とした合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)などがあります。
出典:YouTube
その他のバロック音楽の特徴
- テラス型強弱: 音量が段階的に変化する(例えば、ピアノ(弱)からフォルテ(強)へ、突然切り替わる)のが特徴。
クレッシェンドやデクレッシェンドはあまり用いられませんでした。 - 装飾音: 旋律を華やかに彩るためのトリル、モルデントなどの装飾音符が多用されました。即興的に付け加えられることもありました。
- 舞曲形式の多用: メヌエット、ガヴォット、サラバンド、ジーグなど。
宮廷舞踏で用いられた舞曲が、組曲などの器楽曲形式に多く取り入れられました。
参考|音楽之友社|専門書にチャレンジ!第13回バロック音楽演奏の息吹に触れる
バロック音楽を彩る巨匠たち:代表的な作曲家と名曲

バロック時代には、後世に多大な影響を与えた多くの偉大な作曲家が活躍しました。
ここでは特に重要な人物を何人かご紹介します。
今回紹介するのは以下の8人です。ホントはた〜くさんいますが、とくに有名な作曲家をピックアップしています。
なお、関連記事がある作曲家については参考記事も掲載しますので、そちらも参考にしてください!
J.S.バッハ (Johann Sebastian Bach / 1685-1750 / ドイツ)
「音楽の父」と称される、バロック音楽最大の巨匠。
ドイツの教会音楽家としての活動が中心でしたが、その作品は教会音楽(カンタータ、受難曲、オルガン曲)から世俗音楽(協奏曲、室内楽曲、鍵盤楽曲)まで、あらゆるジャンルに及びます。
対位法の技法を極限まで高め、緻密な構成と深い精神性を湛えた普遍的な作品を数多く残しました。
代表曲:「ブランデンブルク協奏曲」「マタイ受難曲」「平均律クラヴィーア曲集」「無伴奏チェロ組曲」「G線上のアリア(管弦楽組曲第3番より)」
マタイ受難曲:出典:YouTube
G.F.ヘンデル (George Frideric Handel / 1685-1759 / ドイツ→イギリス)
バッハと同年に生まれましたが、より国際的に活躍し、特にイギリスで絶大な人気を博した作曲家。
イタリア様式のオペラで成功を収めた後、ロンドンでオラトリオ(宗教的題材による劇音楽)の作曲家として名声を確立しました。
彼の音楽は、バッハに比べ、より明快で祝祭的、劇的な性格を持っています。
代表曲: オラトリオ「メサイア」(特に「ハレルヤ・コーラス」)、組曲「水上の音楽」、組曲「王宮の花火の音楽」
出典:YouTube
A.ヴィヴァルディ (Antonio Vivaldi / 1678-1741 / イタリア)
ヴェネツィアで活躍した司祭であり、ヴァイオリンの名手。「赤毛の司祭」として知られています。生涯に500曲以上の協奏曲を作曲し、特に独奏協奏曲の形式確立に大きく貢献しました。
明快な形式、リズミカルな躍動感、そして鮮やかな旋律は、当時のヨーロッパ中で人気を博し、バッハにも影響を与えました。
代表曲: ヴァイオリン協奏曲集「四季」、協奏曲集「調和の霊感」、宗教曲「グローリア ニ長調」
J.パッヘルベル (Johann Pachelbel / 1653-1706 / ドイツ)
バッハより前の世代の、南ドイツを代表するオルガニスト・作曲家。今日では、もっぱら「パッヘルベルのカノン」で知られています。この曲は、3つのヴァイオリンが同じ旋律を追いかけるように演奏するカノン形式の美しい作品で、彼の死後、20世紀になってから広く知られるようになりました。
代表曲: 「3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調」
出典:YouTube
A.コレッリ (Arcangelo Corelli / 1653-1713 / イタリア)
ローマを中心に活躍したヴァイオリニスト・作曲家。
合奏協奏曲(コンチェルト・グロッソ)やトリオ・ソナタといった器楽形式の発展に大きく貢献しました。
彼の作品は、優雅で均整の取れた様式美を特徴とし、後の作曲家にとって模範となっています。
代表曲: 合奏協奏曲集 作品6(特に第8番「クリスマス協奏曲」)、ヴァイオリン・ソナタ集 作品5(特に第12番「ラ・フォリア」)
クリスマス協奏曲:出典:YouTube
G.P.テレマン (Georg Philipp Telemann / 1681-1767 / ドイツ)
バッハ、ヘンデルと同時代の作曲家で、驚異的な多作家として知られています(記録では3000曲以上!)。当時のヨーロッパの様々な音楽様式を巧みに取り入れ、国際的で洗練された、親しみやすい作品をあらゆるジャンルで残しました。生前はバッハをしのぐほどの人気と名声を誇りました。
代表曲: 「ターフェルムジーク(食卓の音楽)」、「ヴィオラ協奏曲 ト長調」、「パリ四重奏曲集」
ターフェルムジーク(食卓の音楽):出典:YouTube
あまりにも作品数が多いため、現在でも作品整理が続けられています。
J-B.リュリ (Jean-Baptiste Lully / 1632-1687 / イタリア→フランス)
イタリア出身ですが、フランスのルイ14世の宮廷で活躍し、フランス・バロック音楽様式を確立した人物。
フランス語の抑揚を生かした「叙情悲劇(トラジェディ・リリック)」と呼ばれるオペラ形式や、荘重な「フランス風序曲」を創始しました。
宮廷音楽の総監督として絶大な権力を持ち、その音楽はフランス宮廷の威厳と壮麗さを象徴しています。
代表曲: オペラ「アルミード」、オペラ「アティス」、バレエ音楽「町人貴族」
町人貴族より:出典:YouTube
リュリは太陽王ルイ15世の庇護のもと、時代の寵児となりました。指揮棒で足を突き、それが原因で亡くなったことでも知られています。
H.パーセル (Henry Purcell / 1659-1695 / イギリス)
イギリス・バロック期最大の作曲家。「ブリタニアのオルフェウス」と称えられます。
短い生涯の間に、独創性に富んだ劇場音楽、教会音楽、歌曲などを残しました。
イタリアやフランスの影響を受けつつも、英語の響きを生かした独自の叙情性が特徴です。
代表曲: オペラ「ディドとエネアス」(特にアリア「私が地に横たわる時」)、劇音楽「妖精の女王」
アリア「私が地に横たわる時」:出典:YouTube
バロック音楽の響きを形作る楽器たち

バロック音楽の独特なサウンドは、当時使用されていた楽器によっても大きく特徴づけられています。現代の楽器とは異なる、その時代の楽器(古楽器)を知ることで、より深く音楽を理解できるはずです。
鍵盤楽器
ピアノ登場以前の主要な鍵盤楽器はチェンバロとオルガンでした。チェンバロは弦を爪で弾くため、輝かしく繊細な音色が特徴です。オルガンは教会を中心に用いられ、その荘厳な響きは宗教音楽に不可欠でした。
チェンバロ(ドイツ語)、クラヴサン(フランス語)、ハープシコード(英語)はすべて同じ楽器を指します。
弦楽器
ヴァイオリン族(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)は基本的な形は現代と同じですが、羊腸などを用いたガット弦や、形状の異なるバロック弓が使われ、より柔らかくニュアンスに富んだ音色でした。ヴィオラ・ダ・ガンバ族も広く用いられました。
ヴィオラの小さい版がヴァイオリン、大きい版がチェロです。
管楽器
リコーダーや木製のフラウト・トラヴェルソ(フルートの祖先)、キーの少ないオーボエやファゴットなどが活躍しました。バルブ装置のないナチュラル・トランペットやナチュラル・ホルンは、輝かしい音色で祝祭的な場面を彩りました。
近年では、これらの古楽器を用いて当時の演奏様式を再現する「ピリオド演奏」も盛んです。
バロック音楽と現代―受け継がれる遺産
バロック音楽は、単なる過去の音楽ではありません。
その影響は現代にも脈々と受け継がれています。
- クラシック音楽の基礎: バロック時代に確立された和声理論や対位法、ソナタや協奏曲といった形式は、その後の古典派、ロマン派へと続く西洋音楽の発展の礎となりました。
- 現代のポピュラー音楽への影響: パッヘルベルの「カノン」のコード進行(カノン進行)は、ポップスやロックなど、ジャンルを超えて数多くの楽曲で引用・参照されています。
また、対位法的な発想や、バロック調の編曲なども、現代の音楽制作においてしばしば用いられます。 - 普遍的な魅力: 緻密な構成美、豊かな感情表現、そして時には荘厳で、時には軽快なバロック音楽の持つ魅力は、時代を超えて多くの人々の心を捉え続けています。
バロック音楽の特徴や代表的作曲家・名曲:まとめ
この記事では、「バロック音楽の特徴」を中心に、その時代背景、音楽様式、代表的な作曲家や楽器、そして現代との関わりについて解説してきました。
改めてバロック音楽の主な特徴をまとめます。
- 感情表現を重視(情念論)
- 通奏低音が音楽を支える
- 高度に発展した対位法(フーガなど)
- 協奏曲形式の確立
- バッハ、ヘンデル、ヴィヴァルディなどの巨匠が活躍
- 古楽器による独特の響き
- 現代音楽にも影響を与えている
バロック音楽は、知れば知るほどその奥深さと魅力に引き込まれる世界です。まずは、ご紹介した有名曲を気軽に聴いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。きっと、あなたの日常を豊かに彩る、新たな音楽との出会いがあるはずです。
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。