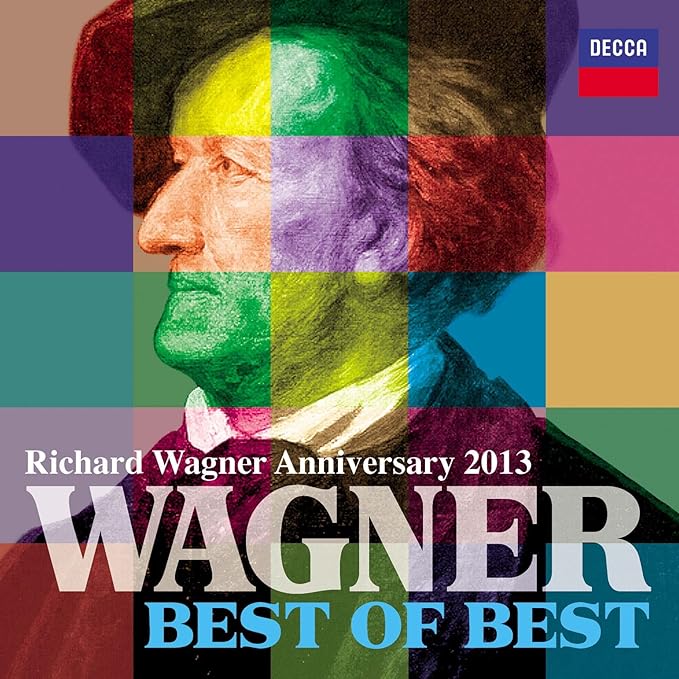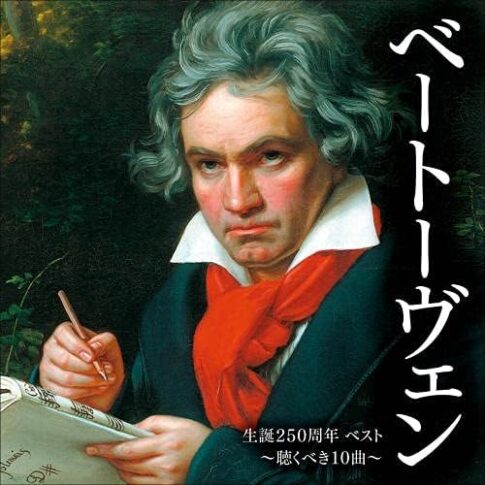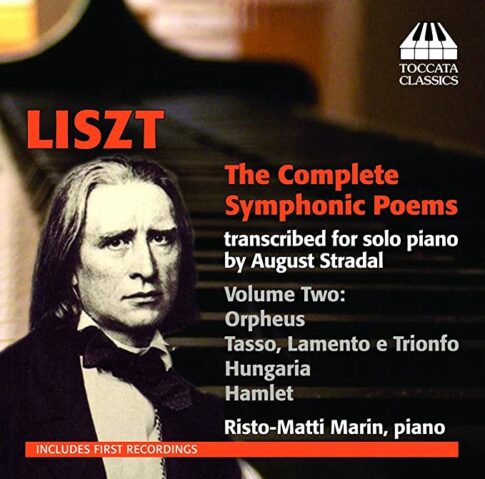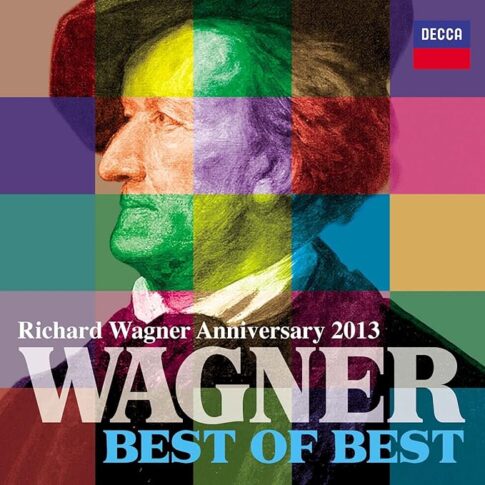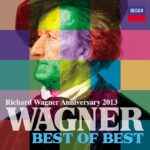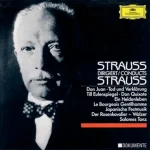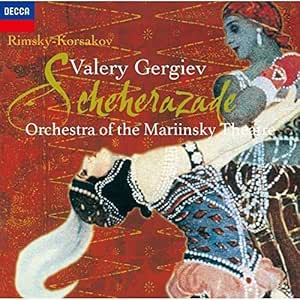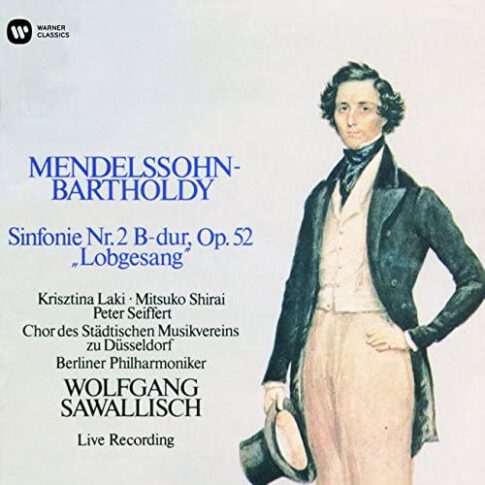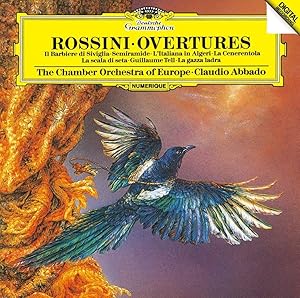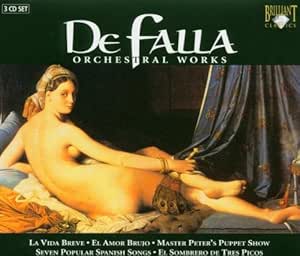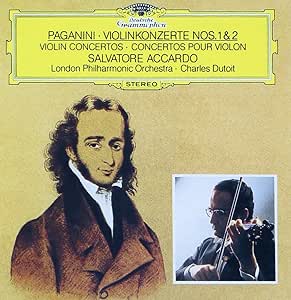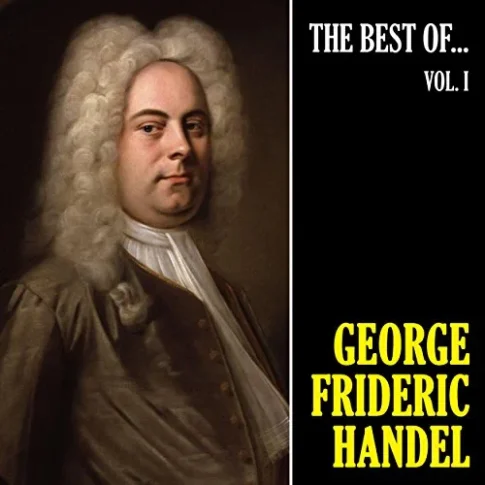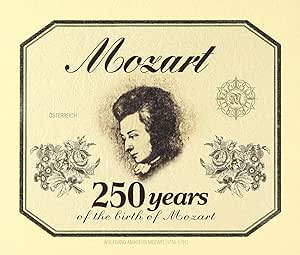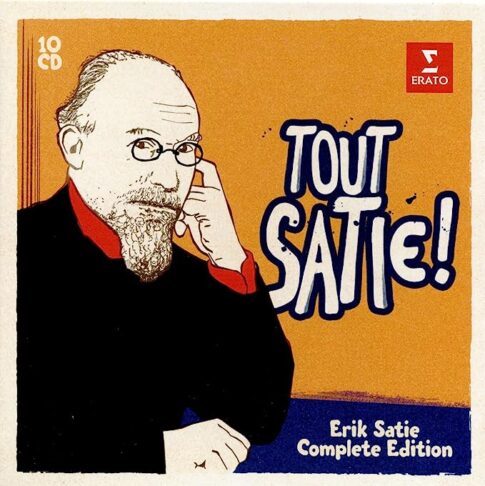この記事では楽劇王リヒャルト・ワーグナーについて紹介します。
クラシック音楽を聴き始めたばかりの方にとっては、少しとっつきにくい感じがしなくもないですが・・・。
でも『タンホイザー』や『ワルキューレの騎行』といった作品は、1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
作品紹介は次回の記事で解説するとして、今回はワーグナーの人生についていつもながらざっくりと解説します。
明日話せる豆知識やエピソードも紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください!
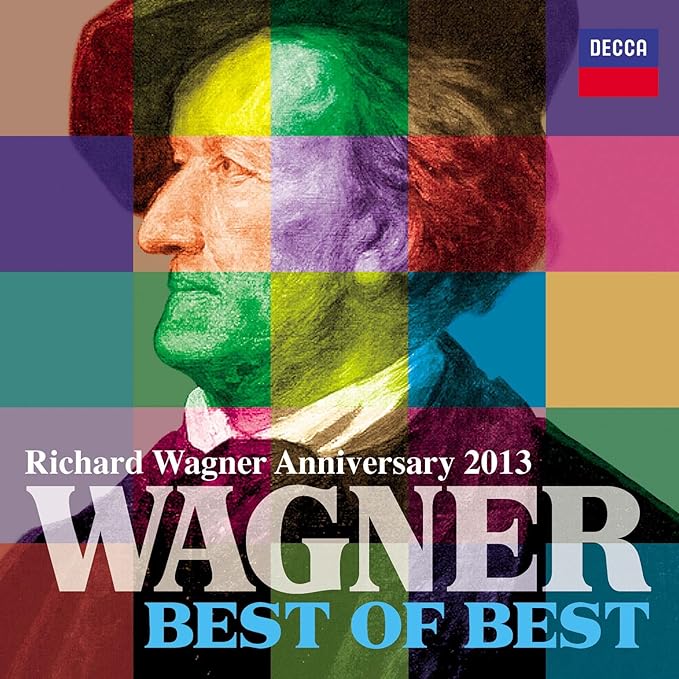
リヒャルト・ワーグナーの生涯年表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1813年 | 5月22日、ドイツ・ライプツィヒに生まれる。幼少期から文学や演劇に興味を持つ。音楽よりも最初は戯曲好き。 |
| 1831年 | ライプツィヒ大学で音楽を本格的に学び始める。ベートーヴェンやウェーバーに影響を受ける。 |
| 1833年 | 最初のオペラ《妖精》を作曲。指揮者としても活動を始め、各地の劇場を渡り歩く。 |
| 1842年 | オペラ《リエンツィ》がドレスデンで成功。続く《さまよえるオランダ人》で独自のスタイルが見え始める。 |
| 1845年 | オペラ《タンホイザー》初演。伝統的オペラとは異なる「楽劇」の方向性を模索。 |
| 1849年 | ドレスデンでの革命運動に関与し、逮捕状が出る。スイスへ逃亡し、亡命生活に入る。 |
| 1850年代 | スイス滞在中に《ニーベルングの指環》構想をスタート。《トリスタンとイゾルデ》の作曲にも取り組む。 |
| 1864年 | バイエルン国王ルートヴィヒ2世に見出され、経済的支援を受けるようになる。ミュンヘンに移住。 |
| 1876年 | 自ら設計したバイロイト祝祭劇場で《ニーベルングの指環》全曲上演(バイロイト音楽祭の始まり)。楽劇の理想を実現。 |
| 1882年 | 晩年のオペラ《パルジファル》を完成・初演。宗教的・精神的な世界観を描く。 |
| 1883年 | 2月13日、イタリアのヴェネツィアにて死去。享年69歳。遺体はバイロイトに埋葬され |
リヒャルト・ワーグナーの生涯

19世紀のクラシック音楽に重大な影響を与えたワーグナー。
そんな彼はどのような人生を送ったのでしょうか。
傲慢で天才、革新的で斬新。
彼が生み出したさまざまな手法は、その後のクラシック音楽に大きな変革をもたらしました。
リヒャルト・ワーグナーの生涯1、音楽に囲まれた一家に生まれる
リヒャルト・ワーグナーは1813年5月22日、ザクセン王国(現ドイツ)のライプツィヒ生まれました。
1813年というと、ベートーヴェンやシューベルトといった大作曲家がまだ生きていた時代です。
ワーグナーの父は警察署で書記官をつとめた人物でしたが、生後間も無くこの世を去っています。
ワーグナー家はとにかく音楽にあふれた家族だったようで、家庭内で演奏会を開くなど、幼い頃から音楽を身近に感じて育ちます。
とりわけ幼いワーグナーに影響を与えたのが、『魔弾の射手』の作曲者として知られる、
カール・マリア・フォン・ウェーバーの存在でした。
独善的で傲慢な性格で知られるワーグナーですが、ウェーバーに対する尊敬と憧れの念は生涯変わらなかったと言われています。
また、青年期のワーグナーにとってウェーバーと同じくらい心酔したのが、ベートーヴェンです。
ベートーヴェンに心酔した15歳の青年ワーグナーは、17歳で『交響曲第9番』のピアノ独奏を編曲。
のちに埋もれていた『第9』を復活させるという偉業をなしとげています。
ちなみに、ピアノ独奏版を出版社に持ちこんだそうですが、
出版には至りませんでした。
生涯その2、青年期〜パリ時代、オペラの成功
ベートーヴェンにどっぷりの青春時代を送ったワーグナー。
18歳でライプツィヒ大学に入学すると、哲学や音楽の勉強を始めます。
最終的に大学を中退したワーグナーですが、この頃から本格的な作曲活動も始めており、
1832年に『交響曲ハ長調』や最初のオペラ『婚礼』などを作曲しています。
特にオペラ『恋愛禁制』はシェークスピアの戯曲をもとに、ワーグナー自身が台本を執筆し、大きな話題となりました。
さらに1830年代半ばからは評論家としての活動を開始。
1834年にワーグナー初となる論文『ドイツのオペラ』を新聞に発表しています。
1830年代後半からは、当時空前の人気を獲得していた作曲家マイヤベーヤを頼り、
パリ進出を計画するも失敗。
これによりマイヤベーヤへの確執が生まれ、パリ楽団やユダヤ人への敵視へと繋がり始めます。
オペラ『リエンツィ』のパリ上演の希望は叶わなかったものの、1842年にドレスデンで行われた初演は大成功を収め、作曲家としてのワーグナーの認知がようやく高まり始めたのでした。
また、よく1843年には代表作『さまよえるオランダ人』を発表しましたが、
こちらは『リエンツィ』ほどの評判は得られなかったそうです。
しかし同年にザクセン宮廷指揮者に任命され、
作曲家・指揮者・評論家としての地位を着実に固めていきます。
生涯その3、亡命時代
宮廷指揮者として活動するワーグナー。
一方で、1845年にはオペラ『タンホイザー』を発表し、オペラ作曲家としての地位も高まり始めます。
またこの頃のワーグナーはドイツ神話に関心を寄せ始め、古代ゲルマン神話の研究の没頭したそうです。
しかし時は革命時代。
1848年革命(三月革命)に参加したワーグナーは、1849年のドレスデン蜂起において主導的立ち回りをしたことで当局から目をつけられ、ドレスデンからの逃亡を余儀なくされます。
しかもあろうことか、指名手配という事態にまで発展し、ワーグナーはスイスのチューリッヒへ亡命する事態となりました。
亡命先のスイスでは、ゲルマン神話の研究をさらに進め、『ローエングリン』などの傑作を世に送り出します。
しかし亡命により、ドイツで初演された『ローエングリン』を見ることができず、
ワーグナーが実際に聴いたのは、初演から11年が経った1861年だったそうです。
そして1864年、ようやくザクセンでの指名手配追放令が解かれ、ワーグナーはバイエルン国王ルートヴィヒ2世の寵愛を受けることとなります。
この時期はまさにワーグナーの黄金時代であり、1865年にはルートヴィヒ2世のために『パルシファル』を、そして1867年には『ニュルンベルクのマイスタージンガー』を作曲。
オペラ作曲家としての地位を不動のものにしていきます。
生涯その4、バイロイト祝祭劇場建設〜晩年
指揮者・作曲家・評論家として絶大な成功を収めたワーグナー。
1872年にバイロイトへ移住したワーグナーは、ここで一大プロジェクトを開始します。
それが現在でも毎年夏に開催されている「バイロイト音楽祭」の開催です。
ルートヴィヒ2世の援助により、自分の作品のためのだけのバイロイト祝祭劇場の建築を開始し、1876年についにワーグナー積年の夢を叶えます。
劇場では『ニーベルングの指環』のほか、ワーグナー最後の作品となる『パルジファル』も初演され、以降ワーグナー作品の聖地として多くの作曲家、そして聴衆の憧れの場所として親しまれるようになりました。
音楽家として貧困を極めた時代から、亡命、成功と波乱の人生を歩んだワーグナー。
そんな彼は、1883年2月13日、旅先のヴェネツィアにて論文執筆中に突然この世を去りました。享年69歳。死因は心臓発作でした。
ワーグナーの死はヨーロッパ中に衝撃を与え、訃報を受けたルートヴィヒ2世は「恐ろしいことだ」と一言述べ、体を震わせたそうです。
また敵対していたブラームスは、ワーグナーの死の知らせに弔意(ちょうい)を示し、合唱の練習を止めたと言われています。
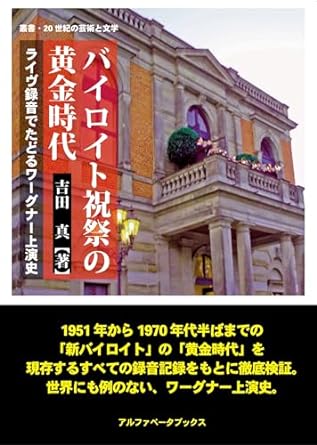
リヒャルト・ワーグナーの豆知識やエピソード

波乱万丈の人生を繰り広げたワーグナー。
そんな彼にはかずずのエピソードが残されています。
その中から、今回は3つのエピソードを見て見ましょう。
リヒャルト・ワーグナーの豆知識やエピソードその1、指名手配される
音楽家であると同時に、ある種の活動家でもあったワーグナー。
そんな彼は、上述したように1849年、ドレスデンで起きたドイツ三月革命に参加しています。
若かりし頃のワーグナーはかなり血気盛んだったようで、一時は国を壊すことも辞さない思想に傾倒していたそうです。
そのため革命ではバリケードの前線に立ち、周囲を扇動する立ち回りを見せました。
しかし当然、これにより当局に目をつけられたワーグナーは、指名手配となりスイスに逃れることとなりました。
スイスでは9年間を過ごしていますが、この手助けをしたのが、義理の父であるフランツ・リストです。
その2、ブラームスとの対立
ワーグナーはロマン派音楽の特徴でもある「標題音楽」の旗手でもありました。
19世紀後半における音楽は、ブラームスに代表される「絶対音楽」と「標題音楽」の対立の時代でもあります、
ちなみに「絶対音楽」とは、音楽のための音楽を目指す作品のことです(超ざっくりとですよ)。
一方「標題音楽」は、作品に物語(文学など)を導入する音楽のこと(こちらもざっくりです)。
その意味において、神話学を熱心に研究し作品に盛り込んだワーグナーと、音楽のための音楽を目指したブラームスはまさに「水と油」の関係でした。
この対立は音楽の2極化を生み、大論争を巻き起こしています。
その3、ユダヤ人批判
ワーグナーは批評家としても重要な役割を果たしています。
その中でも、ユダヤ人に対する批判は現在でも広く知られています。とくに1850年に発表した論文『音楽におけるユダヤ性』が有名で、ワーグナーはこの中でユダヤ人作曲家のマイヤベーヤやメンデルスゾーンを批判の対象としています。
ワーグナーのユダヤ人問題は、短く語ることはできません。
一説によると、マイヤベーヤに対する失望から始まったとも言われていますし、一方でワーグナーは多数のユダヤ人と親交を深めていたこともわかっています。
もしこの問題に興味のある方がおられましたら、ぜひご自身で確かめてみてください!
リヒャルト・ワーグナーの生涯まとめ
今回はリヒャルト・ワーグナーの生涯について簡単ざっくりと解説しました。
パート2も必要かなと思ったですが、ひとまずここまでにします。
次回は作品の特徴や魅力、代表作を解説しますので、そちらも併せてご一読くだされば幸いです!