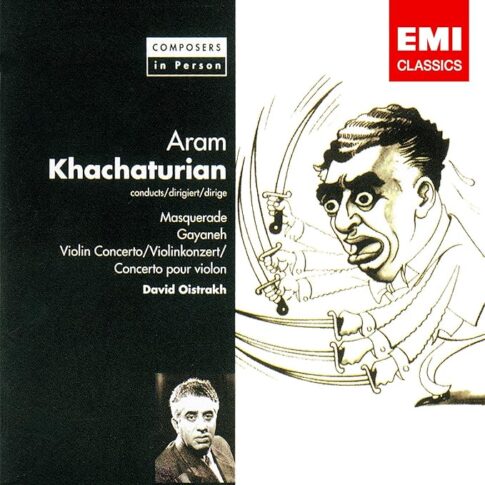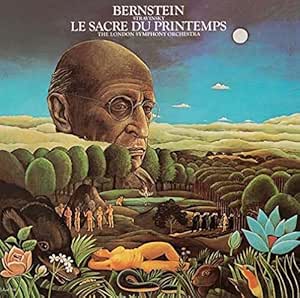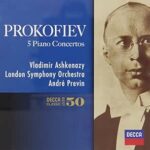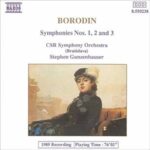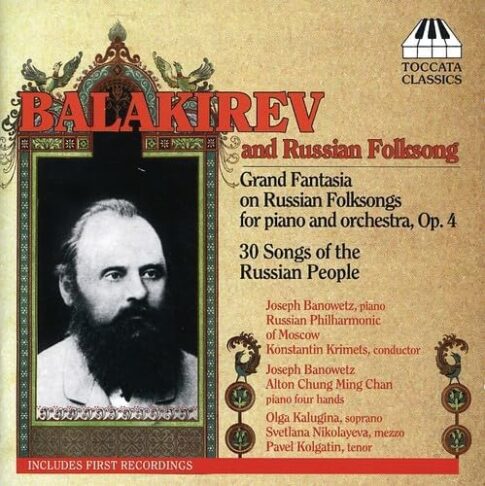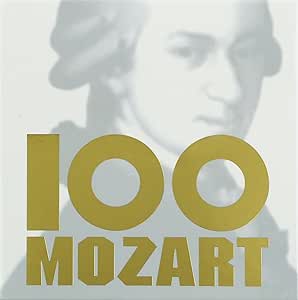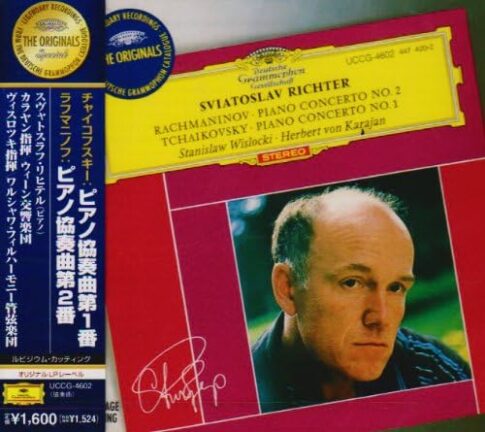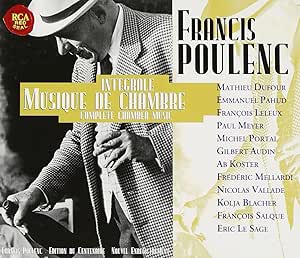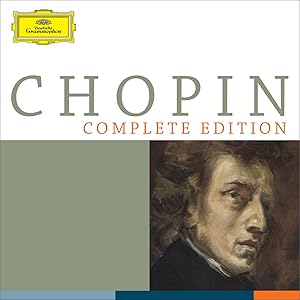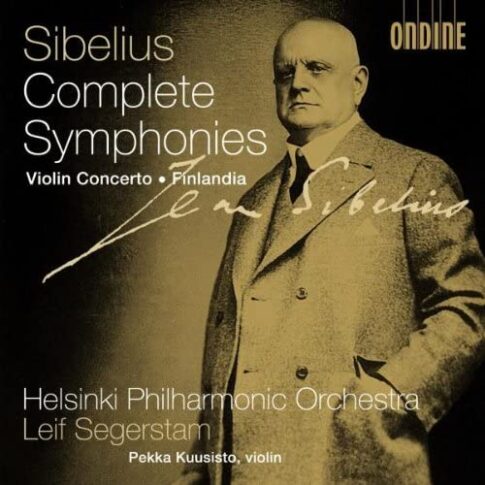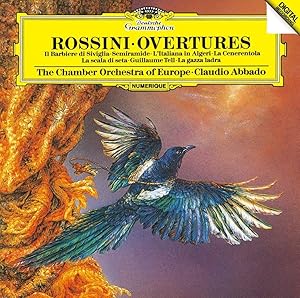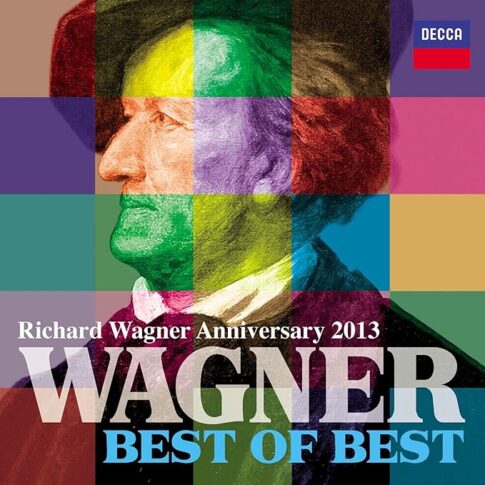今回は、20世紀最高の作曲家と称されるセルゲイ・プロコフィエフ(以下プロコフィエフ)を紹介します。
これまた「聞いたことな」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、プロコフィエフによるオペラ『ロミオとジュリエット』をお聴きいただければ、きっと「この作曲家か!」となるはずです。
幼少期から天才的な才能を発揮したプロコフィエフは、「モーツァルトの再来」とも言われており、その作品は現在でも演奏会の定番曲として演奏されています。
ピアノ曲から交響曲、そしてオペラまで幅広いジャンルで傑作を残した、プロコフィエフとはどんな人物だったのでしょうか。
今回もいつもながらざっくりと解説していますので、ぜひ最後までご一読ください。
同時期に活躍した作曲家にはハチャトゥリアンがいます。
こちらの記事も併せてお読みいただくと、より教養が深まりますよ!👇
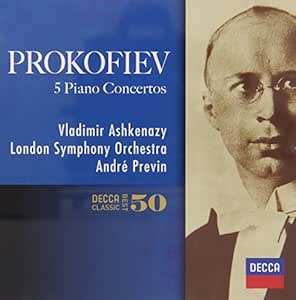
隙間時間も12万冊の本から耳で学べる
amazon audible
いつでも解約OK
プロコフィエフの生涯年表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1891年 | ロシア帝国(現ウクライナ領)のソンツォフカに生まれる。幼少期から作曲を始める。 |
| 1904年 | 13歳でサンクトペテルブルク音楽院に入学。才能を発揮し注目される。 |
| 1913年 | ピアノ協奏曲第2番を発表し、前衛的な作風で話題に。 |
| 1918年 | ロシア革命後、アメリカへ亡命。のちにヨーロッパ各地でも活動。 |
| 1921年 | オペラ《3つのオレンジへの恋》をシカゴで初演。風刺的な作風が話題に。 |
| 1936年 | スターリン体制下のソ連に帰国。児童向け作品《ピーターと狼》を発表。 |
| 1940年 | バレエ《ロメオとジュリエット》の音楽で高い評価を受ける。 |
| 1945年 | 交響曲第5番が成功を収め、ソ連国内での地位を確立。 |
| 1948年 | ジダーノフ批判により「形式主義」とされ、多くの作品が演奏禁止に。 |
| 1953年 | スターリンと同じ日に死去(3月5日)。享年61歳。死後、再評価が進む。 |
プロコフィエフの生涯について

今回はセルゲイ・プロコフィエフの波乱に満ちた人生と音楽について探ります。
革新的な作曲技法と豊かな表現力で知られるプロコフィエフの生涯は、まさに激動の20世紀そのものを体現していると言えるでしょう。
プロコフィエフの生涯その1、早熟な音楽の才能
プロコフィエフは1891年、ロシア帝国エカテリノスラフ県(現在のウクライナ)に生まれました。
父親は農業技術者、母親は音楽を愛する女性でした。
幼いプロコフィエフは、母親のピアノ演奏に触発され、驚くべきことに5歳で最初の作品『インドのギャロップ』を作曲しています。
音楽への情熱は日に日に強まり、9歳になる頃には、オペラ『巨人』や序曲、様々な小品を手がけるまでになりました。
この早熟な才能は、周囲の大人たちを驚かせたのは言うまでもありません。
プロコフィエフの生涯その2、才能の開花と実験的な試み
1902年、プロコフィエフの母親はモスクワ音楽院の学長セルゲイ・タネーエフと出会います。
タネーエフは若きプロコフィエフの才能を見抜き、作曲家のレインゴリト・グリエールに指導を依頼しました。
そして11歳のプロコフィエフは、初めて交響曲の作曲に挑戦し、不協和音や変則的な拍子を用いた実験的な作曲を始めます。
1904年、プロコフィエフはサンクトペテルブルク音楽院の入学試験に合格します。
ここで本格的な音楽教育を受けることになりましたが、彼の革新的な創作スタイルは、時に伝統的な教育方針と衝突することもありました。
生涯その3、音楽界での評価
音楽院在学中、プロコフィエフは徐々に作曲家としての名声を獲得していきます。
1909年には、非常に半音階的で不協和な練習曲集 作品2を発表し、当時の音楽界に衝撃を与えました。
1913年には初めての海外旅行でパリとロンドンを訪問。
そこでセルゲイ・ディアギレフのバレエ・リュスと出会います。この出会いは、後のプロコフィエフの創作活動に大きな影響を与えることになりました。
1914年、音楽院の最終試験「ピアノ勝負」で、自作の『ピアノ協奏曲第1番』を演奏して優勝。このことは、彼が作曲家としてだけでなく、ピアニストとしても優れた才能を持っていたことを示すのに十分でした。
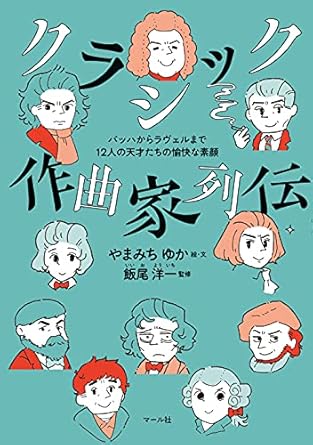
生涯その4、激動の時代を生きる芸術家
やふぁて第一次世界大戦が勃発すると、プロコフィエフは音楽院に戻ってオルガンを学び、徴兵を免れました。
この時期、彼は『交響曲第1番』や『ヴァイオリン協奏曲第1番』を作曲しています。
1917年のロシア革命後、プロコフィエフはアメリカへの亡命を決意。
翌年1918年にサンフランシスコに到着し、アメリカでの活動を開始しました。
しかし、彼の革新的な音楽スタイルは、アメリカの聴衆には理解されにくかったようです。
また、すでに亡命していたラフマニノフとは、しばしば比較対象として見られていたそうです。
その後、プロコフィエフはヨーロッパに移り、パリを拠点に活動を続けます。
1922年にはバイエルンの小村エッタルに移住し、オペラ『炎の天使』の作曲に没頭しました。この頃、彼の音楽はロシア国内でもファンを獲得し始めます。
生涯その5、栄光と苦難の日々
1927年、プロコフィエフは初めてソ連への演奏旅行を実施。
故郷での大成功を経験し、徐々にソ連への帰国を考えるようになります。
そして1936年、彼はついにモスクワに居を構えることを決意しました。
この時期、プロコフィエフは『ピーターと狼』や映画音楽『アレクサンドル・ネフスキー』など、今日でも広く親しまれている作品を生み出しています。
また、ピアノソナタ第6番、第7番、第8番(通称「戦争ソナタ」)を作曲したのもこの時期です。
1938年には、映画監督セルゲイ・エイゼンシュテインと共同で『アレクサンドル・ネフスキー』を制作。
この作品は後にカンタータとして改作され、多くの演奏と録音に恵まれました。

生涯その6、創作の自由と制約の狭間で
第二次世界大戦中、プロコフィエフは他の芸術家たちと共に疎開生活を送りながらも、創作活動を続けました。
戦時中は「社会主義リアリズム」の制約が緩和され、比較的自由に作曲することができたようです。
この時期、彼はトルストイの『戦争と平和』を題材としたオペラの作曲に取り組みました。
また『ヴァイオリンソナタ第1番』、交響組曲『1941年』、カンタータ『名もない少年のバラード』なども、この時期に生まれています。
1943年には、カザフスタンの都市アルマ・アタでエイゼンシュテインと再会し、映画音楽『イワン雷帝』や、美しい旋律で知られるバレエ『シンデレラ』を制作しました。
生涯その7、政治的圧力と健康問題、そして晩年(死因)
戦後、プロコフィエフは交響曲第6番やピアノソナタ第9番などを作曲しますが、1948年に「ジダーノフ批判」の対象となります。
彼の多くの作品が演奏禁止となり、経済的にも苦しい状況に陥りました。
健康面でも問題が生じ、医師から作曲時間を1日1時間に制限するよう要請されます。
しかし、そんな中でも彼は創作活動を続け、最後まで音楽への情熱を失うことはありませんでした。
プロコフィエフは1953年3月5日、61歳でこの世を去りました。死因は脳出血による呼吸不全だったそうです。
また、この日は皮肉にも、これはスターリンの死と同じ日でした。
スターリンの国葬の混乱の中、プロコフィエフの葬儀は30人ほどの小規模な参列者で執り行われましたが、葬儀にはショスタコーヴィッチも参列していたそうです。
彼の遺体はモスクワのノヴォデヴィチ墓地に埋葬され、後に妻のミーラ・メンデリソンも同じ場所に眠ることになります。2人の墓石には「私たちは隣り合わせに葬られることを望む」という言葉が刻まれているそうです。
プロコフィエフの豆知識やエピソードについて

数々の天才エピソードが残されているプロコフィエフ。
そこで今回は、明日話せる豆知識やエピソードを簡単に3つ紹介します。
サラッとはなせれば、「クラシック好き」と思われる可能性大です。

プロコフィエフの豆知識やエピソードその1、チェスの名人でもあった
音楽史上最高クラスの才能を発揮したプロコフィエフ。
ところが、彼が強い興味を示したのは音楽だけではありませんでした。
なかでも夢中になったのがチェスだったそうで、7歳の頃までにはチェスの指し方を完璧マスターしていたのだとか。
やがてチェスの世界王者ホセ・カパブランカとも知り合いになり、模擬戦で勝利するほどの腕前だったそうです。
プロコフィエフの豆知識やエピソードその2、日本に2か月滞在した
第一次世界大戦時の1918年、アメリカへの亡命を決心したプロコフィエフ。
5月にシベリア鉄道に乗ってモスクワを発つと、同月末に福井県敦賀(つるが)港に到着し、6月1日には東京を訪れています。
その後、次の船の便を待つ間2か月間日本を旅し、京都の祇園や琵琶湖、大阪、奈良、軽井沢、箱根などを訪れています。
また、奈良滞在中には『ピアノ協奏曲第3番』の構想をねり、作曲家のインスピレーションに大きな影響をもたらしたと言います。
また、同年7月に東京と横浜でピアノ・リサイタルを開いており、異国の地を十分に満喫したそうです。
プロコフィエフの豆知識やエピソードその3、ストラヴィンスキーとの確執(かくしつ)
ロシアの総合芸術プロデューサー、セルゲイ・ディアギレフがオペラ『3つのオレンジの恋』に関心を示したときのこと。
ディアギレフはプロコフィエフにピアノ伴奏版の演奏を依頼します。
この依頼にまんざらでもなかったプロコフィエフですが、オーディションの時に事件が勃発。
当時オーディション会場にいたストラヴィンスキーは1幕が終了後に聴くのを拒否し、プロコフィエフに対して「オペラを作曲して時間を浪費している」と非難を浴びせます。
しかしこれに対しプロコフィエフは「自身が誤りに対する耐性がないのだから、芸術の常道を主張できる立場にない」と反論。ストラヴィンスキーはこれに激怒し、殴り合いの喧嘩に発展しそうになったのだとか。
これ以降、二人の間に確執が生まれ、ストラヴィンスキーによるプロコフィエフ批判が続いたそうです。
プロコフィエフの豆知識やエピソードその4、短編小説家でもあった?
ソビエトを離れた1918年以降、プロコフィエフはいくつかの短編小説を手がけています。
アメリカへの移動時間も長いし、常に楽器に触れたわけではないので、もしかしらた気晴らしで書いていたのかもしれません。
しかしながら、21世紀に入った2003年にプロコフィエフの小説がロシアで刊行され、2009年には日本語版も販売されています。
音楽だけでなく、小説も読んでみたい方はぜひ一読してみてはいかがでしょうか。
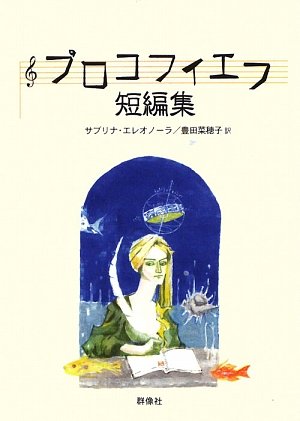
プロコフィエフの生涯まとめ
ということで、今回はプロコフィエフの生涯をざっくりと解説しました。
どのジャンルでも優れた作品を残した彼は、まさに「20世紀最高の作曲家の一人」と言えるでしょう。
チェスの名人だったり、小説も書いていたというのは、プロコフィエフ好きな方でも、始めた耳にした方もいらっしゃるかと思います。
また、プロコフィエフにそれほど関心がなかった方も、この記事をきっかけに改めて知る機会になれれば幸いです。
別記事は作品の特徴やおすすめ代表曲も紹介していますので、ぜひそちらも併せてご一読ください。
新着記事一覧
楽器をお探しの方に向けた記事も書いていますので、参考にしてください👇