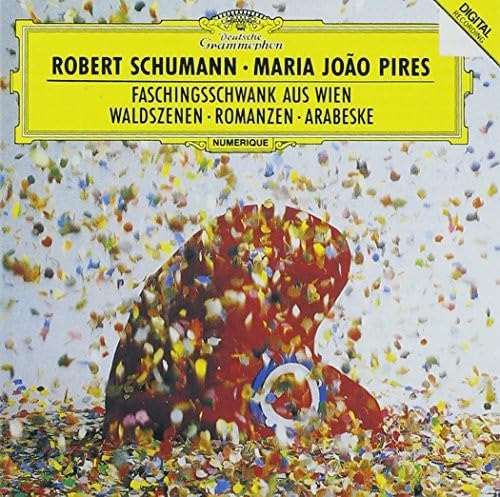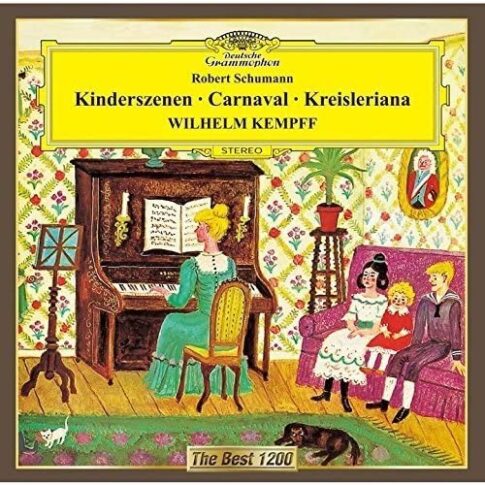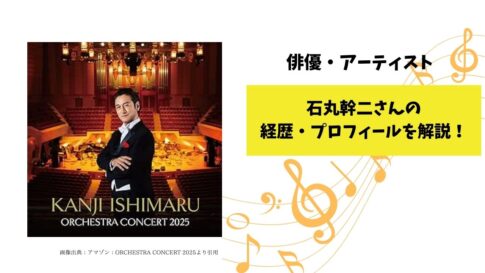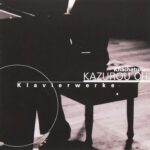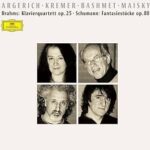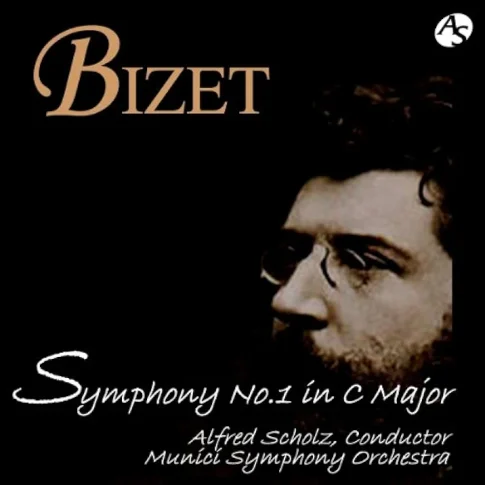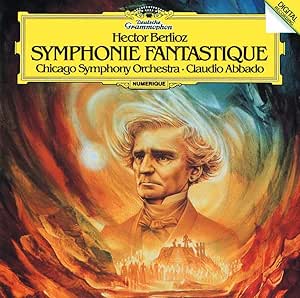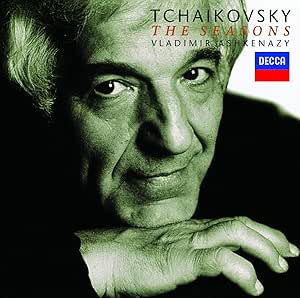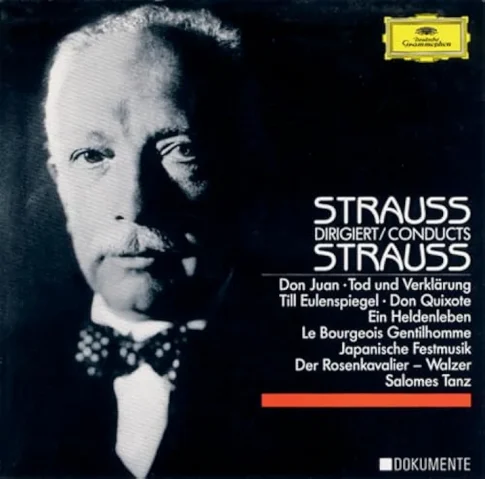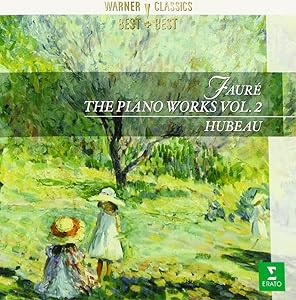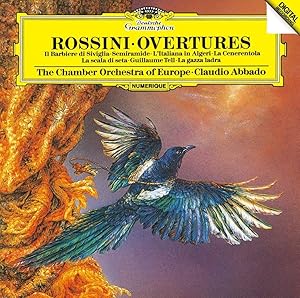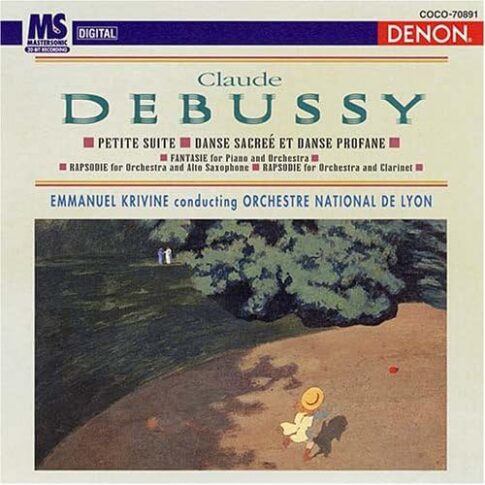今回はシューマンの色彩豊かな「ウィーンの謝肉祭の道化」の難易度を解説します。
ロマン派の作曲家、ロベルト・シューマン。
シューマンの作品って、詩的で内省的な世界観でありながら、情熱的な表現が魅力ですよね。
この記事では、シューマンの「ウィーンの謝肉祭の道化」に焦点を当て、作品の概要から、全5楽章それぞれの詳細な難易度、弾きこなすための練習法やコツまでを徹底解説します。
この記事でわかること
各作品には演奏動画もありますので、ぜひ参考にしてください!
筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年ほどピアノに触れています(音大には行ってません)。
シューマンとはどんな作曲家?
29歳頃のシューマン:出典:Wikipedia
作品解説に入る前に、少しだけシューマンについておさらいです。
ロベルト・シューマン(Robert Schumann, 1810-1856)は、19世紀ドイツのロマン派音楽を代表する作曲家、音楽評論家です。
ヨハネス・ブラームスの師匠としても有名ですね。
文学や哲学に深く傾倒し、その影響は音楽に色濃く反映されています。
特にピアノ曲においては、内面的な感情や幻想的な世界を描写した性格的小品集を多く作曲しました。
シューマンの音楽は、流麗で美しい旋律に加え、複雑なリズム、大胆な和声、そして多声的な書法が特徴です。
また、彼は自身の分身ともいえる架空の人物「フロレスタン」(情熱的、衝動的)と「オイゼビウス」(内省的、夢想的)を設定し、これらのキャラクターを通して多様な感情や音楽的アイデアを表現しました。
シューマンについての詳しい解説はこちらの記事が参考になりますよ。
「ウィーンの謝肉祭の道化」とは? 作品の概要と魅力
「ウィーンの謝肉祭の道化」の正式名称は、ドイツ語で『Faschingsschwank aus Wien, Op. 26』です。「Faschingsschwank」は「謝肉祭の冗談」「謝肉祭の道化」といった意味合いを持ち、「aus Wien」は「ウィーンの」を意味します。
文字通り、ウィーンの謝肉祭の様子を描いた作品であり、同時にシューマンらしい諧謔(かいぎゃく)や皮肉、そして深い感情が込められた作品と言えるでしょう。
「ウィーンの謝肉祭の道化」が作曲されたのは1839年。シューマンがウィーンに滞在していた時期にあたります。この時期、彼はクララ・ヴィークとの結婚を巡る問題や、自身の音楽雑誌のウィーンでの普及に苦心していた時期でもあります。
そのような状況下で生まれたこの作品には、ウィーンのにぎわいと共に、シューマンの内面的な葛藤やユーモアが込められていると言われます。
本作は、5つの作品で構成されるピアノ独奏曲です。
- アレグロ (非常に速く)
- ロマンス (いくらか遅く)
- スケルツィーノ (いくらか速く)
- 間奏曲(きわめて速く)
- フィナーレ (きわめて速く)
各楽章は独立した性格を持ちながらも、全体として一つの物語のような流れを持っています。
ウィーンの街を練り歩く謝肉祭の賑わい、仮装した人々の喧騒、そしてその中に垣間見える内省的な瞬間や、シューマンが当時オーストリアで禁じられていたフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の断片を忍ばせるなど、遊び心も満載です。
参考|ピティナ・音楽事典|シューマン :ウィーンの謝肉祭の道化芝居「幻想的情景」 Op.26
「ウィーンの謝肉祭の道化」全曲の総合的な難易度
本作は、ピアノ曲として非常に高い技術と音楽性を要求される作品です。
総合的な難易度:★★★★☆
星4つかなと。なので、かなりの難曲です。
この曲の難しさの理由を思いつく限り上げてみました。
超絶技巧: 特に第1楽章、第4楽章、第5楽章には、速いパッセージ、広い跳躍、オクターブ、重音、複雑なリズムなどが頻繁に登場し、高度な指の訓練が必要。
両手の独立性: 左右の手が全く異なるリズムや動きをすることが多く、両手の独立したコントロールが求められます。
音楽性の深さ: 単に音符を追うだけでなく、シューマン特有の感情の機微、ユーモア、そして各楽章のキャラクターを描き分ける表現力が大切。
構成感: 全5楽章を通して演奏するには、全体の構成を理解し、各楽章の関係性を意識した演奏が求められます。
持久力: 特に終楽章は長く、技術的な要求も高いため、最後まで集中力と体力を維持する持久力が必要です。全体の演奏時間はだいたい20分程度。
これらの観点からすると、「ウィーンの謝肉祭の道化」は、ピアノ学習者にとっては相当な上級レベルに達してから取り組むべき作品と言えると思います。
シューマンはロマン派の中でも、とっつきにくいかもしれません。
各楽章の詳細な難易度と攻略ポイント【動画あり】
全曲版:出典:YouTube
ここからは、「ウィーンの謝肉祭の道化」の各楽章に焦点を当て、それぞれの難易度と演奏上のポイントを詳しく解説していきます。それぞれの楽章の雰囲気を掴むために、ぜひ動画も参考にしてください。
第1曲:アレグロ (非常に速く) – 難易度と解説
難易度:★★★★☆
ソナタ形式で書かれており、ウィーンの謝肉祭の賑わいを描いたかのような、非常に活気に満ちた楽章です。冒頭から速いパッセージが連続し、演奏者には高度な指のテクニックが要求されます。
攻略ポイント:ゆっくりとしたテンポから始め、正確な音とリズムで練習することが不可欠です。メトロノームを積極的に活用しましょう。音楽的には、Allegroの速さの中に、歌うべき旋律や表情の変化を見つけることが重要です。
出典:YouTube
第2曲:ロマンス (いくらか遅く) – 難易度と解説
難易度:★★★☆☆
一転して内省的で美しいロマンツェです。シューマンらしい甘く切ない旋律が特徴的で、技術的な難しさよりも、音楽的な表現力が問われる楽章と言えます。
攻略ポイント:主旋律を丁寧に歌う練習から始めましょう。
内声部の動きを意識し、それぞれの声部が埋もれないようにバランスを取る練習をします。
様々なペダリングを試しながら、最も美しい響きを見つけましょう。
出典:YouTube
第3曲:スケルツィーノ (いくらか速く) – 難易度と解説
難易度:★★★☆☆
第3曲目は「スケルツィーノ」。つまり小さなスケルツォです。軽快でユーモラスな雰囲気が特徴で、短いながらもシューマンらしい遊び心が詰まっています。
攻略ポイント:指のトレーニングとして、スタッカートとレガートを交互に練習するなどの方法が有効。メトロノームを使って、徐々にテンポを上げていく。楽譜に書かれた強弱やアーティキュレーションを丁寧に読み込み、キャラクターを明確に表現することを意識してみましょう。
出典:YouTube
第4曲:間奏曲 (きわめて速く) – 難易度と解説
難易度:★★★★★
この作品の中で最も技術的に難易度が高いとされる楽章です。シューマンがウィーンで密かに引用したとされる「ラ・マルセイエーズ」の断片が登場するなど、音楽的にも非常に興味深い内容を持っています。
「ラ・マルセイエーズ」の引用: 隠された引用部分を、音楽的にどのように表現するかも課題となります。
攻略ポイント:ポリリズムの練習は、それぞれの声部を片手ずつ完璧に弾けるようにしてから、両手でゆっくりと合わせる練習を根気強く行います。メトロノームを使い、拍子を意識することが重要です。複雑な対旋律は、それぞれの声部を異なる音色やタッチで弾き分ける練習をしましょう。
出典:YouTube
第5曲:フィナーレ (きわめて速く) – 難易度と解説
難易度:★★★★☆
全曲を締めくくる華やかで壮大なフィナーレです。第1曲と同様に速いテンポで、技術的な見せ場が多く含まれています。演奏効果バツグンのフィナーレです!
攻略ポイント:オクターブや重音は、手首や腕の力を抜き、バネのように使う練習すると良いです。音楽的には、フィナーレにふさわしい壮大さ、そして謝肉祭の終わりの名残惜しさのような感情も表現できると良いでしょう。
出典:YouTube
「ウィーンの謝肉祭の道化」を弾きこなすための練習法・コツ
出典:YouTube
ここまで各作品について、演奏のポイントや難易度を解説してきました。
「これなら弾けそう!」「まだムリそうかな・・・」など、なんとなくイメージできたのではないでしょうか。
どちらにせよ、「ウィーンの謝肉祭の道化」は、簡単に弾けるようになる曲ではないと思います。時間をかけて、1曲ずつ丁寧に練習してみましょう。
ここでは、効率的な練習法やコツをいくつか紹介します。
本作だけに当てはまるものではないのですが、意識して取り組んでみてください。
基礎練習の徹底: スケール、アルペジオ、オクターブ、重音などの基礎練習は、毎日欠かさず行い、指の独立性、均一性、瞬発力を高めましょう。
部分練習: 難しいパッセージや跳躍、ポリリズムの箇所は、全体を通す前に徹底的に部分練習を行います。ゆっくりとしたテンポから始め、徐々に速度を上げていきます。
リズム練習: 特に第1楽章や第4楽章のようなリズムが複雑な箇所は、メトロノームを使って正確なリズム感を養う練習が重要です。様々なリズムパターンで練習するのも効果的です。
音楽的な分析: 楽譜に書かれた指示(強弱、アーティキュレーション、速度変化など)を丁寧に読み込み、作曲家が意図した音楽を理解しようと努めます。曲の形式や構成を理解することも、演奏に深みを与えます。
参考音源を聴く: 様々な演奏家の音源を聴くことで、解釈の幅が広がり、自身の演奏のヒントになります。ただし、鵜呑みにせず、自身の音楽性を大切にすることも重要です。
ウィーンの謝肉祭の道化:おすすめ楽譜
最後におすすめ楽譜を紹介します。
さまざまな版が出ていますので、ご自身に合った楽譜を選びましょう。
なお、ピアノの先生から指定されたものがあれば、そちらを使用してくださいね!
ヘンレ版
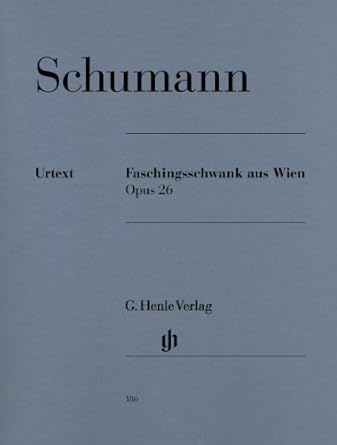
高品質な原点版です。校訂が丁寧で、譜面も非常に見やすいです。多くのプロの演奏家や教育者が使用しています。ちょっとお値段高めです。
ペータース社版
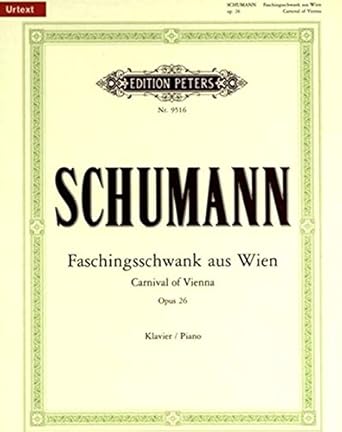
こちらも信頼性の高い版を提供しています。研究に基づいた正確な譜面が特徴です。
全音版
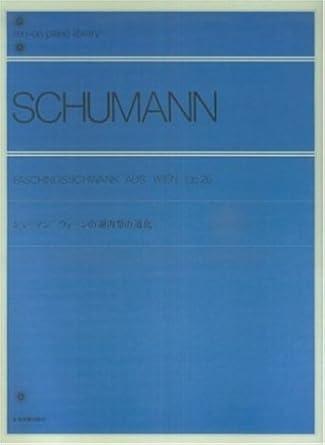
海外の楽譜は難しそう・・・。
という方は安定の全音版がおすすめです。
オンライン・ピアノレッスンに興味がある!という方はこちらの記事もおすすめです。
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。
そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。
もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!
「ウィーンの謝肉祭の道化」の難易度解説:まとめ
シューマンの「ウィーンの謝肉祭の道化」は、技術的にも音楽的にも非常に要求の高い作品です。
ウィーンの活気とシューマンの内面が交錯するこの魅力的な作品は、演奏者の表現力を引き出し、ピアニストとしての成長を促してくれます。挑戦してみたいと思われたなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。