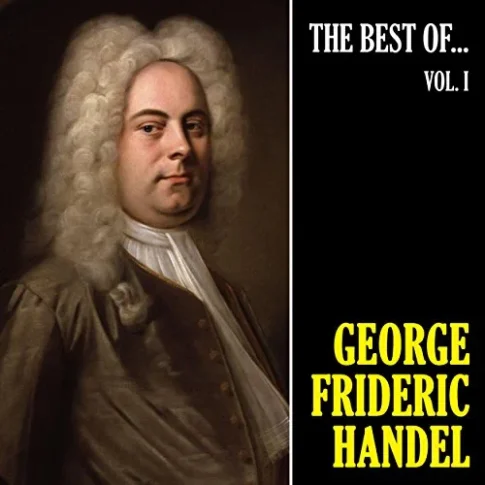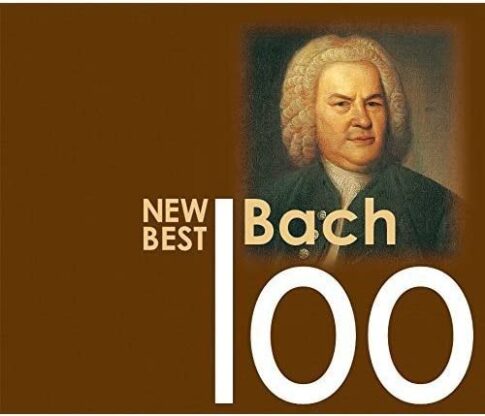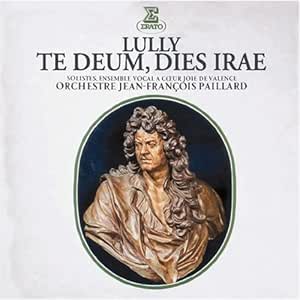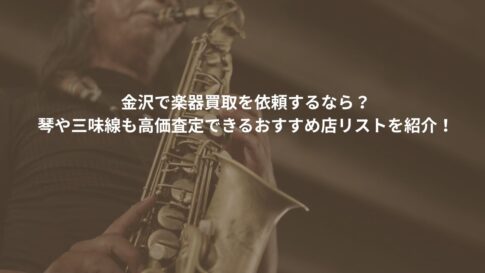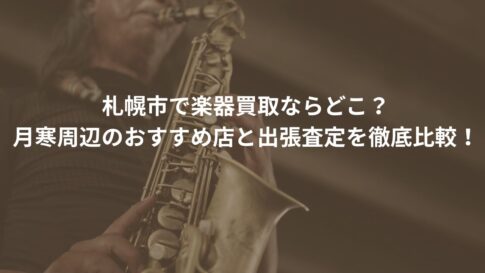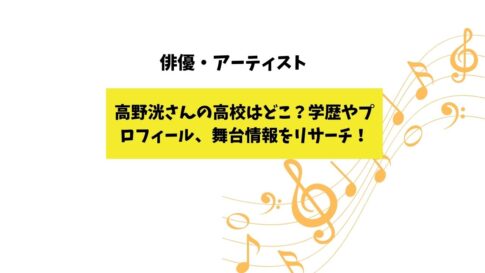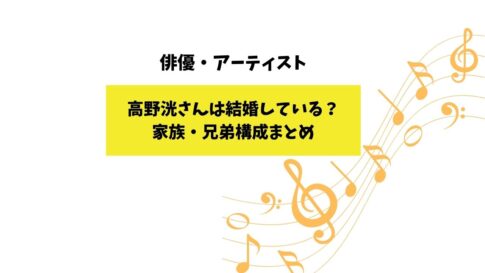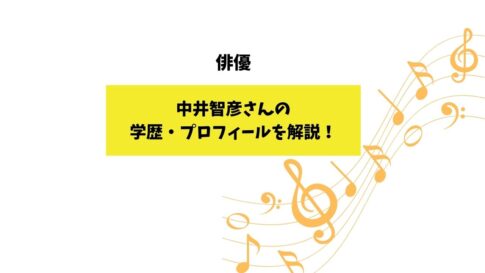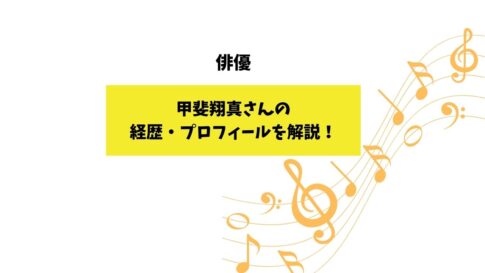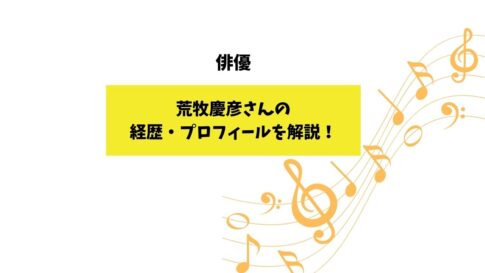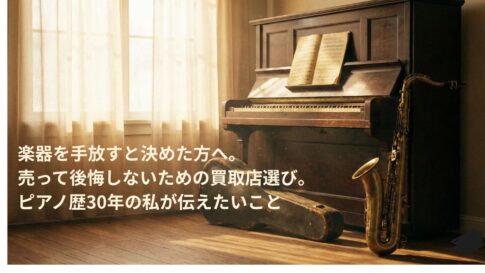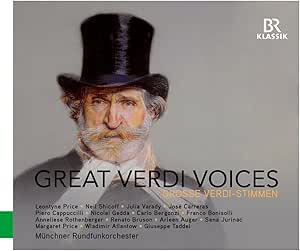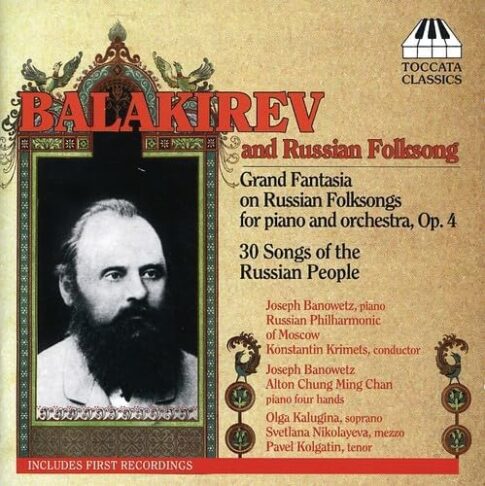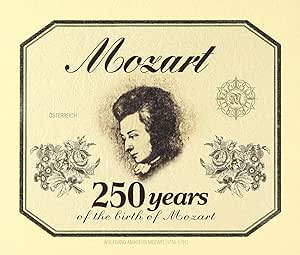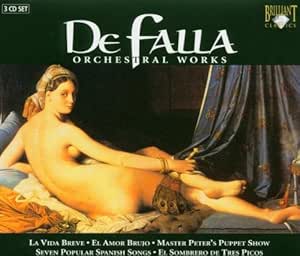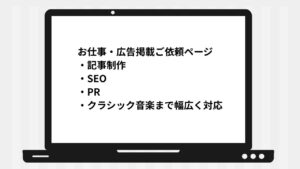この記事では、ジャン=フィリップ・ラモー(以下ラモー)について、エピソードを交えつつ紹介します。
ラモー(1683-1764)は、バロック音楽後期のフランスを代表する巨匠の一人。
「和声」の理論について深く探求しました。
その探求の成果は、現代の音楽理論教育に大きな影響を与えたことでも知られています。
そんなラモーの波乱に満ちた生涯を追いながら、代表曲やエピソードを分かりやすく解説。
この記事を読めば、ラモーという人物がどれほど革新的で、フランス音楽史においてどれほど重要な存在であったのかを知ることができますよ!
この記事でわかること
記事後半では、参考動画も紹介していますので、あわせてご覧ください!
ラモー、バッハ、ヘンデルの生涯年表比較(簡易版です)
バロック時代を代表するラモー。
ほぼ同時代に活躍したバッハやヘンデルの生涯と比較すると、わかりやすいと思います。
| 年代 | ラモー(1683–1764) | バッハ(1685–1750) | ヘンデル(1685–1759) |
|---|---|---|---|
| 1683 | 【誕生】ディジョンにて誕生 | ― | ― |
| 1685 | ― | 【誕生】ドイツ・アイゼナハにて誕生 | 【誕生】ドイツ・ハレにて誕生 |
| 1702 | パリへ移住(失敗して戻る) | リューネブルクに移る | 大学入学(中退後、音楽専念) |
| 1706 | イタリア音楽に影響を受け始める | オルガニストとして活動開始 | イタリア旅行で作曲研鑽 |
| 1715 | 音楽理論に関心を深める | ヴァイマル宮廷で活躍 | オペラ《リナルド》でロンドンデビュー |
| 1722 | 『和声論(Traité de l’harmonie)』を発表 | ケーテンで世俗音楽を中心に活動 | ロンドン定住、王立音楽アカデミー設立 |
| 1723 | ― | ライプツィヒ・聖トーマス教会カントル就任 | オペラ作曲家としての地位確立 |
| 1733 | オペラ《イポリートとアリシー》初演(成功) | 《ロ短調ミサ》の草稿開始 | 《オルガン協奏曲集》発表 |
| 1745 | 王室楽長となる(ヴェルサイユで活躍) | 晩年の宗教音楽に集中 | 《メサイア》イギリスで大ヒット |
| 1750 | ― | 【死去】65歳 | ― |
| 1754 | ルソーとの「ブフォン論争」激化 | ― | 《ユダス・マカベウス》など晩年の傑作 |
| 1759 | ― | ― | 【死去】74歳 |
| 1764 | 【死去】81歳 | ― | ― |
ジャン=フィリップ・ラモーとは?

ということで、本題です。
ジャン=フィリップ・ラモーは、17世紀末から18世紀にかけて、特にバロック音楽後期のフランスで活躍した中心的人物。同時代のドイツにヨハン・セバスチャン・バッハやゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルがいたように、フランスにおいては彼が最も重要な存在と言えるでしょう。
ディジョンでオルガン奏者の父のもとに生まれ、幼少の頃から音楽、特にオルガンやクラヴサンといった鍵盤楽器の演奏と即興に非凡な才能を発揮しました。
作曲家としてはジャン=バティスト・リュリが確立したフランス・オペラの伝統を受け継ぎつつ、そこに自身の革新的な和声と劇的な表現を導入して成功を収め、新たな時代を切り開きました。
ジャン=フィリップ・ラモーの生涯
ラモーの人生は、偉大な業績を残した一方、必ずしも若い頃から順風満帆だったわけではありませんでした。才能がありながらも、その真価が広く認められたのは、晩年にかけてのこと。そんな大器晩成のラモーの波乱に満ちた人生を見てみましょう。
ラモーの生涯:誕生から音楽の道へ
ジャン=フィリップ・ラモーは、1683年9月25日にフランス東部の都市ディジョンで生まれました。父親は当地のノートルダム教会のオルガン奏者であり、音楽教師も務めていた人物。
ラモーは幼い頃から父親から音楽の手ほどきを受け、早くからオルガンやクラヴサン(チェンバロ)といった鍵盤楽器の演奏に才能を示しました。
一方、学校の勉強にはあまり熱心ではなかったとのこと。それよりも、音楽に没頭する日々だったようです。彼の父親はラモーに法律を学ばせようとした時期もあったようですが、ラモーの音楽への情熱と才能は明らかであり、結局音楽の道に進むことになります。
青年期には、短期間イタリアへ旅行を経験。当時のヨーロッパではイタリアが音楽の中心地であり、この旅で最先端の音楽に触れたことが、彼の音楽観に影響を与えたとも考えられています。
帰国後、彼はフランス国内の様々な都市、例えばリヨン、クレルモン=フェラン、故郷ディジョンなどでオルガン奏者や音楽教師として働きました。
この時期に、後の彼の音楽理論の基礎となる、和声の響きや連結に対する深い考察を始めたと考えられています。和声感覚を養う上で、オルガン奏者としての経験が生かされたそうです。
音楽理論家としての確立(パリ進出〜主要な理論書の発表)
ラモーの人生にとって、大きな転機となったのは、1722年にフランス文化の中心地であるパリに進出したことです。当時のパリは、多くの芸術家や学者たちが集まる活気に満ちたヨーロッパ屈指の大都市。
ここでラモーは、彼の名を不朽のものとする画期的な音楽理論書を出版します。
それが、1722年に刊行された『和声論(正式名:自然の諸原理に還元された和声論)』です。
この本の中で、ラモーはそれまで経験則に基づいて扱われてきた和音や和声進行について、全く新しい、科学的で体系的な理論を展開します。
『和声論』は当時の音楽界に大きな衝撃を与え、ラモーは一躍、音楽理論家としてその名を知られるようになります。その後も、いくつかの重要な理論書を発表し、これによって、彼は近代音楽理論の礎を築いた人物として不動の地位を確立しました。
作曲家としての成功とオペラへの挑戦
音楽理論家として名声を得たラモー。
しかし、彼の最大の野心は作曲家、特にオペラ作曲家として成功することでした。
当時のフランス・オペラは、ルイ14世の宮廷音楽を支えたジャン=バティスト・リュリが確立したスタイルが依然として主流であり、その強固な牙城を崩すのは容易ではありませんでした。
そんなラモーが本格的にオペラ作曲に乗り出したのは、ようやく50歳を過ぎてからでのこと。
1733年に初演された彼の最初のオペラ『イポリートとアリシー』は、その革新的な音楽語法と劇的な表現により、当時の音楽界に激しい論争を巻き起こしました
リュリの伝統を重んじる保守的な人々(リュリ派)と大きな対立(「ラモー論争」)があったものの、当時のフランス社会における芸術や文化のあり方を巡る重要な議論となったのでした。
こうした論争にもかかわらず、ラモーは臆することなく次々と意欲的なオペラ作品を発表。
異国情緒あふれる『優雅なインドの国々』(1735年)、深い人間ドラマを描いた『カストールとポリュックス』(1737年)などのオペラを生み出し、ラモーはフランス・オペラの新たな巨匠としての地位を確立したのでした。
晩年と揺るぎない地位
晩年のラモーの名声はフランス国内に留まらず、やがてヨーロッパ各地に広がりをみせます。
特に、ルイ15世の宮廷との関係が深まると、ついに1745年、宮廷作曲家としての地位も獲得
作品は宮廷で頻繁に上演され、国王や貴族たちからも高い評価を受けるようになります。
作曲家としてはこれ以上ない大出世を果たしたラモー。
しかしラモーは晩年まで精力的に作曲を続け、特に、オペラ・バレ(バレエ)という形式の作品に新たな境地を開き、舞踏の要素が強く視覚的な華やかさも重視された作品を数多く生み出したのでした。
また、晩年には哲学者ジャン=ジャック・ルソーとの間でも音楽に関する論争を繰り広げています。これは、フランス音楽とイタリア音楽の優劣、そして音楽の役割についてのもので、当時のフランス社会の思想的な対立を反映したものでもありました。
ルソーがイタリア音楽の自然さや旋律の重要性を主張したのに対し、ラモーは自らの音楽理論に基づいた和声の表現力を強く主張しています。
ラモーの死去(死因)
数々ヒット作を世に送り出したラモーですが、1764年9月12日、パリにて死去。
80歳という、当時の平均寿命を考えるとかなりの高齢でした。
彼の死因については、病名が明確に記録されてはいませんが、一般的には老衰による自然死と考えられています。晩年は健康状態があまり優れなかったという記録もありますが、亡くなる直前まで創作意欲は衰えず、新しいオペラの構想を練っていたとも言われています。
葬儀は盛大に行われ、多くの人々が偉大な作曲家であり理論家であった彼の死を悼みました。
彼は生前に多くの栄誉を受け、その功績は高く評価されていましたが、彼の音楽理論の真の重要性が広く理解されるのは、彼の死後、さらに時代が進んでからのこととなります。
ラモーの代表曲5選

ここまで、ラモーの生涯についてざっくりと解説しました。
なんとなく軌跡をたどったところで、以下ではラモーの作品をちょっとだけみてみましょう。
ラモーの代表的な作品の中から、特に有名で聴きやすい5曲を紹介します。
ここはあくまでも「筆者の独断」ですので、その旨、あらかじめご容赦ください。
ラモーの代表曲その1:『優雅なインドの国々』より「未開人の踊り」
出典:YouTube
オペラ・バレ『優雅なインドの国々』の終幕で演奏される、非常にリズミカルでエキゾチックな舞曲。タムタムやフルートが効果的に使われ、当時のヨーロッパ人が抱いていた「野蛮」な文化のイメージが描かれています。ラモーの管弦楽法の妙が光る人気曲です。
ラモーの代表曲その2:『カストールとポリュックス』より序曲
出典:YouTube
彼の代表的な悲劇的オペラの一つ。この序曲は、ゆったりとした荘厳な部分と、それに続く活気のあるフーガ風の部分からなるフランス風序曲の形式を取りながらも、ラモーらしい劇的な表現力を併せ持っています。オペラの始まりを告げるにふさわしい、力強い音楽です。
ラモーの代表曲その3:クラヴサン曲集より「鳥のさえずり」
出典:YouTube
クラヴサン曲集の中でも特に有名で愛らしい小品。高音域の細かい音符やトリル、分散和音などを用いて、まるで鳥たちが楽しげにさえずっているかのような情景を描写しています。聴いていると心が和むような、描写音楽の傑作です。
クラヴサン(フランス語)、ハープシコード(英)、チェンバロ(独)、すべて同じ楽器です。
ラモーの代表曲その4:クラヴサン曲集より「タンブーラン」
出典:YouTube
プロヴァンス地方の伝統的な太鼓(タンブーラン)のリズムを模した、軽快で活気のある舞曲。シンプルながらも耳に残るメロディーが印象的な作品です。繰り返されるリズミカルなパターンなど、ラモーらしい和声の面白さも随所に感じられます。
ラモーの代表曲その5:『ダルダニュス』よりシャコンヌ
出典:YouTube
オペラ『ダルダニュス』の中で演奏される、壮大で力強いシャコンヌです。低音で繰り返される短い主題(バス)の上に、様々な旋律や和声が展開される変奏形式で書かれています。ラモーの構成力と、オーケストラの響きを最大限に活かした音楽が堪能できます。
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!
ここまでお読みいただき「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。
もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです。
少しでも関心のある方は、ぜひご一読ください!
ラモーの豆知識・知られざるエピソード3選
ラモーの作品、いかがでしたか?
バロックらしい響きでありながら、斬新さが随所に見える作品ばかりだと思います。
さて、そんな偉大な作曲家ラモーですが、彼の人間性についてもう少し深堀してみましょう。
ここでは、彼の知られざる一面が垣間見えるような、「なるほど」と思うようなエピソードを3つご紹介します。
豆知識・エピソード1:気難しい性格と論争好き
ラモーは非常に知的な人物でしたが、同時に非常に気難しい性格であったと言われています。自分の音楽理論や考え方に対して強い信念を持っており、それを巡ってしばしば他の音楽家や学者と激しい論争を繰り広げたとのこと。
特に有名なのが、前述の「ラモー論争」や、ジャン=ジャック・ルソーとの論争です。
ルソーはイタリア音楽の自然さやメロディーの重要性を主張し、ラモーの複雑な和声やフランス音楽の様式を批判しましたが、ラモーは一歩も引かず、自らの理論の科学性やフランス音楽の構造的な美しさを強く主張しました。
これらの論争は、当時のパリの知識人たちの間で大きな話題となり、ラモーの名前をさらに広く知らしめることにも繋がりました。
豆知識・エピソード2:生涯独身だった理由
ラモーが生涯結婚理由について、詳しいことはわかりません。
しかし、一説には、彼の音楽と理論研究への並々ならぬ情熱が、結婚や家庭生活に割く時間を許さなかったためだと言われています。
彼の伝記には、食事中や散歩中も音楽のことばかり考えていたという記述も見られます。例えば、散歩中に突然立ち止まり、地面に杖で音符や和音の記号を書きつけて考え込む姿が目撃されたという話もあります。
豆知識・エピソード3:晩年の意外な趣味?
厳格で気難しいイメージのあるラモー。
しかし、晩年には意外な一面を見せたというエピソードも残っています。
それは、鳥の鳴き声に耳を傾けることを楽しんだという話です。
彼のクラヴサン曲には、上に紹介した「鳥のさえずり」という可愛らしいタイトルの作品がありますが、これは単なる標題音楽ではなく、実際に鳥の鳴き声からインスピレーションを得て作曲したと言われています。
晩年、彼は庭で鳥の鳴き声を聞きながら、その音程やリズムを注意深く聞き取り、楽譜に書き留めることもあったそうです。
ラモーってどんな作曲家?代表曲は?:まとめ
ということで、今回はラモーの生涯や代表曲について解説しました。
ラモーが偉大な作曲家・音楽理論家であることが、ちょっとでも伝われば幸いです。
音楽史でも大変重要案人物ですので、この記事をきっかけに、あらためて作品に触れてみてはいかがでしょうか。
今回の内容を下記にまとめます。
- バロック後期の巨匠で、特にオペラを革新し、フランス音楽に新たな表現をもたらしました。
- 『和声論』を出版し、和音の根音などの概念を提唱、近代音楽理論の基礎を確立しました。
- 代表曲には、オペラ・バレの**「野蛮人たちの踊り」やクラヴサン曲の「鳥のさえずり」などがあります。
- 気難しい性格で、ルソーなどと論争も辞さず、自らの信念を貫きました。
- 生涯独身を貫き、その人生の全てを音楽の研究と創作に捧げました。
- 晩年には鳥の鳴き声に耳を傾けるなど、自然からインスピレーションを得る一面も持っていました。
- 1764年に老衰で死去しましたが、その革新的な理論と作品は後世に大きな影響を与えました。