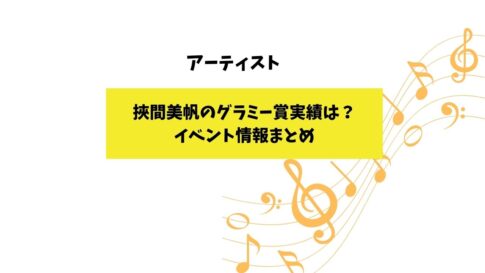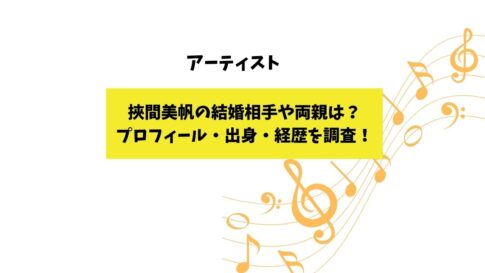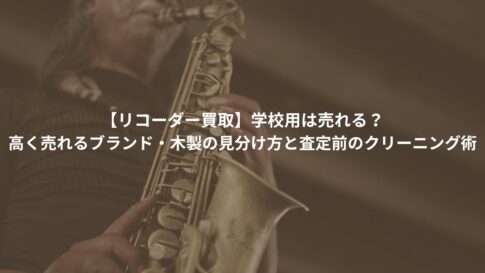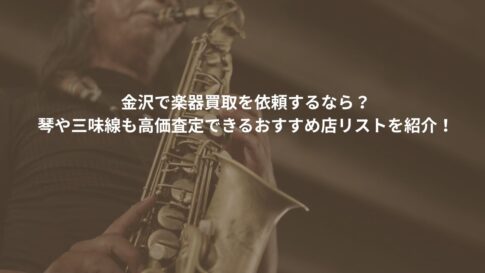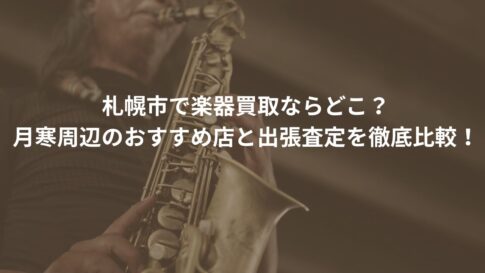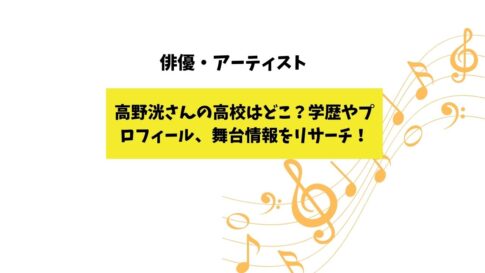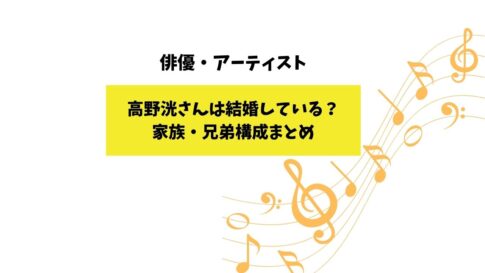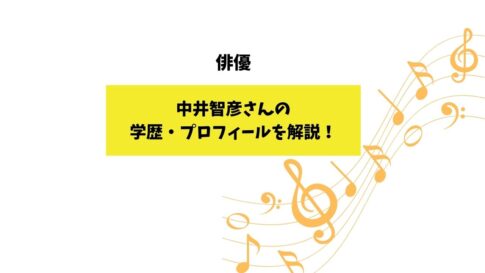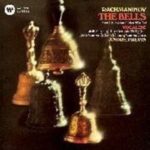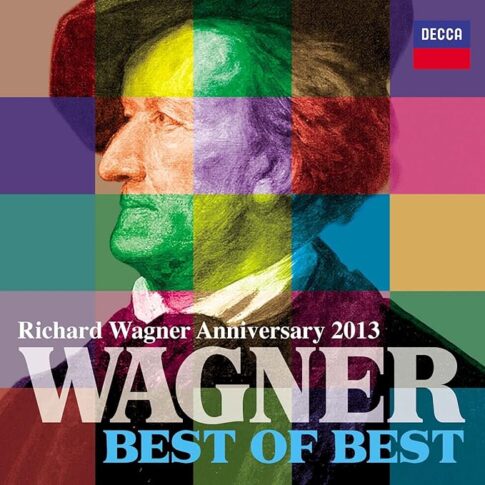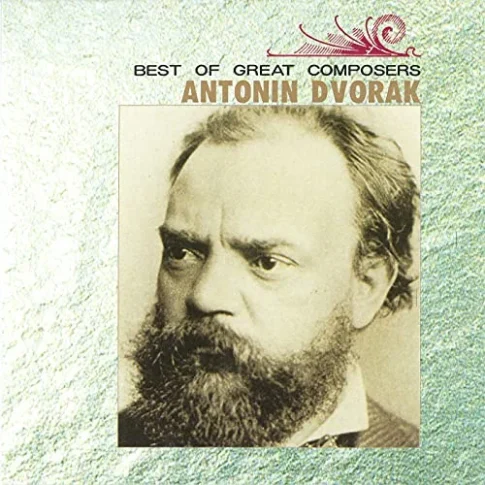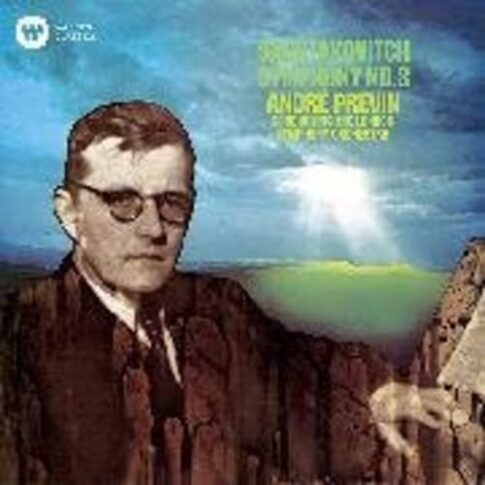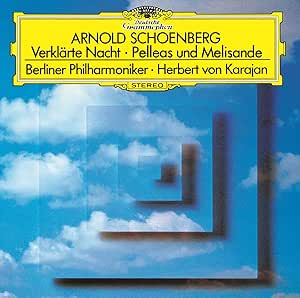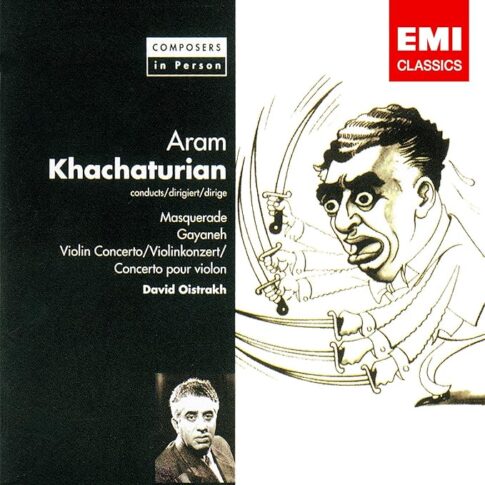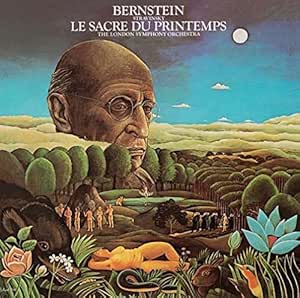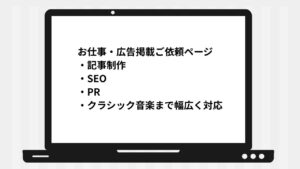この記事ではラフマニノフのピアノ曲「楽興の時」の難易度をサクッと解説します!
ピアノ学習者にとって、ラフマニノフの作品は魅力的なレパートリー。
なかでも『楽興の時』は、技術的な難しさと音楽的な豊かさを兼ね備えた作品として親しまれています。
とはいえ、これから練習する方にとっては、「難易度はどれくらい?」「自分にも弾ける曲があるかな?」と思っている人も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、今回はラフマニノフの「楽曲の時」6曲の難易度を1曲ずつ解説します。
演奏動画もありますので、ぜひ参考にしてくださいね!
ラフマニノフの生涯と『楽興の時』の時代背景

作品解説の前に、ちょっとだけラフマニノフについて解説します。
人生や歴史的背景を知ると、より作品が身近に感じられるはずです。
ラフマニノフの生い立ちと音楽的才能
セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)は、ロシアのノヴゴロド県に生まれた作曲家、ピアニスト、指揮者です。幼少期からピアノの才能を発揮し、9歳でペテルブルク音楽院に入学。
その後モスクワ音楽院でピアノと作曲を学んでいます。
スクリャービンとのピアノ対決なんかも有名ですね。
ラフマニノフで有名と言えば、手の大きさ(オクターブ以上の音程を簡単に弾くことができた)。一説によると、難病のマルファン症候群だったと言われていますが、現在では先端巨大症だったとする説も言われています。
ラフマニノフは20世紀を代表するピアニストとしても活躍し、その強靭な技術と豊かな表現力は今日も多くのピアニストの憧れの的と言えるでしょう。
ラフマニノフについての解説はこちらの記事も参考にしてください。
『楽興の時』が作曲された時期と背景
『楽興の時』Op.16は、1896年に作曲されたラフマニノフのピアノ曲です。
この時期のラフマニノフは経済的に苦しい状況であるだけでなく、電車でお金を盗まれるという災難にも巻き込まれていました。
タイトルの「楽興の時」は、シューベルトの同名作品に敬意を表していますが、内容は完全にラフマニノフの個性が表れた作品です。
全6曲からなるこの作品集は、ロシアの民族的要素と複雑な和声進行、そして技巧的なピアノ書法が特徴的です。
発表当時は高評価を獲得したものの、翌1897年に発表した「交響曲第1番」が大不評となり、この評価も一掃されることに・・・。
そしてこの失敗から、ラフマニノフが大きなスランプに陥ったのは有名な話ですね。
しかし現在では、ラフマニノフのピアノ曲の転換期を象徴する作品として多くの人々に親しまれています。
シューベルトの「楽興の時」と聴き比べてみるのも面白いかもです。
出典:YouTube
ラフマニノフの『楽興の時』の難易度はどのくらい?
ラフマニノフの『楽興の時』は、一般的に中級上〜上級レベルの難易度とされています。
筆者が実際に弾いた感想も「まあ、そうかな〜」という感じです。
ただ、各曲によって難易度にはかなりの差があるのも事実。
比較的取り組みやすい曲から、かなりの技術を要する曲まで様々です。
ベートーヴェンのピアノ・ソナタやバッハのフランス組曲をやっている方なら、チャレンジできるかと思います。
練習のポイントを5つ挙げますね。
各曲の難易度について、もう少し詳しくみてみましょう。
10段階評価で数値化しいます。
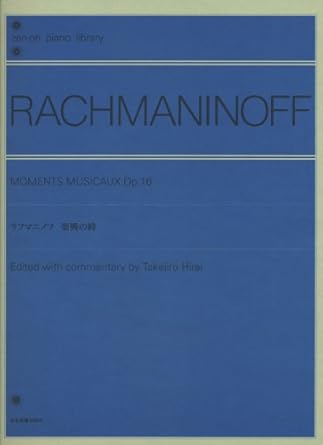
「楽興の時」第1番の難易度
難易度:中級上(6)
アルペジオの連続と内声に現れる旋律線が特徴的。
右手では16分音符のアルペジオを弾きながら、同時に内声部の旋律を浮き立たせる必要があります。
内声の旋律線のバランス
左手の跳躍と和音のコントロール
豊かな和声感と音色の変化
この曲はラフマニノフらしい哀愁を帯びた美しい旋律と、技巧的なパッセージが絶妙に融合しています。内声の旋律を際立たせる練習が重要です。
出典:YouTube
「楽興の時」第2番の難易度
難易度:上級(7)
6曲の中では比較的取り組みやすい曲の一つです。
三部形式で構成され、中間部ではやや技巧的な要素も現れますが、全体としては明るく軽やかな雰囲気を持っています。
軽やかなタッチと明瞭なアーティキュレーション
中間部での左右の手の掛け合い
リズミカルな要素と旋律のバランス
この曲は『楽興の時』の中では技術的に最も取り組みやすく、ラフマニノフ入門としても適しています。しかし、音楽的な表現力や軽やかさを実現するには繊細なコントロールが必要です。
出典:YouTube
「楽興の時」第3番の難易度
難易度:中級(5)
内声部に現れる歌うような旋律と、それを取り巻く複雑な和音進行が特徴です。
複数の声部のバランスとレガート奏法
広い音域にわたる和音と跳躍
複雑なリズムパターンの処理
本作はラフマニノフの作曲スタイルが顕著に表れており、演奏には豊かな和声感と音楽的理解が求められます。
出典:YouTube
「楽興の時」第4番の難易度
難易度:上級(8)
躍動感あふれるリズムと情熱的な性格が魅力です。
6曲の中でも特に有名なので、聴いたことがある人も多いと思います。
急速な音階やアルペジオの連続、左右の手の跳躍など、技術的に挑戦的な要素が多く含まれています。
速いテンポでの明瞭な音階とアルペジオ
左右の手のリズミカルな掛け合い
激しい音型の中での音楽的表現
劇的な性格と技巧的な要素で、聴衆を魅了する力を持っています。
適切なテンポと明瞭さを維持しながら情熱的な表現を実現することが重要です。
これは難しいです・・・。
出典:YouTube
「楽興の時」第5番の難易度
難易度:中級(4)
叙情的な旋律と豊かな和声が美しい。
技術的には比較的取り組みやすいものの、表現力と音色のコントロールが求められます。
歌うような旋律線と伴奏のバランス
豊かな和声の響きを生かした演奏
表現力豊かなルバートとフレージング
この曲は『楽興の時』の中でも特に美しい旋律を持ち、ラフマニノフの叙情的な側面が表れています。技術的な難しさよりも音楽的な表現力が問われる作品かなと思います。
出典:YouTube
「楽興の時」第6番の難易度
難易度:上級(7)
力強い和音の連続と豊かな音響効果が全開の曲です。
ロシアの鐘の音を思わせる響きも印象的で、ラフマニノフの後の作品にも見られる要素が既に現れています。
力強い和音のコントロールと音色
広い音域にわたる音楽的表現
左手の跳躍と重厚なバス音
『楽興の時』を締めくくるにふさわしい壮大さ!
力強さと繊細さを併せ持つ演奏が求められます。
出典:YouTube
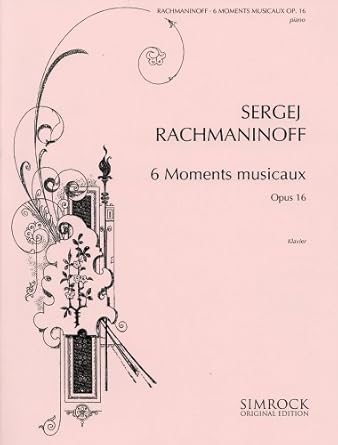
『楽興の時』の難易度ランキング(易しい順)
あくまでも筆者の経験からですが、難易度順(易しい順)に並べてみました。
人によって得意・不得意がありますので参考までということで。
『楽興の時』を練習する際のポイント
ラフマニノフの『楽興の時』を効果的に練習するためのポイントを紹介します。
といっても、他の作曲家の作品も同じですが・・・。
ポイントは以下の7つです。
- 部分練習を重視する:難しいパッセージは、小さなセクションに分けて集中的に練習!
- 声部ごとの練習:ラフマニノフの作品では複数の声部が絡み合うことが多いため、各声部を個別に練習してから統合すると効果的。
- リズム練習:複雑なリズムパターンは、様々なリズム変化をつけて練習すると身につきやすくなりますよ。
- 遅いテンポからの積み上げ:特に技巧的なパッセージは、遅いテンポから始め、確実に音を拾えるようになってから少しずつテンポを上げていきましょう。
- 音色とペダリングの研究:ラフマニノフの音楽は豊かな音色変化が重要。さまざまなタッチとペダリングを試して、最適な音色を見つけましょう。
- 録音を活用する:自分の演奏を録音して客観的に聴くことで、バランスや表現の問題点が見えることも多いです。
- プロの演奏を参考にする:ラフマニノフ自身の録音や、優れたピアニストの演奏を聴いて参考にしましょう。
ラフマニノフの作品は、とくに音符が多いです。
なので、音抜けがないよう1音ずつしっかりと確認しながら練習すると良いかもです。
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。
そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。
もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!
ラフマニノフ『楽興の時』の難易度:まとめ
ラフマニノフの『楽興の時』は、以下のようなピアノ学習者におすすめです。
- 中級から上級レベルに進みつつある学習者
- ラフマニノフの作品に挑戦してみたい人
- 技術的な成長と音楽的表現力の両方を高めたい人
- ロシア音楽の豊かな和声と情感を学びたい人
- 人前で演奏する曲を探している人(特に個別の曲として)
『楽興の時』の6曲はそれぞれ独立した作品として演奏することも可能で、自分の技術レベルに合わせて選ぶこともできます。
また、全曲を通して練習することで、多様な技術と表現を学べるはずです。