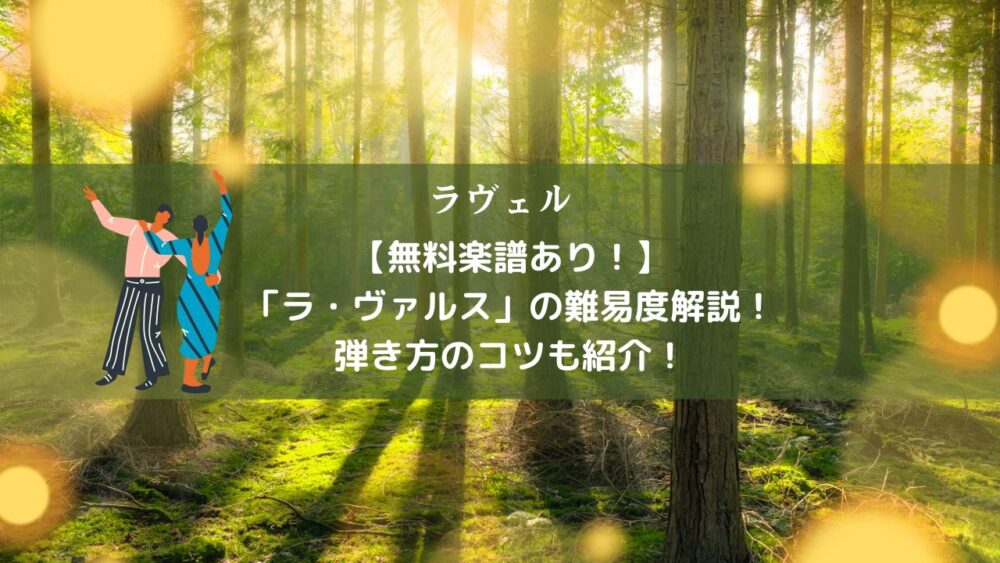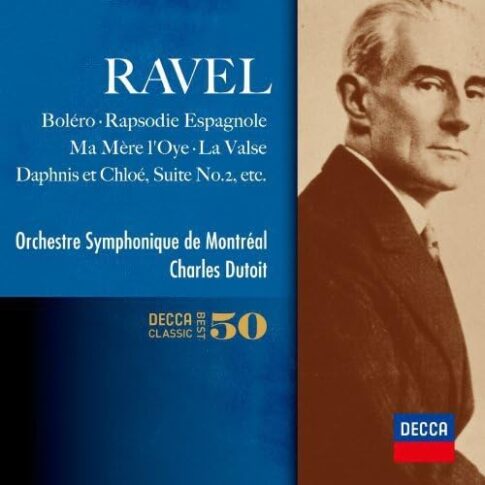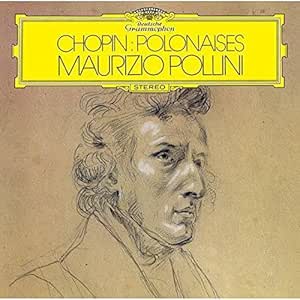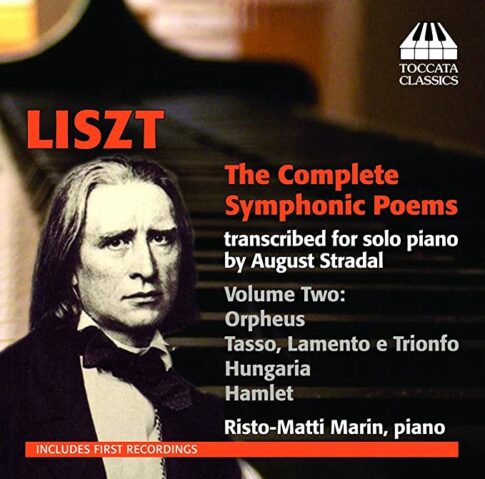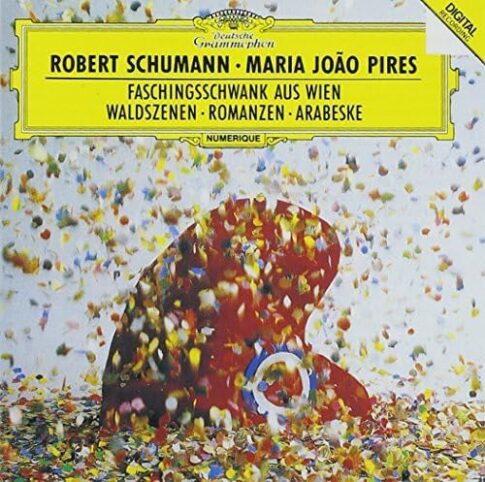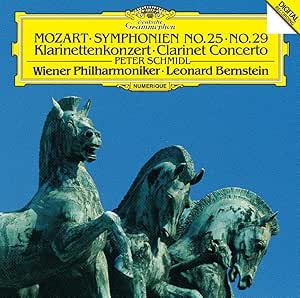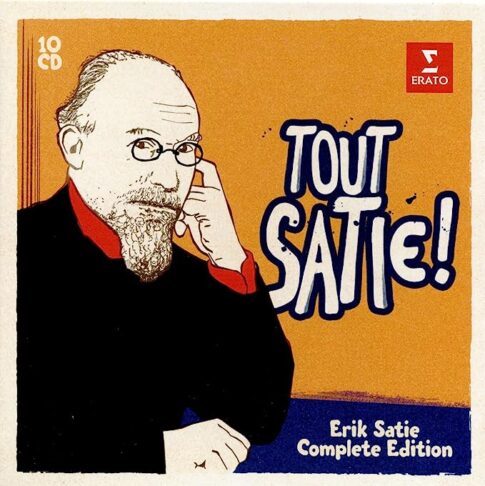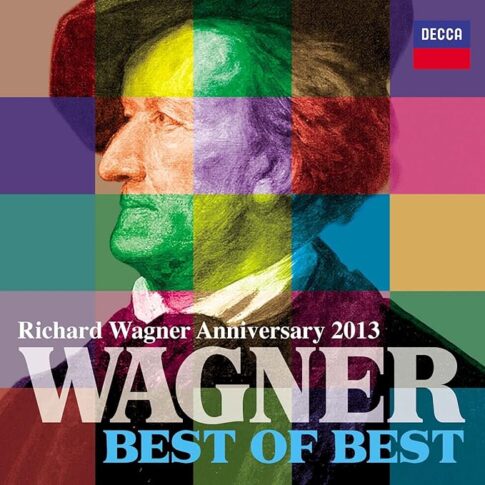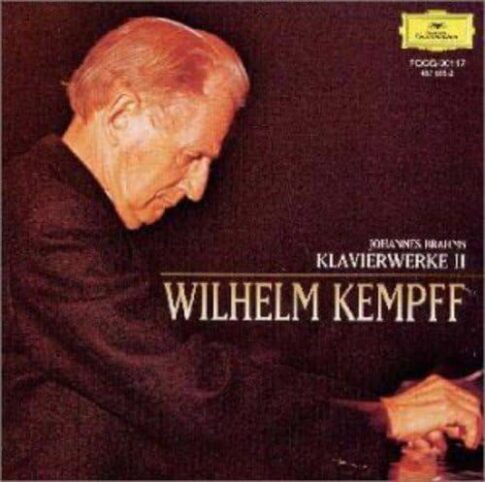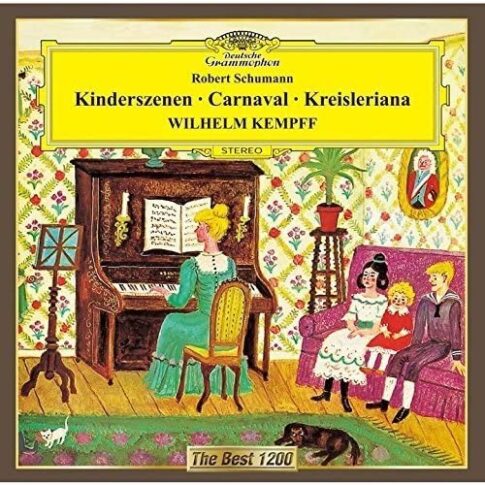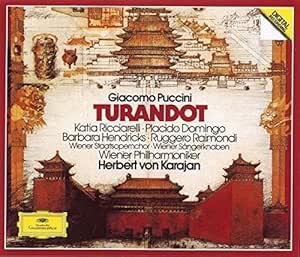「いつかは弾いてみたい」と多くのピアノ学習者が憧れる、モーリス・ラヴェルのラ・ヴァルス。
オーケストラを彷彿とさせる圧倒的な音の洪水、華やかでありながらどこか退廃的な世界観は、一度聴いたら忘れられない強烈なインパクトがあります。
しかし、その魅力にひかれて、楽譜を開いた瞬間、びっしりと書き込まれた音符の黒さに圧倒され、「これは自分に弾けるのだろうか…」と不安に感じた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな「ラ・ヴァルス」に挑戦したい方のために、筆者の実体験を交えながら解説します。
筆者は、3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています。音大には行っておらず、なぜか哲学で修士号という謎の人生です。
ラヴェル「ラ・ヴァルス」とは?作品の概要と魅力
出典:YouTube
難易度解説の前に、いつものようにちょっとだけ寄り道を。
まずはこの曲がどのような背景を持って生まれたのか、その魅力の源泉はどこにあるのかを見ていきましょう。曲への理解を深めると、表現力アップにもなりますしね!
舞踏詩ーウィンナ・ワルツへの憧憬と破壊
「ラ・ヴァルス」は、フランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875-1937)によって、当初バレエ音楽として構想されました。副題として「舞踏詩(Poème chorégraphique)」と記されています。
ラヴェルが本作に込めたイメージは「1855年頃の帝政ウィーンの宮廷」で繰り広げられる、華やかなワルツの饗宴でした。
彼はヨハン・シュトラウス2世に代表されるウィンナ・ワルツに深い敬意と憧れを抱いており、そのオマージュとして本作を構想していたのだとけ。
しかし、作曲が進められたのは第一次世界大戦の直後。
戦争がもたらした破壊と虚無感は、ヨーロッパ社会全体を覆っていました。ラヴェルの音楽もその影響を免れることはできず、当初の華やかな構想は、次第に不穏で破滅的な様相を帯びていきます。
結果として「ラ・ヴァルス」は、ウィンナ・ワルツのきらびやかな世界が、熱狂の渦の中で次第に崩壊・瓦解していくという、二面性を持った強烈な作品として完成しました。
バレエの依頼主であったディアギレフは、この曲を「バレエではない。バレエの肖像画だ」と評し、上演を拒否したという逸話も残っています。
ラヴェルの生涯についてはこちらの記事で書いています。
参考|ピティナ・ピアノ曲事典|ラヴェル:ラ・ヴァルス(ピアノソロ) ニ長調
ピアノ版の魅力ーオーケストラを凌駕する色彩感
ラ・ヴァルスには管弦楽版とピアノ独奏版、そして2台ピアノ版が存在しますが、特にピアノ独奏版は、単なるオーケストラ版の編曲にとどまらない、独立した傑作として知られています。
さすが「スイスの時計師」ですね!
これほど色彩豊かでダイナミックな作品が生まれたのは、ラヴェル自身が卓越したピアニストであり、楽器の性能と可能性を極限まで知り尽くしていたからといえるでしょう。
- 冒頭の混沌とした響き: 地の底から湧き上がるようなコントラバスのざわめき。
- 中間部の華麗なワルツ: きらびやかなシャンデリアの下で踊る男女の姿。
- 終盤の熱狂と崩壊: すべてを飲み込み、破壊し尽くす圧倒的なクライマックス。
【結論】ラ・ヴァルスのピアノ難易度は?実体験から徹底分析
出典:YouTube
ということで、本題である「ラ・ヴァルス」の難易度について、具体的にお話ししますね。
様々なピアノ曲を演奏してきた筆者の経験から、客観的な評価と、その根拠となる「難しさの正体」を分析しました。
ラ・ヴァルスの総合難易度:★★★★★★★★★☆ (9/10)
結論から言うと、「ラ・ヴァルス」の難易度は、最高レベルに近い「星9つ」です。
これは、一般的なピアノ学習者が発表会で弾くような曲(例:ショパンの「幻想即興曲」やベートーヴェンのソナタ「悲愴」など)よりもさらに上。
音楽大学の卒業試験や、プロのピアニストがリサイタルのメインプログラムに据えるレベルの難易度と言えます。
他の有名難曲との比較
- リスト「ラ・カンパネラ」: 技術的なパッセージの難しさでは「ラ・カンパネラ」も相当ですが、「ラ・ヴァルス」はそれに加え、複雑なリズム、和声、表現の多面性が求められるため、総合的な難易度は上だと感じます。
- ショパン「英雄ポロネーズ」: 「英雄ポロネーズ」が持つ威厳や力強さとは質の異なる、より複雑で内面的な表現力が必要です。技術的にも、指の独立性や跳躍の正確性など、より高度なスキルが要求されます。
- ラヴェル「夜のガスパール(スカルボ)」: ラヴェル自身の最難関曲「スカルボ」と比較されることも多いです。「スカルボ」が悪魔的な技巧の頂点だとすれば、「ラ・ヴァルス」はオーケストラ的な響きと構成力、そして体力が求められる、別のベクトルでの頂点と言えるでしょう。
こちらの記事も参考になりますよ。
ラ・ヴァルスの難易度を高める「3つの壁」
では、なぜ「ラ・ヴァルス」はこれほどまでに難しいのでしょうか。
あくまでも筆者の意見ですが、大きく分けて「3つの壁」が立ちはだかると考えています。
1. 技術的な壁:超絶技巧のオンパレード
まず、当然ながら、純粋なテクニックの面で要求されるレベルが非常に高いです。
- 複雑なリズムとポリリズム: 冒頭部分から、3拍子の中に2拍子系のフレーズが絡み合うなど、リズムを正確に捉えるのが困難です。拍の頭を見失いやすく、音楽が停滞する原因になります。
- 高速なグリッサンドとアルペジオ: まるで鍵盤を撫でるように、あるいは引き裂くように現れるグリッサンド。オーケストラのハープを思わせる長大なアルペジオは、指の柔軟性とスピードがなければ弾きこなせません。
- 正確無比な跳躍と和音連打: 右手と左手が鍵盤の端から端まで飛び交うパッセージが随所に現れます。特に終盤の和音連打は、強靭な腕と手首、そしてコントロールを失わない精神力が不可欠です。
2. 表現的な壁:オーケストラの響きを再現する色彩感
前述の通り、この曲はピアノ一台でオーケストラ全体を表現することを目指しています。
- 音色の弾き分け: ヴァイオリンの歌うような旋律、チェロやコントラバスの深く渋い響き、フルートの軽やかなパッセージ、金管楽器の輝かしいファンファーレ、打楽器の鋭いリズム…これら全てを、タッチやペダリング、アーティキュレーション(音の奏法)の変化によって描き分ける必要があります。
- 感情のグラデーション: 曲全体を覆う「華やかさ」「優雅さ」から、その裏に潜む「不安」「狂気」、そしてクライマックスの「熱狂」「破滅」へと至る感情のグラデーションを、表現する必要があります。なので、表面的に激しく弾くだけだと、曲の持つ魅力が失われてしまう可能性も。
3. 構成的な壁:長大な曲を弾ききる体力と集中力
演奏時間が約12分にも及ぶこの大曲を弾ききるには、精神的・肉体的なスタミナが不可欠です。
- エネルギー配分: どこで力を抜き、どこでエネルギーを解放するのか。曲全体の設計図を頭に入れ、クライマックスに向けて計画的に音楽を構築していく構成力が求められます。
- 暗譜のプレッシャー: 音符の数が膨大で和声も複雑なため、暗譜は非常に困難です。記憶が曖昧な箇所があると、本番での不安に直結し、演奏のクオリティを著しく下げてしまい恐れも。
ラ・ヴァルス演奏のポイント3選
出典:YouTube
では、具体的にどのような練習をすれば良いのかも気になりますよね。
ここでは、筆者が、とくに重要だと感じた3つのポイントを紹介します。
遠い昔の話ですが、ご参考になれば幸いです。
ラ・ヴァルス演奏のポイント1:冒頭の「混沌」を制するべし!リズムと響きの作り方
多くの人が最初につまずくのが、冒頭の約2分間です。
ワルツのリズムはまだ明確には現れず、低音域のざわめきの中から、様々な楽器の断片が浮かび上がっては消えていきます。でも、ここが曲全体の成功の鍵を握ります。
- 練習法:超スローテンポでリズムを解剖するまずはメトロノームを使い、あり得ないほどゆっくりなテンポ(♩=40程度)で練習してください。
- ペダリングの極意:ペダルを完全に踏み込むのではなく、半分くらいの位置で浅く踏み、響きの量や長さを耳で聴きながら微調整します。また、低音のベース音だけを保持したい場面では、ソステヌートペダルを積極的に活用しましょう。
- タッチの工夫:ppでも芯のある音を弱い音を出すために、指先だけでそっと弾こうとすると、芯のない弱々しい音になってしまいます。ppであっても、指の重み、腕の重みをしっかりと鍵盤の底まで伝える意識が重要です。
ラ・ヴァルス演奏のポイント2:ワルツのリズムを体に叩き込む!
この曲の根幹は、言うまでもなく「ワルツ」です。
しかし、それは単純な3拍子じゃないところがやっかい・・・。
優雅な宮廷の踊りから、破滅的な熱狂へと変貌していく様を、リズムのコントロールで表現する必要があります。
- 基本のワルツ感を養う:まずは、曲中の比較的シンプルなワルツの部分を取り出し、1拍目に重心を置き、2・3拍目はそこから自然に流れ出るような感覚を掴みましょう。少し大げさに体を揺らしながら弾いてみるのも良い方法です。
- 「優雅」と「狂気」のリズムの違い:優雅なワルツでは、1拍目の重みを保ちつつも、全体的には軽やかで流れるようなテンポ感を意識します。フレーズの頂点に向かって少しだけアッチェレランド(だんだん速く)し、頂点を過ぎたらリテヌート(だんだん遅く)する、といった呼吸のような揺れが効果的です。
ラ・ヴァルス演奏のポイント3:色彩豊かな音色の作り方
これは「ラ・ヴァルス」を弾く上で、技術練習と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なポイントです。ピアノの楽譜だけとにらめっこしていても、この曲が要求する多彩な音色を生み出すことはできません。
- 管弦楽版を「教科書」にする幸い、「ラ・ヴァルス」にはラヴェル自身による素晴らしい管弦楽版があります。これを何度も、繰り返し聴き込んでください。
- 脳内で楽器を割り当てる管弦楽版を聴き込んだら、今度はピアノの楽譜を見ながら、各パートを脳内でオーケストラの楽器に割り当ててみましょう。
- 例:「この右手のきらびやかなパッセージはフルートとピッコロ」「この左手の重厚な和音はトロンボーンとチューバ」「この歌うような旋律はヴァイオリンのセクション」…このように考えることで、自然とタッチや音色に変化が生まれます。
ラ・ヴァルスの楽譜紹介
出典:YouTube:たくおん様より
最後に、ラ・ヴァルスの楽譜を紹介して終わりにしますね。
ご自身にあった楽譜を、ぜひ選んでみてください!
おすすめの楽譜
>>アマゾン:zen-on score ラヴェル:ラ・ヴァルス (全音版)
>>アマゾン:ラヴェル=ギンジン/ラ・ヴァルス[ピアノ独奏版]
>>アマゾン:No.256 ラベル/ラヴァルス (Kleine Partitur)👉管弦楽用です!!
ラ・ヴァルスの難易度解説:まとめ
今回は、ラヴェルの大曲「ラ・ヴァルス」の難易度と演奏のポイントについて、徹底的に解説しました。
- 難易度は星9つ(★★★★★★★★★☆)。プロレベルの技術、表現力、構成力、体力が求められる最高峰の難曲。
- 立ちはだかるのは**「技術」「表現」「構成」という3つの壁**。
- 攻略の鍵は、①冒頭の混沌を制する、②ワルツのリズムを体得する、③オーケストラの響きを意識する、という3つのポイント。
「ラ・ヴァルス」は、間違いなくピアニスト人生における大きな挑戦となる曲です。その道のりは険しく、何度も壁にぶつかるかもしれません。
しかし、この曲の持つ魔術的な魅力に取り憑かれ、試行錯誤の末に弾きこなせた時の喜びと達成感は、何物にも代えがたい宝物になります。
この記事が、みなさんの挑戦を後押しする一助となれば幸いです。