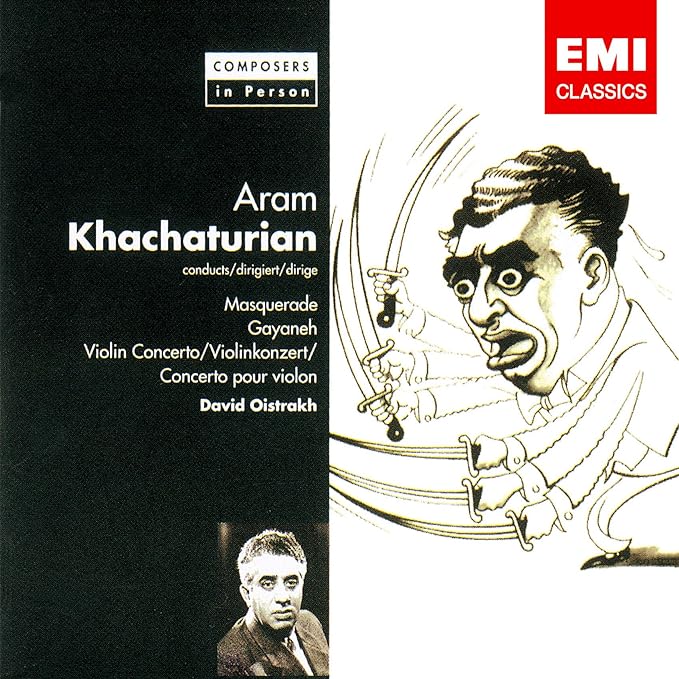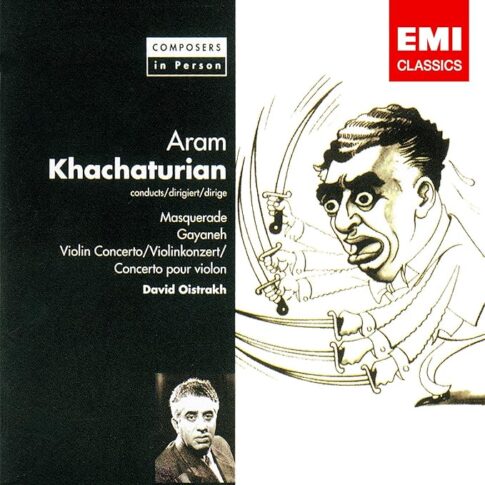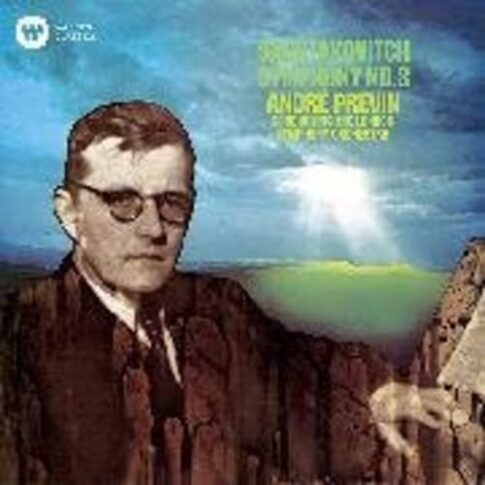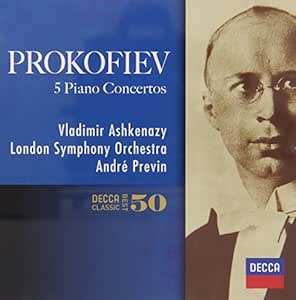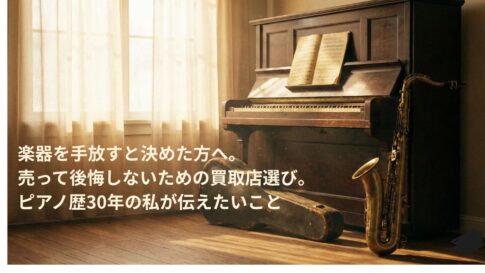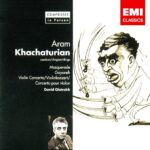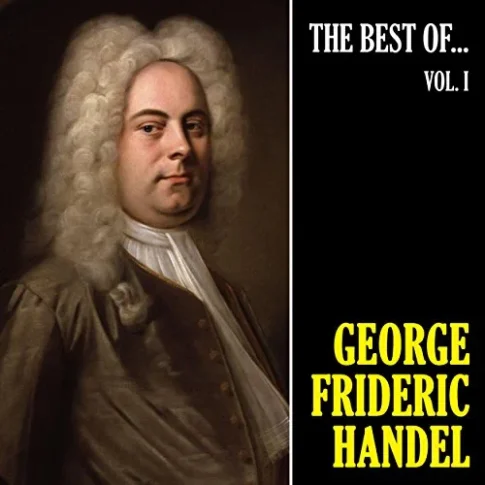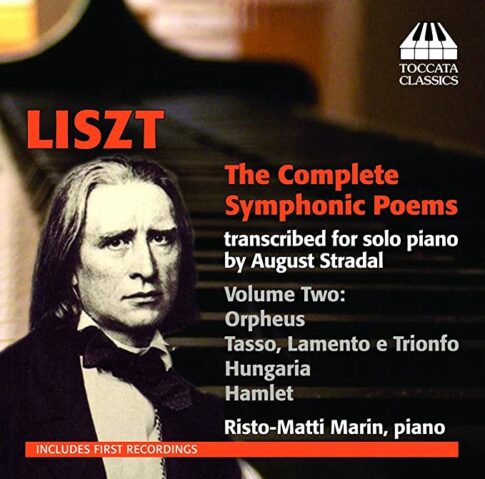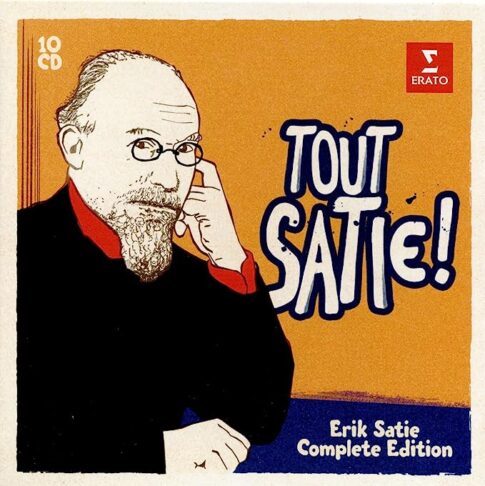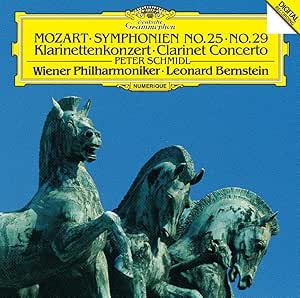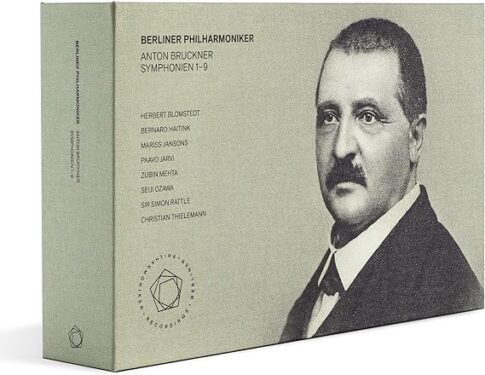この記事では、ハチャトゥリアンの作品の特徴やおすすめ代表曲を解説します。
『剣の舞』ばかりが有名ですが、これ以外にも、優れた名曲ばかりです。
たとえば『仮面舞踏会』の「ワルツ」などは、フィギュアスケートのBGMで使われていたので、1度は耳にしたことがあるかもしれません。
いつもながら、どの作品もざっくり解説しますので、ぜひ気軽に最後までご一読ください!
「ハチャトゥリアンについてもっと知りたい!」という方は、1つ前の記事のコチラをお読みいただくと、さらにちょっぴり教養が深まるハズです。
ハチャトゥリアンの作品の特徴や魅力は?

アルメニアやロシア、ハンガリーやトルコなど、さまざまな国の民謡を取り入れたハチャトゥリアン。
そのため、彼が生み出した作品は異国情緒に溢れ、クラシック音楽の枠にとらわれない、独自の世界観を生み出しています。
そんなハチャトゥリアンの作品には、どのような特徴や魅力があるのでしょうか。
ハチャトゥリアンの作品の特徴や魅力1、民族色豊かな旋律とリズム
ハチャトゥリアン作品の特徴といえば、なんといっても民族的な旋律とリズム。
そしてこの2つが最大の魅力の1つ言っても過言ではないでしょう。
ハチャトゥリアンは、半音を多用した独特の旋法と不均等なリズムパターンを持つアルメニア民族音楽の要素を取り入れ、神秘的で東洋的な世界観を表現しています。
たとえば、代表作「剣の舞」の有名な主題は、そうした民族色豊かな旋律の好例です(クルド人が剣を持って舞う姿を描いた作品)。
また「ガイーヌ組曲」には、アルメニアの民族舞踊のような生き生きとしたリズムが用いられ、エキゾチックな雰囲気を醸し出しています。
ハチャトゥリアンの作品は金管楽器の重厚な響きと、打楽器の迫力に満ちたリズムも魅力なので、その辺りも注意して聴いてみてください!
特徴や魅力2、色彩豊かな管弦楽法
ハチャトゥリアン作品のもう一つの魅力は、優れた管弦楽法です。
とくに、さまざまな打楽器の使用や、弦楽器の分割奏法など、新鮮で色彩豊かな響きを生み出す手法を駆使し、聴く人の心を捉えて離しません。
たとえば、バレエ『スパルタクス』では、金管楽器とティンパニの組み合わせが戦闘的な情景を描き出し、『ガイーヌ』では独特の奏法が民族的な色彩を表現しています。
他にも例はありますが、楽器の持つ多様な音色を巧みに操り、視覚的なイメージを音で表現する卓越した才能がハチャトゥリアン作品の特徴と言えるでしょう。
特徴や魅力3、東洋と西洋の融合
ハチャトゥリアンの音楽は、ルーツであるアルメニアの民族性と、当時のソヴィエト・ロシアの近代性を見事に融合させたユニークな作風でも知られています。
作品内で表現される旋律やリズムには、古来のアルメニア音楽の香りが漂う一方で、
同時に20世紀的な和声処理や管弦楽法が施されのも大きな特徴です。
たとえば『ヴァイオリン協奏曲』を聴いてみると、
中近東的な情緒あふれる主題と西欧の協奏曲形式が見事に調和しているのがよくわかります。
その意味で、ハチャトゥリアンは東洋と西洋の文化を自在に操り、自身の音楽表現に昇華させた重要な作曲家であると覚えておいてくださいね!
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲7選

ということで、ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲を7曲紹介します。
いつもながら、筆者の独断と偏見によるものですが、みなさまにとって新たな発見となれば幸いです。
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲1、ピアノ協奏曲変ニ長調
まずは『ピアノ協奏曲変ニ長調』から。
本作はモスクワ音楽院の卒業作品である『交響曲第1番』の後に作曲され、ハチャトゥリアンが名声を得るきっかけとなった作品です。
1937年に初演され、一定の成功を収めました。
しかし、ハチャトゥリアン本人は初演の成功にそれほど満足しなかったそうです。
モスクワ音楽院に通っていたとはいえ、それまで正式な音楽教育を受けてこなかったなんて、本当に驚きです。
ハチャトゥリアン初期の作品ですが、すでに異国情緒や不協和音などが多様されており、ハチャトゥリアンの才能が発揮されている名曲です。
全3楽章構成で、演奏時間は35分程度。
あまりハチャトゥリアンの作品を聴いたことがない方は、本作から聴いてみると良いかもしれません。
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲2、ヴァイオリン協奏曲
ピアノ協奏曲の次は『ヴァイオリン協奏曲』です。
冒頭部分は、もしかしたらどこかで聴いたことがある方もいるかもしれません。
こちらも民族音楽を連想させる作品です。
アルメニアの首都エレヴァンの民族音楽調査中に、インスピレーションを受けて作曲されましたと言われています。
1940年に作曲された本作は、ヴァイオリニストのダヴィド・オイストラフに献呈され、オイストラフによる初演は大成功を収めました。
また本作はハチャトゥリアンを代表するヴァイオリン協奏曲であるだけでなく、20世紀を代表するヴァイオリン曲でもあります。
全3楽章構成で、こちらも演奏時間は35分程度です。
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲3、交響曲第2番「鐘」
本作は、1943年に完成されたハチャトゥリアンにとって第2作目となる交響曲です。
副題の「鐘」は本人によるものではなく、ソ連の音楽学者ゲオルギー・フーボフによるものだそうです。
1942年の夏頃に作曲が開始され、1943年の12月に初演が行われました。
全体として激しい、そして物悲しさと不安感が漂っていますが、これは第2次世界大戦を背景として作曲されたためと考えられています。
1944年に改訂が行われ、アメリカでの初演はレナード・バーンスタインの指揮により演奏が行われました。
また本作は、ショスタコーヴィチの『交響曲第7・8番』、プロコフィエフの『交響曲第5番』と並び「戦争交響曲」の1つに数えられています。
演奏時間はおよそ50分です。
作品の雰囲気を比べるのも面白いです。
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲4、交響曲第3番「交響詩曲」
本作は1947年に、ロシア革命30周年を祝う目的でされた交響曲です。
上記の作品とはことなり、単一楽章形式で構成され、オルガンが使用されているのが特徴です。
また、オルガンの難易度があまりに高いため、短縮されて演奏されることもあるそうです。
確かに、動画を見てるとオルガンの音の数が半端ない!!
記念祝典のために作曲された作品ですが、編成が大きすぎるため「地方で演奏不可能」と注意を受けたいうエピソードも残されています。
演奏時間は25分程度です。
アマゾン:ハチャトゥリアン:ハチャトゥリアン:交響曲第3番「交響詩曲」他
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲5、チェロ協奏曲
協奏曲からもう1曲。
こちらも掲載しないわけにはいきません・・・。
本作は、1946年にスヴャトスラフ・クヌシェヴィツキーのために作曲された『チェロ協奏曲』です。
ハチャトゥリアンにとっての最後の協奏曲ですが、ピアノ、ヴァイオリンの両協奏曲に比べると、演奏頻度は低いようです。
聴いていて「なんとなく暗いな」と思って調べてみたら、ハチャトゥリアンが戦時中に体験した悲しみが込められているとのこと。
全3楽章で構成されており、とくに第2楽章が魅力的な作品です。
演奏時間はおよそ20分。
アマゾン:ハチャトゥリアン:チェロ協奏曲・コンチェルト・ラプソディ
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲6、バレエ「ガヤネー(ガイーヌ)」
ガイーヌより「レズギンカ」
ガイーヌより「剣の舞」
ハチャトゥリアン作品でもっとも有名「剣の舞」が登場するバレエ音楽です。
1942年の初演後、1952年の改訂を経て完成版となりました。
現在でこそ、名曲として世界中で上演されていますが、発表当初はそれほど大きな成功とはならず、ソ連以外の国で上演されることはほとんどなかったそうです。
ハチャトゥリアンの祖国アルメニアを舞台に、
民族間のロマンスや裏切り、友情などが目まぐるしく展開します。
バレエ全体の演奏時間は約2時間30分程度と長めですが、作中の曲を抜粋した組曲版もコンサートでしばしば演奏されます。
なかでも「剣の舞」は、多くの人が聴いたことがある名曲です。
ハチャトゥリアンのおすすめ代表曲7、組曲「スバルタクス」
スパルタクスより「バッカナール」 ユーリ・シモノフ指揮
『ガイーヌ』と並び、ハチャトゥリアンを代表するバレエ作品です。
1954年に作曲が開始され、翌年1955年に初演が行われました。
物語の舞台は古代ローマ。
奴隷解放の英雄スパルタクスの偉業をテーマとして物語が展開します。
こちらもそれほど大きな成功を収められなかったそうですが、現在でも世界中のファンから愛されているバレエ作品です。
また『ガイーヌ』と同じく組曲版にも改変されており、管弦楽曲としても人気のある作品となっています。
動画のシモノフさんの演奏が本当に素晴らしい!!
アマゾン:ハチャトゥリアン:バレエ音楽「スパルタクス」(1968年ボリショイ版…Y.グリゴローヴィチ編曲)
ハチャトゥリアンの代表曲まとめ
今回は、ハチャトゥリアンの作品の特徴や魅力、そして代表曲を紹介しました。
ハチャトゥリアンの作品は、どの作品も本当に表情豊かで、聴く人を飽きさせません。
この記事をきっかけに、ぜひハチャトゥリアンの作品を聴いてみてください