この記事では、「ドビュッシーで弾きやすい」と評価されることの多い名曲を、実体験と一般的な難易度評価を参考に、厳選して10曲ご紹介します。
それぞれの曲の魅力はもちろん、「なぜ弾きやすいのか」という具体的なポイントや、練習で大切にしたいコツも詳しく解説していきます。
この記事を読めば、きっとあなたにぴったりの一曲が見つかるはずです。
参考動画も紹介しますので、そちらもご覧くださいね!
クロード・ドビュッシーとは?
19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランスで活躍したクロード・ドビュッシー(Claude Debussy, 1862-1918)。
彼は、音楽の世界に「印象主義」という新しい風を吹き込み、色彩豊かな絵画や、揺らめく光を見るかのような、独特で革新的なサウンドを生み出した作曲家です。
従来の音楽のルール(和声や形式)にとらわれず、自由な発想と感覚的な響きを追求したドビュッシーの音楽は、後世の作曲家たちに計り知れない影響を与えています。
特にピアノ音楽の分野では、それまで誰も聴いたことのなかったような響きや表現技法を開拓し、ピアノという楽器の可能性をもたらしました。
ちなみに、本人は「印象主義」と呼ばれることは好きじゃなかったらしい・・・。
詳しい生涯については、こちらの記事で紹介しています。
ドビュッシーのピアノ曲はなぜ魅力的?
ドビュッシーのピアノ曲を聴くと、水のきらめき、光のゆらぎ、風のささやき、異国の風景、夢の中のような情景…様々なイメージが心に浮かんできますよね。
繊細で感覚的な響き、夢幻的で美しいメロディーと、捉えどころのない不思議なハーモニーは、私たちを一瞬で日常から解き放ち、特別な世界へと誘ってくれます。
この世界観こそがドビュッシーの大きな魅力です。
立ちはだかる「難しい」の壁…
しかし、その唯一無二の世界観ゆえに、ドビュッシーの曲は「なんだか難しそう…」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
「和声が複雑で理解できない」「リズムがふわふわして捉えにくい」「どう弾けばあの独特の雰囲気が出るの?」といった声は、ピアノ学習者からよく聞かれます。
「いつかはドビュッシーの素敵な曲を弾いてみたい!」という憧れはあっても、「自分にはまだ早いかも…」「どの曲から手をつければいいのか分からない…」と、挑戦をためらってしまう気持ち、よく分かります。
こうしたことが、ドビュッシー作品の「難しさ」を強めているのかもしれません。
ドビュッシーにおける「弾きやすい」の基準とは?
たしかに、ドビュッシーのピアノ曲には、厳密な意味での「初心者向け」というものはほとんど存在しません。彼の音楽は、ある程度の読譜力、指の独立性、そして何より音楽的な表現力が求められるため、一般的にはソナチネアルバムを終え、ソナタアルバムといったレベル(中級程度)に進んでいる方が対象となります。
この記事でいうドビュッシーの弾きやすさは、以下の点を踏まえたものです。
- 技術的な複雑さが比較的少ないこと: 指がもつれるような速いパッセージ、広範囲な跳躍、複雑な指使い、重音の連続などが少ない、または限定的であること。
- 曲の構成が比較的シンプルであること: 曲の形式(A-B-Aなど)が分かりやすく、全体の流れを掴みやすいこと。
- リズムが比較的明快であること: ドビュッシー特有の曖昧模糊としたリズムではなく、拍子感やリズムパターンがある程度はっきりしていること。
- 演奏時間が長すぎないこと: 集中力を維持しやすく、比較的短期間で完成を目指せる長さであること。(一般的に5分以内程度)
これらの点を総合的に見て、「比較的弾きやすい」とされる曲を選んでいます。
ただし、注意点も。
ドビュッシーの曲は、技術的に弾きやすいものであっても、独特の「響き」「雰囲気」「ニュアンス」を表現する難しさは常に伴います。
【レベル別】ドビュッシーの比較的弾きやすい名曲10選

ということで、上記の基準から➕一般的な難易度を考慮し、「中級前半~中級レベル」と「中級後半レベル」に分けてご紹介します。難易度はあくまで目安ですが、★の数(5段階)で示していますので、選曲の参考にしてください。
まずは、ドビュッシー入門として特に人気が高く、技術的なハードルが低い曲を選びました。
星の数が少ない=簡単、ではないのでご留意ください!
【ドビュッシー 弾きやすい曲①】アラベスク 第1番
出典:YouTube
* 難易度:★★☆☆☆
* 収録作品:2つのアラベスク
ドビュッシー初期の作品で、最も有名な曲の一つ。
流れるように優雅で、装飾的な旋律(アラベスク模様)が美しく、聴く人を心地よい世界へ誘います。発表会などでも人気があります。
右手のアルペジオ(分散和音)が中心で、指の形に慣れれば比較的スムーズに弾き進められます。曲の構成もA-B-Aの三部形式で分かりやすいです。左手は和音や単純な動きが多く、比較的負担が少ないでしょう。ドビュッシー 弾きやすい曲の代表格と言えます。
さらに詳しい解説はこちらの記事で書いています。
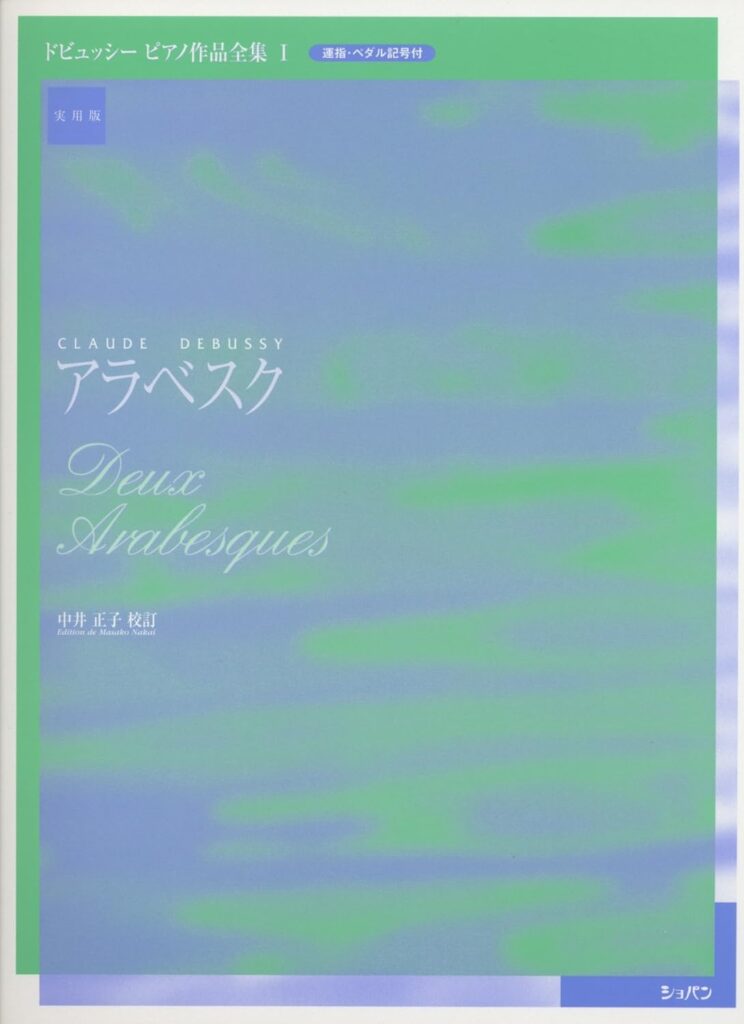
【ドビュッシー 弾きやすい曲②】小さな羊飼い
出典:YouTube
* 難易度:★★☆☆☆
* 収録作品:『子供の領分』
ドビュッシーが愛娘のために書いた組曲『子供の領分』の中の一曲。
タイトル通り、笛を吹く羊飼いを思わせる、素朴で少し寂しげな旋律が印象的です。短く愛らしい小品。
曲が非常に短く(1分半~2分程度)、テンポも穏やかです。
使われている音域も狭く、複雑な和音や速い動きはほとんどありません。
メロディーラインが明確で、音楽の流れを掴みやすいのも弾きやすい理由です。
単旋律の美しさを大切に。息の長いフレーズ感を意識し、素朴さの中に込められた繊細な表情(寂しさ、憧れなど)を表現しましょう。
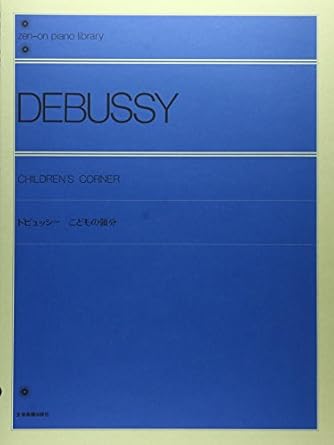
【ドビュッシー 弾きやすい曲③】亜麻色の髪の乙女
出典:YouTube
* 難易度:★★★☆☆
* 収録作品:『前奏曲集 第1巻』より
ドビュッシーの全作品の中でも屈指の人気を誇る名曲。
非常に叙情的で、穏やかで美しい旋律は、一度聴いたら忘れられません。
清らかで、どこか懐かしい雰囲気を持っています。
テンポが非常にゆったりしており、技術的に難しいパッセージは少ないかなと。
和声進行も比較的シンプルで、ドビュッシー特有の美しい響きを存分に味わいながら弾きやすい曲と言えます。音量も全体的に小さめ(p~pp)です。
美しいメロディーラインを、歌うように表情豊かに弾くことが最も重要です。
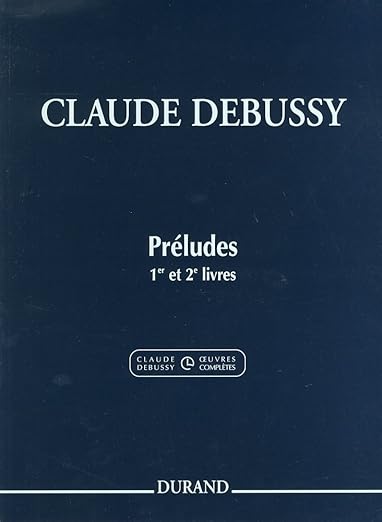
【ドビュッシー 弾きやすい曲④】夢 (Rêverie)
出典:YouTube
難易度:★★★☆☆
ドビュッシーが20代後半に作曲したとされる、甘美でロマンティックな雰囲気を持つ小品。
「夢」というタイトル通り、ゆったりとした時間の流れの中で、美しい旋律がたゆたうように展開します。
全体的にテンポは遅く、左手は分散和音のパターンが繰り返される部分が多いです。
右手のメロディーも比較的穏やかで、指使いも自然で弾きやすいと思います。
複雑なリズムも少なく、譜読みもしやすいかなと。
左手の分散和音を滑らかに、そして右手の美しいメロディーを邪魔しないようにバランス良く響かせることが大切です。
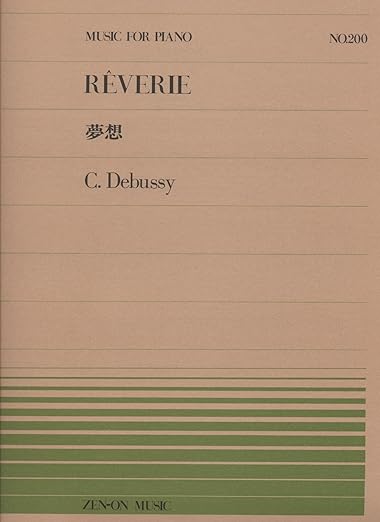
【ドビュッシー 弾きやすい曲⑤】月の光
* 難易度:★★★☆☆
* 収録作品:『ベルガマスク組曲』 より
おそらくドビュッシーのピアノ曲の中で最も有名な曲でしょう。
その名の通り、月の光が静かに降り注ぐ夜の情景を描いたような、幻想的で美しい音楽です。誰もが一度は弾いてみたいと憧れる名曲中の名曲。
有名なため「弾きやすいのでは?」と思われがちですが、技術的には中級レベルが必要かと(結構難しい)。
特に中間部のアルペジオは、粒を揃えて滑らかに弾かないと雰囲気が崩れてしまうことも。
でもまあ、全体的にテンポはゆったりしており、極端に速い箇所はありません。
弾きやすいというよりは「取り組みやすい有名曲」と捉えるのが良いかもしれません。
ベートーヴェンのソナタ「月光」と聴き比べてみるのも思い白いと思います。
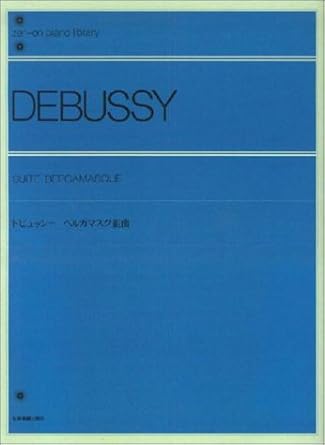
中級後半レベルで挑戦しやすい弾きやすいドビュッシー
ここからは、中級レベルの中でも少しステップアップし、よりドビュッシーらしい表現や技巧に触れられる曲をご紹介します。
【ドビュッシー 弾きやすい曲⑥】ゴリウォーグのケークウォーク
出典:YouTube
* 難易度:★★★☆☆
* 収録作品:『子供の領分』より
『子供の領分』の終曲で、ユーモラスでリズミカルな楽しい曲。
当時の黒人音楽(ラグタイム)の要素を取り入れた、コミカルな動きが特徴です。中間部にはワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』のパロディも登場します。
シンコペーション(リズムをずらす)が特徴的ですが、リズムパターンは明確で、一度掴めば比較的ノリ良く弾けます。繰り返しも多く、曲の構成は掴みやすいです。技術的な難所も限定的で、楽しみながら弾きやすい一曲です。
軽快で弾むようなリズム感を出すことが大切。
【ドビュッシー 弾きやすい曲⑦】パスピエ
出典:YouTube
* 難易度:★★★★☆
* 収録作品:『ベルガマスク組曲』より
『ベルガマスク組曲』の終曲。
パスピエとは古いフランスの舞曲で、快活でリズミカルな性格が特徴です。
古典的な形式感の中に、ドビュッシーらしい独特の和声や響きが散りばめられています。
全体に動きはありますが、音型がパターン化されている部分が多く、指に馴染めば弾きやすく感じるはず。リズムも比較的明確です。スタッカートなど、はっきりとしたタッチの練習に適しています。
軽快なテンポ感を保ちつつ、スタッカートを歯切れよく、レガートを滑らかに弾き分けることが重要です。
【ドビュッシー 弾きやすい曲⑧】雪の上の足跡
出典:YouTube
* 難易度:★★★★☆
* 収録作品:『前奏曲集 第1巻』 より
まさに雪景色の中を一人歩むような、静寂と孤独感に満ちた非常に印象的な曲。
使われている音は驚くほど少なく、ミニマルな表現の中に深い情感が込められています。
音数が少なく、テンポは極めてゆっくり(「このリズムは悲しく凍った風景のような響きでなければならない」と指示がある)。技術的に指を速く動かす必要はほとんどありません。
その意味では、譜読み自体は比較的弾きやすいかもしれません。
一方で、この曲の難しさは技術ではなく表現にあります。
一つ一つの音の響き、間の取り方、極度の弱音(ppp)のコントロールが非常に重要です。
ペダルを使って響きを保持しつつ、楽譜に書かれた指示を丁寧に読み解きましょう。
【ドビュッシー 弾きやすい曲⑨】沈める寺
出典:YouTube
* 難易度:★★★★☆
* 収録作品:『前奏曲集 第1巻』より
海底に沈んだ伝説の寺院が、霧の中から荘厳な姿を現し、また沈んでいく…という物語を描いた、壮大で神秘的な曲。オルガンのような重厚な和音の響きが特徴的です。
ゆっくりとした部分が多く、重厚な和音の響きが秀逸。
曲想がはっきりしているため、イメージを掴みやすいはずです。
中間部の盛り上がり以外は、比較的穏やかな動きです。技術的に弾きやすい箇所も多いですが、表現の幅が求められます。
神秘的な雰囲気から荘厳なクライマックスまでを、いかにドラマティックに表現できるかがポイント。重音をしっかり掴む練習がマストです。
【ドビュッシー 弾きやすい曲⑩】雨の庭 (Jardins sous la pluie)
出典:YouTube
* 難易度:★★★★☆
* 収録作品:『版画』(Estampes) より
組曲『版画』の終曲で、雨が降り注ぐ庭の情景を鮮やかに描いた、技巧的で華やかな曲。
フランス民謡のメロディーも引用されています。急速なパッセージが多く、輝かしい効果を持っています。
技巧的な曲ではありますが、同じ音型やパッセージが繰り返される部分が多く、一度指が覚えてしまえば弾きやすく感じられるかもしれません。曲の構成も比較的明確です。挑戦しがいのある、中級後半のステップアップとして人気があります。
雨粒が跳ねるようなスタッカート、流れるようなレガートの対比を明確に。ペダルは効果的に使い、響きが濁流にならないように注意が必要です。
ドビュッシーを弾きやすく、美しく響かせるための練習のコツ

さて、弾きやすいとされる曲を選んでも、やはりドビュッシー。
その独特の美しさを表現するためには、いくつか押さえておきたい練習のコツがあります。
これらを意識することで、演奏がぐっと弾きやすくなり、ドビュッシーらしい響きに近づけるはずです。
魔法のタッチを求めて – 鍵盤の底まで叩かない
ドビュッシーの音は、硬く叩きつけるのではなく、鍵盤の重みを感じながら、そっと触れるような、あるいは撫でるようなタッチが基本。
指先だけでなく、腕や肩の力を抜き、柔軟な手首を使って、鍵盤にエネルギーを優しく伝えるイメージを持ちましょう。
響きを操るペダリング – 濁らせず、混ぜ合わせる
ドビュッシーの音楽において、ペダルは単に音を伸ばすだけでなく、響きに色彩や深みを与える重要な役割を担います。
でも、踏みっぱなしでは音が濁ってしまいます。
基本は「ハーフペダル」(完全に踏み込まず、少し浮かせる)を使いこなし、響きの移り変わりを注意深く聴きながら、繊細に踏み替えを行うことが重要です。
時には、異なる和音の響きをあえて混ぜ合わせる(響きを重ねる)ことで、独特の浮遊感や色彩感を生み出すこともあります。
楽譜のペダル記号だけでなく、自分の耳を頼りに、最適なペダリングを探求しましょう。
リズムとテンポの柔軟性 – 拍に縛られすぎない
ドビュッシーの音楽は、規則正しい拍の流れよりも、音楽自身の呼吸やフレーズの流れ(ルバート)が重視されることが多いです。
メトロノーム通りきっちり弾くことよりも、旋律がどこへ向かおうとしているのか、どこで息継ぎをするのかを感じ取り、自然な抑揚をつけることが大切です。
もちろん、基本的なテンポ感は必要ですが、時には少し揺らしたり、間(ま)を取ったりすることで、音楽がより表情豊かになりますよ!
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心して通える音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方もいると思います。
そんな方のために、おすすめ音楽教室&楽器店を紹介しました。
もちろん、幼児からシニアまでの全世代向けです!
ドビュッシーの弾きやすい曲:まとめ
今回は、「ドビュッシー 弾きやすい曲」をテーマに、中級レベルのピアノ学習者の皆さんにおすすめの10曲と、その練習のコツをご紹介しました。
ドビュッシーの音楽は、確かに一筋縄ではいかない奥深さを持っています。
しかし、その難しさの中にこそ、他の作曲家では味わえない唯一無二の魅力が詰まっているのです。
技術的な難易度にとらわれすぎず、まずは「この曲、素敵だな」「弾いてみたいな」と感じる心に従って、一曲選んでみてはいかがでしょうか。
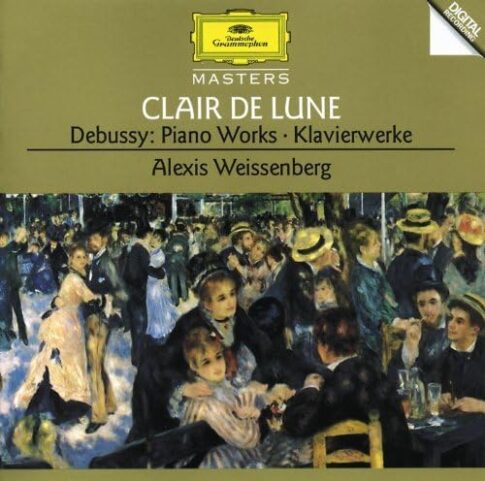
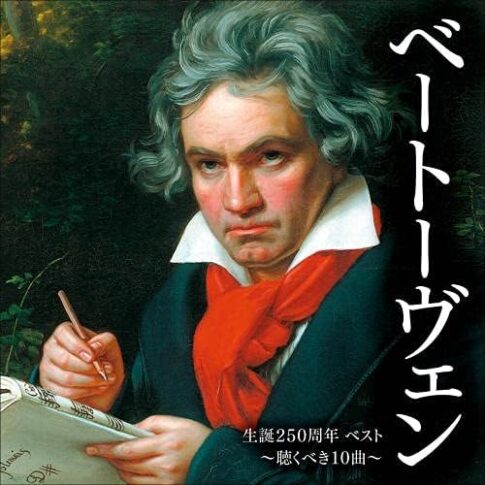



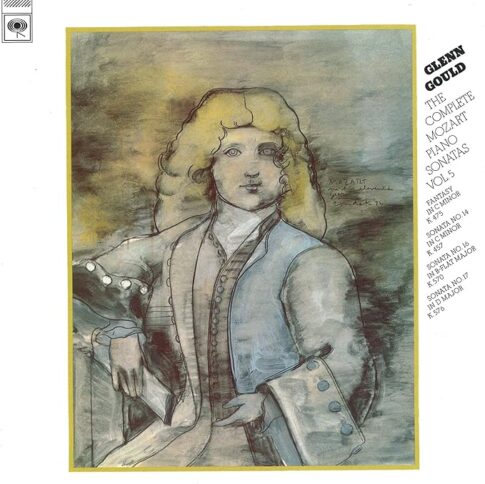
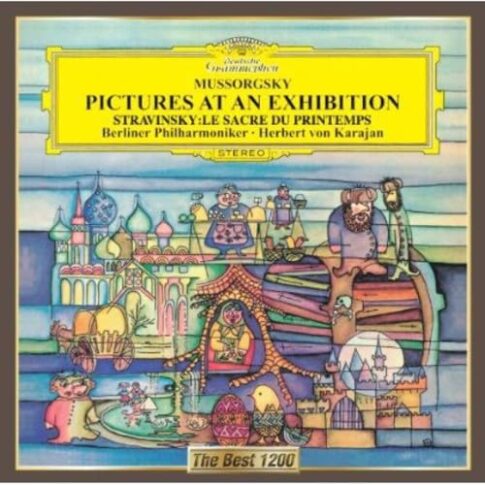
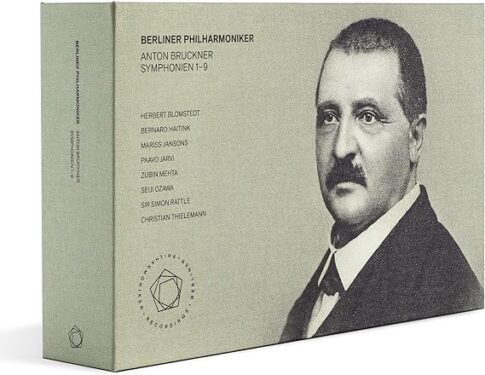

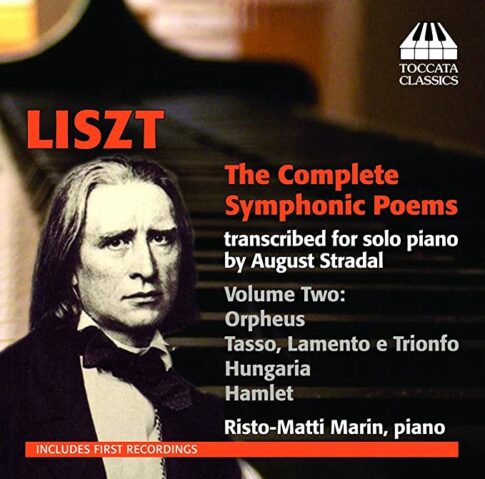
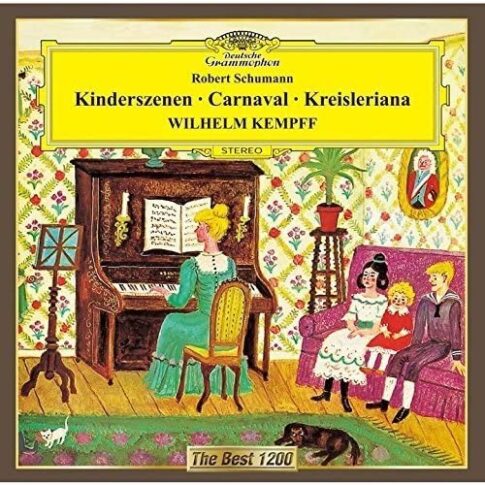



3歳でピアノを開始
一時期は音楽学校を目指すも、能力のなさに気づき、なぜか哲学の道へ。
大学院にて修士課程を修了。
その間もピアノを続け、現在に至る(ピアノ歴30年くらい)。