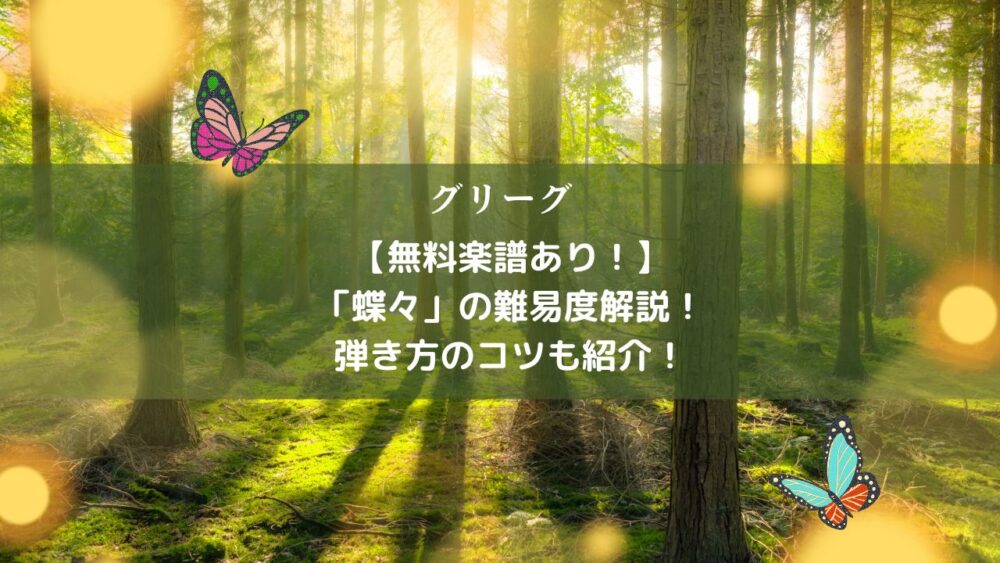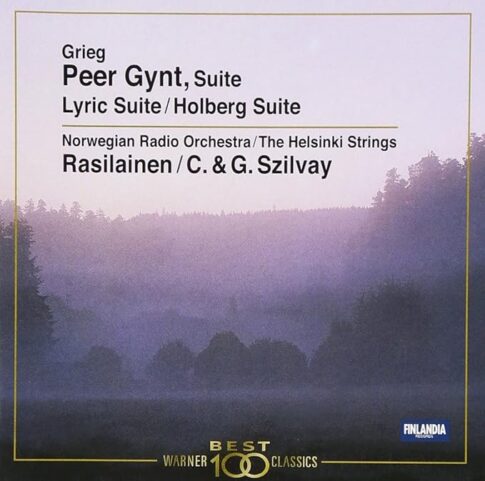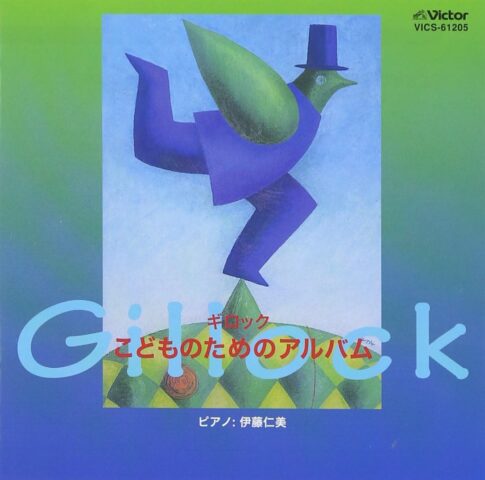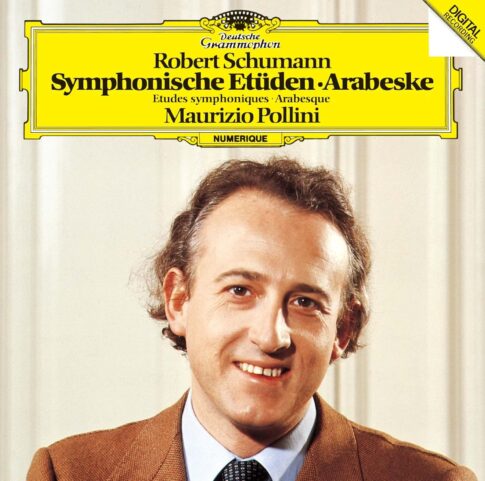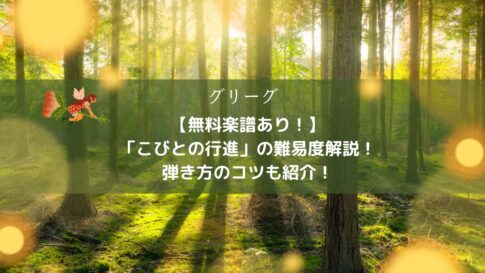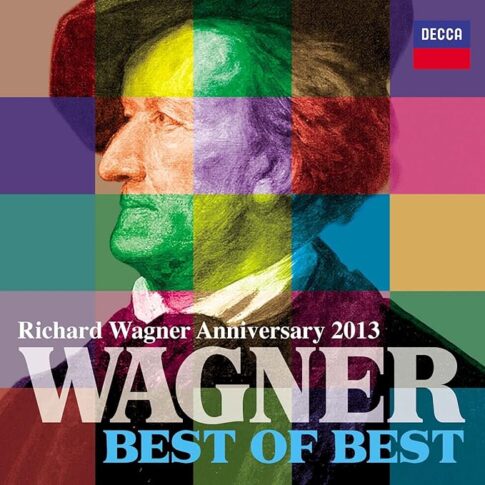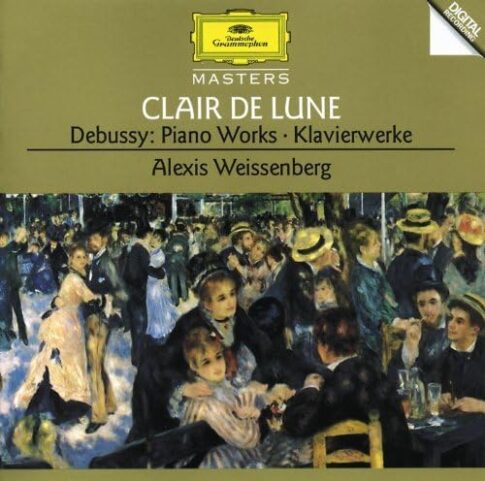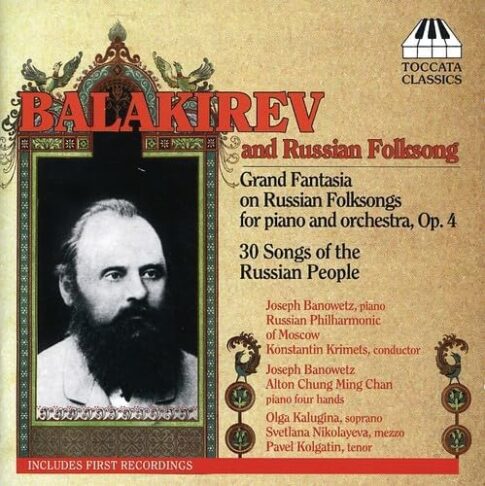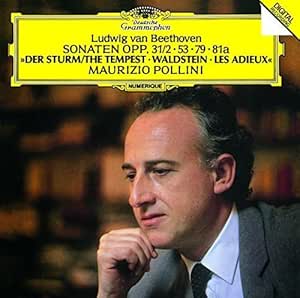クラシックピアノの小品の中でも、可憐で愛らしい印象を持つグリーグの「蝶々」。
そのタイトルどおり、軽やかに舞う蝶のような音楽は多くのピアノ学習者に親しまれています。
この記事では、実際に「蝶々」を弾いた筆者の経験をもとに、楽曲の特徴や難易度、弾き方のポイントを詳しく解説します。
記事の後半では、無料楽譜の紹介もありますよ!
楽譜を探している方、次の発表会曲に悩んでいる方、グリーグの世界に興味のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています。音大には行っておらず、なぜか哲学で修士号というナゾの人生です。
エドヴァルド・グリーグについて
エドヴァルド・グリーグ(Edvard Grieg, 1843-1907)は、ノルウェーを代表するロマン派の作曲家であり、その音楽は北欧の風景や民族音楽に根ざしています。
北欧音楽に特有の詩情が溢れ、多くの人々の心を癒してきました。
代表作としては、「ペール・ギュント」組曲や「ピアノ協奏曲 イ短調」などがありますが、中でもピアノのための『抒情小品集』は、グリーグの繊細な感性と詩的な表現を堪能できる作品群として現在でも人気があります。
今回ご紹介する「蝶々」は、『抒情小品集 第1集(作品12)』に収録された1曲で、短いながらもグリーグらしい叙情的な美しさと躍動感に満ちた魅力を放っています。
グリーグについては、こちらの記事で詳しく紹介しているので、ぜひご一読ください!
「蝶々」の楽曲解説
出典:YouTube
「蝶々(Schmetterling)」は、グリーグの『抒情小品集 第1集(Op.12)』の第3曲です。
小曲で、およそ1分30秒から2分ほどで演奏できますが、その中に豊かな表情が詰まっています。
蝶々がヒラヒラと舞う情景が目に浮かびますよ!
楽曲は軽快な6/8拍子で書かれており、右手には細かく素早い動きが連続し、跳ねるようなモチーフが繰り返されるのが特徴です。
まるで春の陽気な空気の中を自由に飛び回る蝶の姿が、そのまま音楽になったかのようです。左手はシンプルな伴奏に徹しており、右手の動きを支える役割を担っています。
また、和声の進行やリズム処理がグリーグ独特で、単なる可愛い小品にとどまらず、演奏者の感性を問うような奥深さを感じさせる作品と言えるでしょう。
「蝶々」の難易度解説
出典:YouTube
何年くらいで弾ける?
「蝶々」は、中級〜中級中レベルの曲かなという印象です。
全音のピアノピースでは、難易度「C」(中級)に位置しています。
見た目の譜面が簡単そうに見えることもありますが、実際にはテンポの維持や右手の動きに柔軟さが求められるため、ある程度の基礎力が必要です。
ピアノ学習を始めてから3年〜5年程度の生徒がチャレンジしやすい楽曲で、ブルグミュラー25番をスムーズに弾けるようになったあたりが目安です。
その後、半年〜1年の練習で「蝶々」に必要なテクニックが備わってくるでしょう。
ただし、跳躍や速い音型に対する反応力・読譜力・手のフォームの安定がないと、音が濁ったり、走ってしまったりするので、指導者と一緒に丁寧に仕上げていくとよいでしょう。
筆者は小学5年生くらいで演奏した記憶があります。
目安となる教則本
「蝶々」に取り組む前に、次のような教則本を一通り弾けていると、スムーズな導入ができます:
- ブルグミュラー25の練習曲(「アラベスク」「バラード」「やさしい花」など)を修了
- ソナチネアルバム第1巻の前半(クーラウやクレメンティ)
- ギロックの作品(「フラメンコ」「ガラスのくつ」など)
また、ツェルニー30番の中盤あたりが弾けていると、指の独立や跳躍への準備が整っていて、弾きやすいと思います!
せっかくなので、こちらの記事も参考にしてみてください!
発表会にもおすすめ
「蝶々」は演奏時間が短く、構成も明快なため、発表会にとても適した1曲です(発表会としては短すぎる気もしますが)。
聴く人にとっても分かりやすく、明るい印象を与えることができるので、子どもから大人まで幅広い層に支持されています。
特に小学校高学年から中学生くらいの生徒にとっては、技術的にも達成感が得られるレベルでありながら、表現面でも個性を出しやすい点が魅力。
テンポ感と軽快さをうまくコントロールできれば、客席からも「すごい!」と声があがるような仕上がりになります。
衣装や舞台演出を工夫すれば、視覚的にも音楽的にも華やかな印象を残せるので、プログラムの中のアクセントとしても重宝されるでしょう。
「蝶々」の弾き方のポイント3選
出典:YouTube
1. 右手の跳躍をスムーズに!
この曲では、右手が頻繁にオクターブ内を移動する跳躍や、分散和音の動きが目立ちます。鍵盤の位置を素早く把握し、安定したポジションで弾けるようにすることが重要。
練習のコツとしては、跳躍先の音を目で確認する”先読み”の習慣を身につけること。
そして、手首を柔らかく保ちながら、手全体で移動する意識を持つと、スムーズな運指につながります。特に速いテンポの中で正確に音をとらえるには、無理な力が入らないように気をつけることが大切です。
2. 軽やかなタッチを意識しよう
「蝶々」の世界観を損なわないためには、重たい打鍵は禁物です。音の粒をそろえながらも、柔らかく軽快なタッチを維持しましょう!
このためには、腕の重みを抜き、指先でコントロールする感覚を養いましょう。鍵盤を押し込むのではなく”触れる”ような感覚を意識すると、音がクリアになります。スタッカートに近い音形も多いため、跳ねすぎず、滑らかすぎずの中間を狙うのがポイントです。
3. ペダルは控えめに
テンポが速く、細かな音が多い「蝶々」では、ペダルを使いすぎると音が濁ってしまいます。基本的にはペダルなしで弾くか、どうしても必要な箇所にだけ軽く使うようにしましょう。
特にフレーズの切れ目や跳躍の前後では音を分離することが大切で、ペダルによって音の輪郭がぼやけてないように注意が必要です。
もし使用する場合は、浅めに踏んで素早く戻す“ハーフペダル”のような工夫も効果的ですよ!
【無料楽譜あり】蝶々の楽譜紹介
出典:YouTube
IMSLPの無料版
グリーグの「蝶々」はすでにパブリックドメイン(著作権が切れている状態)となっており、IMSLP(International Music Score Library Project)を利用して無料でダウンロードできます。
蝶々の楽譜ダウンロードはこちら!
IMSLPでは複数の版が公開されており、原典版・校訂版など好みに応じて選べるのが特徴です。演奏者のレベルに応じて、自分に合った楽譜を選びましょう。
有料楽譜や校訂版
日本国内で入手しやすい有料の楽譜も多数あります。
たとえば、1曲だけ欲しい方は、全音ピアノピース一択です。
全曲版だと、音楽之友社も良いですね。
>>アマゾン:グリーグ 抒情小曲集1: New Edition 解説付 (標準版ピアノ楽譜
これらの楽譜は、運指や強弱、解説が丁寧に書かれているため、学習者にとってとても使いやすいです。特に独学の方は、指番号が示されているものを選ぶと効率的に練習できます。
グリーグ「蝶々」の難易度解説:まとめ
グリーグの「蝶々」は、演奏時間は短いものの、その中にさまざまなテクニックと表現が詰め込まれた珠玉の1曲です。初級後半〜中級初期の学習者にぴったりの課題曲として、技術だけでなく音楽的な感受性も育むことができます。
この記事のポイント:
- 「蝶々」はグリーグの『抒情小品集』第1集に収録された詩的な小品
- 難易度はブルグミュラー〜ソナチネ程度、テクニックと感性のバランスが必要
- ピアノ歴3〜5年程度の学習者におすすめ
- 右手の跳躍、軽やかなタッチ、ペダルの節度が演奏の鍵
- 発表会曲としても華やかで印象に残りやすい
- IMSLPで無料楽譜を入手できるが、有料版での学習も効果的
- 自分らしい表現を見つける楽しさが味わえる1曲
ぜひ、この愛らしくも奥深い「蝶々」に挑戦して、グリーグの音楽世界に触れてみてください!