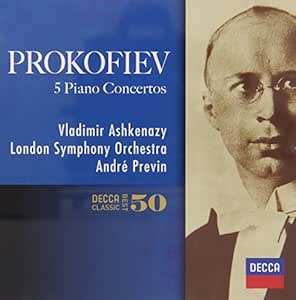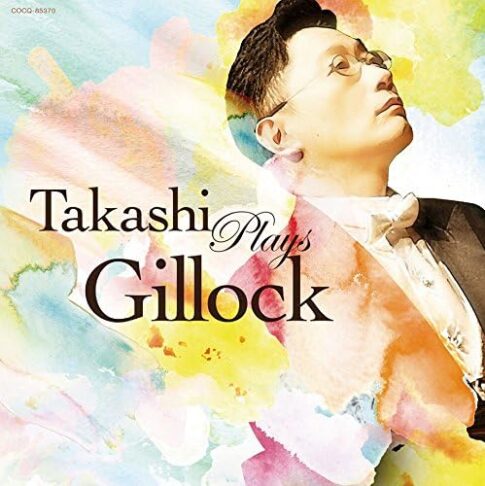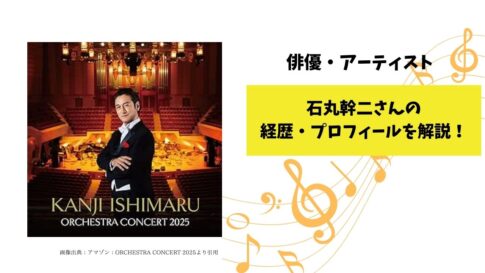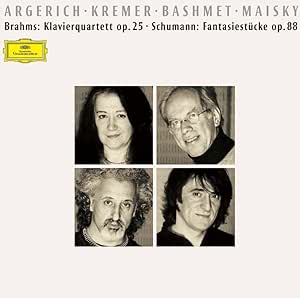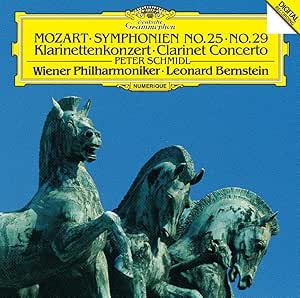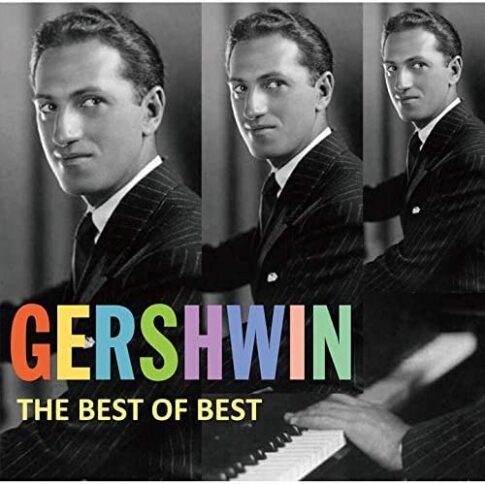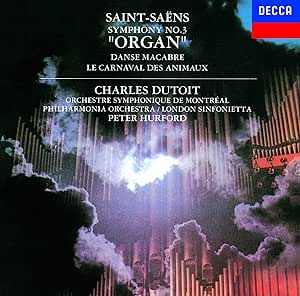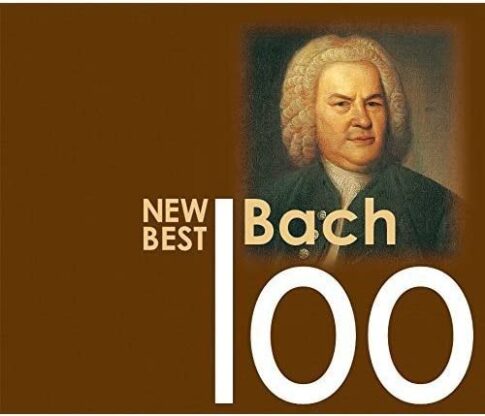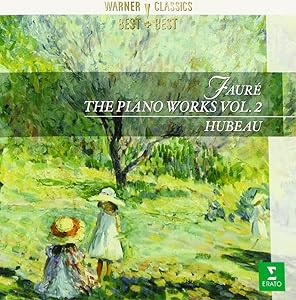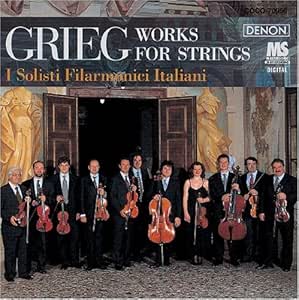この記事では、カバレフスキーの「ソナチネ13-1」の難易度を解説しています。
カバレフスキーの「ソナチネ Op.13 No.1」について、このような疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。
しかし、その人気とは裏腹に、具体的な難易度や効果的な練習方法については、意外と情報が少ないのが現状です。
そこでこの記事では、ピアノ指導の経験を持つ筆者が、カバレフスキーの「ソナチネ13-1」の難易度、楽曲の魅力、そして上手に弾きこなすための3つの重要なポイントを「超絶解説」していきます。
さらに、記事の後半では楽譜の情報もご紹介しますので、すぐにでも練習を始めたい方も必見です!
筆者は3歳からピアノを開始紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています。音大には行っておらず、なぜか哲学で修士号という謎の人生です。
カバレフスキーってどんな人?
出典: YouTube
難易度解説の前に、いつものようにちょっとだけ寄り道を・・・
まず、作曲者であるドミトリー・カバレフスキー(1904-1987)について超簡単に紹介しますね。
カバレフスキーは、プロコフィエフやショスタコーヴィチと並び、旧ソビエト連邦を代表する作曲家の一人。彼の作品は、明快で親しみやすいメロディーと、生き生きとしたリズムが特徴です。
特にカバレフスキーは、子供のためのピアノ教育に情熱を注いだことで知られています。
子供たちが音楽の楽しさを感じながら、無理なく技術を習得できるような優れたピアノ曲を数多く作曲しました。
この記事で紹介する「ソナチネ13-1」も、そうした彼の教育的な配慮と、芸術的な魅力が見事に融合した傑作の一つです。
せっかくなので、こちらの記事も本記事を読了後にご一読ください。
カバレフスキー「ソナチネ13-1」の楽曲構成
出典:YouTube
「ソナチネ13-1」は、クラシックのソナタ形式に沿った3つの楽章で構成されています。それぞれの楽章が持つ異なる魅力を知ることで、曲全体の理解が深まりますよ!
ここでも一つずつ解説しますね!
参考|ピティナ・ピアノ曲事典|カバレフスキー・ソナチネ 第1番 ハ長調 Op.13-1
第1楽章:Allegro assai e lusingando
非常に快活でエネルギッシュな楽章です。冒頭から駆け上がるようなスケール(音階)が印象的で、聴く人の心を一気につかみます。軽快なリズムの中に、時折現れる歌うようなメロディー(この辺がカバレフスキーらしいです)がアクセントとなっており、演奏していて非常に楽しい楽章です。
第2楽章:Andantino cantabile
第1楽章とは対照的に、穏やかで美しい歌謡風の楽章です。“cantabile”(カンタービレ)とは「歌うように」という意味。右手の美しいメロディーを、左手の優しい和音がそっと支えます。きれいな詩を読むかのように、豊かな表現力が求められます。
第3楽章:Presto
「Presto(プレスト)」は「急速に」を意味する音楽用語で、その名の通り、めまぐるしいスピード感あふれるフィナーレです。トッカータ風の技巧的なパッセージが次々と現れ、曲の終わりに向かって華やかに盛り上がっていきます。弾きごたえがあり、発表会などで演奏すると非常に見栄え(聴き映え)がする楽章です。難易度高めです。
カバレフスキー「ソナチネ13-1」の難易度を徹底解説!
出典:YouTube
ということで、「ソナチネ13-1」の難易度について、具体的な指標と筆者の実体験交えながら解説します。
全音ピアノピースの難易度では販売されていませんが、実感として「難易度C級(中級)〜D級」くらいかなと。
ピアノ学習の中盤に差し掛かった学習者が取り組むのに最適なレベルだと思います。
同じレベルの作品は?
他の作曲家の作品と比較するとこんな感じです(あくまでも目安です)。
- クーラウ、クレメンティ:「ソナチネアルバム第1巻」に収められている多くの曲
- バッハ:「インヴェンション」の易しい曲
- ギロック:「叙情小曲集」
これらの曲集に現在取り組んでいる方や、終えたばかりの方にとっては、次のステップとして良い目標になると思います。
ギロック作曲「ワルツエチュード」が弾ければ、チャレンジできると思いますよ!
>>アマゾン:J.S.バッハインヴェンションとシンフォニア 全音ピアノライブラリー
教則本だとどの程度?
日本の代表的な教則本で言えば、「ツェルニー30番練習曲」に入ったくらいのレベルが目安かなと。指の独立や基本的なテクニックが身についていることが、この曲を弾きこなす上で必須だと思います。さらに、全体で7分くらいあるので、結構な体力も必要です!
ピアノを始めて何年くらいで弾ける?
練習環境や進度には個人差があるため一概には言えませんが、一般的にはピアノを始めてから3年~5年程度で挑戦する方が多いようです。
毎週のレッスンを継続し、毎日コツコツと練習を続けていれば、十分に到達可能なレベルです。
筆者は3歳から始めたので、小学3〜4年で演奏した記憶があります。
カバレフスキー「ソナチネ13-1」演奏のポイント3つ
出典:YouTube
ここからは、この曲をより素敵に演奏するための具体的なポイントを3つに絞って解説します。
といっても、すべて基本的なことですが・・・。
でも、基本が一番大事ですから。
1. 指をしっかり動かし、粒の揃った音を出す
特に第1楽章と第3楽章では、速いパッセージやスケールが数多く登場します。そのため、大切なのは「一音一音をハッキリと、均一な音量で弾くこと」です。
- 練習方法:
- まずは非常にゆっくりなテンポで、指の形を意識しながら練習しましょう。
- メトロノームを使い、一音ずつ正確なリズムで弾けているか確認。
- 指先に意識を集中し、鍵盤の底までしっかりと打鍵する感覚を掴みましょう。
「粒の揃った音」が出せるようになると、演奏全体がクリアでプロフェッショナルな印象になります。
2. 左右の手のバランスを意識する
このソナチネでは、左右の手がそれぞれ独立したメロディーを演奏したり、会話のように役割を交代したりする場面が多く見られます。
- ポイント:
- 主役はどちらか?:楽譜をよく見て、今どちらの手がメロディー(主役)を弾いているのかを常に意識。
- 伴奏は控えめに:伴奏(脇役)を担当する手は、主役のメロディーを邪魔しないように、少し音量を抑えて演奏します。特に第2楽章では、このバランスが曲の美しさを大きく左右します。
片手ずつ練習する際に、自分の演奏を録音して聴き比べてみるのも効果的!
3. ダイナミクス(強弱)で音楽に立体感を出す
カバレフスキーの楽譜には、p(ピアノ)やf(フォルテ)といった強弱記号がたくさん書き込まれています。これらを忠実に、そして少し大胆に表現することが、生き生きとした演奏への鍵となります。とはいえ、雑にならないように気をつけましょう!
- ポイント:
- クレッシェンドとデクレッシェンド:ただ強く・弱くだけでなく、だんだん強く(クレッシェンド)したり、だんだん弱く(デクレッシェンド)したりする過程を丁寧に表現しましょう。
- 場面の切り替え:例えば、静かな部分から急に力強い部分へ移る場面では、その変化を思い切って表現することで、聴衆を惹きつけることができます。
強弱の変化は、音楽の物語を語るための最も重要なツールの一つです。設計図である楽譜を読み解き、自分なりの表現を加えてみましょう。
カバレフスキー「ソナチネ13-1」の楽譜紹介
出典:YouTube
それでは最後に、楽譜情報を紹介します。
現在、日本で最も手に入りやすいのは、全音楽譜出版社から出ている「カバレフスキー こどものためのピアノ小曲集」でしょう。解説も丁寧で、学習者にとって使いやすいです。
>>アマゾン:カバレフスキー 二つのソナチネ Op.13 (ピアノライブラリ-)
残念ながら、カバレフスキーの作品は著作権保護期間が続いているため、国際楽譜ライブラリープロジェクト(IMSLP)で、無料楽譜のダウンロードはできません。
カバレフスキー「ソナチネ13-1」の難易度まとめ
最後に、この記事で解説した「ソナチネ13-1」の難易度とポイントをまとめます。
【本記事のポイント】
- ソナチネ13-1はピアノ中級レベルの名曲
- 弾きこなすには「粒の揃った音」「左右のバランス」「豊かな強弱表現」が鍵
- ソナチネやバッハのインベンション、ツェルニー30番程度の実力があればOK
- 全音ライブラリーの楽譜紹介
この曲は、ピアノの基本的なテクニックを定着させながら、音楽を表現する喜びを味あわせてくれます。この記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ練習に取り組んでみてください!