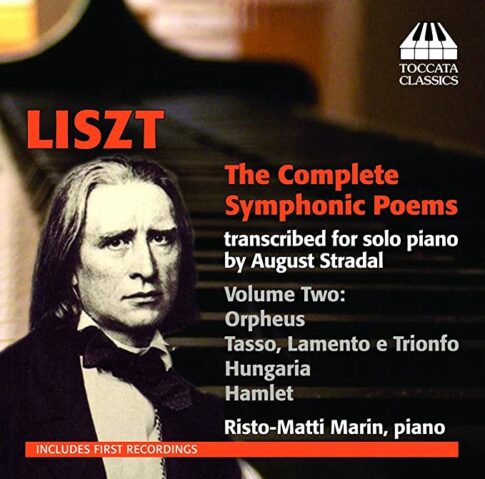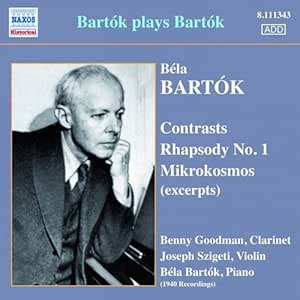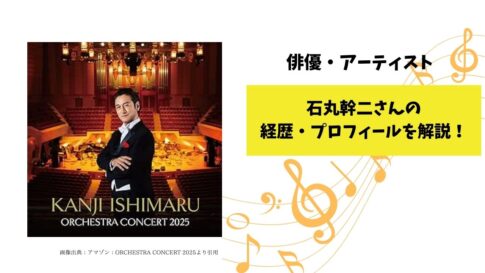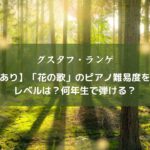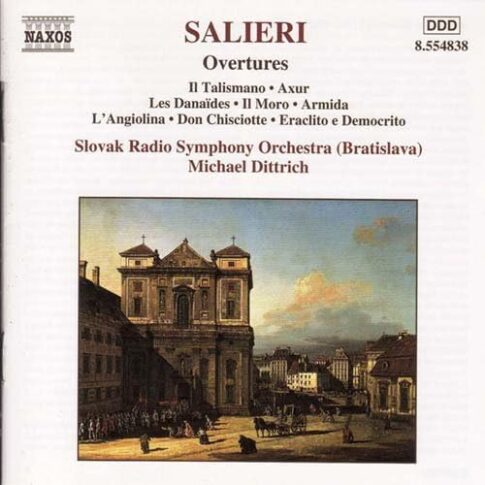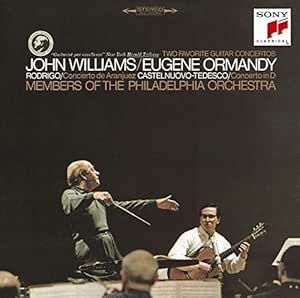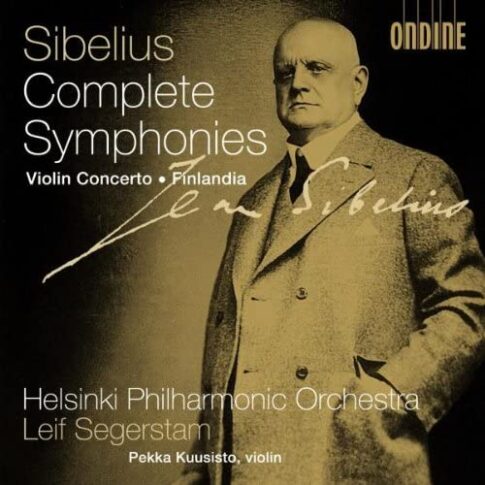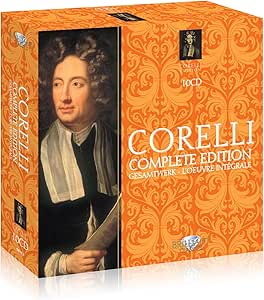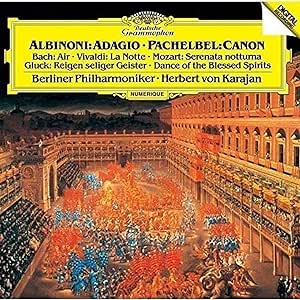この記事では、ハンガリーを代表する作曲家コダーイ・ゾルターン(以下コダーイ)を紹介します!
オーケストラの演奏会で、曲の冒頭に奏者全員が派手な「くしゃみ」をする、というユニークな演出をご存知でしょうか。このユーモアあふれる曲こそ、ハンガリーの国民的作曲家コダーイの代表作、組曲『ハーリ・ヤーノシュ』です。
作曲家であると同時に、民族音楽蒐集家、音楽教育者としても活躍し、とくに音楽教育の分野では「コダーイ・システム」の創始者としても知られています。
この記事では、偉大な音楽教育家であり、母国ハンガリーの魂を音楽で表現し続けたコダーイの生涯やエピソード、そして絶対に聴いておくべき代表曲を、分かりやすく紹介します。
筆者は3歳からピアノを開始。紆余曲折を経て、かれこれ30年以上ピアノに触れています。音大へは行っておらず、なぜか哲学で修士号というナゾの人生です。
コダーイとは?ハンガリーの音楽教育を築いた国民的作曲家

まずは、コダーイがどのような人物だったのか、基本的なプロフィールから見ていきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フルネーム | ゾルターン・コダーイ |
| 生没年 | 1882年 – 1967年 |
| 出身 | ハンガリー・ケチケメート |
| 主な功績 | ・ハンガリー民族音楽の研究と収集<br>・音楽教育法「コダーイ・システム」の確立 |
| 代表作 | 組曲『ハーリ・ヤーノシュ』、『ガランタ舞曲』、『孔雀変奏曲』 |
コダーイの生涯①:幼少期〜青年期(1882年〜1905年)
民謡との出会いが人生を変えた
1882年、ハンガリーのケチケメートに生まれたコダーイ。父親が鉄道職員だった関係で各地を転々とする少年時代を送りました。とくに幼少期を過ごしたガランタの地では、ジプシー(ロマ)音楽や民族舞曲に触れる機会が多く、後の創作に大きな影響を与えます。
青年期にはブダペスト大学で言語学を、フランツ・リスト音楽院では作曲とチェロを学び、学問と芸術の両面で才能を発揮。この頃から、音楽を「自国文化の根幹」としてとらえる姿勢が見られました。
コダーイの生涯②:バルトークとの出会いと民謡研究(1905年〜1920年代)
学問としての民族音楽に情熱を注ぐ
1905年、彼の人生において最大の転機が訪れます。それが、作曲家バルトーク・ベーラとの出会いでした。2人は音楽院の仲間であると同時に、民族音楽への共通の関心を持ち、ハンガリー各地の村々を訪れて民謡を採集。
この時代、蓄音機を持ち歩いて録音しながら、何千曲にも及ぶ民謡を採譜・分類しました。
彼らの活動は、のちに民族音楽学(エスノミュージコロジー)という新たな分野を切り拓く基礎となり、コダーイにとっては“音楽は国民の魂”という思想を確信する時間となりました。
コダーイの生涯:教育者としての確立期(1920年代〜1940年代)
音楽はすべての人に——コダーイ・システムの誕生
第一次世界大戦後の混乱の中、コダーイは作曲活動よりも教育の道を重視するようになります。1925年ごろから本格的に音楽教育の改革に取り組み、ハンガリー全土の初等教育で導入できるような教育法を構築しました。
子どもたちが自国の民謡に親しみ、遊びや歌を通じて音楽を学べるように工夫されたこのシステムは、後に「コダーイ・メソッド(コダーイ・システム)」として世界に広まり、教育者としての彼の名声を決定づけました。
コダーイの生涯:晩年と世界的評価(1950年代〜1967年)
国民的英雄から、世界の音楽教育の象徴へ
第二次世界大戦後も、コダーイはハンガリー国内で教育改革に携わりながら、国際的な音楽教育のカンファレンスに出席するなど、活動の場を広げていきます。1950年代以降はアメリカや日本を含む各国の教育者たちが彼のメソッドを学びにブダペストを訪れるようになり、「音楽教育の父」としての評価を世界的に確立しました。
また、作曲家としても晩年まで創作意欲を失わず、交響曲第1番(1961年)など新たな挑戦を続けました。
1967年に85歳で逝去。ブダペストにある国立墓地「ファルカシュレート墓地」に葬られ、現在もハンガリーの誇りとして讃えられています。
「コダーイ・システム」とは?音楽教育への情熱
コダーイの功績を語る上で欠かせないのが、彼が体系化した音楽教育法「コダーイ・システム」です。これは、「音楽はすべての人々のものであり、質の高い音楽教育は人格形成に不可欠である」という彼の強い信念に基づいています。
最大の特徴は、子どもたちが母語を覚えるのと同じように、自国の「わらべうた」や「民謡」に親しむことから音楽を学ぶ点。難しい理論から入るのではなく、歌うこと、遊ぶことを通して、自然に音楽の基礎を身につけることを目指しました。音階を身体で覚えるための「ハンドサイン」なども、この教育法で用いられる有名な手法の一つです。
コダーイ・システムは、日本の教育現場でも実践されていますよ!
知れば知るほど尊敬できる!コダーイの豆知識・エピソード5選

コダーイの音楽と教育法の背景には、人間味あふれる深い情熱が感じられます。
困難な時代を「いかに豊かに生きるべきか」、コダーイはその答えを芸術に求めたのかもしれません。ここでは、コダーイにまつわるエピソードを5つ紹介します。
コダーイの豆知識・エピソード:① 生涯の友・バルトークとの民謡収集の旅
コダーイは、同じくハンガリーを代表する作曲家バルトーク・ベーラと生涯にわたる友情を結びました。二人は共に、近代化の波にのまれて消えゆく運命にあった自国の民謡を救うため、馬車に乗って国内の辺境の村々まで足を運びます。蓄音機を担ぎ、何千もの民謡を採譜・録音した彼らの地道な活動は、ハンガリーの文化にとって計り知れない財産となりました。
ハンガリーを代表する国民楽派の作曲家として、バルトークとコダーイを覚えておきましょう!
豆知識・エピソード:② 政治的圧力に屈しなかった強い信念
彼の生涯は、オーストリア=ハンガリー帝国、ナチス・ドイツ、そしてソ連といった大国の支配と常に隣り合わせでした。しかし、コダーイは政治的な圧力に屈することなく、ハンガリー独自の文化と音楽を守るために生涯を捧げました。その毅然とした態度は、多くの国民から深い尊敬を集め、20世紀におけるハンガリーにおいて、もっとも偉大な芸術家と称されています。
豆知識・エピソード:③ 教育者としての情熱「3歳から90歳までの音楽教育」
「音楽教育に早すぎることも、遅すぎることもない」と考え、幼児教育の重要性を誰よりも早くから説いたコダーイ。音楽は一部の才能ある人間のためだけのものではなく、豊かな人生を送るためにすべての人に必要であると、生涯を通じて訴え続けました。
>>アマゾン:いっしょにあそぼうわらべうた (3・4歳児クラス編) :コダーイ芸術教育研究所
豆知識・エピソード:④ 日本の音楽教育との意外なつながり
彼が確立した「コダーイ・システム」は世界中に広まり、戦後の日本にも紹介されました。わらべうたを重視する考え方や、身体を使って音感を養う手法は、日本の音楽教育者たちに大きな影響を与え、現在の音楽の教科書や教育現場にもその精神が息づいています。
豆知識・エピソード:⑤ 遅咲きのシンフォニー
作曲家として早くから名声を得ていたコダーイ。しかし意外にも交響曲第1番を完成させたのは70代後半になってからでした。これは、彼が作曲活動よりも、ライフワークである民族音楽の研究や音楽教育法の確立を優先させていたためだったとのこと。彼の真摯で誠実な人柄がうかがえるエピソードと言えるでしょう。
【初心者向け】これだけは聴きたい!コダーイの代表曲3選
ハンガリーの色彩と温かみに満ちた、彼の代表的な管弦楽曲をご紹介します。
筆者が初めて聴いた作品は、組曲「ハーリ・ヤーノシュ」でした。おもちゃ箱から出てきたような、本当に楽しげな作品です!
コダーイの代表曲①:組曲『ハーリ・ヤーノシュ』
退役兵のハーリ・ヤーノシュが語る、奇想天外な冒険の「ほら話」を音楽にした作品。物語の始まりにオーケストラが派手な「くしゃみ」をするのは、「これから始まるお話は、全くの嘘ですよ」というおまじないです。特に第3曲「歌」の美しいメロディや、第4曲「戦いとナポレオンの敗北」、第5曲「間奏曲」の情熱的な音楽は必聴です!
出典:YouTube
代表曲②:ガランタ舞曲
コダーイが幼少期を過ごした村ガランタで聴いた、ジプシー(ロマ)楽団の音楽の思い出を基に作曲された作品。次第に熱を帯びていき、最後は情熱的な舞曲で華やかに締めくくられます。ハンガリーの魂ともいえる哀愁と活気が詰まった名曲です。テンションを上げたい時にも良いかもしれません。
出典:YouTube
>>アマゾン:バルトーク:管弦楽のための協奏曲&コダーイ:ガランタ舞曲
代表曲③:孔雀が飛んだによる変奏曲
ハンガリー民謡「飛べ、孔雀」を主題とした、管弦楽のための変奏曲。民謡をもとにした本作は、オスマン・トルコからの解放を願う内容を持つとされ、コダーイはこの曲に、抑圧された祖国の自由への祈りを込めたと言われています。荘厳で美しく、そして力強い、彼の最高傑作の一つです。
気になった曲を、プロの演奏で楽しもう!
この記事で気になった作品、耳でも味わってみませんか?
Amazon Music Unlimitedなら、クラシックの名曲がいつでも聴き放題。
名演奏を聴き比べたり、新たなお気に入りを見つけたりと、楽しみ方は自由自在!
今なら30日間無料体験も実施中。
ぜひ気軽にクラシックの世界をのぞいてみてください!
コダーイとはどんな人物?:まとめ
今回は、作曲家であり偉大な音楽教育家でもあったコダーイの人物像と、その音楽の魅力をご紹介しました。 彼が音楽を通して、いかに自国の文化を愛し、次世代を担う子どもたちの心を豊かにしようと尽力したかがお分かりいただけたのではないでしょうか。
まずは『ハーリ・ヤーノシュ』の愉快な世界から、コダーイの温かくも情熱的な音楽に触れてみてください。