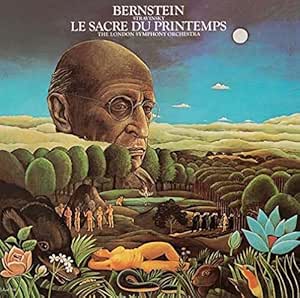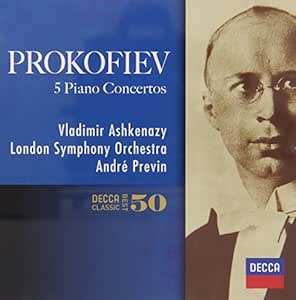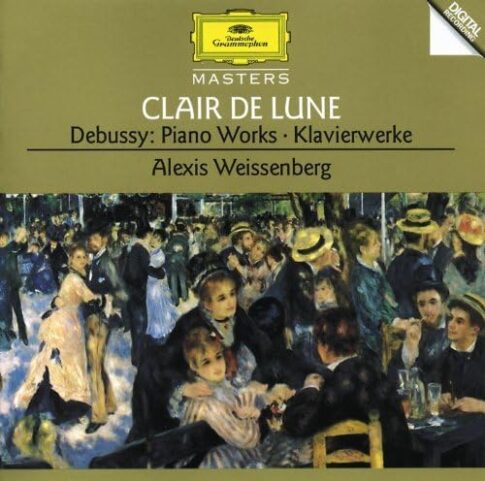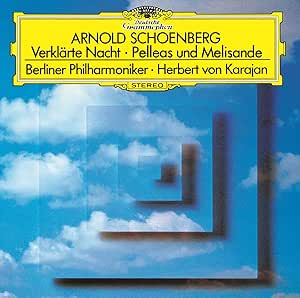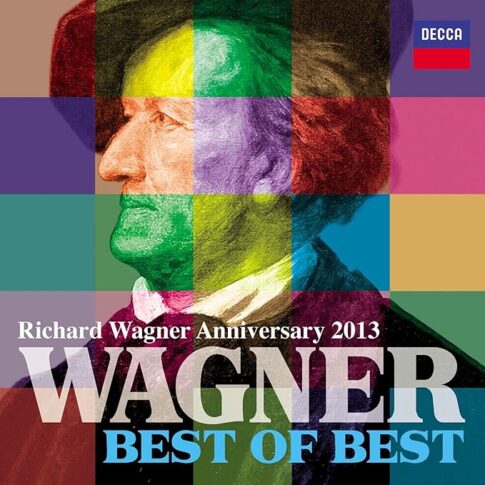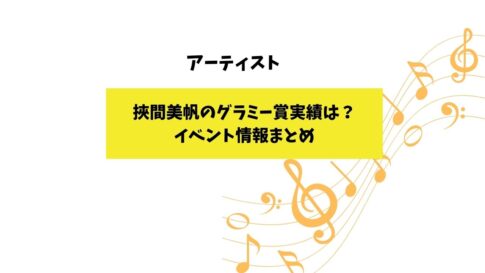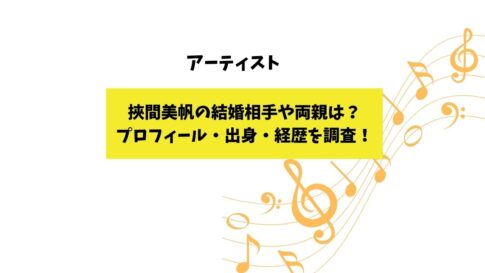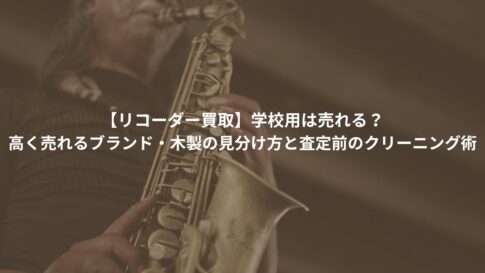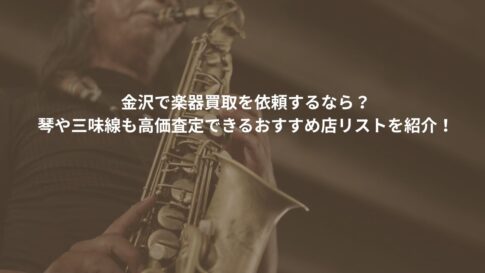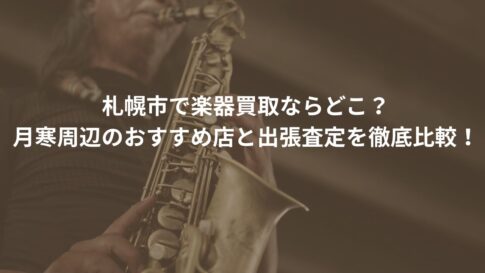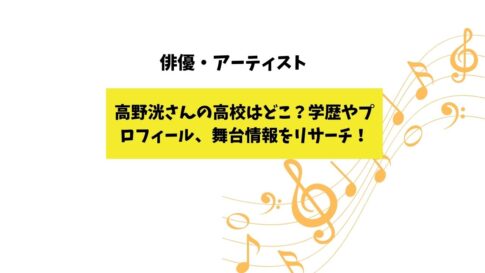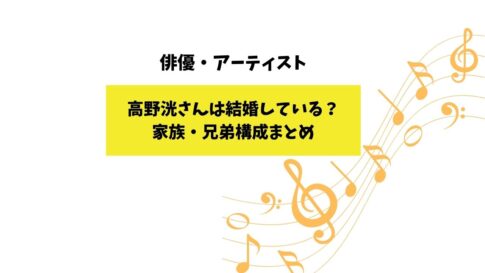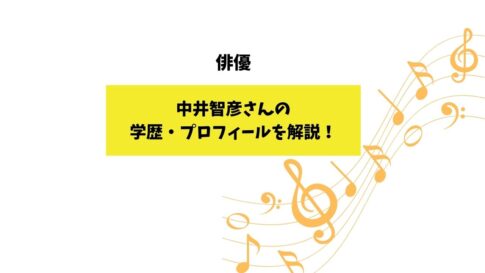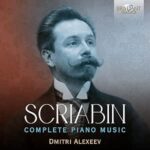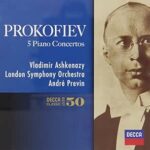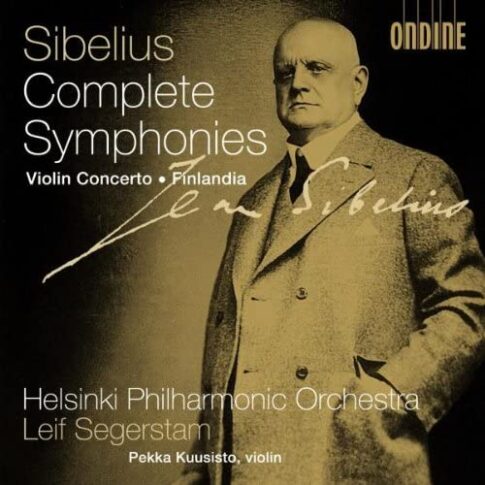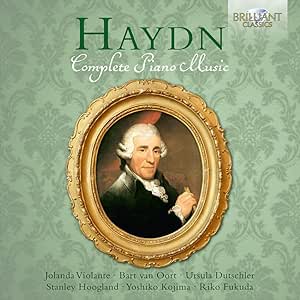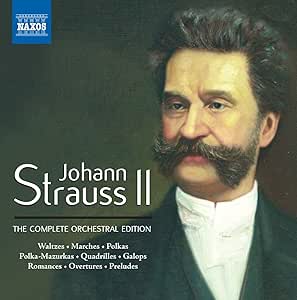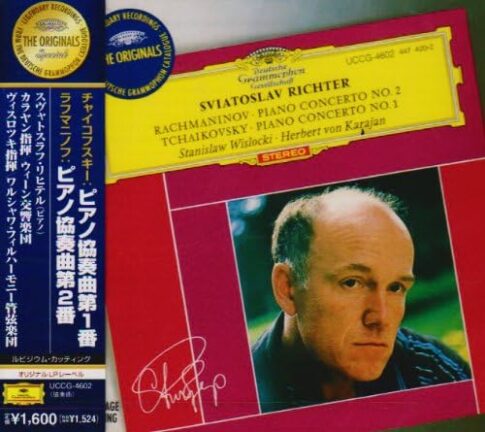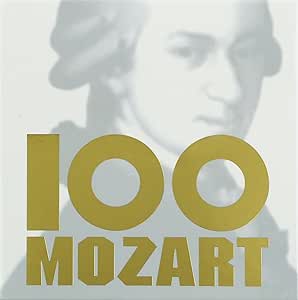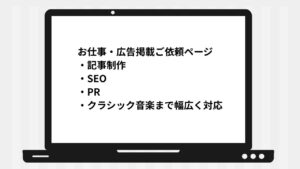この記事では、ロシアを代表する作曲家アレクサンドル・スクリャービンを紹介します。
聞き慣れない方も多い作曲家かもしれませんが、ロシアのクラシック音楽界を語る上では重要な人物です。
また、スクリャービンが作曲したピアノ曲は、現在でも多くのピアニスト、ピアノ学習者によって愛され続けています。
独特のメロディーで聴衆を魅了し続けているスクリャービンとは、どのような人物だったのでしょうか。ライバルだったラフマニノフとの関係も併せて紹介します。
いつもながらのざっくり解説ですので、ぜひ最後までお付き合いください。
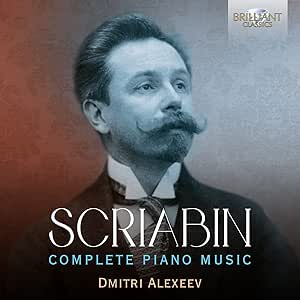
12万冊以上の本が聴き放題!
スキマ時間を「学び時間」に。
解約もいつでもOK
amazon audible
スクリャービンの生涯年表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1872年 | ロシア・モスクワに生まれる。幼少期からピアノと作曲に親しむ。 |
| 1888年 | モスクワ音楽院に入学。ラフマニノフとは同級生。 |
| 1892年 | 音楽院を卒業し、ピアニスト・作曲家として活動開始。 |
| 1894年 | パリで演奏活動。ショパンに影響を受けた初期作品を作曲。 |
| 1903年 | 後期ロマン派から脱却し、独自の神秘思想・音楽理論を探求し始める。 |
| 1905年 | 《神聖な詩(交響曲第3番)》を完成。以後、「神秘主義的音楽」へ傾倒。 |
| 1908年 | 交響詩《法悦の詩》を発表。官能的かつ哲学的な音楽で話題に。 |
| 1910年 | 《プロメテウス〜火の詩》を作曲。「色光ピアノ」を用いた演奏を構想。 |
| 1915年 | 皮膚感染症によりモスクワで急逝。享年43歳。未完の大作《神の劇》を構想中だった。 |
スクリャービンの生涯

ショパンの影響を受けつつ、作品にロシア的感性を見事に融合させたスクリャービン。
その繊細かつ独特な音色は、ピアノ学習者であればだれでも一度は魅了されるはずです。
20世紀のクラシック音楽に革命的な進歩をもたらし、のちのストラヴィンスキーやプロコフィエフにも影響を与えたスクリャービンとは、どのような人物だったのでしょうか。
スクリャービンの生涯その1、貴族の血を引く天才の誕生
1872年1月6日、モスクワで生を受けたアレクサンドル・スクリャービン。
その誕生は、音楽界に新たな革命をもたらす序曲となりました。
スクリャービンの家系は、ロシアの貴族社会に深く根ざしていました。
父方の曽祖父は1819年に世襲貴族となり、母方の血筋は古代ルーシの王朝にまで遡るという、まさに「青い血」の持ち主でした。
しかし、スクリャービンの人生は順風満帆だったわけではありません。
彼が1歳になる前に、母リュボフ・ペトロヴナが産褥熱で急逝。
この悲劇により、幼いスクリャービンは叔母リューバの手によって育てられることになりました。
人生の早くから逆境に苦しんだスクリャービンでしたが、それこそが、彼の音楽への情熱を育んだといっても過言ではありません。
そして、アマチュアピアニストだった叔母の演奏に魅了されたスクリャービンは、自然と音楽への道を歩み始めます。
早熟だったスクリャービン。
このころから人形を使った自作の劇やオペラを楽しそうに披露していたとのこと。
内気なイメージがありますが、少年時代は周囲を楽しませるような社交的な少年だったようです。
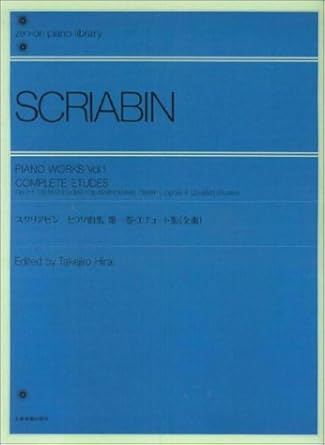
スクリャービンの生涯その2、才能の開花と苦難の日々
そんなスクリャービンの才能は、周囲も驚くほど早くから開花。
10歳で陸軍兵学校に入学しながらも、14歳からはモスクワ音楽院に通うことを許されます。
そしてスクリャービンは、セルゲイ・タネーエフやニコライ・ズヴェーレフといった大物音楽家たちの指導を受け、その才能をさらに
しかし、音楽の道は必ずしも簡単ではなかったようです。
練習中に右手を損傷し、医師からは「回復の見込みなし」と宣告されるという絶望も味わいます。
その後、この挫折を乗り越えたスクリャービンは、不屈の精神で音楽と向き合い続け、最初の大作『ピアノ・ソナタ第1番』の誕生につなることとなりました。
1888年には、周囲の勧めによりモスクワ音楽院に入学。
ピアノ科、作曲科で音楽を学んでいます。
ライバルとなったセルゲイ・ラフマニノフと出会ったのも、音楽院での出来事です。
スクリャービンの生涯その3、革新的音楽家としての道
1898年、スクリャービンはモスクワ音楽院の教授に就任。
この頃から、彼はピアノ作品だけでなく、交響曲の作曲にも挑戦し始めます。
教育者としてのスクリャービンは、学生の間でも評判がよく、真面目で学生の意欲を尊重するような教育方針だったとのこと。
彼の音楽は、技巧的な難しさと深い感情表現で知られ、当時の音楽界に新風を吹き込みました。
そして1904年にはスイスに移住。
同地ににて『交響曲第3番』を構想し、1905年にパリで行われた初演が成功を収めると、彼の名がヨーロッパに知れ渡るきっかけとなりました。
そして1908年、ニューヨークにて『交響曲第4番「法悦の詩」』が初演されると、スクリャービンの名は全世界なものへ広がっていきます。
この作品の独特な和声法と色彩豊かな音楽性は、当時の多くの聴衆を魅了したといいます。
晩年のスクリャービンは、音楽と哲学、そして神秘主義を融合させようと試みました。
彼が構想した壮大な作品『ミステリウム』は、音楽、詩、舞踊、香り、光を統合した総合芸術でした。
この構想は完成には至りませんでしたが、後世の芸術家たちに大きな影響を与えることとなりました。
スクリャービンの生涯その4、栄光と悲劇の最期(死因)
1909年、再びロシアに帰国したスクリャービンは、総合劇術プロデューサーのセルゲイ・ディアギレフと関わりを持ち、それまでにないような、壮大なプロジェクトに参加し始めます。
1915年4月2日、サンクトペテルブルクで行われた最後のコンサートは、スクリャービンの音楽人生の集大成となりました。
批評家たちは彼の演奏を「最も感動的で影響力のある」ものと絶賛。
スクリャービン自身も、「周りに人がいるホールで演奏していることをすっかり忘れていた」ほど、深い没入状態に陥ったと語っています。いわゆるゾーンだったのでしょう。
しかし、栄光の絶頂にあったスクリャービンの人生は、突如として幕を閉じることになります。
1915年4月14日、わずか43歳で敗血症により帰らぬ人となったのです。
彼の死は音楽界に大きな衝撃を与えましたが、スクリャービンの革新的な音楽は、彼の死後も多くの作曲家たちに影響を与え続けています。
同じロシアの作曲家ストラヴィンスキーやプロコフィエフなども、スクリャービンから大きな影響を受けた人物の一人です。
スクリャービンの死因について
敗血症の原因となった小さな吹き出物に気がついたのは(最初の原因は虫刺され)、亡くなるわずか10日前のことだったそうです。
それから急速に熱が出始め、体温が41度までに上昇したと伝えられています。
みるみるうちに大きくなった吹き出物について、スクリャービンの主治医は「紫色の炎のようだ」と表現したそうです。
そして4月12日、吹き出物の手術(切開)が実施されたものの、時すでに遅しでした。
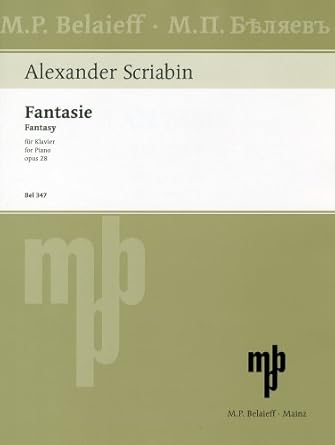
スクリャービンの遺産と現代への影響
スクリャービンの音楽は、20世紀の音楽に多大な影響を与えました。
彼の実験的な和声法や音階の使用は、後の前衛音楽の先駆けとなったのです。
また、スクリャービンは共感覚(音を色として感じる能力)を持っていたと言われています。彼はこの能力を活かし、音と色を結びつけた独自の音楽表現を追求しました。この試みは、現代の視聴覚アートにも大きな影響を与えています。
アレクサンドル・スクリャービンの生涯は短かいものでした。
しかし、彼が音楽界に残した足跡は計り知れません。
革新的な和声法、哲学的な音楽観、そして音と色を融合させようとした壮大な構想。
これらはすべて、後世における音楽の可能性を大きく広げたことは間違いないでしょう。
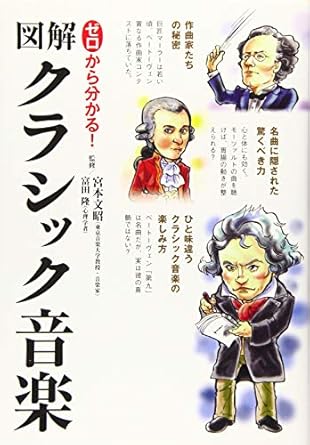
スクリャービンの豆知識やエピソードについて

スクリャービンは、ドビュッシーやシェーンベルクらと共に、
20世紀におけるいわゆる「現代音楽」の先駆者とも称されています。
知名度では両者にやや劣るものの、音楽的形式の観点においては、まさに革命をもたらした人物でした。
そんなスクリャービンの豆知識やエピソードをいくつかざっくりと紹介します。
スクリャービンの豆知識・エピソードその1、ピアノを自作する
早熟だったスクリャービン。
それは、なにも音楽にだけにとどまらなかったようです。
ピアノの複雑な構造にも魅了された彼は、なんとピアノを自分で作ってしまったのだとか。
もちろん原寸大のピアノではありませんが、
興味を持ったことにつていはとことん突き詰める性格は、幼少期から養われたようです。
なお、作ったピアノを演奏会のゲストにプレゼントとして贈ることもしばしばでした。
豆知識・エピソードその2、連取しすぎて右手を負傷する
音楽学生時代、超絶技巧の制覇数を同級生のヨゼフ・レヴィーンと競っていたスクリャービン。
負けず嫌いだった彼は、毎日のように凄まじい練習量をこなしました。
しかし、あまりにも難曲を練習したため、ついに右手を負傷。
主治医から「回復の見込みなし」と宣告されてしまうことに・・・。
普通であれば、ピアノの練習をやめてしまうものですが、そこが違うのがスクリャービン。
今度は、残った左手の猛特訓を開始し、「左手のコサック」と称されるようになります。
右手が不自由となったスクリャービンですが、
これにより左手の可能性を切り開き、彼独自のピアノ書法を生み出すに至ります。
もし、この出来事がなければ、現在のスクリャービンの神秘的な音色は生まれていなかったかもしれません。
豆知識・エピソードその3、ラフマニノフに敗北する
ピアノ科と作曲科に在籍したスクリャービンですが、当時の彼は作曲科を修了することができず、ピアノ科のみを修了しています。
その頃、作曲科で有力視されていたがのラフマニノフ、そしてピアノ科で有望視されていたのがスクリャービンだったそうです。
そんな2人が争うことになったのが、ピアノの卒業試験。
どちらも甲乙つけ難い実力に、周囲も期待の目を向けます。
結局、結果はラフマニノフが1位、スクリャービンが2位となり、学生時代のライバル対決に終止符が打たれたのでした。
豆知識・エピソードその4、哲学や神智学に没頭する
20世紀に入る直前の1900年頃から、スクリャービンは哲学に没頭し始めます。
とりわけ彼が心酔したのは、ドイツの哲学者ニーチェでした。
ニーチェの「超人思想」に共鳴したスクリャービンは、やがて神智学(しんちがく)にも関心をもち、哲学・神智学から音楽的インスピレーションを受けるようになります。
そのほか、ショーペンハウアーやワーグナーにも傾倒し、吸収した哲学的思想を音楽を通して伝えました。
その代表作が上述の『交響曲第4番「法悦の詩』や『交響曲第5番「焔の詩」』です。
交響曲第4番
交響曲第5番「焔の詩」
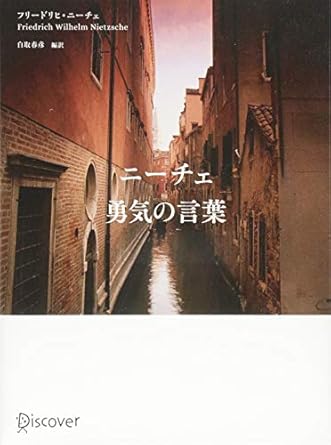
スクリャービンの「幻想曲」についても解説しています。
気になった曲を、プロの演奏で楽しもう
この記事で気になった作品、耳でも味わってみませんか?
Amazon Music Unlimitedなら、クラシックの名曲がいつでも聴き放題。
名演奏を聴き比べたり、新たなお気に入りを見つけたりと、楽しみ方は自由自在!
今なら30日間無料体験も実施中。ぜひ気軽にクラシックの世界をのぞいてみてください。
>>Amazon Music Unlimitedでクラシックを聴いてみる
スクリャービンの生涯まとめ
今回はスクリャービンの生涯をざっくりと解説しました。
ざっくりですが、なかなか波瀾万丈な人生だったことがご理解いただけたと思います。
また、作品の特徴や代表曲については、別記事で紹介していますので、そちらもぜひ併せてご一読くだされば幸いです。