バッハ作品の特徴やおすすめ代表曲を解説します。
バッハは生涯で1000曲以上もの作品を残しました。
なので、有名な曲はたくさんあるのですが、とくに「これ知ってたらすごい!」と思われる作品を選んでみました。
どの作品も音楽史上、いや人類史上最高の傑作ばかりなので、ぜひ参考にして聴いてみてください。
もちろん今回も「超ざっくり」解説です。
クラシックに詳しくない方も最後まで読んでみてください。
バッハ作品の特徴5つ

バッハの作品の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。
バッハの音楽と聞くと、「難しそう」と思う方も多いかもしれません。
確かに、「本格的に」勉強するとなると、めちゃくちゃ難しいです。
でもこのブログでは、小難しいことは言いません。
おすすめ作品とともに、ぜひバッハ音楽に触れてみてください。
バッハの生涯については前回の記事で取り上げましたので、
まだの方はぜひ合わせてお読みください。
バッハ作品の特徴1、複雑な対位法を用いた
複雑な対位法の技法を用いた作曲バッハは、美しく緻密な音楽を生み出しています。特に、『無伴奏チェロ組曲』や『ゴルトベルク変奏曲』などの器楽曲において、緻密な音楽構造が際立っています。
対位法とは
対位法とは、いくつかのメロディーがお互いに調和しながら進行するように作曲されます。
西洋音楽の中でも古くから存在する技法であり、バロック音楽やルネサンス音楽などで広く用いられています。
バッハ作品の特徴2、宗教音楽の傑作を多数作曲
宗教音楽における卓越した作曲能力を発揮したバッハは、『マタイ受難曲』や『ヨハネ受難曲』などの合唱曲に代表されるように、壮大かつ感動的な音楽を作り出しました。
バッハ作品の特徴3、深い信仰心
バッハは深い宗教的信仰を持ち、その信仰が彼の作品に大きな影響を与えています。
『マタイ受難曲』をはじめ、『クリスマス・オラトリオ』などの宗教音楽は、
バッハの信仰心が反映された作品として知られています。
バッハ作品の特徴4、楽器の特徴を最大限活かした
バッハは、様々な楽器の音色を生かした器楽曲を多く作曲しています。
『無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ』や『無伴奏チェロ組曲』などは、それぞれの楽器の特徴的な音色を生かしながら、美しい旋律や複雑な音楽構造を表現しています。
補足 バッハ作品の「BWV」とは?
少しクラシック音楽を知っている人向けに解説。
バッハの作品には「BWV」というアルファベットがついています。
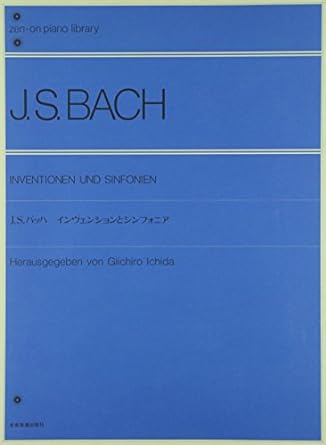
バッハのおすすめ代表曲10選

整然としたバッハの作品を聴いていると、心が整う感じがします。
今回紹介する作品は、クラシックがお好きな方でない限り、初めて聴く人が多はず。
というのも、「あ〜、こんな曲もあるんだ」と思って欲しいので・・・。
いわゆる「バッハといえば!」という作品は今回は紹介しません(いくつかはあるかな)。
壮大なキリスト教音楽も紹介するので、この記事を機会に、ぜひバッハの深さに触れてみてください!
バッハのおすすめ代表曲1:マタイ受難曲
まず 1曲目はマタイ受難曲。
でも、曲解説の前に「マタイって何?」ですよね。
マタイとは、キリスト教の新訳聖書に出てくる人物です。
イエス・キリストの12使徒(弟子)のうちの一人。
新訳聖書には4つの有名な「福音書」と呼ばれる物語があり、そのうちの『マタイによる福音書』を題材にした作品が『マタイ受難曲』。他にも、「ルカによる福音書」「マルコによる福音書」「ヨハネによる福音書」などもあります。
1727年に初演され大好評となりました。
しかし、バッハの死後長く忘れさられ(バッハ本人も)、およそ100年後、メンデルスゾーンが再演したことで再び注目を集め、バッハの再評価に繋がり繋がりました。
クラシック音楽だけでなく、キリスト教音楽の最高傑作として、現在も広く親しまれています。演奏時間3時間という大作です。
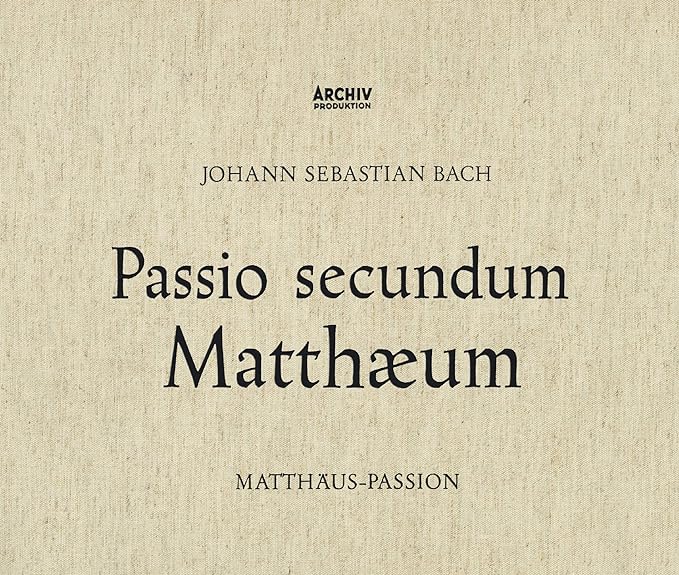
2、ヨハネ受難曲
バッハは新約聖書の『ヨハネによる福音書』も題材にしています。
あっ、福音書と受難曲の説明忘れてた。
福音書(ふくいんしょ)・・・イエス・キリストが行ったことや語った言葉をまとめたもの
受難曲(じゅなんきょく)・・・「イエス・キリストが裁判や処刑で苦しめられたときの言葉」を音楽に乗せて表現した曲のことです。
『マタイ受難曲』の3年前の1724年に初演されています。演奏機会は『マタイ受難曲』ほど多くないですが、こちらもバッハ作品として重要な作品です。演奏時間はおよそ2時間で、さまざまなコラールが用いらています。
コラール・・・キリスト教ルター派で歌われる讃美歌のこと
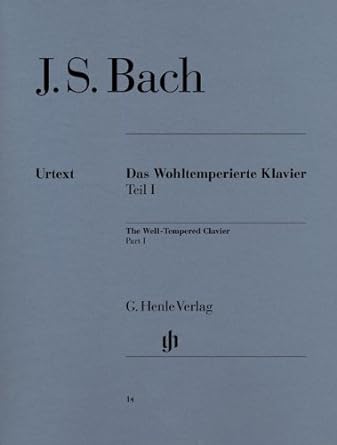
3、マニフィカト
これはもしかしたら聴いたことがあるかも・・・。
タイトルの『マニフィカト』とは「我が心、主を崇(あが)め」という意味です。
キリスト教の聖なる歌(聖歌)の一つ。歌われている内容は、上に書いた『ルカによる福音書』の「聖母マリアの祈り」が使われています。全12曲からなり、冒頭の華やかなトランペットのメロディーが特徴的です。
4、ブランデンブルク協奏曲
全6曲で構成された合奏協奏曲集です。
ブランデンブルク=シュヴェーという地域を収めていた、クリスティアン・ルートヴィヒ伯に捧げられたことから、このタイトルがつけられました。1721年作曲。
しかし、タイトルはバッハ本人によるものではなく、『バッハ伝』という本を書いたシュピッタという人が命名したそうです。また一説によると、バッハがこの作品を作曲したのは「職を得るため」だっととか。
5、無伴奏チェロ組曲
チェロ独奏用の組曲です。
詳しい作曲年代はわかっていませんが、1717年〜1723年頃に作曲されたという説が有力です。こちらも全6曲あり、とくに第一組曲が有名です。『マタイ受難曲』と同じくバッハの死後は忘れさられましたが、チェリストのパブロ・カザルスが再発見したことで、現在では「チェロの聖典」とみなされています。
バッハの深い精神性が感じられ作品です。
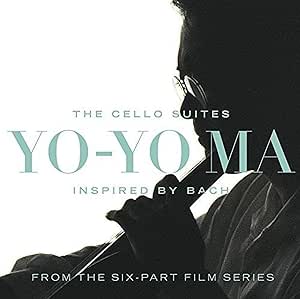
6、無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ
チェロ作品の次は、ヴァイオリンのおすすめ曲を。ソナタとパルティータがそれぞれ3曲ずつ収められたバッハの代表作の1つ。
とくに、『パルティータ3番』のガボットは有名なので、聴いたことがあるかもしれません。1720年、バッハ35歳のときの作品で、ベルリンの国立図書館にはバッハの自筆譜も残されています。
パルティータとはバロック時代(1600年〜1750年)に使われた音楽形式です。イタリアが発祥とされ、「変奏曲」として用いられました。
7、イタリア協奏曲
1734年に作曲されたバッハを代表する鍵盤曲です。とても明るく、メロディアスな作品として人気があります。実際、バッハが生きていた頃も人気があったそうです。
ところで、この作品タイトルで何か気がつきませんか?
そう、「協奏曲」というタイトルがつけられながらも、「一人で演奏する」作品なんです。
というのも、この時代の鍵盤楽器といえばオルガンやチェンバロでした。
チェンバロには鍵盤が2段になっているものがあり、バッハはその表現力を存分に活かして、音楽に「協奏曲風の」厚みをもたせたんです。
なので、「協奏曲」というタイトルがついています(ざっくりとですよ〜)。

それと、チェンバロはドイツ語です。
フランス語ではクラヴサン、英語ではハープシコードと言います。
呼び方が違うだけで同じ楽器なので、ぜひ覚えておいてください。
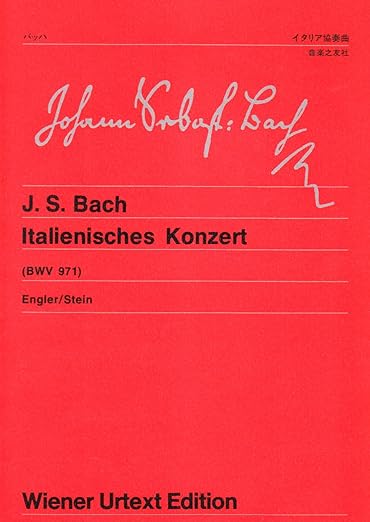
8、フランス組曲
1722〜1723年頃に作曲された6曲からなる組曲です。ピアノを習われている方なら、練習した方もいるかもしれません。
現在では『フランス組曲』のタイトルで知られていますが、バッハ本人は『クラヴィーアのための組曲』と命名しています。当時のフランス風音楽のように洗練された作品であるため、このタイトルが付けられたそうです。
とくに『フランス組曲5番』が有名で、演奏会でもよく取り上げられています。
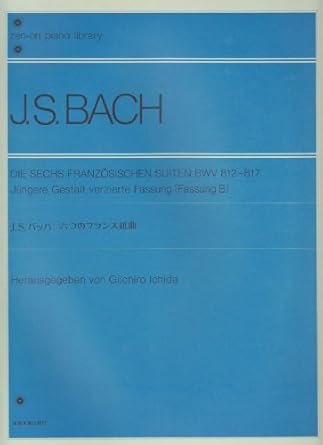
9、ゴルトベルク変奏曲
バッハの鍵盤作品中もっとも広く知られ、演奏機会が多い作品です。また、『フーガの技法』と並ぶ最高傑作でもあります。
1741年に出版された本作は、不眠症に悩むカイザーリンク伯爵のために作曲されました。
タイトルの「ゴルトベルク」とは,バッハの教え子の名前です。ゴルトベルク君が、カイザーリンク伯爵の求めに応じて演奏していたとか・・・。
今で言う睡眠用BGMですね。
32小節からなるアリアが最初と最後に演奏され、あいだに30の変奏が置かれています。とりあえず、『アリア』の美しいメロディだけでもご堪能ください!
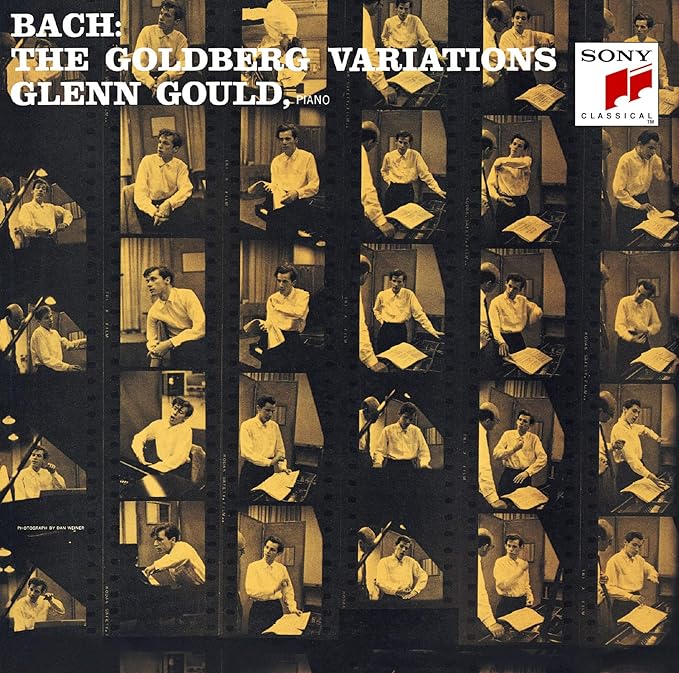
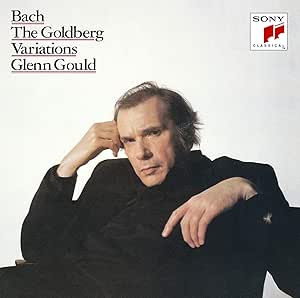
10、トッカータとフーガ ニ短調
この作品は誰れでも1度は聴いたことがあると思います。
荘厳なパイプオルガンの音色と、インパクトのある冒頭が有名です。
完成度がとても高い作品ですが、バッハ21歳の頃の作品だと言われています。
トッカータとは、速いメロディーや音の変化を特徴とする即興的作品のことです。
即興的とは、演奏家がその場で思いついた演奏をすること。
また、トッカータとはイタリア語で「触れる」を意味するトッカーレに由来します。
じつはこの曲、「バッハの作品じゃないんじゃない?」という話もありますが、真偽はわかっていません。でも一応、バッハの作品として知られています。
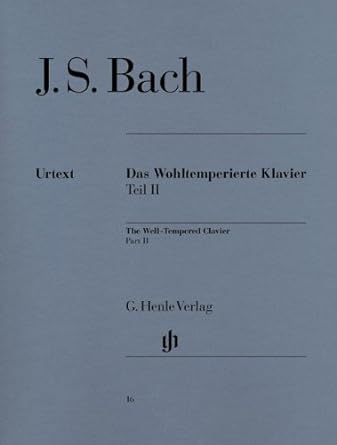
20世紀の指揮者レオポルド・ストコフスキーが編曲した管弦楽版もあるので、
比較のために聴いてみてください。
バッハ作品の特徴まとめ
今回はバッハ作品の特徴とおすすめ代表曲を紹介しました。おそらく全部お聴きになる方はいないと思います。でも、どれも音楽史に残る名曲であるのは間違いありません。
今回の作品を通じてバッハ作品に興味を持っていただき、新たな扉を開いていただけたら幸いです。次回から数回にわたって、個別作品(ピアノ曲)の紹介をしていきます。
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。
最新記事一覧
前回の記事はこちら👇
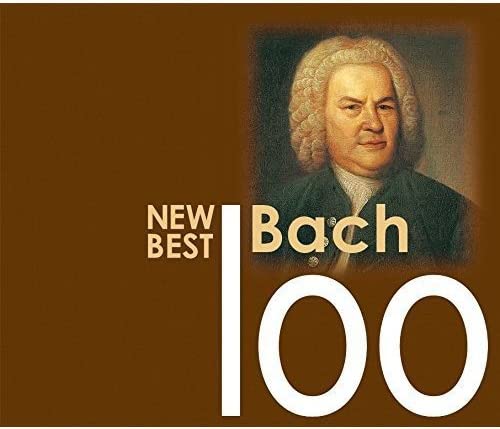
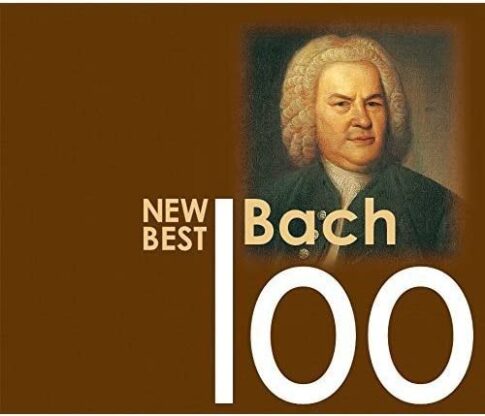
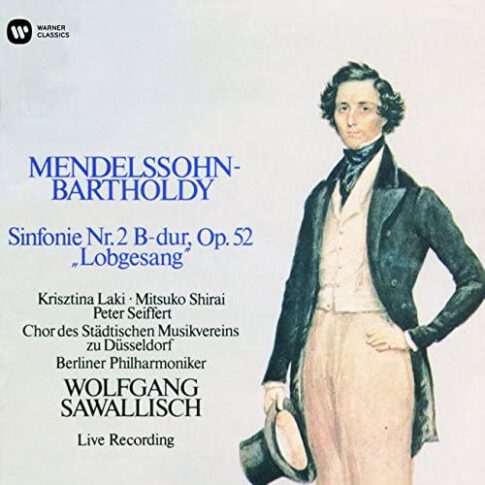









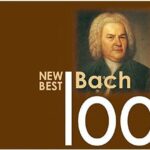

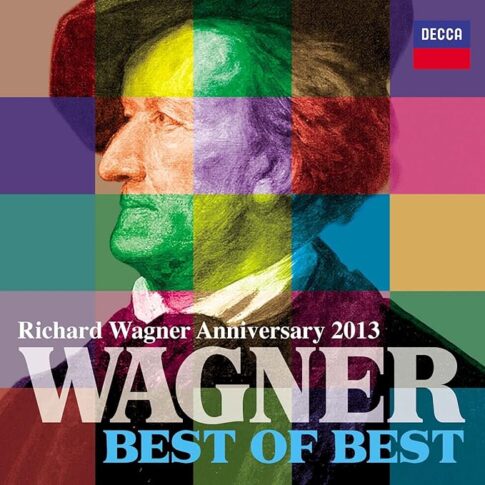
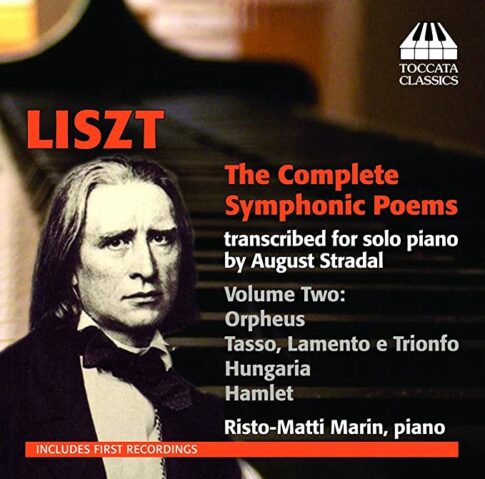
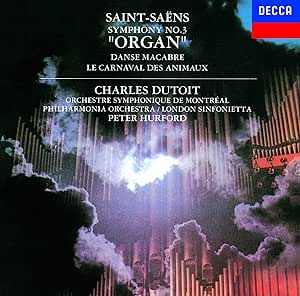

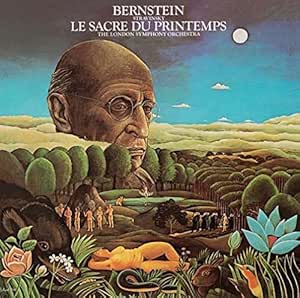
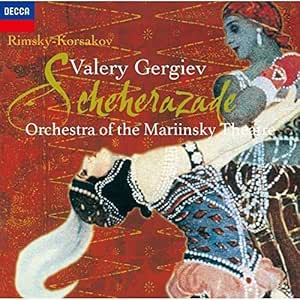
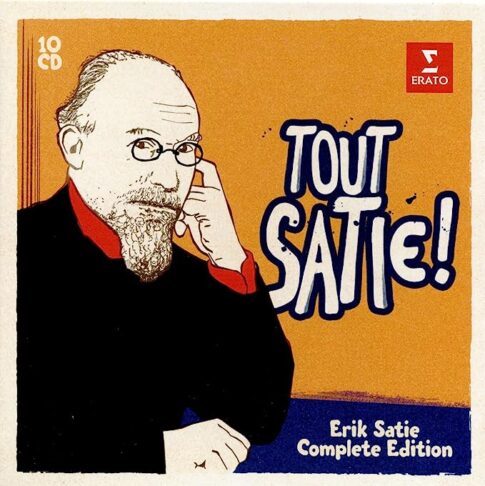



これは、
・Bach・・・バッハの
・Werke・・・作品
・Verzeichnis・・・目録
の頭文字をとったものです。
バッハ本人がつけたものではなく、
20世紀に入り音楽学者により整理されました。