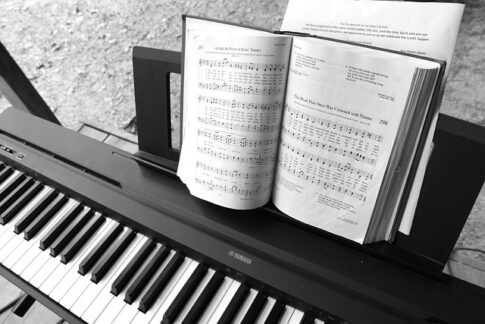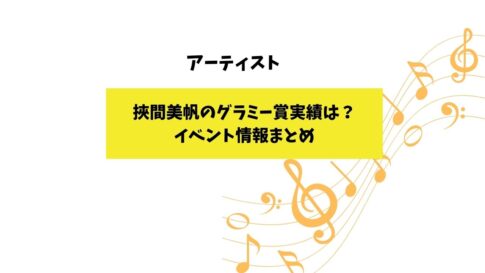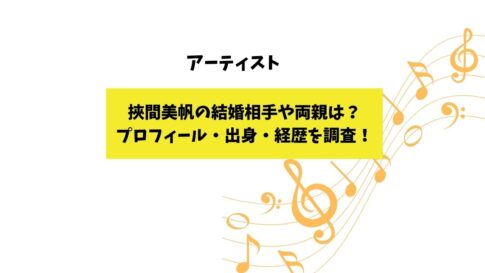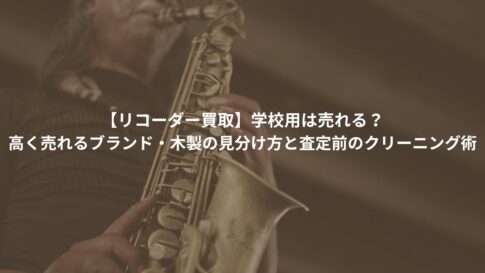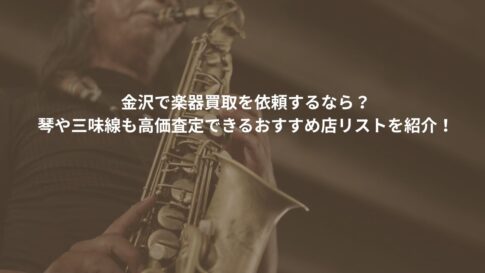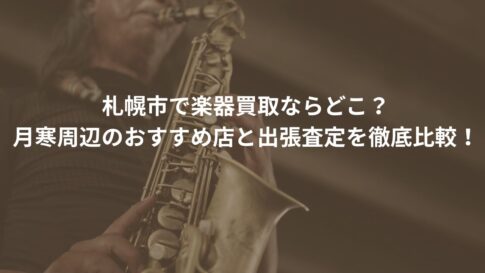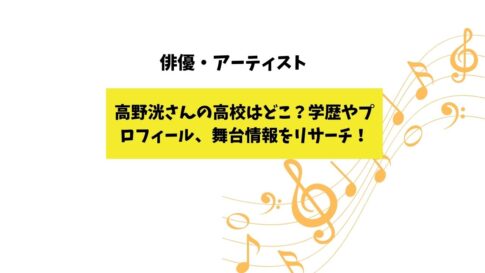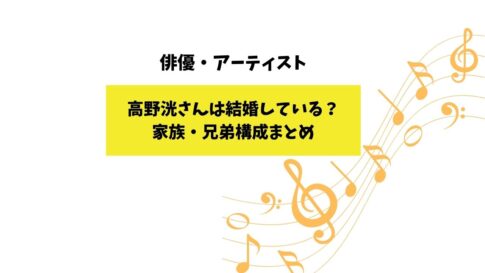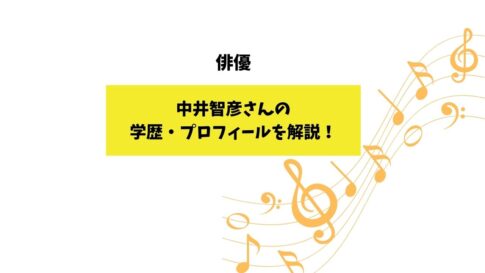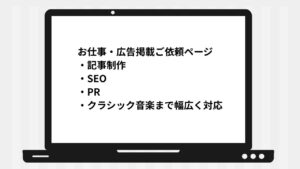この記事では「ピアノ独学の危険性」についてわかりやすく解説します。
実際、「ピアノを独学で弾けるようになりたい!」と思い立ったものの、思うように上達せずに挫折してしまう人、結構いるのではないでしょうか。
自己流の練習には自由度がある反面、知らず知らずのうちに“落とし穴”にハマり、間違った弾き方を身につけてしまう危険性も…。
そうならないために、この記事では、ピアノ独学者が陥りやすい7つの落とし穴を詳しく解説し、対策や実践的なヒントを紹介します。
これから「独学でピアノをやりたい!」方にとって参考になりますので、ぜひ最後まで読んで実践してみてください!
単発でピアノレッスンを受けるなら、ココナラ!
ピアノを独学で学ぶメリット3つ
「レッスンに通うのはちょっとな・・・」
「時間もお金もかかるから・・・」
「課題が達成できないかもしれないし」
などなど。
ピアノ独学を選ぶ理由は人さまざま。
また、「ピアノの独学は危険」という声も目にしますが、独学で学ぶメリットもあります。
そこでまずは、独学で学ぶメリットを見てみましょう。
主なメリットは次の3つです。
1つずつ解説します。
ピアノを独学で学ぶメリットその1:時間的な制約
現代人はとにかく「忙しい」。
そのため、定期的なレッスンに通う時間を確保するのが難しい人も多いと思います。
その点、独学は時間を有効活用できる選択肢。
夜遅くや早朝、休日など自分の空いた時間に集中して練習できることが大きなメリットです。
特に不規則な勤務形態の方にとっては、決まった時間に予約を入れる必要がない独学は現実的な選択と言えるでしょう。
ピアノを独学で学ぶメリットその2:経済的な負担が少ない
月に数回のレッスンでも、年間で考えると相当な費用になるピアノ教室。
でも独学であれば、教材費や動画サブスクリプション料金程度で学習を続けることができます。初期投資として電子ピアノを購入しても、長期的に見れば経済的な負担減も。
特に趣味として楽しむ程度であれば、高額なレッスン料を支払う必要性を感じない方も多いのはないでしょうか。
「どんな電子ピアノが良いの?」という方はこちらの記事が参考になりますよ!
ピアノを独学で学ぶメリットその3:自由度が高い
教室では基本的に先生が選んだ曲や教材に沿って進む必要があります。
でも独学なら、自分の好きな曲を自由に練習できるのがメリット。
さらに、クラシックからポップス、アニメソングまで、自分の興味のある音楽に集中することで、モチベーションを維持しやすいという利点があります。
またYouTubeなどで様々な演奏スタイルに触れることで、自分好みの表現方法を探求できることも魅力の1つです。
「電子ピアノでも上達できる?」と心配の方はこちらの記事をどうぞ。
ピアノの独学は危険?注意すべき7つのポイント

独学には多くのメリットがある一方で、見落としがちな危険性も。
ここでは特に注意すべき7つのポイントを詳しく解説します。
ポイントは以下の7つです。
ピアノの独学の危険性その1. 危険な手のフォームによる腱鞘炎のリスク
独学では正しい姿勢や手の形、指の使い方を学ぶ機会が少なくなりがちに。
そのため、間違ったフォームが定着し、将来的に腱鞘炎などの身体的トラブルを引き起こす可能性もあります。
特に力任せに弾く癖がつくと、長時間の練習で手や腕に負担がかかり、深刻な障害につながることも。
症状例:
- 練習後の手首や前腕の痛み
- 指の疲労感が長時間続く
- 指が思うように動かなくなる
対策:
- オンライン動画の中でも、特に手のフォームに焦点を当てた解説を参考にする
- 鏡や録画で自分の姿勢を定期的にチェックする習慣をつける
- 痛みを感じたら必ず休憩し、無理な練習は避ける
ピアノを弾く時の姿勢は結構重要です!
こういう動画も参考にしてみてください!
出典:YouTube
ピアノの独学の危険性その2. リズム感や拍子の不安定さ
楽譜の音符の長さは理解できても、実際にリズムを正確に刻むことは独学では難しい課題かもしれません。リズムが不安定になると、どんなに正確な音を弾いていても、曲全体の印象が大きく損なわれてしまいます。
症状例:
- テンポが一定に保てず、速くなったり遅くなったりする
- 複雑なリズムパターンで混乱する
- 楽譜通りに弾いているつもりでも、聴き手には不自然に聞こえる
対策:
- メトロノームを必ず使用し、様々なテンポで練習する
- リズムだけを手拍子で練習してから鍵盤で弾く
- 自分の演奏を録音して、リズムの安定性を客観的にチェックする
メトロノームはアプリでOK。新しく購入する必要はないです。
ピアノの独学の危険性その3. 音楽理論の理解不足
出典:YouTube
音符の高さや長さは分かっても、和声の進行や曲の構造を理解しないまま練習すると、機械的な演奏になりがちに。音楽理論の基礎知識は、表現力を身につけるためにも大切な要素です。
症状例:
- 曲の盛り上がりや緊張感を表現できない
- フレーズのつながりが不自然になる
- 和音の美しさや緊張感を活かせない
対策:
- 基礎的な音楽理論(調性、和声、形式など)を学べる書籍やオンライン講座を活用する
- 一つの曲を深く分析してから練習を始める
- 同じ曲の様々な演奏を聴き比べ、表現の違いを観察する
レッスンに通わなくても、単発でもならえますよ!
ピアノの独学の危険性その4. モチベーション維持が難しい
独学では進み具合やフィードバックがないのがデメリット。
そのため、練習の継続が続かないケースが多く見られます。目標が明確でないと、日々の練習が単調に感じられ、モチベーションが低下していきますよね。
症状例:
- 練習の頻度が不規則になる
- 同じ箇所で何度も挫折する
- 上達している実感が得られない
対策:
- 短期・中期・長期の具体的な目標を設定する
- オンラインコミュニティに参加して同じ境遇の学習者と交流する
- 小さな成功体験を積み重ね、達成感を味わう機会を作る
- 定期的に演奏動画を撮影し、成長の記録を残す
SNSなどを通じて、同じ仲間を見つけるのがベストです。
ピアノの独学の危険性その5. 客観的な評価が得られない
独学の場合、自分の演奏を客観的に見られないのもデメリット。
誤った音やリズム、タッチの問題に気づかないまま練習を続けてしまうことがあります。
改善すべき点が見過ごされ、上達が停滞することも。
症状例:
- 間違った音を弾いていても気づかない
- 特定の指が弱くて音量にムラがある
- ペダルの使い方が不適切で音が濁る
対策:
- 演奏を録音・録画して客観的に聴き直す習慣をつける
- 可能であれば数ヶ月に一度でも専門家の意見を聞く機会を設ける
- 譜読みの段階では非常にゆっくりとしたテンポで正確さを確認する
ピアノの独学の危険性その6. 非効率的な練習方法による時間の浪費
出典:YouTube
独学では適切な教材選びや練習方法を自分で考える必要があり、非効率な方法で多くの時間を費やしてしまうことがあります。限られた練習時間を有効に使うためには、計画的なアプローチが不可欠です。
症状例:
- 難しすぎる曲に挑戦して挫折する
- 曲の最初から最後まで何度も通して弾くだけの練習になる
- 苦手な箇所を避けて得意な部分ばかり練習する
対策:
- 技術レベルに合った教材や曲を選ぶ
- 短い区間に分けて集中的に練習する方法を身につける
- 練習の記録をつけ、苦手な部分を重点的に取り組む
- テクニック別の基礎練習(スケールやアルペジオなど)を日課に取り入れる
ピアノの独学の危険性その7. 練習内容が単調になりがち
好きな曲や特定のジャンルばかり練習していると、演奏技術や表現方法が身につきにくくなるかもしれません。なので、様々な時代やスタイルの曲に触れることで、豊かな音楽性を育むことも大切です。
症状例:
- 同じような雰囲気の曲しか弾けない
- 新しいスタイルの曲に挑戦すると極端に弾きにくく感じる
- 表現のレパートリーが限られている
対策:
- 意識的に異なる時代やスタイルの曲を選んで練習する
- クラシック、ジャズ、ポップスなど様々なジャンルにチャレンジする
- 表現方法(タッチ、ダイナミクス、アーティキュレーション)を意識的に変えて練習する
指導者から学ぶことの重要性
「独学でお金をかけずに練習したい!」という気持ちはわかりますが、指導を受けることで、独学では得られない多くのメリットがあるのも事実です。
以下では、専門家のガイダンスがもたらす具体的な価値について説明します。
ポイントは3つです。
1. 的確なフィードバックと課題が見える
ピアノの先生は、やはり教え方のプロ。
先生の指導を受けることで、自分では気づかない問題点を的確に指摘してくれます。
特に初心者のうちは、何が正しく何が間違っているのかを判断するのが難しいもの。
そのため、専門家の耳と目によるフィードバックは、上達のプロセスを大幅に加速させる要素となるはずです。
2. 体系的なカリキュラムによる効率的に上達できる
プロの指導者は生徒の現在のレベルをきちんと把握しています。
そのため、教材の選び方も適切。段階的に技術を積み上げていくカリキュラムにより、無理なく着実に上達することができますよ。独学で陥りがちな「難しすぎる曲に挑戦して挫折する」というパターンを避けられます。
3.きちんとした基礎練習により上達のスピードが早まる
初心者のうちから正しい姿勢、手の形、指の使い方を身につけることで、将来的な発展の土台を築くことができます。
これ実はめちゃくちゃ大事。
一度でも変な癖がついてしまうと変更が難しいため、最初から正しく学ぶことが重要です。
慣れないうちは「堅苦しい」と思うかもしれません。
でも将来的に高度な技術を習得する際のハードルを大幅に下げることができますよ!
おすすめのオンライン・ピアノレッスンについてはこちらで紹介しています。
ピアノ独学の危険性を回避する:具体的な方法5つ
気を付けるべき点は次の5つ。
1つずつ解説します。
1.姿勢と手の形を常に意識する
上述したように、正しい姿勢と手の形はピアノ上達において基盤中の基礎。
姿勢は背筋を自然に伸ばし、肩の力を抜いた状態で、肘が鍵盤と同じ高さになるよう椅子を調整します。
手の形は指に自然な丸みを持たせ、特に親指と小指に力が入りすぎないように注意。
練習前に姿勢チェックする習慣をつけ、定期的に鏡や録画で確認するのアリです。
2.メトロノームを活用してリズムを安定させる
リズム感の不安定さは独学者の一般的な問題ですが、これはメトロノームで改善できます。
新曲学習時は必ずメトロノームを使い、無理なく弾ける速さから始めて、徐々に本来のテンポへ近づけます。
また、複雑なリズムは手拍子で練習してから弾くと効果的です。
スマートフォンアプリを使うと、拍の強弱設定機能もあるので便利です。
不安定な箇所は録音して客観的に聴き直すことで、気づかないリズムのずれを発見できます。
3.基礎的な音楽理論を学ぶ
ピアノは「理解する」楽器でもあります。
音階、和音、調性の基本概念を理解することで、厚みのある演奏が可能に。
和音進行の理解は指の動きに論理的裏付けを与え、暗譜も容易になります。
初心者向け理論書籍やオンラインコースを活用し、弾く曲の和音にマーキングする習慣をつけましょう。もちろん、動画で学んでもOKです。
4.録音して自分の演奏を客観的にチェックする
演奏中は客観的視聴が難しいため、定期的に録音して聴き直す習慣を。
ときどきスマートフォンで録音し、楽譜と照らし合わせて音の正確さ、均一性、リズム、フレージングをチェック!
可能ならプロの演奏と比較するとさらに効果的です。習慣化すると上達が早まり、自己批評力を養います。
5.オンラインレッスンやワークショップを活用する
月に1回程度でもオンラインレッスンを受講することで、独学の落とし穴を減らせます。YouT
たとえば、オンラインワークショップも専門家の視点に触れる機会です。
質問機能付きのライブ配信や、演奏動画へのフィードバックをもらえるコミュニティも活用できますよ!
完全独学より部分的にでも専門家のアドバイスを取り入れることで、上達の速度と質の向上が期待できます。
ココナラでプロのオンラインレッスンを受けてみる!
ピアノの独学は危険?:まとめ
ということで、今回は「ピアノ独学の危険性」と解決するための具体的なポイントを紹介しました。内容のまとめは次のとおり。独学でも十分に上達可能なので、ぜひ楽しみながらピアノライを送ってください!
- ピアノの独学には時間や場所の自由度、コスト面でのメリットがある
- 独学の主な危険性として以下の7つが挙げられる:
- 誤った手のフォームによる腱鞘炎リスク
- リズム感の歪みと不安定さ
- 音楽理論の理解不足による表現力の欠如
- モチベーション維持の難しさ
- 客観的な評価が得られないことによる盲点
- 非効率的な練習方法による時間の浪費
- 表現力の幅が狭くなる単調な練習内容
- 指導者から学ぶメリットは、的確なフィードバック、体系的なカリキュラム、モチベーション維持、正しい基礎の習得
- 独学のリスクを最小限に抑えるには、正しい姿勢の意識、メトロノームの活用、音楽理論学習、録音によるチェック、オンラインレッスンの活用、学習仲間との交流、計画的な練習が効果的
- ピアノ学習は完全な独学よりも、部分的にでも専門家のアドバイスを取り入れることで効率的に上達できる
【無料体験レッスンあり限定!】初心者も安心!おすすめ音楽教室6選!
「楽器を習ってみたい!」「新しい楽器を探してる!」という方に向けて書きました。