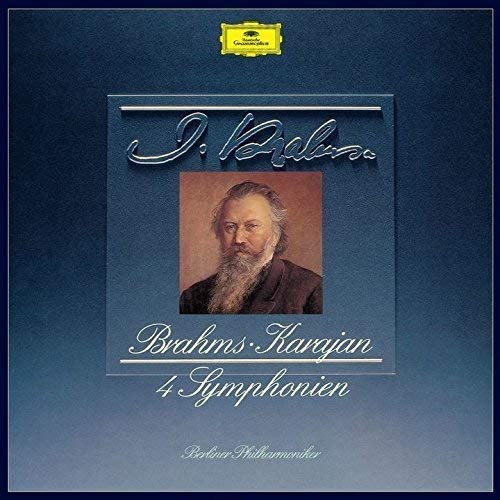今回は前回の「おすすめ代表曲」紹介の続きとなります。
前回の記事はこちらから!!。ブラームスシリーズをまだ読まれていない方は👇からお読みいただけます。
前置きはこれくらいにして、早速作品紹介。残り6曲はソナタと室内楽のおすすめ作品です。
ヨハネス・ブラームスのおすすめ代表曲、ソナタ編
ブラームスのソナタにはどんな作品があるのでしょうか?といっても、それほど作品数多くないので、意外にコンプリートしやすいと思います。
今回はヴァイオリン、ピアノ、クラリネットソナタを紹介してみます。
おすすめ代表曲その10、ヴァイオリンソナタ
まず1つ目は『ヴァイオリンソナタ1番』。
ブラームスは生涯で3曲の「ヴァイオリンソナタ」を作曲しています。
この作品は1878年と1879年の夏に作曲され1879年11月に一般初演されました。
なかなか「ヴァイオリンソナタ」を聴く機会はないと思いますが、そんな人にもおすすめの作品です。
なんといっても、この作品はメロディーがどこまでも穏やか。聴いていると、安らぎに包まれます。これを作曲したときのブラームスの内面が充実していたのでしょうね。
第3楽章冒頭の主題は、ブラームスの代表歌曲『雨の歌』の主題が用いられています。
この切ないメロディーがたまらん!
この作品以前にもブラームスはヴァイオリンソナタを作曲しており、師匠シューマンから出版を勧められていたようですが、気に入らなかったのか破棄してしまったそうです(もったいない)。
気になった方は、第3楽章だけでもぜひ聴いてみてください!!
全3楽章構成で、演奏時間は30分程度です。
ヨハネス・ブラームスのおすすめ代表曲その11、チェロソナタ2番
お次はチェロソナタ「深い安定感」のあるチェロの音色って、なんだか落ち着きます。
ヴァイオリンソナタ同様、ブラームスは3曲の『チェロソナタ』を作曲しています。
聴いていただくとわかりますが、冒頭からエネルギッシュ!!
『ヴァイオリンソナタ1番』とは違った趣とチェロの持つ力強さを存分い楽しめると思います。
いや、ヨーヨーマの演奏が素晴らしいのかな?
それはさておき、本作は1886年にこれまたスイスの避暑地で作曲されました。
50代になり、円熟味を帯びたブラームスの傑作の1つといえるでしょう。
第迫力の4楽章構成で、演奏時間が30分んという大曲です。
その12、ピアノソナタ1番
お次は『ピアノソナタ第1番』。シューマンとブラームスの運命を決定づけた作品として知られていますね。
その時のエピソードについてはシューマンシリーズで書いているので、ぜひそちらを。
ヨーゼフ・ヨアヒムの勧めにより、シューマンの元を訪れたブラームス。
この作品を聴いたシューマンはあまりの感動に、外にいたクララを室内に呼び戻したと言われています。
ブラームス、20歳時の出来事です。
弱冠20歳の若者にこれほど完成度の高い作品を披露されたら、さすがのシューマンも度肝を抜かれたことでしょう。
また、エクトル・ベルリオーズもこの作品に対して賛辞を述べたと言われています。
本作はシューマンとの縁を取り継いだ、ヴァイオリニストで友人のヨーゼフ・ヨアヒムに献呈されました。
ブラームスの作曲家人生を決定付けた記念碑的作品なので、第1楽章だけでも聴いてみてください。
ツィーマーマンの演奏最高すぎる!!(ホント天才)。
その13、クラリネットソナタ
最後は『クラリネットソナタ第1番』です。ブラームスシリーズ最初の記事で書いたように、自身の肉体的衰えに悲観したブラームスは、一時期引退を考えます。
この引退宣言的なものはかなり本気だったようで、遺書を書いたり身辺整理までしたほどでした。
そんな失意の底に沈んでいたブラームスですが、あることをきっかけに作曲家としての意欲が再燃します。
それは、クラリネット奏者リヒャルト・ミュートフェルトとの出会いでした。
ミュートフェルトの演奏に感銘を受けたブラームス。
この出会いにより創作意欲を取り戻し、ブラームスは再び音楽の道に戻りました。
正直、僕はあんまり聴いたことないし、メジャーかどうかと聴かれると「それほどメジャーじゃない」と思います。もちろん、他の代表作に比べればってことですが・・・。
でも、聴いてみるとクラリネットが持つ優しさとロマン派の抒情性が見事だなと。
ブラームス自身も気に入っていたようで、のちにヴィオラ版、ヴァイオリン版にも編曲されています。
ヨハネス・ブラームスのおすすめ代表曲、室内楽・変奏曲編
残すところあと2曲。せっかくここまで読んでいただいたので、もう少しお付き合いください。
「ブラームスの室内楽もよく聴いたな〜」と自分ながら懐かしいですが、今回は1曲だけ。
ヨハネス・ブラームスおすすめ代表曲その14、ピアノ四重奏曲
なんとなくですが「室内楽をゆっくりと聴けると大人な感じ」がしてます。
といっても、この作品、ブラームスが20代前半で書いた曲なので、完全に僕の主観ですね(笑)。
それにしても、20代前半でこれほどの曲を作曲する精神性は「凄い!」の一言に尽きます。
並の作曲家なら「晩年の傑作」と言われても疑わないんじゃないかと思う・・・。
楽器構成はピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロです。
4手連弾用版の他、シェーンベルクによる管弦楽版もあります。
でも、「なぜシェーンベルクが編曲を?」と思って調べてみたところ、「偉大な作曲家に対して敬意を表するため」らしいです。
20世紀の初頭の多くの作曲家たちにとって、ブラームスはやはり憧れだったのだな〜と改めて思います。シェーンベルクについてもいつか書きます。
本作は4つの楽章で構成され、演奏時間はおよそ35分のこれまた大曲です。
その15、パガニーニの主題による変奏曲
本ブログで間接的に大人気のパガニーニ。
パガニーニについてはリストシリーズでちょっと紹介しています。シューマンの時にも少し書いたかも・・・。
楽譜動画を見つけたので、そちらで紹介します。
しかし、まぁ「激ムズにもほどがある」ってくらい激ムズです。
パガニーニの『24の奇想曲』中でもっとも有名な24番をモチーフに作曲されました。
作曲のきっかけは、リストの弟子カール・タウジヒの提案だったそうです。
どんな意図があって提案したのか定かではありませんが・・・。
もしかしたら、「先生よりすごいの作ってみろ」的な挑戦状だったりして(邪推ですよ〜)。
1855年から1861年にかけて作曲されていて、ブラームスの弟子エリザベート・シュトゥクハウゼンに献呈されています。ちなみにこの曲、「練習曲」だそうです・・・。
ヨハネス・ブラームスの代表曲。その特徴とは?
ようやく15曲の紹介が終了。もっと少なくても良いかと思ったのですが、思い出が蘇ってきたので多くなってしまった・・・。
しかし、1曲でも読者の方に気に入っていただける作品があることを願います。
ヨハネス・ブラームスの作品の特徴は?
ここまで「その①」「その②」と、2回に渡りブラームスの作品を紹介しました。
シューマン亡き後、ロマン派を牽引したブラームスですが、同時にベートーヴェンやハイドンなどのいわゆる古典派の伝統を受け継いだ人物でもあります。
このことはブラームス自身も意識しすぎるくらい意識しすぎていて、であるが故に『交響曲第1番』の作曲に21年かかったわけです。
ブラームスは『交響曲第1番』を作曲するにあたり、次のような言葉述べました。
ブラームスがどれほどベートーヴェンを意識していたかがよくわかるセリフです。
ベートーヴェンという巨人が背後から行進してくるのを聞くと、とても交響曲を書く気にならない
なので、ブラームスの大きな特徴としては「古典派とロマン派の両方を折衷した」と考えられます。
声楽や宗教曲なども作曲
今回の紹介では主に「器楽曲」を中心に紹介しました。
しかし、ブラームスは声楽曲や宗教曲なども作曲していて、なかでも『ドイツ・レクイエム』はクラシック音楽に燦然と輝くレクイエムとして知られています。
まぁ、ブラームスはもちろんキリスト教徒だったので、宗教曲を作曲するのは当然ですが・・・。
その他、『ブラームスの子守唄』や『永遠の愛』なんかも広く知られています。
この『子守唄』もよいんだよな〜〜〜。
まとめ
今回は2記事にわたりブラームスのおすすめ作品紹介しました。
何度も言いますが、他にも紹介したい曲がたくさんあります!!。
でも、今回紹介した作品を聴いていただければ、ブラームスの良さがわかってもらえるかと・・・。自分の好きな作曲家について書くのはなかなか楽しいですね(当然か)。
ということで、次で最後です(続くのか!)。次の記事では、最後の最後に出てきた『ドイツ・レクイエム』について超簡単に解説します。